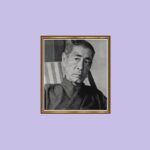第2回 世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”
2-1. 世界はなぜブロック経済へと走ったのか
■ 世界恐慌という地殻変動
1929年、ニューヨークの株式市場が大暴落した。この「世界恐慌」は、たった一国の金融危機ではなく、あっという間に世界中の経済に連鎖反応を引き起こした。経済がグローバルにつながり始めた時代だからこそ、その影響は深く、広く、長く続いた。
アメリカをはじめとする主要国では、銀行の破綻、企業の倒産、失業率の激増という深刻な社会不安が広がった。とりわけ資本主義の旗手であったアメリカが打ち出した政策が、その後の国際経済の流れを決定づける。それが「保護主義」への転換である。
アメリカは1930年に「スムート=ホーリー関税法」を制定し、2000品目以上にわたる輸入品に高関税を課した。これに他国も追随し、互いに関税を高め合う“関税戦争”が勃発する。国際貿易は急速に冷え込み、各国は自国経済を守るため、植民地を囲い込む形での「ブロック経済」へと傾斜していった。
■ ブロック経済の実態と論理
では、「ブロック経済」とは何だったのか。
簡単に言えば、それは“自分たちだけで経済圏を作り、他者を排除する仕組み”である。植民地を含む自国圏内で資源、労働力、市場を循環させ、他国からの輸入を抑えることで内需を維持しようとする政策だった。
イギリスは「スターリング・ブロック」を形成し、インド、カナダ、オーストラリアなど英連邦内での貿易を優遇。フランスは「フラン・ブロック」を構築し、北アフリカや東南アジアの植民地を自国経済の延長線に取り込んだ。オランダ、ベルギー、ポルトガルも同様の動きを見せる。
これは、表向きには“経済の安定化”を目的とするものだったが、実際には他国を排除する排他的経済構造であり、自由貿易とは真逆の動きだった。そしてこのブロック経済化こそが、日本の「追い詰められた選択」の発端となる。
■ 日本にとっての死角──ブロック経済の脅威
日本は、天然資源に乏しく、工業製品の輸出で外貨を稼ぎ、その外貨で石油・鉄・ゴムなどの資源を輸入するという「外需依存型経済」の国であった。
ところが世界恐慌を契機に、各国が市場を閉ざしていったことで、日本の輸出先が急速に縮小していく。たとえば、日本の主力輸出品であった生糸や綿製品は、アメリカや中国市場からの締め出しを受け、大打撃を受けた。
さらに、日本には広大な植民地や経済圏が存在せず、国内市場も狭いため、ブロック経済に対抗する術が乏しかった。つまり、日本は「入る場所のない世界」の中に取り残される構造的な不利を背負っていたのである。
この“排除された経済構造”のなかで、日本は自給自足の道を模索せざるを得なくなる。そして、その最も現実的な選択肢として浮かび上がってきたのが、満洲をはじめとする中国大陸への進出だった。
■ 自国第一主義の世界と日本の孤独
世界各国が“自国を最優先する政策”に走った結果、国際協調という理念は失われ、国際連盟の存在意義も急速に希薄化していった。各国は互いを信頼せず、助け合うどころか競争と排除を強めていく。日本は国際連盟の理想に忠実に従おうとしたが、その場に残されたのは「正直者が損をする」構図だった。
日本政府は当初、満洲進出を公然とは認めず、国際社会との協調を模索した。しかし、外貨不足と資源難、失業と貧困の拡大が続くなかで、外交努力だけでは事態を打開できないことが明らかになっていく。
その結果、日本はやがて「内向き」から「外向き」、そして「進出」へと舵を切る。これは好戦的な野望ではなく、構造的に追い詰められた経済状況のなかでの“生存戦略”だった。
■ 経済戦争としての1930年代
このように、1930年代とは、銃や大砲の代わりに関税と禁輸で国を締め上げる“経済戦争”の時代だった。日本は一発の銃声も交えずに、経済的に「干される」ことによって、国の根幹を揺さぶられていった。
戦争とは何も武力によるものだけではない。食糧、資源、外貨、雇用、あらゆる経済的基盤を奪われていくなかで、国家は「最後の手段」として戦争を選ぶ場合もある。
この章の結論は明白である。日本は世界恐慌という津波に飲み込まれ、ブロック経済という壁に閉ざされ、「外へ出るしか生きる道がない」という時代に突入したということだ。
それは、選びたくて選んだ道ではなかった。まさに、「選択肢なき国家」の苦悩が、ここにあった。
2-2. 英米の壁、植民地の利権、日本が入る余地はどこにあった?
「扉を閉ざされた世界」の実像
1930年代の世界は、まさに経済的な壁が国境のように立ち塞がる「経済的鎖国時代」に突入していた。世界恐慌の影響により各国が自国経済の保護に走り、「ブロック経済」と呼ばれる経済圏が形成される。だが、その経済圏はすべて“植民地”を土台に構築され、日本のような植民地を持たない国にとっては、参加の余地すらなかった。
イギリスは英連邦を中心に「スターリング・ブロック」を築き、フランスは「フラン圏」、アメリカは「ラテンアメリカ圏」を抱え込む。これらはすべて、自国内+植民地との交易を優先し、他国の参入を排除する設計だった。つまり、国際市場は一部列強国とその支配地域によって囲い込まれ、日本には“誰かの経済圏に入る”という選択肢さえ閉ざされていた。
世界の貿易は、イギリスやアメリカがルールを決める“クラブ活動”のようなものであり、日本はそのクラブに招かれない異端者であった。問題は、その排除が“経済的圧迫”にとどまらず、“国家の生存”そのものを脅かすレベルにまで達していたことだ。
植民地を持つ国と、持たざる国の絶望的格差
イギリス帝国は当時、インドを中心にアジア・アフリカ・オセアニアに広大な植民地網を持ち、あらゆる資源をほぼ自国内で循環させる仕組みを作り上げていた。鉄、石炭、ゴム、綿花、食料、労働力──全てを植民地から調達できた。アメリカもまた、フィリピンをはじめとした太平洋地域を“裏庭”として活用していた。
一方の日本は、資源に乏しく、人口過剰で、しかも輸出入に頼る経済構造だった。つまり、日本が外国と自由に貿易できないという事態は、単なる経済不振ではなく、国民の食糧・燃料・生活用品の確保に直接関わる“国家の危機”であった。
そして、日本が入ろうとしたどの経済ブロックにも、英米は「No」を突きつけた。日本が中国市場や東南アジアに経済的影響力を伸ばそうとすれば、「侵略」と非難され、欧米の既得権益に触れた途端に制裁が課される構図が固定化していった。
「平等な競争」は幻想だった――差別された日本
日本が自由貿易を求めたとき、欧米諸国が語ったのは「開かれた市場の原則」だった。だが、その原則が日本にも平等に適用されたことは一度もない。
たとえば、英米は中国市場に「門戸開放」を主張していたが、これは彼ら自身の既得権益を維持するためのものであり、日本が同じく権益を求めると、すぐに「帝国主義」と非難された。また、列強各国の植民地には関税自主権がなく、母国がすべての経済ルールを握っていた。つまり、外から経済活動を行おうとする日本には、事実上の参入障壁が存在していた。
アメリカでは「黄禍論」に基づく排日運動が展開され、カリフォルニア州では日系移民が土地を持つことすら禁じられた。これは単なる人種差別ではなく、日本の成長を「危険視」する国家戦略だった。つまり、日本が平和的に経済成長を目指そうとしても、それは英米にとって“敵対行為”とみなされたのだ。
閉ざされた扉の向こうに――「選択肢」の不存在
日本にとって、1930年代は「選択肢の時代」ではなかった。選択する以前に、“選択肢が与えられていなかった”というのが実情だ。
ソ連とはイデオロギーの違いと国境を接する安全保障上の問題から提携が困難。中国は欧米列強がすでに利権で分割し尽くしていた。東南アジアは英蘭の植民地で、触れれば「侵略」と呼ばれる。アメリカの西半球政策に対しても、日本は入り込む余地すらない。
その中で唯一、地理的・歴史的に縁があり、しかも列強の統治が不十分だったのが“満洲”だった。ここで経済圏を築くことこそが、日本に残された最後の「生存の道」だった。これは軍部の暴走でも、外交の失敗でもなく、むしろ国際環境という構造的な圧迫が生み出した“必然の選択”であったと見ることができる。
英米の二枚舌――植民地支配と日本非難の二重基準
忘れてはならないのは、当時の英米自身がアジア・アフリカを「侵略」してきた歴史を持っていたことだ。イギリスのインド支配、フランスのインドシナ支配、オランダの東インド支配、そしてアメリカのフィリピン支配。これらはすべて、現地の同意もなく、軍事力で押し切った典型的な“植民地化”である。
その彼らが、日本が満洲で築こうとした自治国家に対し「傀儡政権」と断じ、リットン報告書で「侵略」と決めつけた。その一方で、自国の植民地政策には一切口を閉ざす。こうした“勝者の正義”によって、日本は不平等な扱いを受け、かつ国際社会の場でも反論の余地を奪われていった。
入れない世界、市場なき国――出口なき経済戦略
資源もなく、植民地も持たず、排外主義に囲まれた日本。貿易の活路を求めても、市場は閉ざされ、経済制裁がちらつく。つまり、1930年代の日本は、「経済の自立なくして外交も軍事も立ち行かない」という“存在の危機”に直面していたのである。
日本は、世界のどこにも“歓迎される国”ではなかった。むしろ、成長するほどに危険視され、締め出される。そんな中、満洲への進出は、「侵略」でなく「必要な逃げ場」として国民に受け止められていった。
なぜ“選ばれなかった”のか
1930年代の日本は、「他国と同じ土俵で競争する」ことすら許されない立場にあった。植民地を基盤とした世界のブロック経済は、平等な市場原理とは無縁であり、日本がそれに反論しようとすれば、“ルールを破る異分子”とされる。
その閉ざされた構造のなかで、日本は「自ら選んで侵略へ向かった国」と誤解されてきた。だが実際には、“入れてもらえなかった”国家として、最後の選択肢を模索し、行動しただけだったのではないか。
「扉の外にいた日本」がなぜ、そうせざるを得なかったのか――この問いを忘れてしまえば、戦前の日本人が置かれていた真の苦悩は見えてこない。
2-3. 輸出立国・日本の絶望的な現実
—
輸出立国としての宿命
日本は明治維新以降、産業の近代化と経済成長を急速に進めてきた。だが、それを支えていたのは、国内市場ではなく、海外への輸出であった。とくに1920年代から30年代にかけての日本経済は、「輸出なくして成長なし」というほどに、国際貿易に依存する構造を深めていた。
最大の外貨獲得源は生糸だった。世界の市場で高く評価された日本の生糸は、アメリカを中心に大量に輸出されていた。この生糸輸出によって得た外貨が、鉄や石油、機械などの輸入に充てられ、日本の工業や軍需、生産インフラを支えていた。
つまり、生糸を売れなければ鉄も買えない、生糸が余れば国民生活が干上がる。それが、当時の日本の現実だったのである。
世界恐慌がもたらした輸出崩壊
1929年の世界恐慌は、この輸出構造を根底から崩した。アメリカは保護貿易政策に転じ、関税を引き上げて外国製品の締め出しを始めた。さらに、消費が冷え込み、輸入量も激減。日本の生糸の主な買い手であったアメリカ市場が、一夜にして“消えた”のだ。
輸出が激減すれば、生産が止まり、雇用が失われ、生活が破綻する。特に農村部では深刻で、米の価格が暴落し、自作農も生活が成り立たなくなった。「娘を売る」という悲劇的な現実が、この時期の日本各地で相次いでいた。
都市部でも、工場閉鎖・賃下げ・大量解雇が続発し、日本社会全体に「経済の底が抜けた」という感覚が広がっていた。まさに、「一億総苦境」の時代であった。
政府の対策と限界
日本政府もこの危機に手をこまねいていたわけではない。昭和初期の政府は財政出動を行い、軍需予算の拡大や公共事業の増加によって景気浮揚を図った。これがのちの軍事拡大と結びつくことになるが、当時としては失業と飢餓から国民を救うための「現実的選択」だったともいえる。
また、輸出の活路を求めて中国市場や東南アジアへと視線を移した。だが、そこにはすでにイギリス・フランス・オランダなどの利権が広がっており、日本の進出はすぐに「侵略」として非難された。つまり、日本が輸出を再建しようとすればするほど、列強との摩擦が激化する構図ができあがっていたのである。
植民地を持たない国の限界
イギリスやフランスは、自国の植民地を閉鎖的な経済圏に組み入れ、自国製品を優先的に流通させていた。これがブロック経済である。植民地は原材料の供給地であると同時に、完成品の販売先でもあった。
だが、日本はこうした植民地ネットワークを持たなかった。台湾や朝鮮は存在したが、英仏の帝国的支配圏と比べれば、貿易規模も経済的自立度も桁違いに小さい。だからこそ、日本はどうしても中国大陸や東南アジアに市場を求めざるを得なかったのだ。
これは「拡張主義」や「軍国主義」から出た発想ではなく、むしろ資源と市場のない国が生き残るための“経済的必然”だったといえる。
民衆の実感としての「出口のなさ」
当時の新聞や雑誌を読むと、日本国民が感じていたのは、「なぜ日本だけがこんなに苦しまなければならないのか」という素朴な怒りだった。欧米列強は植民地を搾取し、国内を豊かに保っていた。日本はそれに挑もうとすれば「侵略者」と非難され、手をこまねけば国が滅ぶ。
この二重基準に対する苛立ちは、単なる外交問題ではなく、庶民の生活感情にまで浸透していた。「日本は真面目に働いても損をする国だ」という意識が、徐々に社会を覆っていった。
その空気のなかで、軍部や開拓団による「満洲での夢」が語られたとき、それは苦境を脱するための“現実的な希望”として、多くの国民に受け入れられたのである。
「選択肢のなさ」がもたらした悲劇
振り返れば、この時期の日本に本当に“他の道”はあったのか。
アメリカは市場を閉ざし、英仏は排他的な経済圏を築き、中国は列強の利権で分断されていた。日本が自主的に経済成長できる場所は、ほとんど残っていなかったのである。
満洲への進出が、その後の悲劇的な戦争へとつながっていくことは事実である。しかし、そこに至る過程を「軍部の暴走」や「日本人の狂気」と決めつけるだけでは、あまりにも一面的だ。
むしろ、「輸出がなければ生きられない国」が、「輸出できる市場をすべて封鎖された」という現実に、どう対応すべきだったのか。それを考えることこそ、歴史を学ぶ意味なのではないだろうか。
2-4.「暴発」ではなく「追い詰められた選択」だった
戦争は“選択”ではなく“帰結”だったのか
歴史を振り返るとき、私たちはしばしば「なぜあのとき日本は戦争に踏み切ったのか」という問いを投げかける。そこには「他の選択肢もあったはずだ」「もう少し冷静な判断ができたのではないか」という現代人の視点が含まれている。しかし、1930年代から40年代初頭の日本を覆っていた現実は、私たちの想像以上に過酷だった。
この節では、日本の対外進出や開戦決断が、果たして「暴発」であったのか、それとも「追い詰められた末の選択」だったのかを、具体的な歴史的文脈から検証していく。
経済と外交が同時に閉ざされた国家
前節までで述べてきたように、日本は世界恐慌後、ブロック経済の波に取り残されていく。イギリス、フランス、アメリカはそれぞれ植民地や影響圏に閉じこもり、関税障壁を高くしていった。日本にとって、この閉塞感は単なる貿易問題にとどまらなかった。国家の生存そのものが脅かされていた。
たとえば、アメリカによる鉄や石油の禁輸措置は、工業生産のみならず日常生活にも大きな打撃を与えた。さらに外交面でも、リットン報告書による国際的批判と国際連盟脱退によって、日本は事実上「国際社会の場」から退場させられたのである。
このような状況で、日本がとり得る選択肢はどれだけ存在していたのだろうか?
「暴発」論の問題点──当時の現実を無視していないか?
戦後の歴史教育では、日本の開戦は「軍部の暴走」や「拡張主義の暴発」として語られることが多かった。この見方は、確かに一部の事実に基づいている。陸軍内の強硬派が政府の統制を無視して独自に行動した事例も多く、その結果として外交交渉の余地が狭まったことも否定できない。
しかし同時に、「暴発」という言葉には、「冷静で合理的な選択肢が他にあったのに、それを無視した」という前提が含まれている。この点が、当時の国際情勢と日本の立場を過小評価してしまう原因となっているのではないか。
現実には、外交も経済も袋小路に入り、庶民の生活も疲弊し、政党政治はすでに力を失っていた。そうした中で、日本が取った行動は、果たして本当に「選べた」ことだったのか。
庶民感覚としての「もう、これしかない」
当時の新聞記事や雑誌の投書欄、農村の青年の日記などを見ると、戦争を「喜んで」迎えていたわけではないことがよくわかる。むしろ、「これ以上我慢できない」「このまま何もしなければ、日本は滅びる」という、切迫感と諦めが交錯していた。
たとえば、1937年の日中戦争開戦時、「中国との戦争は本意ではないが、挑発には応じざるを得ない」といった論調が多数見られた。つまり、戦争は積極的に選ばれたというよりも、「他の手段が尽きた」末の苦渋の決断であったという感覚が支配していたのである。
この「追い詰められた選択」は、エリート層だけでなく、一般庶民の心情にも深く浸透していた。人々は国策を支持するというよりも、「国家が生き延びるためなら仕方がない」という意識で戦争へ向かっていったのだ。
外交交渉がことごとく失敗した理由
「外交努力は本当に尽くされたのか?」という問いも重要だ。実際、近衛文麿内閣や松岡洋右外相による対米交渉、日独伊三国同盟による抑止戦略など、当時の政府はそれなりに外交的解決を模索していた。
しかし、アメリカの態度は硬化の一途をたどり、ハル・ノート(1941年11月)では日本の要求をほとんど無視した内容が提示された。これにより、日本の中枢でも「外交交渉は完全に失敗した」との認識が広がる。こうした経緯を見れば、日本が武力行使に傾いていった過程は、決して「好き好んでの暴発」ではなかったと理解できるだろう。
地政学的な限界とリスクの分散
日本の戦略環境は、地政学的にも極めて不利だった。北にはソ連、西には中国、南にはアメリカやイギリスが支配する植民地。天然資源が乏しく、食料自給率も低かった日本にとって、どこかで「独自の生存圏」を確保しない限り、長期的な国家維持は不可能だった。
満洲の開発や南方への進出は、こうした「地理的条件」にも強く影響されていた。どちらも「余裕ある選択」ではなく、「やらねばならぬ選択」だったことを理解しなければ、当時の政策判断は正しく評価できない。
歴史は“断罪”ではなく“理解”するもの
ここで私たちが持つべき視点は、歴史を断罪することではなく、その背景を“理解する”ことである。
なぜ当時の日本人が、国家も国民も一丸となってあの道を進まざるを得なかったのか。その構造的な圧力と心理的背景を知ることで、戦争を再発させないための本質的な学びが得られる。
「戦争国家」と一括りにするのではなく、「追い詰められた選択」だったという視点で、もう一度あの時代を静かに見つめ直すこと──それこそが、「もう一つの昭和史」を読む意義ではないだろうか。
2-5. 日本国内の議論――誰が経済戦争への道を選んだのか
昭和初期、日本は世界恐慌とブロック経済という国際的な潮流に翻弄され、経済的孤立に追い込まれていった。その中で、日本国内では「平和外交による打開」と「経済的自立を求めた軍主導の強硬策」とがせめぎ合い、最終的には後者の路線が採られるに至った。だが、その意思決定は一枚岩ではなく、政府・軍・財界・メディア・知識人・国民世論が交錯する中で生まれた“消極的な合意”でもあった。本章では、この日本国内での議論と、その中でいかにして経済戦争への道が選ばれたのかを検証していく。
◆ 軍の台頭と「統制経済」構想
昭和6年(1931年)に起きた満洲事変は、日本軍部の行動が外交に先行する転換点となった。陸軍の中では、経済危機を国家改造の好機ととらえた統制派が台頭し、「自由経済では国防に耐えられない」とする主張が強まった。彼らがまとめた有名な文書『国防の本義とその強化の提唱』、通称「陸パン」は、統制経済・国家総力戦体制の必要性を説き、日本の経済構造の転換を訴えた。
この提言に対し、財界や自由主義的な知識人からは強い反発が起きた。だが、昭和恐慌に苦しむ農村や中小企業、さらには将来に不安を抱える都市中間層の中には、統制による安定を期待する声もあり、軍の主張は次第に“現実的な選択肢”として受け入れられていく。
◆ 文民政府の脆弱さと「軍による政局支配」
昭和11年の「二・二六事件」に象徴されるように、軍部は武力による政治的影響力を強めていった。同年には「軍部大臣現役武官制」が復活し、軍の推薦なしには内閣が成立しない体制が再び整えられた。これは事実上、軍が政局を左右する権限を握ったことを意味していた。
さらに重要なのは、軍部内部の対立が“暴走”ではなく、ある種の「理想国家像」の追求から来ていた点である。統制派の将校たちは、ナチス・ドイツに倣い、国家改造と総力戦体制によって日本の存続を図ろうとした。彼らは、自由経済の放任では英米に太刀打ちできないと考え、経済戦争への準備こそが“自衛”であると確信していたのである。
◆ 政治家たちの分裂と“沈黙の合意”
政治家の中でも、英米との対立を避けたい穏健派と、軍の主張を容認する妥協派が分裂していた。元老の西園寺公望を中心とした穏健グループは、外交による打開を模索していたが、時代の空気に抗いきれなかった。
その一方で、平沼騏一郎らの強硬派は「国体護持」を掲げ、軍との協調を是とする姿勢を取り続けた。こうした分断の中で、最も顕著だったのは「明確な反対の声を誰も上げなかった」という“沈黙の合意”の広がりだった。多くの政治家は、軍部との対立を避け、保身に走った。
◆ メディアと世論が生んだ「空気」
国民の間でも、戦争を望んでいたわけではなかった。しかし新聞は、経済的困窮や外交的屈辱感を刺激し、対外的な強硬姿勢を歓迎する論調を強めていった。昭和16年の東京日日新聞(現・毎日新聞)の社説では、アメリカの対日政策を「戦わずして日本の国力を消耗せしめる」謀略と断じ、「最短距離の完遂」──すなわち戦争を容認するような論調が現れ始めていた。
こうして、軍部が進める経済戦争路線は、必ずしも“熱狂”ではなく、“空気”によって支持されていったのである。
◆ 経済人・知識人たちの対応
財界の中には、ブロック経済体制下で輸出が激減し、生き残りのために「満洲市場の拡大」や「軍需産業への転換」を受け入れざるを得ない企業が多数あった。結果として、多くの企業が“無言の協力者”と化していく。
一方、知識人の中には、経済制裁を「見えざる侵略」とみなす声もあった。アメリカのケロッグ国務長官は、「経済的に重大な打撃を与える政策も侵略の一種」と認めていたという逸話も紹介され、日本側が自らの行動を“自衛”と考える根拠ともなっていた。
◆ 「選択肢なき選択」へと至った背景
こうしてみると、日本が経済戦争、さらには対米戦争という道を選んだのは、一部の軍部や政治家が独断で暴走したというよりは、さまざまな立場の人々が“現実”に向き合った結果であったことが分かる。
外交の打開策が見いだせない中で、軍の主張する「満洲の経済圏拡大」や「ブロック経済への対抗措置」が、結果的に最も“具体的な選択肢”として浮上したのである。そこには、大義よりも「生き残るための道」があった。
「暴発」ではなく、「追い詰められた選択」であったという見方は、こうした多層的な国内の力学を踏まえると、より現実味を持って理解されるのである。
◆ 次章への展開へ
次節では、いよいよ昭和6年に始まった「満洲事変」と、それに対する国際社会の対応、そして「リットン報告書」の虚構と偏向に焦点を当てていく。果たして日本は「侵略国家」として断罪されるに値する行動を取っていたのか──その実像に迫る。
(第2回 完)
(C)【歴史キング】
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
- {第1回}1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?
- {第2回}世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”
→ 今、このコラムを読まれています - {第3回}満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?
- {第4回}経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本
- {第5回}日独伊三国同盟――なぜ日本はこの道を選んだのか?
- {第6回}山本五十六の苦悩――「戦争では国が滅びる」
- {第7回}皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?
- {第8回}ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造
- {第9回}北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化
- {第10回}南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?
- {第11回}日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談
- {第12回}アメリカの暗号解読――すべては読まれていた?
- {第13回}松岡の誤算とヒトラーの誘惑――“世界再編の夢”とその代償
- {第14回}チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず
- {第15回}ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力
- {第16回}山本五十六、真珠湾を選んだ日
- {第17回}なぜ日本は東南アジアに進出したのか?
- {第18回}白人支配からの解放――「大東亜共栄圏」という理念
- {第19回}現地の証言から読み解く「感謝」と「葛藤」
- {第20回}戦後アジア各国から見た日本の戦い
- {第21回}東京裁判という“戦勝国の正義”
- {第22回}戦後教育に埋め込まれた価値観とは?
- {第23回}GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?
- {第24回}特攻精神と武士道の再評価
- {第25回}「反省」と「誇り」は両立するのか?
- {第26回}歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較
- {第27回}歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと
- {第28回}私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的
- {第29回}日本人が知るべきアジアからの声
- {第30回}100年後も読み継がれるために――「もう一つの昭和史」総まとめ

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。