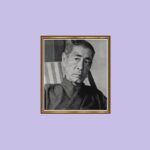第3回 満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?
3-1. 満洲事変とは何だったのか──その背景と動機
はじめに:歴史の分岐点としての「満洲事変」

昭和6年(1931年)9月18日夜、奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路が爆破された事件は、日本と中国の関係、ひいては世界の国際秩序そのものを大きく揺るがす転換点となりました。いわゆる「満洲事変」の始まりです。この事変は日本の軍部が独断で起こしたとも言われ、「侵略戦争の起点」と批判され続けてきました。しかし、本当にそうだったのでしょうか? 本章では、事変に至る背景、関東軍の動機、そして国民や政府、天皇の反応を通じて、その実相に迫ります。
関東軍の動機:ソ連の脅威と「生命線」としての満州
まず前提として、日本が大陸に軍を常駐させていた理由は何か――それは単純な「侵略欲」ではなく、「安全保障上の最前線」という位置づけでした。日露戦争で莫大な犠牲を払いながら勝ち取った「南満州鉄道付帯地」は、日本にとって国防上の生命線であり、経済活動の基盤でもありました。ソ連の南下、共産主義の浸透への恐怖が、軍部にとっては喫緊の課題だったのです。
この状況で満州の治安は著しく不安定化していました。張学良率いる中国東北軍の影響力が増す中、日本人居留民や資産の安全が脅かされる事件も頻発していたことから、現地にいた関東軍幹部は「中央の指示を待っていては間に合わない」と判断し、独断行動に出る素地ができていたのです。
柳条湖事件の真相と「謀略」の構造
満洲事変の引き金となった「柳条湖事件」は、日本軍による自作自演であったという説が一般的に流布されています。実際、現地司令官である板垣征四郎と石原莞爾は、上層部の許可を得ないままに行動を起こし、鉄道爆破を中国軍の攻撃と偽って反撃を開始しました。これは軍法会議にかけられれば死刑に値する重大な統帥権干犯でしたが、結果的に軍上層部も政府もこれを追認し、事変は事実上、黙認されたのです。
しかし注意したいのは、関東軍がこの行動に踏み切った背景には「日本の正当防衛」という意識があったことです。ソ連の脅威、中国の無秩序、国際連盟の鈍さ――こうした複合的要因の中で「自らの国民と領土を守るには先制的に動かざるを得なかった」との考えが支配していたのです。
満洲国の建国と「傀儡」のレッテル
満洲事変の目的は、単に領土を拡大することではありませんでした。石原莞爾らが描いた構想は、「満蒙を独立国とし、各民族の平等な発展を目指す」というものであり、形式上は日本の直轄支配ではなく、自主的な国家を支援するという立場を取っていました。もちろん、実態としては日本の保護国、いわゆる「傀儡政権」としての満洲国であったことは否定できませんが、それは当時の国際政治の中で、他国も同様にやっていた手法でした。
さらに言えば、現地の中国人や満州族の中にも、日本の統治によって秩序や生活が安定することを歓迎した層があったことも見逃せません。この点を無視して、「侵略一辺倒」と決めつける議論は、極めて一面的です。
昭和天皇の反応と「勅語」の重み
満洲事変に対する昭和天皇の姿勢は、当初は慎重そのものでした。関東軍の暴走ともいえる行動に対し、天皇は「拡大せぬように」と何度も伝えています。しかし、事変が進行し、中国軍が次々と撤退し、日本の勢力が広がると、天皇も結果的には「よくやった」との趣旨の勅語を出しています。
これは、政府・軍部・国民が一体となって動く「国策」としての方向性を支持したとも受け取れますが、昭和天皇にとっても葛藤の多い判断だったと推測されます。実際、『昭和天皇独白録』ではこの時期の詳細な心境についての記述はほとんどなく、内心においても複雑な思いがあったと見られています。
国民の熱狂とメディアの加担
驚くべきことに、この事変を最も後押ししたのは、軍ではなく「世論」でした。新聞は一斉に関東軍を礼賛し、「満蒙新秩序」「曠野に咲く新国家」などというスローガンを掲げ、大衆のナショナリズムを煽ります。神社には必勝祈願の参拝者が殺到し、陸軍大臣の元には「血書」の応援状が山積みとなったほどです。
これは単にメディアが軍に利用されたというだけでなく、「不況」「共産主義の脅威」「国際社会の理不尽」に直面していた日本国民の中に、強いリーダーシップと突破力を求める空気があったことを意味しています。つまり満洲事変は、関東軍だけでなく、「時代そのもの」によって生み出された出来事でもあったのです。
おわりに:「侵略」か、「自衛」か――今こそ冷静に問い直すとき
満洲事変は、日本の現代史において「軍部の暴走」の象徴として語られることが多い一方で、当時の安全保障環境や国内事情を踏まえると、単純な「侵略」として断罪することは極めて不正確です。「暴発」ではなく、「計画」でもなく、「追い詰められた選択」であったという認識が必要です。
この事変の評価をめぐる議論は、日本人が自国の歴史をどのように語るべきかを問う、まさに原点とも言える問題です。本連載が、その問いに向き合う一助となれば幸いです。
3-2. 国際連盟の調査団は公平だったのか?
1932年、日本は満州事変をめぐって国際社会から激しい非難を浴びていました。この状況に対応するため、国際連盟は英国のリットン卿を団長とする調査団を日本・満州に派遣し、現地調査を行いました。この「リットン報告書」は、当時の国際政治と日本外交の行方を大きく左右する重要な文書となります。
では、そのリットン調査団は果たして「公平」だったのでしょうか?
「中立調査団」のイメージと現実
リットン調査団は、表向きは「公平・中立」を掲げて派遣されたものでした。団長であるリットン卿は英国貴族であり、他にもフランス、イタリア、ドイツ、中国などからの代表者を含む5名で構成されていました。
しかし、その構成自体に初めから日本は懐疑的でした。なぜなら、各国の代表はすべて「植民地を持つ列強」ばかりであり、中国と同様にアジアに利害関係を持っていたからです。つまり、彼らが果たして「無色透明な第三者」として調査に臨めたのか、という根本的な疑問があったのです。
実際、調査団は現地の状況を約3ヶ月間にわたって視察し、多数の証言や資料を集めました。ところが、その結論は、収集された事実と矛盾する部分が多く、「最初から結論ありきだったのではないか」との批判が、日本国内でも根強く存在したのです。
調査報告書の内容と日本の衝撃
リットン報告書が日本にもたらした最大のショックは、「日本が近代国家として扱われなかった」という心理的屈辱でした。日本は国際連盟の常任理事国であり、第一次世界大戦では戦勝国側として連合国に参加していたにもかかわらず、今回の調査では「欧米列強 vs アジアの後進国」という構図の中に放り込まれたのです。
しかも報告書は、「中国側にも問題がある」としながらも、最終的には日本の行動を「容認できない」と結論づけました。つまり、現地での秩序維持や自衛の必要性を一部認めつつも、「新国家(満洲国)の承認には応じない」「日本軍は満州から撤退すべき」と勧告したのです。
この結論に対し、日本は「法的にも道義的にも、非難される理由が見当たらない」と反論しました。列強は自らの植民地支配は当然の権利として黙認しながら、日本の行動だけを問題視する――このダブルスタンダードに、日本の知識層や国民は深く失望し、怒りを覚えたのです。
「中国の中央政府は存在しない」というリットン報告の記述
注目すべきは、リットン報告自体が「中国には中央政府と呼べるほどの実態は存在しない」と明言していたことです。軍閥が各地を支配し、蔣介石の南京政府ですら「法的擬制(fiction)」にすぎない――そんな国家に対し、「日本の行動は侵略だ」と一方的に断じたところに、報告書の矛盾が浮かび上がります。
この点に対し日本側は、「中央政府と呼べない相手と国際法上の正規な外交が成り立つのか」「中国が無秩序であるからこそ、日本が治安を確保した」と強く主張しました。実際に、満洲では日本軍の進出後、治安が大幅に回復した地域もあったのです。
日本にとって「公平」とは何だったのか
リットン調査団が日本にとって「不公平」と映った最大の理由は、その背後にある「白人列強の論理」でした。彼らは、中国における自国の権益確保が最優先であり、日本の行動がその利権を脅かす限り、それを「侵略」と断じることが都合がよかったのです。
このような構図の中で、日本はリットン報告を「公平な国際裁定」とは受け止められませんでした。それは「事実に基づく審判」というよりも、「既得権益の防衛手段」としての調査だったからです。
一方、調査団の報告には、「中国の後進性」や「共産主義の混乱要素」についても明確な記述があり、中国に対しても厳しい目が向けられていたことは事実です。リットン報告は、日本だけを悪者にしたわけではなく、「中国も問題国家である」と冷静に指摘していたのです。
リットン報告後の国際社会と日本の立場
リットン報告書は1932年10月に国際連盟に提出され、翌年の1933年2月、連盟総会は日本軍に満州からの撤退を求める決議を採択しました。投票は「42対1」、唯一の反対国が日本でした。
この結果を受けて、日本政府は国際連盟からの脱退を決定。松岡洋右全権代表は連盟の場で退場宣言をし、日本は孤立への道を歩み始めることになります。
これは日本外交の敗北とされがちですが、当時の新聞や世論は「よくやった」「これぞ誇りある行動」と称賛し、日本の国際的な地位を自ら守ったとの受け止めも強かったのです。
調査団は本当に公平だったのか――読者への問いかけ
歴史を振り返るとき、「公平」とは一体何なのでしょうか。すべての国が自国の利益を最優先に動く国際政治の中で、「完全な中立」などというものが存在し得るのでしょうか?
リットン報告書は、形式的には中立を装いながらも、実質的には列強の利害調整を優先したものであり、結果として日本の立場を正当に評価したとは言いがたいものでした。
しかし、それでも我々が学ぶべきは、「事実」と「解釈」は別物であるという教訓です。どれほど事実を積み上げても、結論は時に政治的な思惑によってねじ曲げられる。その現実を知ることが、現代における「歴史認識」を鍛える第一歩になるのです。
3-3. 満洲は“侵略”か、“生命線”か──現地の証言とその重み
はじめに:問い直される“侵略”の定義
満洲事変をめぐって、世界は日本に「侵略国家」のレッテルを貼りました。しかし、その評価は果たして妥当だったのでしょうか。本節では、「満洲は日本の侵略によって奪われたのか」それとも「日本が守らねばならなかった生命線だったのか」を、当時の現地の声や国際的な認識を手がかりに検証していきます。
満洲事変当時の現地情勢──統治も秩序も崩壊していた中国東北部
1931年、満洲(中国東北部)は清朝の滅亡以降、軍閥が支配する無政府状態に近い混乱の中にありました。国際連盟のリットン報告書でも、中国に中央政府と呼べる統一的な権力は存在していないことが確認されています。報告書はこう述べています。
「1911年の革命以来、中国では政治動乱、内戦、社会・経済不安が続いている。中央政府と呼べるものは実質的に存在せず、軍閥が割拠し、排外思想と犯罪集団が蔓延している」
つまり、当時の満洲における「国家的統治」は形だけで、実際には各地で匪賊(武装集団)による暴力が横行し、現地住民は生命と財産の危機に晒されていました。この無秩序な状況の中で、日本は満洲における自国民や権益を守るために行動を起こしました。
「日本の生命線」としての満洲
満洲は日本にとって経済的・軍事的にきわめて重要な地域でした。日露戦争でロシアを撃退し、莫大な犠牲と資金を投じて獲得した南満州鉄道や租借地には、日本人労働者や企業が多数進出し、安定した治安と秩序の確保が必要でした。
昭和初期の政治家や軍部は「満洲は日本の生命線である」と繰り返し主張しました。この表現は満鉄の幹部で後に外相となる松岡洋右の発言が起源です。
議会では、「満洲は二十億の国費と十万の同胞の血によって得た地」であり、それを失うことは日本の死活問題であると強く訴えられました。こうした主張はスローガン化され、一般国民の間でも「満洲死守」の意識が広まりました。
満洲に生きた人々の証言──“感謝”と“安定”の記憶
満洲の現地住民の一部は、日本による統治が治安と生活の安定をもたらしたと感じていたことも事実です。
たとえば、当時の農民や商人にとって、日本の鉄道整備や警察制度の導入は日常生活の安全保障につながりました。特に匪賊の排除やインフラ整備によって、農業生産が安定し、教育制度も普及し始めました。
また、日本が設立した「満洲国」では、形式的には清朝最後の皇帝・溥儀を元首に据え、満洲族の自治国家という体裁をとりました。現地では「独立国」としての誇りを持ち、実際に国として機能しようとする動きも見られました。
もちろん、こうした動きが日本の主導による「傀儡政権」であったという批判はあります。しかし一方で、「満洲国は欧米による中国の分割支配よりも、まだ秩序があり、庶民にとっては生活が安定していた」とする声もあるのです。
国際社会の“矛盾”と“偽善”
リットン報告書は、一見すると日本を批判しているように見えますが、内容を精査すると、その中には多くの「矛盾」や「偽善」が見られます。
例えば同報告書は、中国の反外国感情や共産主義勢力の拡大が「世界の不安定要因」になっていると明確に指摘しています。さらに、「中国には中央政府が存在せず、排外主義が建設的改革を遅らせている」と、事実上中国側の不安定さを非難しているのです
。
それにもかかわらず、結論部分では「日本は行きすぎ、中国は遅れすぎ」として双方に責任を負わせ、日本には「撤退」を求めるというバランスを欠いた勧告を行いました。これでは、日本側にとっては到底納得できる報告とは言えません。
それでも「侵略」とされた満洲国
このような現地事情や日本の主張があったにもかかわらず、欧米列強は満洲国を認めず、「侵略国家・日本」という構図を描きました。その理由の多くは、満洲における自国の利権確保と対日包囲網の一環でした。
アメリカやイギリスは、日本が独自に満洲の資源を掌握することを好まず、これを封じ込めるために「道義的批判」という形で日本を包囲しました。日本の行動がどれほど現地の安定に資していても、欧米にとっては「利益の阻害者」でしかなかったのです。
満洲事変とは何だったのか──“生命線”の現実的意味
満洲事変を“侵略”と一言で断じることは簡単です。しかし、当時の東アジアの地政学的状況、満洲の無秩序な現状、現地住民の安定への願い、そして欧米列強の思惑を考慮すると、満洲は単なる侵略の対象ではなく、日本にとっての「生存の場」「秩序の拠点」であったと言えます。
現地の証言や歴史的文脈から見れば、満洲における日本の行動は一方的な「侵略」ではなく、少なくとも「選択肢なき介入」であったことは否定できません。
3-4. 国際連盟脱退、日本の孤立と民意の反応
満洲事変後、国際連盟は日本の行動を問題視し、現地調査団――通称リットン調査団――を派遣した。この調査報告書が提出されたのは1932年秋。そして翌1933年2月、日本政府はついに国際連盟を脱退するという重大な決断を下した。この決断は、国際社会との決定的な決裂を意味するものであり、日本の対外的な孤立を深める結果となった。
では、日本がこの決断に至った背景には、いったいどのような事情があったのだろうか。また、この決断を受けた日本国内の反応はどのようなものだったのか。
#### 不可避だった「退場」の選択
日本政府にとって、リットン報告書が採択される国際連盟総会の場は、すでに勝敗が決していた舞台であった。報告書には満洲国の正統性を否定し、日本軍の行動を「侵略」と断定する内容が含まれており、日本側の主張や事情をほとんど考慮しない形でまとめられていた。
その上、報告書の採択にあたり、欧米列強は事前に水面下で賛同票を固めていたと言われている。1933年2月24日、国際連盟総会にてこの報告書が採択されると、日本の代表・松岡洋右は即座に退場を宣言し、会場を後にした。そして3月27日、日本は正式に国際連盟からの脱退を通告した。
この退場劇は世界に衝撃を与えたが、日本国内ではむしろ一種の痛快さをもって受け止められた。欧米列強による不当な干渉を断固として拒絶したという意味において、多くの国民がこの決断を歓迎したのである。
#### 「孤立」か「自立」か――国内世論の分裂
当時の新聞各紙を見ても、国際連盟脱退を「国辱をすすいだ」とする論調が多く見られた。たとえば、読売新聞は社説にて「列国の不正義に対する毅然たる姿勢を示した」と高く評価し、朝日新聞も「日本の進むべき道を自ら切り拓く覚悟を示した」と論じた。
一方で、知識人や一部の外交官の間では、連盟脱退が将来的な外交的孤立を招くのではないかという懸念もくすぶっていた。特に中国大陸での軍事行動を継続する限り、欧米諸国との関係悪化は避けられず、貿易や経済面での制裁が強まることが予想されていた。
しかし当時の国民感情としては、欧米列強の「偽善」に対する反発が極めて強かった。多くの日本人にとって、連盟脱退は「正義」を貫いた結果であり、むしろ国家としての誇りを取り戻した瞬間であったと言える。
#### 転換点としての連盟脱退
この決断は、日本の対外政策にとって大きな転換点となった。国際協調からの離脱は、以降の日本が軍事的自立路線を突き進むきっかけとなり、英米との関係悪化に拍車をかけることになった。
ただし、国際連盟という枠組み自体が、すでに有効性を失っていたという見方もできる。アメリカはそもそも連盟に加盟しておらず、イタリアやドイツもこの頃から連盟と距離を置き始めていた。つまり、日本の脱退は孤立というよりも、国際秩序の再編の一環であったとも言える。
#### 日本人の記憶に残った「松岡の退場」
松岡洋右が国際連盟の会場から毅然として退場した姿は、映画館でのニュース映像や新聞報道を通じて、全国の人々の記憶に強烈に刻まれた。これは単なる外交辞任の瞬間ではなく、「日本の誇り」を象徴する映像として、戦後も語り継がれることとなった。
この象徴的な場面は、軍事的な拡張路線の正当性を支える“物語”として、大きな影響力を持つようになった。つまり、国際連盟脱退という出来事は、単なる政治判断ではなく、国民的感情と結びついた「歴史的転機」として、昭和史に深く刻まれていったのである。
3-5. なぜ「正当性」を誰も伝えようとしなかったのか
見捨てられた日本の主張
昭和7年、日本が国際連盟に提出した満州事変に関する主張は、単なる弁明ではなく、自国の安全保障とアジアの安定を守るための正当な説明であった。だがその声は、国際社会に届くことはなかった。
リットン報告書は、調査団が実際に収集した事実と矛盾した結論を導き出していた。たとえば、報告書は日本の行動を批判しながらも、中国の実情に関しては、中央政府が事実上存在せず、各地に軍閥が割拠し、共産主義勢力や犯罪集団が支配しているという実態を認めていた
。つまり、中国国内は「秩序ある国家」とは到底言い難い状況であり、その混乱の中に位置する日本の居留民や権益が、たえず脅かされていたことを示している。
だが、そうした背景を考慮せず、「侵略」という一語によって日本の行動が断罪されたことは、日本にとっては深刻な不公平であった。日本側の反論では、自衛のための行動であること、中国側の排外的態度や共産主義勢力の影響が事態を複雑化させていることを繰り返し訴えたが、そうした論点は国際世論に届かなかった。
報じなかった「もう一つの現実」
国内においても、情報の偏りが深刻な問題であった。当時の日本の新聞は、国際連盟脱退に対して「快挙」と持ち上げ、松岡洋右を「英雄」と報じた。だが、その裏で松岡自身は「連盟脱退は外交の失敗である」と自認していたにもかかわらず、その告白すら報道されなかった。
なぜ報じなかったのか。報道機関が国策に迎合し、軍部の意向を忖度し、真実を伝えることを放棄していたからである。新聞の役割が「国民の目」から「国家の喉笛」へと変わった時、日本は言論による正当性の主張を、自ら封じたとも言える。
国民は「世界が日本を不当に扱っている」「我々は被害者である」という感情に駆られ、国際社会を敵視する風潮が強まっていった。この閉塞的な空気の中では、日本がどれだけ冷静に正当性を訴えても、内にも外にも届かなくなっていた。
正当性を伝えるという営み
国際社会においては、ただ正しいことを主張するだけでは、理解されないことが多い。ましてや日本のように、英語を母語とせず、欧米的な外交文化に馴染まない国家にとって、自己の正当性を「翻訳」して伝えることには困難が伴った。
たとえば、リットン報告は、南京政府を「中央政府」と見なす一方で、その実体が無力であることを認めてもいた。日本から見れば、そのような「法的擬制」こそが国際的欺瞞であり、満州国の成立はむしろ現実的な対応だった。しかしながら、そうした論理を伝えるための「国際的発信力」は日本には不足していた。
さらに日本政府は、連盟から脱退する前にこそ、もっと徹底的に自国の主張を国際社会に届ける努力をすべきであった。しかし、そうした姿勢が希薄で、むしろ「分かってもらえないなら付き合わない」という一種の感情的反応に近い脱退決定となったことが、以後の孤立を決定づけた。
「正当性」の空白が生んだもの
正当性を誰も伝えなかった、あるいは伝えきれなかった。その代償は大きかった。以後、日本は軍部主導による外交と戦争の道を突き進むことになる。情報の遮断、国際社会との断絶、そして国内世論の熱狂と排外的ナショナリズムの高まり。すべては、「日本の行動には大義があった」という論点が語られないままに置き去りにされたことの結果である。
日本は「侵略者」としてのイメージを一身に背負いながら、戦後までそのラベルを外すことができなかった。それは、あの時期に「伝える」ことを怠った日本全体の過ちだったのかもしれない。
昭和天皇は、国際連盟脱退に際しても「脱退するまでもないのではないか」と語ったという記録が残っている。
天皇ですら、その決定に懸念を抱いていた。だが政府はすでに進退を賭して決定しており、国内世論もそれを歓迎していた。もはや、誰も止められなかった。
記憶と記録の断絶
後世においても、日本の正当性を客観的に伝える作業はほとんどなされてこなかった。戦後の占領政策、教育制度の変更、メディア統制の中で、満州事変における日本の立場を正しく伝える言説は排除され、「侵略」の記憶だけが強調された。
だが、当時の資料を紐解けば、日本が一方的に悪であったとは言い難い現実が浮かび上がってくる。問題は、その現実を語ろうとする者が少なすぎたことにある。
正当性を語ることは、時に「言い訳」と捉えられるかもしれない。しかし、それでも語らなければ、誤解は訂正されず、レッテルはそのまま定着していく。
歴史とは、語られた記録であり、伝えられた記憶である。だからこそ、誰も語らなかった「正当性」を、いま語る意味がある。
(第3回 完)
(C)【歴史キング】
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
- {第1回}1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?
- {第2回}世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”
- {第3回}満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?
→ 今、このコラムを読まれています - {第4回}経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本
- {第5回}日独伊三国同盟――なぜ日本はこの道を選んだのか?
- {第6回}山本五十六の苦悩――「戦争では国が滅びる」
- {第7回}皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?
- {第8回}ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造
- {第9回}北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化
- {第10回}南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?
- {第11回}日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談
- {第12回}アメリカの暗号解読――すべては読まれていた?
- {第13回}松岡の誤算とヒトラーの誘惑――“世界再編の夢”とその代償
- {第14回}チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず
- {第15回}ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力
- {第16回}山本五十六、真珠湾を選んだ日
- {第17回}なぜ日本は東南アジアに進出したのか?
- {第18回}白人支配からの解放――「大東亜共栄圏」という理念
- {第19回}現地の証言から読み解く「感謝」と「葛藤」
- {第20回}戦後アジア各国から見た日本の戦い
- {第21回}東京裁判という“戦勝国の正義”
- {第22回}戦後教育に埋め込まれた価値観とは?
- {第23回}GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?
- {第24回}特攻精神と武士道の再評価
- {第25回}「反省」と「誇り」は両立するのか?
- {第26回}歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較
- {第27回}歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと
- {第28回}私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的
- {第29回}日本人が知るべきアジアからの声
- {第30回}100年後も読み継がれるために――「もう一つの昭和史」総まとめ

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。