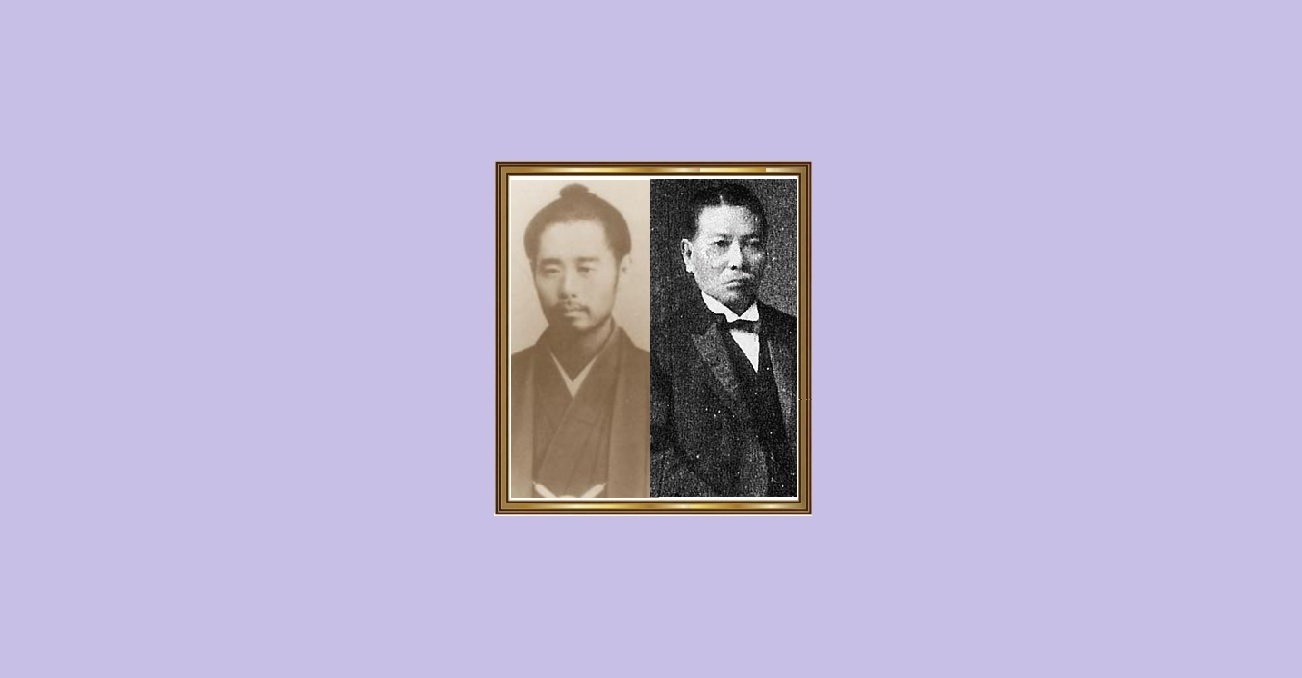11.片寄平蔵、屋井先蔵│父と呼ばれた日本人
🔵産業の近代化から重工業化へのエネルギー基盤を築いた「石炭の父」と世界初の発明を成した「乾電池の父」

福島県│新潟県
明治期の日本は驚異的なスピードで近代産業の基盤を整え、強力な軍事力と経済力をもって近代国家を創り上げました。その際、資源の乏しい日本が何よりも必要としたのは火力(エネルギー)でした。
維新の前夜、人びとを驚かせた黒船の煙突から出る黒煙は石炭を燃やした煙です。そのメカニズムを知った笠間藩の用達を務める材木商・片寄平蔵は、「石炭の火力は薪の比ではない。石炭の産出場所を見つければ、国の富源となり、計り知れない利益を生む」と考え、湯長谷藩領の弥勒沢で石炭の露頭を発見、1857(安政4)年に石炭からコールタール(油)の製造に成功します。以後この地域で、京浜工業地帯の重工業化に石炭を供給する常磐炭田(現在の福島県富岡町から茨城県日立市付近にかけて存在した大炭田)が発展しました。片寄が「石炭の父」と呼ばれるゆえんです。
翌年、軍艦操練所での訓練に使用する石炭3000俵の納品を命じられ幕府御用商人となった片寄は、横浜一の石炭貿易商として名を馳せ、横浜のまちづくりに尽力します。ところが、当時の貿易商は攘夷派の志士たちから命を狙われていました。片寄も郷里への帰途、浪士の刃に倒れます。のちに横浜の商人たちから神として祭られ、「片寄神社」が建立されたと伝わっています(所在地は不明)。
その後、20世紀にかけて電力の時代が到来するわけですが、電力の効率的利用において乾電池の発明が有益だったことを忘れてはなりません。世界で初めて乾電池の特許を取得したのは、ドイツのガスナーとデンマークのヘレセンですが、その数年前に乾電池を発明した日本人がいました。「乾電池の父」と称される屋井先蔵(さきぞう)です。
屋井は故郷の新潟県長岡と東京の時計店での奉公を経て独学を続け、16歳のときに動力なしで動く永久自動機械を考案します。1885(明治18)年に屋井乾電池合資会社を設立し、1891(明治24)年に「連続電気時計」でわが国初の電気に関する特許を取得しました。この間、乾電池の製造を始め、安全で携帯に便利なマンガン乾電池の発明に成功したのです。
1893(明治26)年、シカゴ万国博覧会に出品された東京帝国大学製の地震計には「屋井乾電池」が使われます。これを見た世界の人びとは驚愕し、模造品の外国製乾電池が日本市場を席巻します。屋井は特許を取得していなかったのです。転機は日清戦争のときに訪れます。屋井乾電池が極寒の中国大陸でも通信用電源として作動することが報道され、爆発的に売れたのです。その後、改良品の本格量産によって屋井乾電池は生産量日本一を誇り、屋井は「乾電池王」と呼ばれました。
屋井が発明した乾電池は、筒型の金属ケースを使った現在と同じ形状のものでした。屋井は電気機械の専門教育を受けていませんが、dry battery(drycell)という言葉は日本語の乾電池を英訳したものであり、もともと英語にはなかったと強く主張したそうです。この気概が、世界の科学者たちに勝る快挙を成し遂げる原動力だったのでしょう。
(C)【歴史キング】

(角川文庫 う 21-2) 文庫 – 2011/4/23
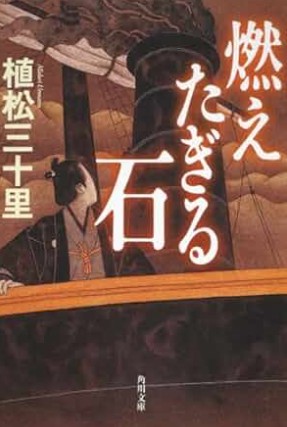
鎖国下の日本近海に異国船が頻繁に姿を現し、材木商・片寄平蔵は木材需要の儲け話を耳にする。が、江戸湾に来航したペリー艦隊には、「燃える石」が燃料として渡されたと聞き、平蔵は常磐炭坑開発に取り組む。

乾電池王とよばれた男 ─ 屋井先蔵の生涯 / 上山 明博 (著)
(電子書籍) Kindle版
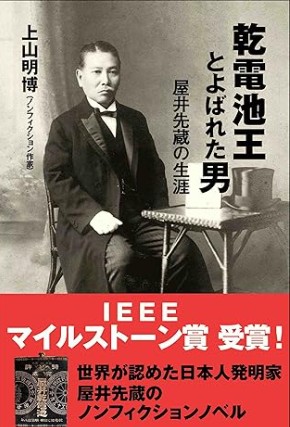
本コンテンツは、2014年4月、乾電池を発明した屋井先蔵が、世界最大の電気電子学会であるIEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.:米国電気電子学会)からマイルストーン賞を受賞したのを記念して、それまで入手不可能となっていた『白いツツジ —「乾電池王」屋井先蔵の生涯』上山明博 著、PHP研究所 刊 の待望の復刻(Kindle)版です。