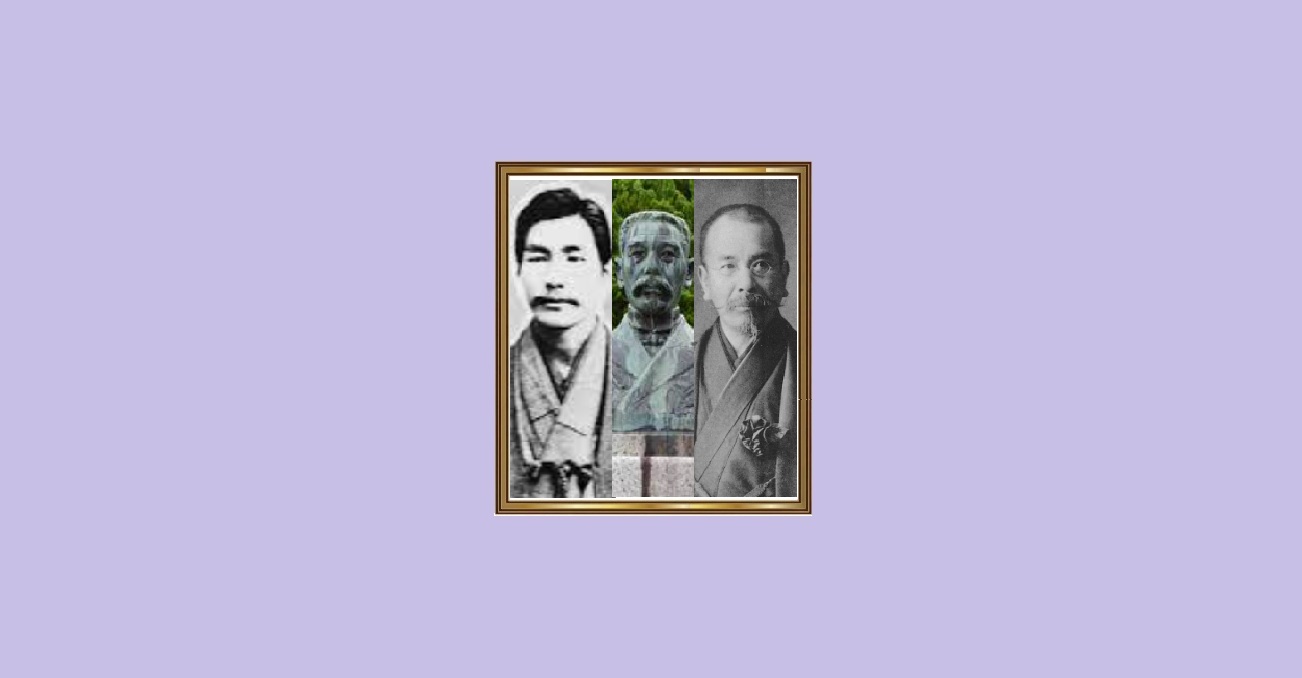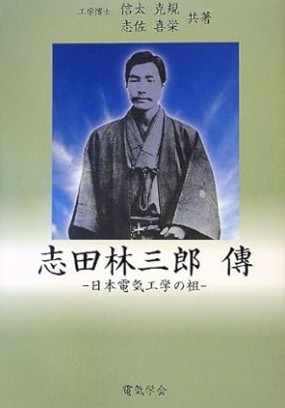13.志田林三郎、小花冬吉、辰野金吾│父と呼ばれた日本人
🔵電気工学、鉱業、近代建築の各分野で「父」と称される工部大学校第1回卒業生

佐賀県│東京都│佐賀県
1873(明治6)年、殖産興業政策を支える工部省管轄の専門教育機関、工部大学校(前身は工学寮)が開校しました。6年の全寮制で、イギリスから招聘した教師が指導に当たった同校は、電気工学、土木、建築などの諸分野で先進的技術者を輩出します。その第1回卒業生である志田林三郎は、日本の電気工学士第1号で最初の工学博士です。佐賀藩の官費給付生で、工学寮在学中の成績は常にトップ、数々の表彰を受け電信科を首席で卒業しました。彼の秀才ぶりは官費留学したイギリスのグラスゴー大学でも発揮され、物理学の大家、ケルビン卿(ウィリアム・トムソン)に師事し、「数ある教え子のなかのベストスチューデント」と言わしめます。帰国後は工部省技官を経て工部大学校教授に就任。1888(明治21)年に創設された電気学会の第1回総会で「将来可能となるであろう十余のエレクトロニクス技術予測」と題した演説を行い、高速多重通信、長距離無線通信、海外放送受信、光通信など、今日の無線、映像(テレビ)、録音などに通じる電信・電気技術の出現と高度情報化社会を予言しました。
36歳の短い生涯でしたが、後進たちは、電気工学の道筋を示し、実現しうる未来技術を先見した彼を「日本電気工学の父」と称えました。
2人目の「父」は、幕臣の三男で江戸生まれの小花冬吉です。小花は工部大学校を卒業後、イギリスで冶金学を修めます。帰国後は工部省鉱山局に出仕し、1887(明治20)年に渡仏して製錬技術を習得すると、「殖産振興、富国強兵」の実現には官営製鉄所の創設が急務であると元勲たちに説いて回ります。その後、八幡製鉄所の初代製銑部長、東京帝国大学教授などを経て、ドイツのフライベルク鉱山大学を範とする鉱業学校の設立に奔走します。そして、秋田鉱山専門学校(現在の秋田大学理工学部)の初代校長として後進の指導に当たりました。小花が、「鉱業界の父」と称されるゆえんです。
「日本近代建築の父」と称される辰野金吾は唐津藩の出身です。工部大学校造家科(現在の東京大学建築学科)でジョサイア・コンドルに師事し、首席で卒業。官費留学したロンドン大学では、コンドルの師、ウィリアム・バージェスの下で学びました。帰国後は工部大学校教授を経て独立し、6年の歳月をかけて日本銀行本店を完工しました。ベルギー国立銀行を参考にした辰野独自の設計は、日本の代表的バロック建築の威風をいまに伝えます。1914(大正3)年に竣工した東京駅も辰野の代表的建築ですが、当時はコンクリート建築への移行期にあり、煉瓦づくりの外観の評判は芳しくありませんでした。ちなみに、関東大震災でコンクリート建築の多くは崩壊しますが、東京駅はびくともしませんでした。
1919(大正8)年、世界中で猛威を振るったスペイン風邪に罹患し、辰野は64年の生涯を閉じました。彼が手がけた建築は、奈良ホテル、京都文化博物館別館など、日本各地で目にすることができます。
(C)【歴史キング】