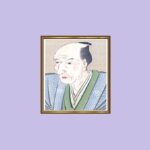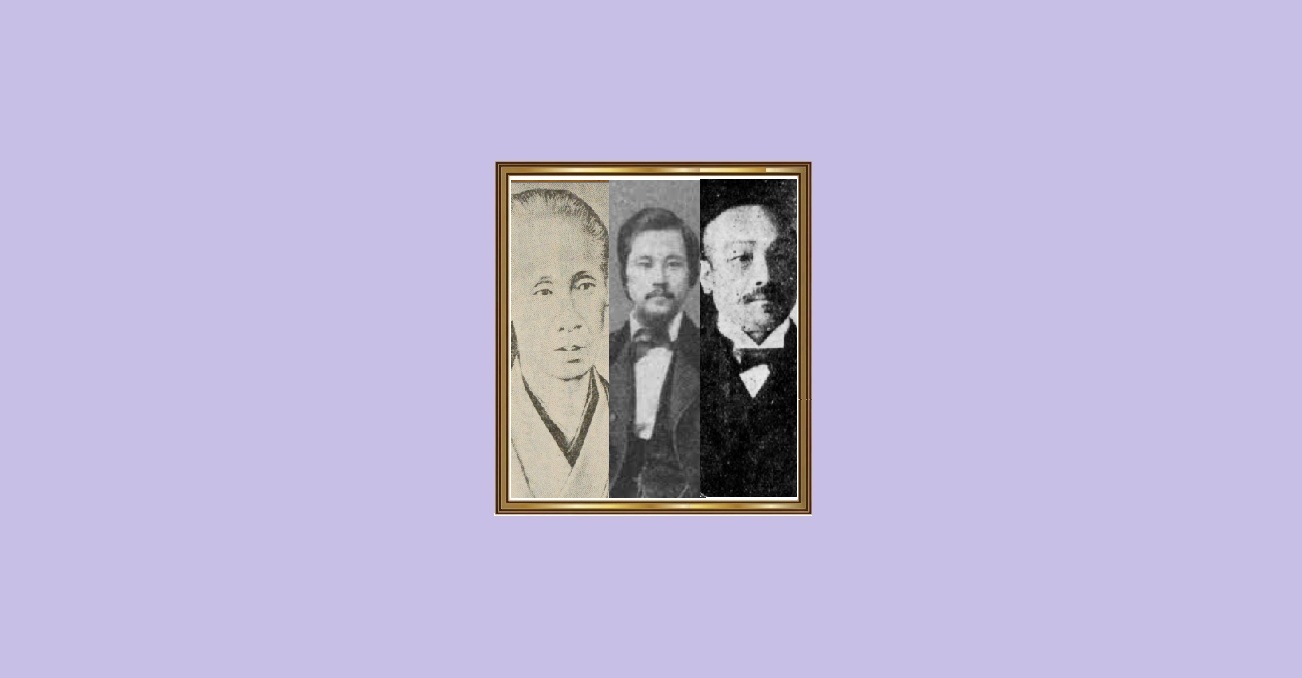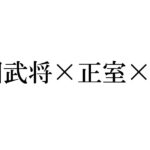
15.本木昌造、ジョセフ・ヒコ、岩谷松平│父と呼ばれた日本人
🔵新しい産業を生み出した「近代活版印刷の父」「新聞の父」「近代日本のPRの父」

長崎県│兵庫県│鹿児島県
明治初期には衣食住のあらゆる分野で西洋化が急速に進み、人びとの生活が劇的に変化しました。なかでも日本で最初の西洋式活版印刷といわれる「流し込み活字」の製造は、社会に大きな影響を与えました。
長崎出身の本木昌造は、1869(明治2)年、長崎製鉄所(現・三菱重工長崎造船所)付属の活版伝習所を設立し、金属活字の鋳造に成功します。その後、開発した明朝書体の号数活字のシステムが今日の活字文化の基礎となったことから、「近代活字の父」「近代活版印刷の父」と呼ばれています。1868(慶応4)年に発行した『崎陽雑報』の印刷技術は、日本最初の日刊紙『横浜毎日新聞』の創刊に生かされました。
これに先立ち、「日本国新聞発祥之地」という記念碑が立つ現在の横浜中華街で、『新聞誌』(のちの『海外新聞』)を発行した人物がいます。播磨国(兵庫県)出身のジョセフ・ヒコ(浜田彦蔵)です。
14歳のとき、江戸見物からの帰りに紀州沖で船が遭難して漂流、アメリカ商船に救助されたジョセフ・ヒコは、アメリカ市民権を取得した日本人第1号です。帰国後は英語新聞を訳した日本最初の新聞を月2回、100部を24号まで発行。市民の知る権利に情熱を注ぎ、「新聞の父」の名をゆるぎないものにしました。
ジョセフ・ヒコは、3人の大統領と正式に謁見し、エイブラハム・リンカーン大統領とは握手まで交わした唯一の日本人です。また初めて英語による自伝を著すなど、多くの「日本人初」の偉業を成し遂げました。1897(明治30)年に61年の数奇な生涯を閉じますが、当時は国籍法がなかったため日本人としての埋葬はかなわず、「ジョセフ・ヒコ」として青山霊園外国人墓地に眠っています。
新聞に代表される明治初期の世俗の変化を「文明開化」と表現したのは福沢諭吉だといわれています。文明開化は新しい産業を生む原動力でした。その一つがたばこの国産化です。煙管(きせる)から紙巻きたばこへの変化により、1884(明治17)年に発売された国産の「天狗煙草」は爆発的に売れました。
仕掛け人は「明治のたばこ王」岩谷松平です。薩摩藩出身の岩谷は、西南戦争後に呉服反物店を開きますが、派手な新聞広告で国産の葉たばこを扱う商社として急成長。アメリカ葉を取り入れた「ヒーロー」を商う村井吉兵衛と、たばこが専売制になる1904(明治37)年まで激しい商戦を繰り広げました。
岩谷は、「国益の親玉・東洋煙草大王」と大書した看板を掲げ、赤装束で赤い馬車を乗り回して大声で宣伝したり、本店の屋根から壁までを真っ赤に塗って大天狗面を掲げたりして、人びとの度肝を抜きました。宮中での宴にも全身赤の装いで参内し、明治天皇が「あれは何者か」と尋ねたそうです。これを聞いた岩谷は、「商一位大薫位功爵国益大妙人、岩谷松平」と宣伝に利用しました。
斬新なアイデアで商品広告のあり方を変え、印刷技術の発展にも影響を与えた岩谷は、「近代日本のPRの父」と呼ばれています。
(C)【歴史キング】