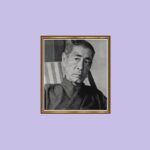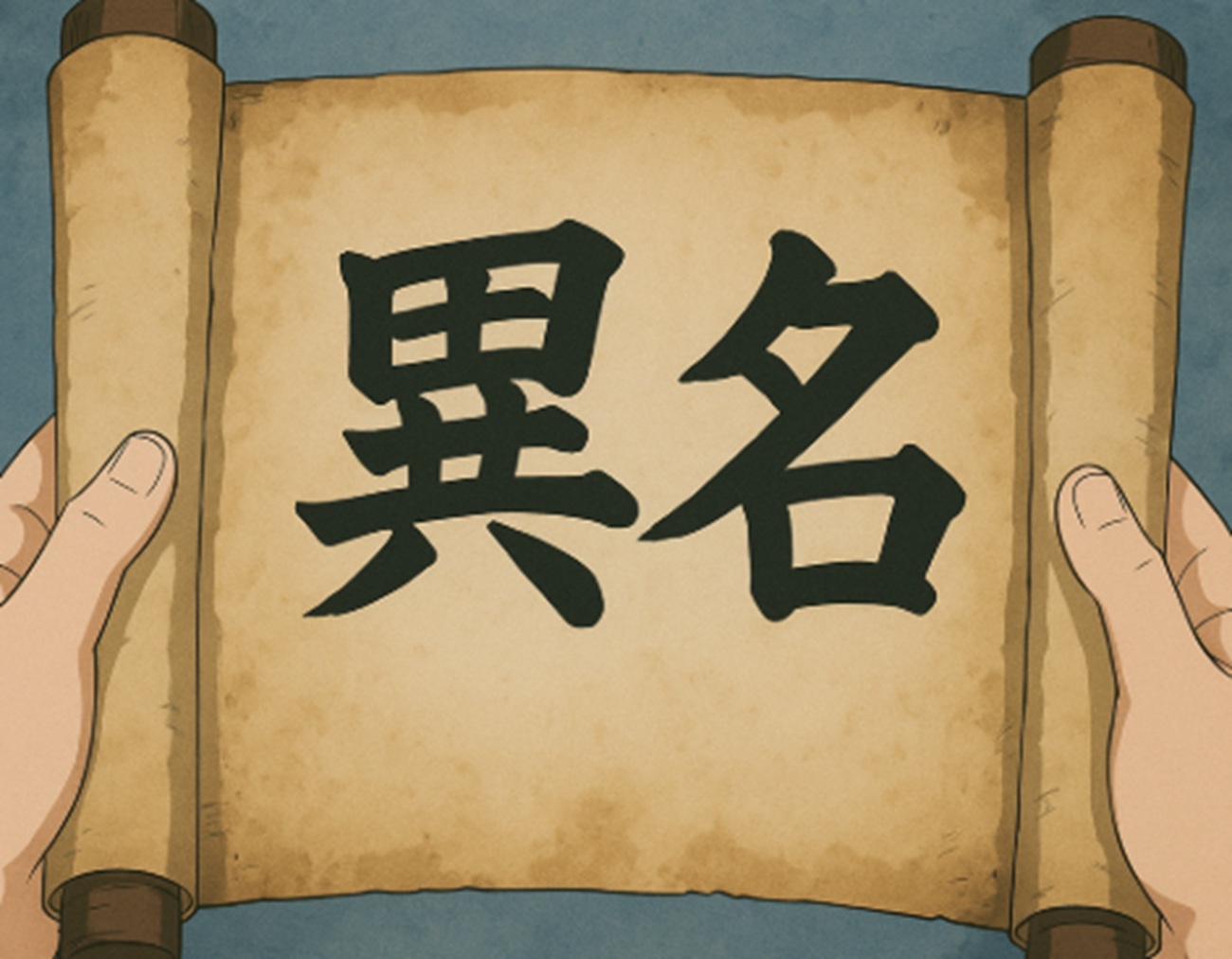{異名}を持つ、戦国武将たち

これからどんどん更新していくので、絶賛【途中】段階です💦
🔴今川家
{海道一の弓取り}{東海一の弓取り}今川義元
【海道=東海】は地名のことで、弓取りは、当時がまだ弓矢で戦うといった手法であったことから【弓取り=武士】といったニュアンスでした。戦国最強武将と言えば、武田信玄の名前が挙がりますが、信長に敗れるまで、義元は優れた政治力と軍事力で、東海道一帯を支配下におく、最強候補の戦国武将でした。そう、あの日、あの時、あの場所までは。
🔴上杉家
{越後の虎}{越後の龍}{軍神}上杉謙信
いずれの異名も、上杉謙信が戦に才能に秀ででおり、無類の強さを誇っていたことに起因します。【虎】は本名「長尾影虎」からきていると考えられ、【龍】は旗印(みだれ龍)からきていると言われています。また、謙信が、闘神である毘沙門天を崇拝していたことから、【軍神】とも称されています。
🔴織田家
{第六天魔王}{尾張の大うつけ}織田信長
『仏教の修行を妨げる悪魔、天上にいる悪魔』のことですが、比叡山焼き討ちの際に、人々が勝手に恐れ、畏怖したのではなく、信長自らが、この異名を用いたとされています。また、武田信玄との書状のやりとりで、ここでも自ら「第六天魔王」と署名したと言われています。{大うつけ}は、若い頃に奇抜な服装や行動で周囲を驚かせていたことから、ネガティブな意味合いで{たわけ者}のような意味で、そう呼ばれていたと言います(信長公記)。
{戦国一の美女}お市の方
織田信長の妹とされるが、出生、幼少期の頃の記録がなく、従妹であるという説もある。戦略結婚により、最初は浅井長政の元へ嫁ぎ、茶々(淀殿)、初(常高院)、江(崇源院)の三姉妹を授かる。後に兄・信長を激怒させた夫・長政は、攻め込まれ浅井家は滅ばされることになるが、お市の方は浅井家と生死を共にする決意だったと言われる(夫・長政が逃がした)。その後、柴田勝家の元へ嫁いだが、今度は秀吉との激突によって敗北。娘たちだけを逃がし、37歳という若さで自害を選択した。{戦国一の美女}は、戦国時代の荒波にのまれた波乱万丈ともいえる生涯であった。
{キンカン頭}{キンカ頭}明智光秀
「きんかん」は柑橘類の「金柑」を連想させ、人肌で赤く光った禿げ頭を思わせます。信長が容姿いじりでそう呼んでいたのかもしれませんが、明智光秀の肖像画を見ても、実際に禿げていたのかはわかりません。
{鬼柴田}{かかれ柴田}柴田勝家
織田信長の父・信秀の頃から織田家に仕えていた古株で、戦に定評があった猛将。一方で情に厚い面もみられ、それが彼の良さであったが、信長亡き後、その一面がマイナスにもはたらき、秀吉に敗れることとなった
🔴豊臣家(織田家)
{さる}{禿げ鼠(はげねずみ)}豊臣秀吉
容姿が猿に似ていたとされ、そのように呼ばれることはあっても、ニックネームや異名のようなかたちで定着することはありませんでした。ドラマ等で織田信長が呼んでいる{さる}も創作ネタであり(呼んでいた可能性はゼロではないが、記録が残っていない)、実際は{禿げ鼠(はげねずみ)}ともっと酷い名称で呼んでいました(笑)しかし、これも、秀吉の妻である【ねね】に送った手紙に書いてあった呼び名であり、普段からそう呼んでいたかは定かではありません。
{天才軍師}{築城の名手}黒田官兵衛
羽柴秀吉(豊臣秀吉)に仕えた武将・軍師。秀吉の重臣であったので、元々は織田家に仕えており、信長亡き後、豊臣家家臣となった。戦では【兵糧攻め】や【水攻め】などの戦術に長けていた。また加藤清正、藤堂高虎と共に{三大築城名手}とも称された
🔴斎藤家
{美濃の蝮(みのうのまむし)}斎藤道三
【出生時の身分】が大きすぎる影響を及ぼす戦国時代において、1番の下剋上を達成したのは、やはり豊臣秀吉ではないでしょうか。なんせ天下人になっていますからね。それに次ぐのは斉藤道三かと思います。元々は一介の油売りでしたが、主君の謀殺や乗っ取りといった調略で国盗りを果たしましたが、その手法から、マムシと恐れられました
{槍の才蔵}{笹の才蔵}可児吉長(通称:可児才蔵)
槍の名手として知られ、最初の主君・斎藤龍興から、→柴田勝家→明智光秀→前田利家→織田信孝→豊臣秀次→佐々成政→福島正則と、多くの武将に仕えたことでも知られる。{笹の才蔵}の異名は、笹の指物を背負って戦い、敵の首を獲った後で、首の切り口に入れておいた(あるいは口にくわえさせた)ことから、そのように称された。
🔴真田家
{日本一の兵(ひのもといちのつわもの)}真田幸村
真田幸村の名前で知られているが、真田信繁(さなだ のぶしげ)が本名である。異名の由来は大坂夏の陣。元々の戦での戦果と、後の征夷大将軍徳川家康を少人数で追い込んだその活躍がそのように評される要因となった
🔴武田家
{甲斐の虎}武田信玄
優秀な家臣を多く抱えて、騎馬隊の精鋭部隊を率い、数々の戦で圧倒的な成果を挙げていたことから、群雄割拠の戦国時代において【最強】と謳われていたのが武田信玄が率いる頃の武田家でした。その勇猛果敢な戦いぶりを【虎】に例えられ、統治国である【甲斐の国】と合わせて、その名がついたと言われています。
{武田四天王}馬場信春、内藤昌秀、山県昌景、春日虎綱
戦国時代において、全国各地にその名を轟かせた武田家ですが、その優秀な家臣の中から、特に目立った存在であったのが、前田、鬼塚、薬師寺、葛西・・・いや、馬場信房(馬場信春)、内藤昌豊(昌秀)、山県昌景、高坂昌信(春日虎綱・高坂弾正)の4名であった。また、信玄の父・信虎と、信玄初期時代では板垣信方、甘利虎泰、飯富虎昌、小山田昌辰(虎満)の4名を指すと考えられる
🔴伊達家
{独眼竜}伊達政宗
幼少期に右目の視力を失い、隻眼となってしまいました。政宗の師である僧侶「虎哉宗乙」(こさいそういつ)から唐(中国)の猛将・李克用を教えられ、政宗は彼に自身を重ね合わせ、奮い立たせたと言われています。しかし遺言で「自分の死後に絵画や像を残すときには両眼にして欲しい」と残しており、本心としては最後までコンプレックスであったのではないかということが伺えます。昭和49年10月に瑞鳳殿を再建するために、338年ぶりに政宗の遺骨や数々の遺品が発掘されたが、それによって身長は約159.4センチ、血液型はB型であったことがわかった。尚、この時の貴重な映像は大河ドラマ【独眼竜政宗】の第1話の冒頭にて見ることができる。
{伊達三傑}片倉景綱、伊達成実、鬼庭綱元
奥州の覇者となった伊達政宗に仕え、その中で特に大きな力となった、片倉景綱、伊達成実、鬼庭綱元の3名を指します。【智】の景綱、【武】の成実、【吏(役人)】の綱元として政宗を支えました
{伊達の双璧}片倉景綱、伊達成実
【伊達三傑】と称された3名の中から、片倉景綱、伊達成実の2名の名を挙げ、こう呼ばれることも多い。才智に優れ、内政・謀略で力を存分に発揮した景綱と、圧倒的な武力によって数々の武勇を築いた成実の活躍は、伊達家の中でも群を抜いていた。ちなみに大河ドラマ【独眼竜政宗】にて、奥州を制覇した後で、それに満足せずに即座に関東に攻め込もうと政宗の展望を聞き、「殿は昇り竜じゃ!これかは殿を」
{鬼の小十郎}片倉重長
伊達政宗の側近中の側近であった、片倉景綱の子。政宗亡き後も、忠宗、綱宗と伊達家3代にわたって仕えた。大阪夏の陣などの戦果から、父・景綱に劣らぬ智勇兼備の名将として恐れられたと言われています。
{守成の名君}伊達忠宗
伊達政宗の子で、伊達氏18代当主。異名は、戦国時代は終わり、江戸幕府が誕生したが、仙台藩の地位と基盤固めに務めて大いに功績を残したことに由来する。
🔴徳川家
{海道一の弓取り}{狸親父}徳川家康
戦国時代において【海道=東海】は地名のことで、東海道を制覇した弓取り(武士)の優れた武将を指した異名は2名の戦国武将が手にしている。今川義元と、徳川家康である。家康は人質として今川家で過ごしていたが、義元亡き後、東海を制したのは家康であった。また、その老獪な政治的手腕から「狸親父」と揶揄された異名もある。
{徳川四天王}酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政
最終的に天下人となり、江戸幕府を開いた徳川家康に仕えて、家康を支えた代表的な家臣である、清水アキラ、ビジーフォー、栗田貫一、コロッケ・・いや、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の4名のことを指します
{赤鬼}井伊直政
🔴北条家
{伊勢新九郎}{早雲庵宗瑞}北条早雲
{伊勢新九郎}{早雲庵宗瑞}は、早雲が名乗った名前であり、異名とは意味合いが少し違う。以下も“異名”ではないが、北条早雲は、一介の素浪人という出生でありながら、一代で一国の主となり、関東に北条王国を築き上げた人物であることから、【戦国武将の先駆け・パイオニア的存在】と言われている。
{相模の虎}{相模の獅子}北条氏康
{甲斐の虎}が武田信玄なら、相模(神奈川県)の虎は、関東を長らく統治した氏康だ。戦や、外交・内政といった政治力、城の改築などと、あらゆる分野に秀でた能力を持っており、名将・名君の一人に数えられる優れた武将。
🔴最上家
{虎将(こしょう)}{羽州の狐}{奥羽の驍将}最上義光
南羽州に勢力を広げ、縁戚である伊達輝宗・政宗らと争った。老骨な知略や戦いから、数々の異名を持つが、最上義光歴史館によると『義光の官職名・左近衛少将(さこのえごんしょうしょう)の唐名である虎賁中郎将(こほんちゅうろうしょう)にちなんだものが虎将であり、義光の異名のうち最も古いものといわれている』ということらしい。
🔴その他
{剣聖}塚原卜伝(つかはら ぼくでん)
日本の史実を振り返ってみても、【最強クラス】の呼び声の高い剣豪で、信長が、ほぼ全国を統一する少し前に活躍した人物。同じく{剣聖}と称される上泉信綱は、直系ではないが、塚原の門下と言える。どちらも異常すぎるほど強いという伝説の持ち主であるので、どちらが強いかは皆さんの想像にお任せしたい。
{剣聖}上泉信綱(かみいずみ のぶつな)
日本史実の最強剣豪五本指にも入るであろう【最強候補】の一人で、先述の塚原卜伝と並び、最強論議に度々登場する。新陰流の開祖であり、自身の驚くべき強さもさることながら、それを多くの弟子たちに伝承していったため、日本剣術史に彼が与えたとされる影響はとてつもなく大きい。塚原卜伝がドラゴンボールのカカロットなら、上泉信綱は孫悟空といったところか。
{天下七兄弟}丹羽山城(助兵衛)、谷出羽、笹野才蔵、稲葉内匠、中黒道随、渡辺勘兵衛、辻小作
義兄弟の誓いをし、武勇に励んだことから、以上の7名を指して、そのように呼ばれたという説がある(江戸時代中期の『常山紀談』)