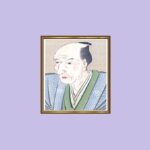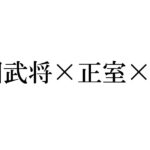
北海道の「父」たち part.4 ~農業の「父」たち~
🔵「男爵薯の父」川田龍吉
日本のじゃがいもの代表品種である「男爵薯(だんしゃくいも)」は日本全国にその味が知れ渡っていますが、北海道のじゃがいも栽培の三割以上の作付面積を誇るこの「男爵薯」の栽培を成功させ、北海道農業の近代化のために尽力したのが「男爵薯の父」と称される川田龍吉(かわだ りょうきち・1856~1951)です。
三菱財閥の創設者・岩崎弥太郎の盟友で後に日本銀行総裁となる土佐藩郷士・川田小一郎(かわだ こいちろう)を父にもつ龍吉は、イギリスで造船技術を学んだ後、函館ドッグ(現函館どつく)の再建のため北海道に渡り、実業家としての手腕を発揮するかたわら、趣味の園芸にもいそしみ、別荘と農場を買い求め、農業の研究も続けました。
すでにその頃の北海道では馬鈴薯(じゃがいものこと)の生産が盛んでしたが、明治二十年代以降、全道的に馬鈴薯の病害、虫害が発生し、全滅するほどの被害を受けていました。この被害を何とかしたいと考えた龍吉は、函館ドッグ勤務の傍ら、欧米から農業専門書を取り寄せて研究します。そして病害虫に強い不死身の馬鈴薯の新種に関する記事をみつけ、この新種をアメリカから取り寄せ、七飯村(現北海道亀田郡七飯町)の農場で試作します。
この試作実験を続けていくと病害虫に強いだけでなく生育期間も短く、夏の短い北海道にも適し、二毛作も可能という優れた品種であることがわかると、この種いもを分けてほしいという人が続出し、たちまち全道に普及しました。
龍吉は、函館ドッグを退職したあとも東京へは戻らず、残された生涯を北海道農業近代化のためにささげることを決意し、当別(現北斗市当別・男爵資料館)に千二百町歩ほどの農場を建設します。アメリカ製の農機具を多数輸入するなど最新の農業設備を導入し、機械化による農業を試み、畑作から酪農、乳製品作りを行いました。このおかげで1913年(大正2)の大飢饉の際には、近隣の住民が食料難を乗り切ったと伝えられています。いつしか農民たちは、龍吉の普及させたジャガイモを「男爵いも」と呼ぶようになりました。龍吉が「男爵薯の父」と呼ばれる所以です。
🔵「北海道稲作の父」中山久蔵
日本人の主食である米ですが、北海道は寒冷地のため近代に入るまで稲作は行われませんでした。明治時代に入り、北海道ではじめて稲作を成功させ、「北海道稲作の父、寒冷地稲作の父」と呼ばれているのが中山久蔵(なかやま きゅうぞう・1828~1919)です。
40歳を過ぎてから北海道に入植した久蔵は、外国人顧問団の稲作に否定的な意見を採用していた開拓使の方針に逆らい、島松(現北広島市島松)で稲作に果敢に挑みます。苦心の末に函館から移植した赤毛種から島松地方に適した地米を作り出し、「中山種」として広く知れ渡ります。
石狩、空地、上川地方の移民へ種もみを無償で配布し、また、北海道庁の民間農業指導員として北海道各地の農民の指導にもあたり、「中山種」は北海道の代表的な品種となります。
🔵「大正金時の父」奥村喜十郎
北海道で栽培されている「いんげんまめ」のうち約7割を占めるのが金時豆です。なかでもよく知られているのが「大正金時」という品種で、粒の大きさ、皮の柔らかさ、味の良さから煮豆に最も適した豆として評価が高いものです。
この品種は、福井県から大正村(現帯広市)に入植した奥村喜十郎(おくむら きじゅうろう・1902~1979)が、昭和初期に幕別村(現幕別町)で「金時」という品種を栽培している畑の中から突然変異の早生・大粒の1株が発見されたのを大正村で量産化に成功させたものです。
冷害と闘う北海道の農民たちにとって、最も成長の早いこの豆は希望の星となり、喜十郎は「大正金時の父」と呼ばれています。
🔵「ホクレンの父」小林篤一
農村の経済的窮乏は産業組合によって救うべきであるとし、協同組織の育成に尽力したのが、兵庫県から美唄市に入植した小林篤一(こばやし とくいち・1890~1972)です。
1915年(大正4)峰延信用購買販売利用組合(現峰延農業協同組合)を設立しますが、さらに全道的な組合連合体の必要性を痛感して北海道信用購買販売組合連合会(現ホクレン農業協同組合連合会)の結成にも尽力、のちに会長に就任します。
農産物の付加価値を高めるために農民自らが工場を持つべきとの信念から、ビート糖(テンサイ糖)工場を建設し、また、米麦、畜産などの他の加工事業の充実も図りホクレンの今日の発展の基礎を築きました。
1962年(昭和37)には、参議院議員となり北海道開発政務次官なども務め、北海道農業の振興に心血を注いだ篤一は「ホクレンの父」「農協組織育ての父」と呼ばれています。