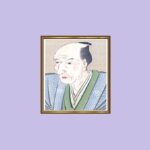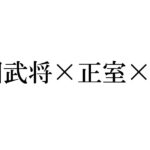
北海道の「父」たち part.5 ~水産業の「父」たち~
🔵二人の「北洋漁業の父」
人生において人と人との出会いによって運命が決まることが少なくありません。「北洋漁業の父」と呼ばれる二人の水産業界の先駆者―堤清六(つつみ せいろく・1880~1931)と平塚常次郎(ひらつか つねじろう・1881~1974)の出会いも二人の運命を、そして日本の北洋漁業の運命をも決定付けたと言っても過言ではありません。
二人が出会ったのは、1906年(明治39)、ロシアの黒龍江下流のブロンゲ岬です。清六26歳、常次郎25歳での偶然の出会いでした。すでに北洋漁業の魅力とりつかれていた常次郎は、ここに出漁に来ていました。一方の清六は、対ロシア貿易を行うための調査に来ていたのです。清六は、常次郎のもとで三日間を過ごし、語り合います。常次郎からこれまでの境遇や北洋漁業の魅力を聞かされた清六は、感動し、北洋での漁業開発がきわめて有望な事業であると確信します。常次郎ともすっかり意気投合し、北洋での漁業を一緒に行うことを誓い合い、再会を約束して別れました。これが業界史では伝説となっている二人の出会いです。
故郷新潟に一旦帰った清六は、両親や親戚を説得し資金を調達し、約束どおり常次郎と新潟で再会を果たし、堤商会を設立します。そして二人は新潟を出港しカムチャッカ海域へ初出漁を行い、北洋漁業への第一歩を踏み出しました。堤商会はその後、日魯漁業(現マルハニチログループ)へと発展していきますが、旧ニチロでは、このときの二人の初出漁のときをもって会社創業と位置づけているそうです。
以後、二人は一心同体となって北洋漁業に従事し、会社をまとめあげていきます。カムチャッカ産の紅鮭を缶詰にして輸出するという方針を打ち出し、当初は手工業的な缶詰生産だったものをアメリカから最新の缶詰機械を購入し、ほぼ完全自動の生産体制へ切り替えるなど、当時としては革新的な経営判断を行い、清六はとくに政治力に長けていたといわれています。
こうして、堤商会は世界屈指の缶詰企業に成長し、さらに世界有数の水産会社・日魯漁業へと発展させていくのですが、その近代的・革新的な経営手法から清六らは、わが国最初の資本主義漁業家との高い評価を受けているのです。 二人の男の運命的な出会い、北洋に夢を賭けたロマン、傑出した先見的・近代的経営手法など、堤清六の人生を彩るこれらの出来事や夢や手法は、どれも大変刺激的です。
函館出身の常次郎は、豪商として函館四天王の一人に数えられた平塚時蔵の甥にあたります。一家でエトロフに移住し、現地の高等小学校を卒業後、札幌露清語学校(後に東京外国語学校に統合)でロシア語を学びますが、学制改革により退学、間もなく徴兵されて入隊、日露戦争に出征し、旅順攻撃や奉天大会戦に参加します。有名な二百三高地の攻撃では、味方の半ば以上が戦死しますが常次郎は運良く生き残りました。この直後に、清六との運命の出会いを果たすのです。二人が、一心同体となって北洋漁業に邁進していったのは前述の通りです。また、二人の関係は仕事上だけのものではなく、常次郎の妻は清六の妹で、血縁関係にもありました。そんな清六が52歳の若さで急死します。「二人は血縁としてだけではなく、事業の上でも全く一個の人格に等しかっただけに、私は身も魂も抜けたような空虚を感じた」と常次郎は語り、二人の結びつきがいかに強かったかがわかります。
しかし、清六の遺志を引き継ぎ、日魯漁業の社長となり、北洋漁業の覇権を手中に収めていきます。その後、敗戦によって日本の漁業は壊滅的な打撃をうけます。なんとか再建の道筋を示しますが、「日魯の再建はすべて日本の再建につながっている」との思いから政治を志します。戦後初の総選挙で衆議院議員に立候補し初当選、日魯漁業の副社長でもあった河野一郎と行動を共にし、第一次吉田内閣で北海道出身者としては初入閣し、運輸大臣を務めました。GHQにより公職追放処分を受けますが、追放解除後政界に復帰、同時に日魯漁業社長にも再就任し、北洋漁業の再建に尽力しました。
常次郎の娘さんは、父・常次郎や母(清六の妹)によく聞かされたことがあるそうです。
「このようにいろいろと自分が世の中に出るようになったけど、そのことは、自分ではなく堤清六が本当は全部やるべき事であったのに、まさか52歳で死んだから、私がその任を負い、番がまわってきたのだ」と。
北洋漁業は、運命的な出会い以後、一心同体となって夢を追い求めた二人の男たちによって開拓されたのです。彼らふたりが「北洋漁業の父」と呼ばれる所以です。
人工孵化と放流事業の先駆者
札幌農学校第1期生としてクラーク博士から直接指導を受けた伊藤一隆(いとう かずたか・1859~1929)は、卒業後開拓使に採用され、1886年(明治19)に北海道庁が発足すると初代水産課長に任ぜられて渡米します。孵化場や水産事情を視察して、帰国後の1888年(明治21)に、千歳川でサケの人工孵化放流事業を始め、1896年(明治29)には、アメリカで目にした捕魚車(インディアン水車)を千歳川に導入するなど、日本の人工孵化放流事業の先駆者で、「日本水産の父」と称されています。タレントの「しょこたん」こと中川翔子は玄孫にあたるそうです。
ホタテ養殖の草分け
和歌山県出身の木下虎一郎(きのした とらいちろう・1903~1966)は、水産講習所(現東京海洋大学)を卒業し、神奈川県水産試験場、和歌山県水産試験場を経て1934年(昭和8)北海道水産試験場に勤務します。サロマ湖でカキの種を採る試験をしていたところ、カキがつかずにホタテの稚貝が付着したことを発見し、これにヒントを得てホタテ採苗が始まり、サロマ湖は、ホタテの名産地として知られるようになり、ホタテは今では「栽培漁業の優等生」とも呼ばれています。ホタテガイの増殖法だけでなく、コンブの増殖法、ワカメの人工採苗法、スサビノリの新養殖法など、北海道の地勢、気象、海況など特殊事情を考慮し、水産増殖上極めて有益な研究を行い、浅海増殖の権威者として高く評価された虎一郎は「北海道水産増殖の父」と呼ばれています。
釧路港発展の立役者
日本有数の水揚高を誇る釧路港を築き上げ、「釧路水産の父」と称されているのが嵯峨久(さが ひさし・1876~1960)です。日露戦争後に海洋漁業に乗り出した久は、室蘭を本拠にトロール漁業に着手しましたが失敗します。釧路に移り、1914年(大正3)まぐろ漁業に発動機船「喜久丸」を導入して成功をおさめ、「釧路発動機組合」を組織して「機船漁業の始祖」とも「まぐろの神様」とも呼ばれました。漁獲物を生産者で値建てすべく仲買人が支配していた市場を買収して、現在の釧路魚卸売市場に発展させ、また、釧路川の開削、港の拡大、休養施設の建設のほか、冷凍・缶詰工場を建設するなど、釧路港の近代化に貢献しました。