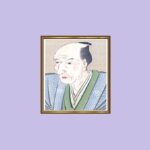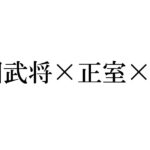
第8回 ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造
8-1. ヒトラーとスターリンの電撃的提携
昭和初期、日本は国際社会の荒波の中で孤立を深めていた。その同じ時期、遠くヨーロッパでもまた、大きな激震が走っていた。1939年8月23日、ドイツとソ連が突如として不可侵条約を結んだ。ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラーと、ソビエト連邦のヨシフ・スターリン――正反対の思想を掲げていたはずの二人の独裁者が、まるで水と油が一瞬で混じり合うように、手を結んだのだ。
この出来事は、単なる「戦争前夜の一外交協定」にとどまらず、世界の力学を一変させる衝撃の瞬間だった。そして何より、日本の外交戦略に致命的な影響を与えることになる。
■ 世界を驚かせた「悪魔の抱擁」
1939年当時、ナチス・ドイツは欧州制覇を狙い、ポーランド侵攻を準備していた。しかしその東側には、共産主義の大国・ソ連が控えている。ドイツがポーランドを攻めれば、ソ連との戦争は避けられないというのが大方の見方だった。
一方、スターリンはスターリンで、ドイツの膨張主義に不安を覚えていた。だが、ここで二つの野心が交差する。互いに警戒しながらも、互いを利用することに決めたのだ。これが「独ソ不可侵条約」の本質だった。
この条約は、名目上は「互いに戦争を仕掛けない」という協定だが、実態は違った。裏には秘密議定書が存在し、ポーランドを分割し、バルト三国やフィンランドなどの勢力圏まで事細かに取り決められていた。まさにヨーロッパの地図を勝手に書き換える「悪魔の密約」であった。
■ 「共産主義 vs. ファシズム」の虚構
当時、日本を含む多くの国々は、国際社会の対立軸を「自由主義 vs. 全体主義」「民主主義 vs. 共産主義」と見なしていた。しかしこの独ソの提携は、それらの枠組みがいかに脆弱で、表層的なものであるかを浮き彫りにした。
なぜなら、世界に衝撃を与えたのは、共産主義とナチズムという、あまりにも異質な二大思想が、利害の一致のもとに、あっさりと手を結んだという事実だった。
日本では当時、ナチス・ドイツに対するある種の幻想があった。「共産主義の防波堤」としてのドイツの存在に期待が寄せられていたのだ。しかしそのドイツが、よりによって最大の共産主義国家と提携した。これによって日本の「対ソ抑止としての対独協調」は一気に崩壊することになる。
■ 日本外交への衝撃――松岡洋右の苦悩
独ソ不可侵条約の報は、日本政府にとってまさに青天の霹靂だった。日独伊三国同盟への道筋を描いていた外務省、特にその中心にいた松岡洋右にとっては、まさに寝耳に水の出来事だった。
三国同盟の前提には、「共産主義に対抗するファシズムの連携」という構図があった。しかしその一角を担うはずのドイツが、突然その“仮想敵”と手を組んだのだ。これにより、日本の外交方針は根底から揺らぐ。
国内でも、この条約をめぐって大きな混乱が生じた。ソ連を敵視していた陸軍の一部では対ソ強硬論が強まる一方で、和平路線を模索する海軍勢力は、事態を静観しつつ方向転換を探っていた。
■ ポーランド分割と第二次世界大戦の引き金
1939年9月1日、ドイツ軍はポーランドに侵攻し、わずか2週間後にはソ連も東側から侵攻した。つまり、独ソ不可侵条約の裏で合意されていた“分割計画”が現実になったのである。
このポーランド侵攻は、英仏の対独宣戦という形で、第二次世界大戦の幕を切って落とす。そしてここでもまた、日本は蚊帳の外に置かれた。表向き同盟国だったドイツは、条約交渉の段階から日本に一切の相談をしておらず、日本は「利用されるだけの存在」であることを痛感させられる結果となった。
■ 日本の誤算と戦略的孤立
独ソ不可侵条約の締結によって、日本の北進戦略は完全に頓挫した。1939年には、ノモンハン事件という大規模な軍事衝突で、ソ連軍との直接対決が行われたばかりだった。
その最中に、ドイツがソ連と提携したという事実は、日本にとって「二重の敗北」ともいえるものだった。軍事的敗北と外交的敗北――それは日本の指導層に深刻な影響を与え、以後の「南進論」への転換の契機ともなる。
■ 再確認される“現実主義”の必要性
この出来事を通じて、私たちが学ぶべきことは何か。それは、国家の論理が“理想”ではなく“現実”によって動かされているという冷厳な事実である。
独ソ不可侵条約は、「敵の敵は味方」といった単純な論理では説明できない複雑な力学を含んでいた。日本もまた、この複雑な国際政治の中で、自らの立ち位置を見誤った結果、外交的にも軍事的にも孤立していったのである。
ヒトラーとスターリンが交わしたこの一握の握手は、20世紀の歴史を大きく変えた“悪魔の契約”だった。その衝撃の余波は、日本にも深く影を落とし、以後の選択を決定づけていくことになる。
8-2. ヨーロッパの勢力地図が激変
昭和14年(1939年)8月、世界を驚愕させる大事件が発生した。宿命的な敵対関係にあったはずのナチス・ドイツとソビエト連邦が、突如として手を結んだのである。後に「独ソ不可侵条約」と呼ばれるこの協定は、単なる不可侵の約束にとどまらず、東欧諸国の分割を定めた極秘の取り決め(秘密議定書)を含んでいた。まさに「悪魔と悪魔が握手を交わした瞬間」であり、この一手が、ヨーロッパの勢力地図を根底から覆すことになる。
■ ポーランドの運命を決した密約
独ソ不可侵条約が結ばれたわずか1週間後、ドイツ軍はポーランドに侵攻した。開戦は1939年9月1日。この日こそが、第二次世界大戦の火蓋が切られた日である。
ヒトラーはこの時点で、すでに英仏との対決を覚悟していた。しかし、それでもポーランド侵攻を決断できた最大の要因は、背後のソ連が中立を保つ、いやそれどころか共にポーランドを分割占領することが、事前に合意されていたからである。
つまり、東からソ連が、西からナチス・ドイツが侵攻するという“挟み撃ち”の構図が、極秘裏に準備されていたのだ。
■ ソ連の“中立”という名の侵略
独ソ不可侵条約が世界に与えた衝撃は計り知れない。とりわけ、これまで「反ファシズム」を掲げていたソ連が、突如としてナチス・ドイツと手を組んだことは、世界中の左派・共産主義者にとっても裏切りであった。
そして、ソ連はただ中立を保っただけではなかった。9月17日、ドイツ軍の進撃から遅れること約2週間、ソ連軍もまた東方からポーランドへ侵攻したのである。これは明らかな武力行使であり、国際法的に見れば“侵略”そのものであった。
さらにソ連は、バルト三国(リトアニア、ラトビア、エストニア)やフィンランドへの軍事圧力も強めていく。のちの「冬戦争」へと発展する一連の動きは、ヨーロッパ全体の勢力図を一変させるものとなった。
■ ヨーロッパ列強の反応と困惑
ドイツによるポーランド侵攻に対して、イギリスとフランスは即座に「対独宣戦布告」を行った。だが、ソ連の侵攻に対してはどうだったか。
意外にも、イギリスもフランスも、ソ連に対しては宣戦布告をしなかったのである。これは、当時の国際政治における“敵と味方”の見えにくさを物語る現象であった。
イギリスとフランスにとって、最大の敵はヒトラーであり、スターリンのソ連に対しては一定の“利用価値”があるとの思惑があったとも言われている。だが、結果的にこの判断は、ヨーロッパの地図とパワーバランスを大きく狂わせる結果となった。
■ バルト三国の併合と“緩衝地帯”の形成
1940年に入ると、ソ連はさらに強硬な手に出た。バルト三国を形式上は「友好条約」の名目で圧迫し、次々に占領。名目上は「自発的な加盟」という形式をとりながら、実質的には武力と脅迫によって自国領に組み込んでいった。
これは「緩衝地帯の形成」という大義名分があったとはいえ、実際には帝国主義的な領土拡張政策に他ならなかった。しかもこれが、アメリカやイギリスから強く非難されることはなかった点にも注目すべきである。
■ “不可侵”条約の皮肉な結末
こうして独ソの密約により分割されたポーランドをはじめ、東欧の国々は国家としての主権を奪われ、多くの国民が粛清、追放、民族移動といった過酷な運命に巻き込まれていった。
だが、皮肉なことに、この不可侵条約そのものが長く続くことはなかった。1941年6月、ヒトラーは突如としてソ連に対する侵攻作戦(バルバロッサ作戦)を開始。スターリンはこれを予測していなかったわけではないが、ドイツとの“密月”がここに終わりを迎えることとなった。
この独ソ戦の勃発が、第二次世界大戦の帰趨を決定づける最大の転機となるのだが、それは次節で詳しく述べることとしたい。
■ 日本から見た独ソ協定の衝撃
日本にとっても、この独ソ不可侵条約は衝撃だった。というのも、日本は当時、ソ連とは満州(現・中国東北部)を挟んで緊張状態にあり、ドイツとは防共協定を結ぶ“同盟国”という立場であった。
そのドイツが、突如としてソ連と手を結んだことで、日本の対ソ外交戦略は大きく揺らぐこととなる。この影響についても、今後の章で詳しく分析していく予定である。
ヨーロッパの勢力地図が、わずか数カ月の間にここまで大きく塗り替えられるという激変。その背後には、ヒトラーとスターリンという二人の独裁者の冷酷な計算と、当時の国際社会の“見て見ぬふり”があった。
歴史はときに、大国同士の思惑によって、無数の人命と国家の運命が踏みにじられることを教えてくれる。だからこそ、私たちはその背景を丁寧に見つめ、次代への教訓とせねばならないのである。
8-3. 日本の外交戦略に与えた衝撃
1939年8月23日に締結された独ソ不可侵条約は、遠く離れた日本にとって、まさに青天の霹靂でした。ナチス・ドイツとソビエト連邦という、思想的にも軍事的にも相容れないはずの両国が手を結んだという事実は、日本の外交戦略、特に「日独伊三国同盟」を推進しようとしていた勢力に壊滅的な打撃を与えました。この密約が日本にもたらした衝撃と、その後の外交路線の転換について掘り下げていきましょう。
「対ソ防波堤」という幻想の崩壊
当時、日本の一部勢力、特に陸軍の強硬派は、ドイツを「共産主義ソ連に対する防波堤」と見なしていました。1936年に締結された日独防共協定も、ソ連の脅威に対抗するための連携という側面が強く、日本はドイツとの関係強化を通じて、北方における安全保障上の優位を確立しようとしていたのです。
しかし、独ソ不可侵条約は、この「対ソ防波堤」という日本の期待を根底から覆しました。共産主義のソ連とファシズムのドイツが手を組んだことで、日本の対ソ戦略は宙に浮き、ドイツを頼りに対ソ圧力をかけるという構想は一夜にして瓦解したのです。この状況は、日本の指導層に深刻な焦燥感と不信感をもたらしました。
松岡洋右外相の困惑と「複雑怪奇」
独ソ不可侵条約の報は、当時外相ではなかったものの、後に三国同盟を推進する松岡洋右にとって、大きな衝撃でした。彼は「日独伊ソ四国協商」という壮大な世界構想を抱いていましたが、その前提となる日独ソの協調が、ドイツとソ連の密約という形で、日本の知らないところで進められていたことに困惑しました。この情報を受けた日本の外務省や軍の反応は、「驚天動地し狼狽し憤慨し怨恨する」といったものでした 。平沼騏一郎内閣が「欧州の天地は複雑怪奇なる新情勢を生じましたので」という言葉を残して総辞職したのは、この衝撃の大きさを物語っています 。
この出来事は、国際政治が日本の想像以上に複雑で、各国の「国益」が、イデオロギーや建前をはるかに超えて優先される現実を突きつけました。当時の日本の指導者たちは、世界の裏側で何が起こっているのかを全く把握できていなかったことを痛感させられたのです 。
ノモンハン事件との皮肉な連動
独ソ不可侵条約が締結された1939年8月は、ちょうど満洲国とモンゴル人民共和国の国境地帯で、日本軍(関東軍)とソ連・モンゴル連合軍との間で大規模な軍事衝突「ノモンハン事件」が勃発し、泥沼の戦いを繰り広げていた時期でした 。日本側は多大な損害を被り、この敗北が陸軍に「対ソ連戦の困難さ」を認識させる大きな要因となります 。
このノモンハンでの苦戦の最中に、同盟を期待していたドイツがソ連と手を結んだことは、日本にとって二重の裏切りと屈辱感を伴うものでした。ソ連がドイツとの条約を締結した背景には、極東の日本を牽制し、ヨーロッパ戦線に集中したいというスターリンの冷徹な計算があったとされます 。まさに、日本がソ連と戦っている間に、そのソ連がドイツと手を組み、日本は利用される形になったのです。
「南進論」への決定的な転換
独ソ不可侵条約は、日本の外交戦略を「北進(対ソ)」から「南進(対英米蘭)」へと転換させる決定的な契機となりました 。北方でのソ連の脅威が一時的に後退したと見なされたことで、日本の目は、石油やゴム、錫といった資源が豊富な東南アジアへと向けられることになります 。
しかし、この南進政策は、必然的に東南アジアに広大な植民地を持つイギリス、オランダ、そしてフィリピンを支配するアメリカとの正面衝突を意味しました 。独ソ不可侵条約は、日本が「避けるべき戦争」である対ソ戦から、より避けがたい「総力戦」である対米英戦へと向かう道を加速させてしまったという皮肉な結果をもたらしたのです。
天皇の懸念と「不信」
昭和天皇は、独ソ不可侵条約の締結について強い不信感を示し、平沼首相に対して「反英運動はなんとか取り締まることはできないのだろうか」と、当時の排英的な世論を憂慮する発言をしています 。また、後に近衛文麿首相が三国同盟締結を報告した際には、「私の子孫の代が思いやられる」と、長期的な国家の行く末を案じる言葉を漏らしています 。これは、ドイツという信頼できない相手との同盟が、将来的に日本を破滅へと導くのではないかという天皇の深い懸念の表れでした。
しかし、こうした天皇の懸念や一部穏健派の意見は、陸海軍の強硬な推進、そして「バスに乗り遅れるな」という当時の国民的熱狂の中で、押し流されていきました 。
歴史の教訓:国際関係における「真の意図」
独ソ不可侵条約が日本に与えた衝撃は、国際関係の複雑さと、各国の「真の意図」を見抜くことの難しさを教えてくれます。表面的な友好や同盟の裏には、常に冷徹な国益計算が潜んでおり、それを読み誤れば、国家は大きな代償を払うことになります。
日本がこの密約から学んだ教訓は、「イデオロギーや建前ではなく、現実の力関係と国益を冷静に見極めること」の重要性でした。しかし、その教訓を活かす間もなく、日本はさらなる大きな決断を迫られることになります。独ソ不可侵条約は、日本が最終的に太平洋戦争へと向かう道を、決定的に方向づけた出来事だったと言えるでしょう。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。