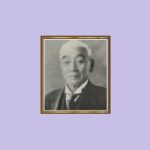第11回 日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談
11-1. 日ソの“電撃和解”の裏事情
「北進」か「南進」か、日本の戦略的苦悩
1940年(昭和15年)9月に締結された日独伊三国同盟は、日本をドイツ・イタリアとの枢軸国陣営へと引き込み、アメリカ・イギリスとの対立を一層深めることになりました。しかし、この同盟締結には、日本側の複雑な思惑が絡んでいました。特に、当時の日本の外交方針は「北進」と「南進」の間で揺れ動いており、ソビエト連邦(ソ連)との関係は依然として日本の安全保障にとって最大の懸念材料でした。
満洲国を挟んでソ連と国境を接する日本は、1939年のノモンハン事件でソ連軍の近代的な火力と機動力の前に苦戦を強いられ、対ソ連戦の困難さを痛感していました 。この経験から、陸軍内部では「対ソ連戦は時期尚早であり、北には手を出さない」という空気が強まり、対照的に東南アジアへの資源獲得を目指す「南進論」が台頭していました 。
このような状況で、日本は「南進」を有利に進めるためにも、北方の安全を確保する必要がありました。そこで浮上したのが、長年の宿敵であったソ連との関係改善、すなわち「日ソ中立条約」締結の構想でした。
松岡洋右外相の「電撃外交」
日ソ中立条約締結の立役者となったのが、当時の外務大臣・松岡洋右でした。彼は国際連盟脱退の立役者でもあり、対外強硬派として知られていましたが、同時に「日独伊ソ四国協商」という壮大な世界再編の夢を抱いていました 。
松岡は、1941年(昭和16年)3月から4月にかけて、ヒトラーとの会談のためにドイツを訪問しました 。その帰途、モスクワに立ち寄り、長年の懸案であったソ連との交渉に臨みます。この時、松岡はスターリンが会談に応じてくれるとは予想していなかったと言われています。しかし、スターリンは予想に反して松岡との会談に応じ、二人の間で「電撃的な会談」が行われることになったのです。
この会談の裏には、スターリンの冷徹な計算がありました。当時、ソ連はドイツの東方進出に強い警戒感を抱いており、ヨーロッパ方面での潜在的な脅威が高まっていました。このような状況で極東の日本との間で戦争となることは、ソ連にとって二正面作戦を意味し、避けたかった事態でした。そこでスターリンは、日本との関係を安定させ、ヨーロッパでの動きに集中するため、日ソ中立条約の締結に積極的だったのです。
秘密裏に進められた交渉とスターリンの「甘い言葉」
松岡とスターリンの会談は異例の速さで進み、1941年4月13日、モスクワで「日ソ中立条約」が調印されました。この条約は、互いの領土保全と不可侵を尊重し、一方の締結国が第三国から軍事行動の対象となった場合、他方の締結国は中立を保つという内容でした 。有効期間は5年間という異例の長さでした 。
この条約は、当時の日本の国民や軍部にとって「北からの脅威が薄れた」という大きな安心感をもたらしました 。松岡は有頂天になり、スターリンがモスクワ駅で見送りに来た際には、肩を抱きながら「お互いにアジア人だからなあ」と語りかけたというエピソードも残っています 。また、スターリンは日本大使館付の海軍武官に対し、南進政策に乗り気だった日本海軍の思惑を読み取ったかのように、「これで日本は安心して南進できますなあ」と声をひそめて語ったといいます 。
しかし、このスターリンの「甘い言葉」の裏には、ドイツがソ連に侵攻する可能性を予見していたという冷徹な戦略がありました。ソ連は日本との中立条約を結ぶことで極東の安全を確保し、対独戦に全力を集中する準備を着々と進めていたのです。日本側は、ソ連が日独伊三国同盟の存在を無視してまで中立条約を結んだことを、ソ連がドイツを恐れている証拠と見て、自らの外交的勝利だと錯覚した側面がありました。
日本の誤算と「外交の恐ろしさ」
日ソ中立条約の締結は、日本にとって北方の安全を確保し、南進政策を加速させるという点で一時的な「外交的勝利」に見えました。しかし、実際にはこれは大きな「誤算」でもありました。
条約締結からわずか2カ月後の1941年6月22日、ドイツはソ連への侵攻を開始します(バルバロッサ作戦) 。これにより、「日独伊ソ四国協商」という松岡の夢は、まさにこの瞬間に雲散霧消し、ソ連はイギリス・アメリカと手を組む連合国の一員となったのです 。
皮肉なことに、日本はドイツとソ連のどちらかが有利になるように動くと、国際情勢が大きく変化するということを理解できていませんでした。ドイツは日本との同盟を、ソ連に対する牽制の道具としか考えておらず、日本に何ら相談することなくソ連に侵攻したのです。これは、国家間の条約や協定が、常に「国益」という冷徹な論理に基づいて一方的に破棄されうるという、国際外交の「恐ろしさ」を日本に突きつけるものでした 。
天皇の懸念と「見れども見えず」の現実
昭和天皇は、独ソ不可侵条約の締結当時から、ドイツへの不信感を抱いていました 。日ソ中立条約が締結された後も、日本の外交がドイツとソ連という二つの強大な国に振り回されていることに懸念を抱いていたかもしれません。
当時の日本の指導者たちは、国際社会の動きを「見れども見えず、聞けども聞こえない」状態にあったと評されています 。国内の「空気」や「独善的な思い込み」に囚われ、現実を冷静に分析する視点を欠いていたのです。日ソ中立条約は、日本が「北は安全になった」と安堵し、さらなる南進へと突き進むきっかけを与えましたが、その裏では、対米英開戦という、より大きな、そして敗北必至の戦いへと追い込まれる布石が打たれていたのでした。
この日ソ中立条約の舞台裏は、国際政治における情報の重要性、そして「自国の思い込み」がどれほど危険な結果を招くかを示す、痛切な歴史の教訓と言えるでしょう。
11-2. 松岡の交渉力と評価の分裂
“国民的英雄”松岡洋右の登場
日ソ中立条約の締結は、当時の日本の外交において、極めて異例かつ劇的な出来事でした。その中心にいたのが、外務大臣・松岡洋右です。彼は国際連盟脱退の立役者として、既に国民の間では「国辱をそそいだ英雄」として高い人気を誇っていました。その強硬な姿勢と弁舌は、閉塞感に苦しむ当時の日本人にとって、まさに希望の光のように映っていたのです 。
松岡は、単なる外交官というよりも、確固たる世界観と大胆な行動力を持つ「政治家」でした。彼は、来るべき世界は英米中心の既存秩序と、日独伊枢軸国を中心とする新秩序とに二分されると見ており、日本が後者の主導的役割を担うべきだと考えていました。日独伊三国同盟も、この壮大な世界再編構想の一環として推進されたものです 。
ヒトラーとの会談、そしてモスクワへの電撃訪問
1941年(昭和16年)3月、松岡は日独伊三国同盟の強化と自らの世界構想を実現するため、ベルリンへ向かいました。ヒトラーとの会談では、ドイツがイギリスを打倒し、ソ連が中立を保てば、アメリカは日本と戦う気力を失うだろうという、ある種の希望的観測を語り合ったとされます 。この会談で、松岡はヒトラーから「シンガポール攻撃」を促される場面もありましたが、明言を避けています 。
ベルリンでの会談を終えた松岡は、帰途にモスクワに立ち寄るという“電撃的な行動”に出ます。長年の宿敵であったソ連との交渉は、日独防共協定を締結していた日本にとっては、本来であればあり得ないことでした。しかし松岡は、自らが提唱する「日独伊ソ四国協商」の実現に向け、スターリンとの直接交渉に踏み切ったのです 。
スターリンを動かした松岡の“交渉術”と、その裏にある思惑
松岡とスターリンの会談は、誰もが予想しなかった「日ソ中立条約」の締結へと繋がりました 。この電撃的な和解は、松岡の“交渉力”の賜物と称賛される一方で、その裏にはスターリンの冷徹な計算がありました。
スターリンは当時、ドイツがソ連に侵攻する可能性を予見しており、二正面作戦を避けるためにも極東の安定を求めていました。松岡がソ連との関係改善を強く望んでいたことを察知したスターリンは、巧みに松岡を利用し、ソ連の対独戦に備えるための時間稼ぎと極東からの兵力引き抜きを可能にする条約締結に成功したのです 。松岡はスターリンから「これで日本は安心して南進できますなあ」と声をかけられ、これを真に受けて有頂天になったとも言われています 。
しかし、日ソ中立条約の締結は、日本が北方の脅威から解放され、安心して南進政策を推進できるという、大きな誤解を生むことになります。実際には、アメリカは日本の外交暗号をすでに解読しており、この松岡とスターリンのやり取りから、日本の南進政策が確実なものになっていることを把握していました。そして、それが後のアメリカによる対日経済制裁強化へと繋がっていくことになるのです 。
松岡の評価の分裂と「狂人外交」のレッテル
日ソ中立条約の締結は、日本国内では「松岡外交の勝利」として大きく報じられ、松岡は“国民的英雄”としての地位を確固たるものにしました。新聞各紙は松岡を礼賛し、「今日、日本にこれほどの英雄はない」とまで持ち上げました。しかし、一方で理性的な層からは、この外交成果がもたらす危険性を指摘する声も上がっていました。
特に、ドイツがソ連と不可侵条約を結んだことへの日本国内の衝撃が冷めやらぬ中、今度は日本がソ連と中立条約を結んだことに、外交の論理が破綻しているという批判も生まれました。永井荷風は、この一連の動きを「初より計画したる八百長」と皮肉り、「以後軍部の専横益甚しく世間一層暗鬱に陥るなるべし」と記しています 。
昭和天皇もまた、松岡の外交姿勢に強い不信感を抱いていました。『昭和天皇独白録』には、「松岡は二月の末に独逸に向い四月に帰って来たが、それからは別人の様に非常な独逸びいきになった、おそらくはヒトラーに買収でもされてきたのではないかと思われる」という、辛辣な言葉が残されています 。天皇は、松岡の外交が、日本の国益よりも個人の名誉や夢想に傾いているのではないかと危惧していたのです。
松岡は「世界は力だけが動かす」という信念の持ち主であり、その強硬な外交は、既存の国際秩序に挑戦する日本の姿勢を象徴していました。しかし、彼の行動は時に過剰な自信や、国際情勢の客観的な分析の欠如からくる「独りよがり」な側面も持ち合わせていました。結果として、松岡は「狂人外交」と揶揄されることもあり、彼の交渉力は、評価が大きく分かれることになります。
外交の理想と現実の乖離
松岡洋右の外交は、日本の国際的孤立を打破し、新しい世界秩序を構築するという壮大な理想に燃えていました。しかし、その理想は、当時の日本の国力や、各国が自国の利益を最優先する冷徹な国際政治の現実とは乖離していました。日ソ中立条約は、日本にとって北方の安全を確保したと思わせる一方で、結果的に日本を対米英戦争へと向かわせる道を加速させることになったのです。
松岡の交渉力は、確かに一時的な外交成果をもたらしました。しかし、その成果が、日本の真の国益や長期的な安全保障に資するものだったのかどうかは、歴史が問い続けるべき課題です。松岡の評価が分裂した背景には、理想を追求する情熱と、現実を見誤った判断との間で揺れ動く、当時の日本外交の苦悩があったと言えるでしょう。
11-3. 中立条約がもたらした誤算
電撃的和解が招いた「安心」という名の罠
1941年(昭和16年)4月13日、モスクワで締結された日ソ中立条約は、日本の外交にとって画期的な出来事として歓迎されました。当時の外務大臣・松岡洋右は、宿敵ソ連との関係を安定させたことで、北からの脅威が薄れ、日本が安心して南進政策を推進できるようになったと確信していました。国民の間でも「これで北方は安全になった。さあ南進だ!」という熱狂的な空気が広がり、マスメディアもこの「電撃和解」を大々的に報じました。しかし、この中立条約は、日本の対外戦略に致命的な「誤算」をもたらすことになります。
ドイツの「裏切り」と日本の孤立の深化
日ソ中立条約締結からわずか2カ月後の1941年6月22日、ナチス・ドイツは突如としてソ連への侵攻を開始しました(バルバロッサ作戦)。この「裏切り」は、日本の外交戦略を根底から揺るがしました。松岡洋右が提唱していた「日独伊ソ四国協商」という壮大な世界再編構想は、まさにこの瞬間に雲散霧消し、ソ連は日本の同盟国であるドイツの敵、そしてアメリカ・イギリスと同じ連合国陣営へと引き込まれていったのです。
日本は、日独伊三国同盟を対米英牽制の切り札と考えていましたが、その同盟国であるドイツが、日本の知らないところでソ連と不可侵条約を結び、さらにそれを一方的に破棄してソ連に侵攻するという事態は、日本の外交的立場を極めて不利なものにしました。当時の日本の指導者たちは、国際情勢が自らの想定とは全く異なる方向に動いていることを「見れども見えず」の状態にありました。このドイツの裏切りは、日本が国際社会において、いかに「利用されるだけの存在」であったかを痛感させるものでした。
「北は安全」という誤った前提
日ソ中立条約は、日本に「北方の安全が確保された」という誤った安心感を与えました。これにより、日本は対ソ警戒のために満洲に配備していた兵力を南方に転用できると考え、南進政策を加速させることになります。しかし、ソ連はドイツとの戦争が始まる前から、日本の暗号電報を解読しており、日本の南進政策が確実なものになっていることを把握していました 。スターリンは、日ソ中立条約締結の際、日本側に対し「これで日本は安心して南進できますなあ」と語ったとされますが、これはまさに日本の思惑を見透かした上での、ソ連にとって都合の良い「悪魔のささやき」であったと言えるでしょう 。
実際、ソ連はドイツとの戦争が始まると、シベリアからヨーロッパ戦線へ兵力を転用し、極東の兵力を削減しました。しかし、これは日ソ中立条約が日本の外交的勝利であったからではなく、ソ連がドイツとの決戦に集中するため、一時的に日本との関係を安定させる必要があったためです。日本が「北は安全」と誤解したことが、結果的に対米英戦への道を突き進む遠因となりました。
チャーチルの警告と日本の「頑なさ」
松岡洋右がモスクワに滞在中に、イギリスのチャーチル首相は駐ソ英国大使を通じて松岡宛に書簡を送っています。その中でチャーチルは、ドイツがイギリスを征服できるか待つことが日本にとって有利ではないか、と遠回しに忠告していました。さらに、日独伊三国同盟への日本の加入がアメリカの参戦を容易にするのではないか、あるいは、もしドイツが敗北すれば、日本の貧弱な生産力では単独での戦争は不可能ではないか、と具体的な数字を挙げて日本の対米強硬路線を牽制しました 。
しかし、松岡はこのチャーチルの忠告を「侮辱」と受け止め、日本が掲げる「八紘一宇」という壮大な理想を実現するため、日独伊ソの連携は不可欠であるという自らの信念を貫きました。彼は「日本の外交政策は、たえず偉大な民族的目的と八紘一宇に具現した状態を地球上に終局的に具体化することを企図し、日本の直面する事態のあらゆる要素をきわめて周到に考慮して決められたものであるから、ご安心くだされたい」と反論しました 。
この松岡の返答は、当時の日本の上層部に蔓延していた「自己過信」と「客観性の欠如」を象徴するものでした。国際社会からの忠告に耳を傾けず、自らの「理想」や「信念」を優先した結果、日本は国際的な現実からますます乖離していくことになったのです。
ヤルタ会談への伏線と情報戦の敗北
日ソ中立条約がもたらした最大の誤算の一つは、ソ連がこの条約を通じて日本の南進政策と、それに伴う千島列島の戦略的価値を正確に把握したことでした 。アメリカは日本の暗号解読を通じて、ルーズベルト大統領がスターリンとヤルタ会談(1945年)でソ連を対日参戦に誘う際の「獲物」として千島列島を位置づけるに至ったのです 。つまり、日本が北方の安全を確保したと信じていたこの条約が、皮肉にも、戦後の北方領土問題へとつながる布石となっていたのです。
これは、情報戦の重要性を軽視し、自国の情報が敵国に筒抜けになっていることに気づかなかった日本の「驕慢な無知」の表れでもありました。松岡は自身の外交手腕に酔いしれ、スターリンの「芝居」を見抜くことができませんでした。
誤算が導いた「避けられたはずの戦争」
日ソ中立条約は、日本が真に求めていた「北方の安全保障」を一時的に確保したかのように見せかけましたが、その実態は、ドイツのソ連侵攻という予期せぬ事態によって、わずか2カ月で崩壊しました。そして、この「誤算」が、日本を対米英戦争へと突き進ませる大きな要因となりました。
もし日本が、ドイツとソ連の密約、そしてその後の関係変化を正確に読み解き、チャーチルの忠告に耳を傾けていれば、対米英戦争という道は避けられたかもしれません。しかし、当時の日本は、自国の「理想」と「信念」に固執し、国際社会の冷徹な現実と、自らの「情報戦」における劣勢を直視することができませんでした。
日ソ中立条約がもたらした「誤算」は、私たちに、歴史を学ぶ上で最も重要な教訓の一つを与えてくれます。それは、国際関係においては、常に冷静な現実認識と情報分析が不可欠であり、自己の都合の良い解釈や感情に流されることが、いかに国家の命運を左右するか、という痛切な教訓です。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。