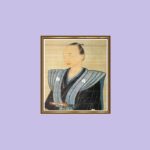
京都の偉人:石田梅岩 — 商業に「道」を見出し、現代に息づく「心学の父」

京都府
「損して得とれ」「負けるが勝ち」。これらの言葉は、現代のビジネスや人間関係においてもよく使われますが、その源流の一つに、江戸時代の京都で活躍した思想家、石田梅岩(いしだ・ばいがん)の教えがあります。京都府亀岡市東別院町に生まれた彼は、庶民の日常生活に根ざした「石門心学」を創始し、特に当時蔑視されがちだった「商人」に道徳的な価値と社会的役割を見出しました。彼の思想は、現代日本の勤勉さや正直さ、そして企業倫理の原点として、300年以上の時を超えて私たちに問いかけ続けています。
商家奉公から「心の学」への探求
石田梅岩は、1685年(貞享2年)に丹波国桑田郡東懸村(現在の京都府亀岡市東別院町)の農家に次男として生まれました。11歳で京都の呉服商「黒柳家」に丁稚奉公に出され、約20年間にわたり番頭として勤め上げます。この商家での経験が、彼の思想の土台となります。
梅岩は幼少期から理屈っぽい性格で、周囲に嫌われることもあったと自ら語っています。しかし、その内向的な性格が、深く自己と向き合い、思索を深めるきっかけとなりました。彼は、人が本来持つ「性(本性)」を理解し、自己を改革することこそが真の学びであると考え、これを「心を知る」あるいは「発明(自分自身を発明する)」と呼びました。梅岩にとっての心学とは、まさに「手前を埒(らち)をあける」、つまり、凝り固まった自分の性格の壁を一つ一つ打ち破り、真の自己を取り戻すための実践的な修養だったのです。
45歳となった1729年(享保14年)、梅岩は黒柳家を辞し、京都市中京区堺町通蛸薬師上ル東側にあった自宅に講席(塾)を設け、教化活動を開始します。彼の講義は、謝礼を取らず、身分や性別を問わず、紹介も不要な完全無料の公開講座でした。当初は聴講者も少なかったものの、彼の熱心な教えは次第に評判を呼び、門弟を増やしていきました。
『都鄙問答』に凝縮された「町人の哲学」
梅岩の思想が広く知られるきっかけとなったのは、毎月開かれた門弟との問答をまとめた主著『都鄙問答(とひもんどう)』です。この書は、当時の庶民が抱いていた「商人は欲深く、卑しい」という賤商観(せんしょうかん)に対し、商売の正当性と道徳的なあり方を明確に説いた画期的なものでした。
- 「諸業即修行(しょぎょうそくしゅぎょう)」の理念: 梅岩は、農民は農耕、職人は物づくり、そして商人は商売という、それぞれの生業に勤勉に励むこと自体が「人生修行」であると説きました。この「諸業即修行」の考え方は、働くことを単なる生計の手段ではなく、人格を磨き、自己を高めるための尊い行為と位置づけました。
- 商人の利潤の正当化: 当時、武士の俸禄は正当なものとされながら、商人の利潤は否定的に見られがちでした。しかし梅岩は、「商人が売買で得る利は、武士の禄と同じである」と述べ、商人の経済活動によって得られる利益は正当なものであり、社会にとって不可欠なものであると主張しました。
- 「正直」と「倹約」の強調: 梅岩は、商人が道を知れば「欲心から離れ、仁心(人を思いやる心)を持って努力し、道にかなって繁盛することができる」と説きました。そのためには「勤勉」「倹約」「正直」を重んじるべきだとしました。彼の言う「倹約」は、単なるケチではなく、「世界のために、従来は三つ必要だったものを二つで済ませるようにする」という、限りある資源を大切にし、社会全体で豊かさを分かち合うという現代のSDGsにも通じる思想でした。
梅岩の教えは、商人に自信と誇りを与え、彼らの心を捉えました。こうして石門心学は、当時の社会で成長しつつあった町民を中心とする庶民層の意識を思想化し、発展の一途をたどっていったのです。
思想の普及と現代への影響
梅岩の死後も、その教えは弟子たちによって全国へと広められ、日本の精神文化に深い影響を与えました。
全国に広がる心学講舎
梅岩の直弟子である手島堵庵(てじまとあん)らは、師の死後、京都に心学講舎「五楽舎」をはじめ、「脩正舎」「時習舎」「明倫舎」などを次々と設立しました。これらの講舎は、石門心学の教化活動の中心となり、その活動は江戸時代後半から明治初期にかけて、全国45カ国、173カ所にまで広がったと言われています。講舎では、識字率の低い庶民にも分かりやすい俗語を用いた講話や、「道歌(どうわ)」と呼ばれる教訓歌が用いられ、身分や男女の隔てなく誰でも無料で学ぶことができました。
特に、講談師出身の柴田鳩翁(しばたきゅうおう)は、巧みな話術で庶民から武士、公家にまで心学を説き、その講話は『鳩翁道話』として出版され、明治時代にはベストセラーとなりました。彼らの活動によって、石門心学は当時の日本社会において一大勢力となり、「勤勉と倹約」という町人哲学を生み出し、今日の日本人の倫理観、生活様式、勤労観に深く根付いていきました。
現代の企業倫理とCSRの原点
近年、石田梅岩の思想は、企業におけるCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)の原点として再評価されています。彼が『都鄙問答』の中で説いた「実の商人は、先も立、我も立つことを思うなり」(相手も利益を得、自分も利益を得ることを考えるのが真の商人である)という理念は、まさに「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)で知られる近江商人の思想と並び、営利活動を否定せず、倫理とビジネスの持続的発展を両立させる日本の経営哲学の基礎となりました。
これは、寄付や援助など本業以外での社会貢献を活動の中心とする欧米のCSRとは異なり、本業の中で社会的責任を果たしていくことを説くという、日本独特のCSR観に通じるものです。
石田梅岩ゆかりの地:心学の息吹を感じる旅
石田梅岩の故郷である京都府亀岡市と、彼が教えを広めた京都市内には、今も彼の足跡をたどるゆかりの地が数多く残されています。
京都府亀岡市:生誕の地と「梅岩の里」
- 石田梅岩生誕地碑・梅岩公園・墓所(京都府亀岡市東別院町東掛):梅岩が生まれた場所には、その生家が今も残り、記念碑や公園が整備されています。
- 春現寺(京都府亀岡市東別院町東掛):梅岩の命日には、生家近くの春現寺で「石田梅岩墓前祭」が行われ、彼の功績が偲ばれます。
- 石田梅岩道(京都府亀岡市東別院町東掛〜JR亀岡駅):梅岩の生涯と心学の教えを伝えるウォーキングコースが整備されています。
- 石田梅岩記念施設「梅岩塾」(京都府亀岡市余部町 道の駅ガレリアかめおか内):梅岩の心学講舎を復元した施設で、石門心学に関する公開講座も開催されています。
- 石田梅岩座像(JR亀岡駅改札前):出身地である亀岡市の玄関口に、梅岩の座像が設置されています。
京都市:心学講舎とゆかりの場所
- 石田梅岩邸跡碑(京都市中京区堺町通蛸薬師上ル東側):梅岩が自宅に講席を開き、心学の教えを始めた場所を示す石碑が立っています。
- 石門心学脩正舎跡碑(京都市下京区麩屋町通五条上る東側):梅岩の弟子である手島堵庵によって開かれた主要な心学講舎の一つがあった場所です。
- 明倫舎跡(京都市中京区室町通錦小路上る 京都芸術センター内):心学教化活動の拠点となり、後に小学校に転用された場所です。
- 石田梅岩の墓(京都市東山区五条橋東6 鳥辺山墓地):鳥辺山には、梅岩の他、手島堵庵や柴田鳩翁といった心学関係者の墓が多くあり、心学の教えが受け継がれた歴史を感じさせます。
大阪:広がる心学の教え
- 石田梅岩供養墓(大阪市天王寺区下寺町 大蓮寺):大阪の門下生によって建てられた供養墓です。
- 心学明誠舎跡碑(大阪市中央区島之内):大阪にも心学の講舎が設けられ、教えが広まったことを示す碑があります。
石田梅岩の遺産:現代社会に生きる私たちへ
石田梅岩の生涯は、まさに「遅咲き」でありながらも、自らの内面と徹底的に向き合い、それを世の人々の幸福へと繋げようとした求道者の姿そのものでした。彼の教えは、単なる道徳論に留まらず、商売や労働といった日常生活の中に精神的な価値を見出すという、非常に実践的なものでした。
現代社会において、私たちは経済活動と倫理の間で揺れ動くことがあります。企業の不祥事や環境問題、格差の拡大など、利潤追求だけでは解決できない課題が山積しています。このような時代だからこそ、石田梅岩が説いた「道徳と経済の両立」という理念は、私たちに深い示唆を与えてくれます。
自分の仕事に「道」を見出し、勤勉に励み、そして社会全体に貢献しようとする彼の精神は、私たち一人ひとりの生き方、そして企業活動のあり方を考える上で、今もなお重要な指針となるでしょう。石田梅岩の心学は、私たち自身の「心」を磨き、より良い社会を築いていくための、普遍的な智慧を教えてくれているのです。




