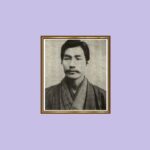
第16回 山本五十六、真珠湾を選んだ日
16-1. 作戦立案から実行までの舞台裏
避けられない開戦と「乾坤一擲」の覚悟
1941年(昭和16年)後半、アメリカによる石油全面禁輸を始めとする経済制裁は、日本を国家存亡の淵へと追い込んでいきました。日本は「戦うか、滅びるか」の瀬戸際に立たされ、外交交渉による解決の道が閉ざされていく中、武力による活路を見出すという選択へと追い込まれていきました。この絶望的な状況下で、連合艦隊司令長官・山本五十六は、自らが最も避けたかったアメリカとの戦争において、「勝つための作戦」ではなく、「早く終わらせるための作戦」として、真珠湾攻撃の立案と実行を決意します。
「ジリ貧」回避と「戦機」の計算
山本五十六は、アメリカの圧倒的な国力と工業生産力を誰よりも深く理解しており、「アメリカと戦争になれば、日本は長期的に勝てない」という現実的な認識を持っていました。彼は「最初の半年や一年は暴れてみせる。しかし二年、三年となれば、私は保証しない」と語り、日本の国力の限界を明確に示していました。
このような状況で、彼が導き出した結論は、「このまま石油が尽きてジリ貧になる前に、短期決戦で活路を見出すしかない」というものでした。日本の海軍兵力は1941年12月末には対米7割に達するものの、その後はアメリカの圧倒的な生産力によってその比率は急速に低下すると予測されていました。つまり、時間をかければかけるほど日本の劣勢は明白になるため、「戦うなら今しかない」という切迫した「戦機」の論理が、山本の胸中に強くあったのです。
真珠湾攻撃作戦の立案と海軍部内の猛反対
山本が立案した真珠湾攻撃は、太平洋艦隊の根拠地であるハワイ・真珠湾を奇襲し、アメリカ太平洋艦隊の主力艦艇に壊滅的な打撃を与えることで、短期決戦に持ち込み、有利な条件での講和を目指すという大胆な作戦でした。
しかし、この奇抜な作戦案に対し、海軍の総本山である軍令部は猛反対しました。彼らは「作戦として無謀すぎる」「太平洋をはるばる渡り、アメリカ艦隊がいなかったらどうするのか」「もし返り討ちに遭って空母が全滅したら、日本海軍は壊滅だ」と、現実的なリスクを並べて山本の作戦を批判しました。これは、当時の海軍部内に依然として存在した「対米協調派」の意見でもありました 。
「辞職覚悟」の山本と、軍令部の「情」
だが山本は、この猛反対に対し一歩も譲りませんでした。彼は「これが通らなければ連合艦隊長官を辞職する」とまで言い切り、幕僚たちも山本の決意に同調して「全員辞職」を申し出ました。この山本の「辞職覚悟」の背景には、「自分がやらなければ、もっと無謀な者が指揮を執る」という深い諦念があったのかもしれません。
軍令部総長・永野修身は、山本の強硬な姿勢と、彼が抱える「この作戦が成功しなければ、日本に勝ち目はない」という悲壮な覚悟を前に、最終的に「山本にそんなに自信があるというのなら、希望通りやらせてやろうじゃないか」と了承したと伝えられています 。国家の運命を賭する作戦が、合理的な議論だけでなく、このような「情」に流されたかのような経緯で決定されたことは、当時の日本の意思決定の複雑さを物語っています。
「桶狭間とひよどり越と川中島」
山本は、真珠湾攻撃を「桶狭間とひよどり越と川中島を併せ行うの已むを得ざる羽目に、追込まるる次第に御座候」と表現しました 。これは、日本史に名を残す三つの奇襲戦術を一度に行うような「無鉄砲」な作戦であり、兵力で劣る日本が、命を懸けて勝機を狙うという悲壮な覚悟が込められていました。
山本にとって、真珠湾攻撃は、最初の一撃で相手の度肝を抜き、短期決戦の流れを作り出すことで、アメリカ世論に「この戦争は損だ」と思わせ、早期講和に持ち込むための「攻撃による平和工作」だったのです。
極秘裏に進められた準備と「ニイタカヤマノボレ」
真珠湾攻撃の作戦は極秘裏に進められました。1941年11月26日午前6時、南雲忠一中将指揮の機動部隊は、千島列島の単冠湾からハワイに向けて出撃しました。そして、12月2日、山本五十六は全軍に対し、暗号による命令「ニイタカヤマノボレ一二〇八」を発します。これは、「開戦、Xデーは12月8日と決定した」という最終命令でした 。
しかし、皮肉なことに、日本が開戦を決定したその翌々日、ドイツ国防軍はモスクワ郊外でソ連軍の猛反撃を受け、退却を開始していました。日本が勝算を当てにしていたドイツが、既に東部戦線で劣勢に立たされていたことを、日本は知る由もありませんでした。
開戦への最終決断と「避けられない」という認識
1941年12月1日、第四回御前会議が開かれ、もはやあらゆる望みが失われた中で、「交渉決裂、戦争を行うだけである」という最終決定が下されました 。木戸内大臣は、開戦の決定を「運命というほかはない」と日記に記しました。
この時、昭和天皇は、最後の最後まで手続きに沿ってことを決めたいという思いから、過去の総理大臣経験者を集めた「重臣会議」を開き、意見を聞いています。この場で若槻礼次郎が「理想のために国を滅ぼしてはならない」と訴えましたが、東条英機首相は「理想を追うて現実を離れるようなことはしない。が、理想をもつことは必要だ」と反論し、日本の決意を固めました 。
山本五十六が真珠湾攻撃を選んだ背景には、彼個人の卓越した戦略眼と、アメリカの国力を知悉した現実認識がありました。しかし、彼が最終的に開戦へと踏み切ったのは、外交的解決の道が閉ざされ、経済的に追い詰められ、もはや「戦わざるを得ない」という国家の究極的な状況判断があったからに他なりません。
真珠湾攻撃は、日本の戦略的選択の集大成であり、同時に「避けられない」とされた戦争への悲壮な覚悟の表れでもありました。この作戦の舞台裏には、日本の指導者層が抱えた深い苦悩と、情報戦の敗北という見えない罠が潜んでいたのです。
16-2. 開戦通告遅延とその後の波紋
「だまし討ち」の烙印が押された日
1941年(昭和16年)12月8日(ハワイ時間7日)、日本海軍機動部隊による真珠湾攻撃は、太平洋戦争の火蓋を切りました。しかし、この攻撃の直前、日本がアメリカに提示すべき「最後通牒」が、わずかな時間差で攻撃開始後に手交されるという致命的な事態が発生しました。この「開戦通告遅延」は、日本に「だまし討ち」という永遠の汚名を着せることになり、その後の日本の国際的な立場と、アメリカ国民の対日感情に計り知れない影響を与えることになります。
国際法上の義務と日本の本音
国際法では、開戦に際しては明確な「事前の通告」を行うことが義務付けられていました。1907年のハーグ陸戦条約「開戦に関する条約」第1条には、「締約国は、理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付き開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なくして、その相互間に戦争を開始すべからざることを承認す」と明記されており、日本もこれを批准していました 。
日本政府は、国際法上の義務を果たすため、ハル・ノートに対する最終回答として、日米交渉の打ち切りと日本の武力行使の決意を記した通告文を作成し、ワシントンの野村吉三郎大使に送りました。この通告文は、ハワイ時間12月7日午前7時、つまり真珠湾攻撃開始の1時間前にアメリカ政府に手渡される予定でした。しかし、軍令部の要望により手交時間は30分繰り下げられ、攻撃のわずか30分前となりました 。
しかし、日本の真の本音は、通告をせずに奇襲攻撃を行いたいというものでした。当時の軍部には、「左手で通告文を渡しながら右手でぼかんと殴る」ような、奇襲による戦術的優位を確保したいという考えがあったのです 。
通信トラブルと大使館の「無神経」
この極めて重要な通告が遅れた原因については、いくつかの説があります。一つは、通信設備の不備や通信量の過多による技術的な問題です。もう一つは、ワシントンにある日本大使館の外交官たちの「怠慢」や「無神経」が指摘されています。彼らは通告文の重要性を十分に理解しておらず、優先順位が低かったために、その作成や翻訳、タイピングに時間がかかってしまったというのです。野村大使に対する外務省エリートたちの反感や不信、非協力的な態度も、この遅延の一因だったとされています 。
結果的に、通告文がハル国務長官に手交されたのは、真珠湾攻撃が開始されてから約1時間後のことでした。この時間差が、国際社会、特にアメリカにおいて「だまし討ち」という強烈な印象を与えることになります。
アメリカの「知っていた」現実
しかし、この「だまし討ち」の汚名には、もう一つの側面があることを忘れてはなりません。アメリカは、日本の外交暗号「パープル」を解読しており、日本の開戦の決意、さらには攻撃の意図までを事前に把握していました。ルーズベルト大統領は、日本からの最終通告の電報を読んだ際、既に「これは戦争だ」と認識していたとされています 。
つまり、アメリカ側は日本の攻撃を予期しており、日本からの通告が遅れたとしても、それが「奇襲」であるという認識は既に持っていたのです。この事実は、日本の「だまし討ち」が、単なる通告の遅れ以上の、情報戦における日本の根本的な敗北に起因していることを示唆しています。
「汚辱の日」とアメリカ国民の憤激
真珠湾攻撃は、アメリカ国民に大きな衝撃と憤激をもたらしました。ルーズベルト大統領は、攻撃翌日の12月8日、上下両院で演説を行い、この日を「汚辱の日(the day of infamy)」と呼びました 。彼は、「アメリカは突如、計画的に、日本帝国により海空から攻撃されました」「日本政府は、謀計によりアメリカをだましたのであります」と述べ、「だまし討ち(treacherous attack)」であることを強調しました 。
この大統領演説は、アメリカ国民の対日感情を決定的に悪化させ、一致団結して戦争に当たるという強い意志を国民全体に植え付けました。「リメンバー・パールハーバー(真珠湾を忘れるな)」という言葉は、当初は使われませんでしたが、後にガダルカナル島をめぐる攻防戦で海兵隊将兵の口から発せられ、それが本国に戻り、アメリカ国民全体のスローガンとなっていきました 。
日本が負った「不名誉」の代償
開戦通告の遅延は、日本にとって戦略的な利益をもたらすどころか、国際的な信用を著しく失墜させ、その後の戦争遂行、そして戦後の歴史認識にまで深く影を落とすことになります。「だまし討ち」という印象は、東京裁判においても日本の「侵略性」を立証する根拠として利用され、日本の行動を一方的に悪と見なす歴史観を助長しました 。
この出来事は、単なる事務的なミスではなく、当時の日本が情報戦の重要性を軽視し、国際法や外交儀礼に対する認識が甘かったことを示しています。また、自国の都合の良いように状況を解釈し、国際社会の反応を読み違えたことも、この悲劇的な結果を招いた一因と言えるでしょう。
歴史の教訓:透明性と情報の重要性
真珠湾攻撃における開戦通告遅延の波紋は、私たちに、国際関係において「透明性」と「情報」がいかに重要であるかを痛切に教えてくれます。たとえ自国が追い詰められた状況にあったとしても、国際法や外交儀礼を遵守し、自国の行動の正当性を明確に伝える努力を怠ることは、予期せぬ、そして長期にわたる不利益を招く可能性があります。
この歴史の教訓は、現代社会においてもなお、情報が複雑に錯綜する中で、国家がいかにして正確な情報を収集・分析し、国際社会との信頼関係を構築していくべきかを考える上で、重要な示唆を与えてくれるでしょう。日本の「だまし討ち」という汚名に潜む、情報戦の敗北という側面を見つめ直すことこそが、自国の歴史を深く理解し、未来へと活かすための第一歩となるのです。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。




