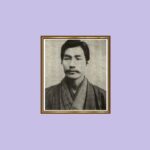
第17回 なぜ日本は東南アジアに進出したのか?
17-1. 植民地支配の現状と日本の選択
白人列強が築き上げた植民地秩序
1930年代から1940年代初頭にかけての東南アジアは、まさに「白人列強の植民地の宝庫」でした。イギリスはシンガポール、マレー半島、ビルマ(現ミャンマー)などを支配し、広大な英領インド帝国を築き上げていました。フランスはインドシナ(現ベトナム、ラオス、カンボジア)を植民地とし、オランダは石油資源豊かな東インド(現インドネシア)を、アメリカはフィリピンをそれぞれ支配していました。これらの地域は、宗主国にとって原材料の供給地であり、製品の市場であり、そして何よりも地政学的な戦略拠点でした。
これらの植民地では、現地住民の意思とは無関係に、宗主国の利益が最優先され、資源は本国へ送られ、教育や政治は宗主国の都合の良いように運営されていました。現地の文化や民族性は抑圧され、人種差別も公然と行われていました。これが当時の東南アジアの「植民地支配の現状」でした。
資源なき日本の「生存権」と南進論
このような状況の中、日本は自国の生存をかけた「選択」を迫られていました。世界恐慌後のブロック経済化により、日本の主要な輸出市場は閉ざされ、アメリカによる石油、屑鉄、ゴムなどの戦略物資の禁輸措置は、日本の国家存亡を脅かすものでした。日本は天然資源に乏しく、これらの物資のほとんどを海外からの輸入に依存していたため、この経済封鎖は文字通り「死活問題」でした。
このような状況下で、豊かな資源を持つ東南アジアは、日本にとって「生き残りのための生命線」として浮上しました。日本の南進政策は、単なる領土拡張主義ではなく、経済的自立と安全保障を確保するための「やむを得ない選択」としての側面が強かったのです。日本の指導層は、このまま経済封鎖が続けば、いずれ国力が枯渇し、国家が滅びるという切迫した危機感を持っていました。
「援蒋ルート遮断」と軍事戦略
東南アジアへの進出は、軍事的な意味合いも強く持っていました。特に、仏印を通る「援蒋ルート」は、日中戦争で抗戦を続ける蔣介石の重慶政権への物資供給路となっており、これを遮断することが、中国戦線の早期解決に繋がると考えられていました。日本は、中国を屈服させ、その資源を活用することで、欧米列強との対立に備えるという戦略的意図を持っていたのです。
北部仏印への進駐は、この援蒋ルート遮断を目的として行われましたが、現地の日本軍の「暴発」により、平和的な進駐の意図は損なわれ、国際社会から「侵略行為」として非難される結果となりました。しかし、この進駐は、その後の東南アジア全体への進出の足がかりともなりました。
「大東亜共栄圏」という理想と現実
日本は、東南アジア進出を正当化する理念として「大東亜共栄圏」を提唱しました。これは、「八紘一宇」の精神に基づき、アジア諸民族を白人列強の植民地支配から解放し、共存共栄の秩序を築くという壮大な構想でした。当時のアジアの独立運動家の中には、日本のこの理念に共感し、日本の行動を白人支配からの「解放」と捉える者も少なくありませんでした。インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、「大東亜戦争というものは、本来なら私たちインドネシア人が独立のために戦うべき戦争だったと思います」とまで語っています。
しかし、この理念は、日本の「生存権確保」という現実的な国益と、アジアにおける日本の主導権確立という思惑が混在していました。また、現地に進出した日本軍が、必ずしも「解放者」として振る舞ったわけではなく、一部で住民に対する略奪や暴行が行われたことも事実であり、理想と現実の間には大きなギャップがありました。
欧米列強の「ダブルスタンダード」
日本が東南アジアに進出した際に、「侵略者」として国際社会から激しく非難されたことは事実です。しかし、その非難の背後には、白人列強自身の「ダブルスタンダード」が存在していたことも見逃してはなりません。彼らは自らが長年アジアを植民地として支配し、資源を搾取してきた歴史を棚上げし、日本の行動だけを一方的に断罪しました。
アメリカのヘレン・ミアーズは、「近代日本は西洋列強がつくり出した鏡であり、そこに映っているのは西洋自身の姿なのだ」と述べ、近代日本の「犯罪」は、それを裁こうとしている連合国の「犯罪」でもあると指摘しています 。つまり、日本の東南アジア進出は、白人列強の植民地支配という既存の秩序に対する「挑戦」でもあったのです。
歴史の複雑さを見つめる
なぜ日本は東南アジアに進出したのか。その理由は、一言で「侵略」と断じることはできません。そこには、世界恐慌後の経済的苦境、欧米列強による経済封鎖という外的圧力、中国戦線の泥沼化という軍事的要因、そして日本の「生存権」を確保しようとする切実な思いが複雑に絡み合っていました。さらに、「白人支配からのアジア解放」という理念も、その行動の背景にはありました。
私たちは、この歴史の局面を、単純な善悪二元論で捉えるのではなく、当時の国際情勢、各国の思惑、そして日本が直面していた苦境を多角的に理解することで、真の教訓を得ることができます。東南アジアへの進出は、日本の生存をかけた苦渋の選択であり、同時に、アジアの植民地化を終わらせるきっかけとなったという、歴史の皮肉な側面も持っていたのです。この複雑な真実を静かに見つめ直すことこそが、「もう一つの昭和史」を学ぶ意味であると言えるでしょう。
17-2. 英蘭米との衝突は避けられたのか?
経済封鎖という「静かなる戦争」の激化
1941年(昭和16年)後半、日本はアメリカによる石油の全面禁輸を含むABCD包囲網によって、経済的に完全に孤立しました。当時の日本は石油の8割以上をアメリカからの輸入に依存しており、この経済封鎖は、日本の国家の存続を根底から脅かすものでした。軍事行動の継続はもちろん、国民生活すら維持できないという切迫した状況の中で、日本は豊富な資源を持つ東南アジアへの進出、すなわち「南進」を、生き残りのための「やむを得ない選択」として位置づけました。
しかし、この南進は、東南アジアに広大な植民地を持つイギリス、オランダ、そしてフィリピンを支配するアメリカとの直接的な衝突を意味しました。果たして、この衝突は避けられたのでしょうか。
アメリカの「生存権」と日本の認識
アメリカは、日本の対中政策や仏印進駐を、自国の国益と国際秩序に対する脅威と見なし、経済制裁を段階的に強化していました。アメリカのルーズベルト大統領は、日本が資源を枯渇させて「窒息死」するのを待つという対日政策を明確に持っていたとさえ言われています。これは、武力を使わない「経済戦争」であり、日本から見れば、自国の「生存権」が根本から脅かされているという認識でした。
当時の日本の指導層は、アメリカが日本を「戦わずして日本の国力を消耗せしめる」謀略を企んでいると見ており、このまま手をこまねいていれば、日本は抵抗する力すら失ってしまうと焦っていました。永野修身軍令部総長が天皇に「物がなくなり、逐次貧しくなるので、どうせいかぬなら早いほうがよいと思います」と語ったのは、その切迫感の表れです。
外交交渉の限界とハル・ノート
日本は開戦直前まで、アメリカとの外交交渉を継続しようと試みました。野村吉三郎駐米大使は、日米関係を改善するため懸命な努力を続けましたが、アメリカの態度は一貫して強硬でした。特に、1941年11月26日に提示された「ハル・ノート」は、日本の中国からの完全撤兵や三国同盟からの離脱など、日本のそれまでの努力を全て否定し、日本の「生存権」を否定するに等しい内容でした。
このハル・ノートを受け取った日本の指導層は、外交的解決の可能性が完全に閉ざされたと判断しました。パール判事が後に「日本のような国でなくとも、あのような通牒を受けたなら戦わざるを得ない」と述べたように、これを「最後通牒」と認識した日本は、武力行使以外に道はないと結論付けざるを得なかったのです。
アメリカは日本の暗号を解読しており、日本の外交戦略や軍事計画を全て把握していました。ルーズベルト大統領は、ハル・ノート提示の時点で日本の開戦の意図を正確に読み取っており、この強硬な要求は、日本を戦争へと追い込むための意図的なものであった可能性も指摘されています。
「戦機は今」という焦燥と日本の選択
日本の指導層は、石油の枯渇という「死のタイムリミット」に直面し、このまま座して滅びるか、それとも武力によって活路を開くかという究極の選択を迫られました。山本五十六連合艦隊司令長官も、アメリカの圧倒的な生産力を熟知し、長期戦では勝ち目がないことを認識しながらも、「戦機は後には来ない」として真珠湾攻撃作戦を立案しました。彼にとっての真珠湾攻撃は、勝利を目指すというよりは、「早く戦争を終わらせるための攻撃」であり、日本の生存を賭けた「窮鼠猫を噛む」戦略でした。
1941年12月1日、第四回御前会議で「対米英開戦」が最終決定されます。木戸内大臣は、この決定を「運命というほかはない」と日記に記しました。この時、昭和天皇は「理想のために国を滅ぼしてはならない」と述べた若槻礼次郎に対し、「理想を追うて現実を離れるようなことはしない。が、理想をもつことは必要だ」と答えた東条英機首相の意見を受け入れました。これは、当時の日本が、経済的困窮と国際的孤立という厳しい現実の中で、国民の生活と国家の存続を守るためには、もはや武力行使しか道がないという「やむを得ない決意」に至っていたことを示しています。
避けられなかった衝突と植民地秩序への挑戦
当時の国際情勢、特に白人列強が築き上げた植民地秩序を考えると、英蘭米との衝突を完全に避けることは極めて困難であったと言えるでしょう。
資源の偏在と日本の脆弱性: 東南アジアの資源は、すでに英蘭米によって独占されており、日本が平和的に資源を入手する道は閉ざされていました。
「生存権」をめぐる認識の相違: 日本は経済封鎖によって「生存権」を脅かされていると認識しましたが、英蘭米はこれを日本の「侵略」を抑え込むための正当な措置と見なしていました。
植民地秩序への挑戦: 日本の南進は、白人列強による植民地秩序への直接的な挑戦であり、既存の国際秩序を維持しようとする英蘭米にとっては、看過できない行為でした。
日本が戦争を回避できた可能性は、チャーチルの忠告やルーズベルトの和平示唆、そして日米交渉の継続に見られたかもしれません。しかし、日本の指導層は、情報戦における劣勢、自国の過信、そして国内の「空気」に流される中で、そうした機会を逸してしまいました。
英蘭米との衝突は、日本の南進政策が、植民地秩序という既得権益の壁にぶつかった結果であり、当時の国際社会の構造的な問題と、日本の置かれた地政学的な限界が深く絡み合った「避けられなかった」側面があったと言えるでしょう。この衝突は、結果としてアジアの植民地支配に終止符を打つきっかけの一つとなったという、歴史の皮肉な側面も持っていました。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。




