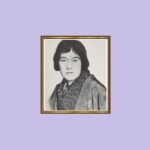第20回 戦後アジア各国から見た日本の戦い
20-1. 独立指導者たちの言葉に耳を傾ける
「侵略」のレッテルを超えて
大東亜戦争(太平洋戦争)は、戦後日本の歴史において「侵略戦争」として位置づけられ、その「加害者」としての側面が強調されてきました。しかし、この戦争がアジア諸国にもたらした影響は、決して一面的に語れるものではありません。特に、長年欧米列強の植民地支配に苦しんできたアジアの独立指導者たちの言葉に耳を傾けるとき、日本の戦いが、彼らにとって「白人支配からの解放」という大きな意味を持っていたことが見えてきます。
インド独立の父、ネルーの回想
インドの初代首相ジャワハルラール・ネルーは、自らの著書で、日本の日露戦争勝利がアジアの人々に与えた精神的影響を深く語っています。彼は「私の子供の頃に日露戦争というものがあった。(中略)その日本が勝ったのだ。私は、自分達だって決意と努力しだいでは勝てないはずがないと思うようになった。そのことが今日に至るまで私の一生をインド独立に捧げることになった。私にそういう決意をさせたのは日本なのだ」と述べています。
ネルーはさらに、日本の勝利が「アジアの人々の心を救った」と強調しており 、インド国民の間に「大英帝国をインドから放逐すべきだ」という独立運動が広がったきっかけとなったことを明らかにしています 。彼の言葉は、日本の戦いが、直接的な武力介入とは異なる形で、アジアの人々の民族意識を覚醒させたことを示唆しています。
インドネシア独立の旗手、モハメッド・ナチール元首相の証言
インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、日本の大東亜戦争を「アジアの希望は植民地体制の粉砕だった。大東亜戦争は私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものだ」と表現しています。彼は、インドネシア人が独立のために戦うべき戦争を、日本が代わりに戦ってくれたとまで述べています。
さらにナチールは、日本がインドネシア語の公用語化を徹底的に推進し、インドネシア国民としての連帯感を植え付けたこと、そして若者に民族意識を植え付け、革命の戦闘的な雰囲気をもたらしたことを評価しています。特に日本軍が組織した祖国防衛義勇軍(PETA)の存在は大きく、「これなくしてインドネシア革命はあり得なかった」とまで指摘しています。これらの証言は、日本の存在がインドネシアの独立に直接的、間接的に貢献した事実を示しています。
ビルマ独立の立役者、バー・モウ元首相の評価
ビルマのバー・モウ元首相は、自著『ビルマの夜明け』の中で、日本の貢献について率直に語っています。「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない」と述べ、「真のビルマ独立宣言は、(日本占領下で独立を宣言した)1943年8月1日に行われたのであって、真のビルマの解放者はアトリーの率いる労働党政府ではなく、東条大将と大日本帝国政府であった」とまで断言しています。
彼はまた、日本ほど多くの事柄に対して手本を示したにもかかわらず、その諸民族から誤解を受けている国はないとも指摘しており、戦後の一方的な「侵略者」としての評価に異を唱えています。
マレーシアからの感謝の言葉
マレーシアのラジャー・ダト・ノンチック元上院議員は、日本軍のマレー半島進撃を「歓呼の声」で迎えたことを回想し、「敗れて逃げてゆく英軍を見た時に今まで感じたことのない興奮を覚えました」と述べています。彼は、日本軍がマレーシアを日本の植民地とせず、将来の独立と発展のために各民族の国語を普及させ、青少年の教育を行ったことを高く評価しています。また、日本の出現によってマレーシアの分断構造が解体され、「一つのマレーとしての民族意識を持つことができるようになった」とも指摘しています。
1991年にはマレーシアのコタバルで日本軍上陸50周年を記念する式典が行われ、戦争博物館が設立されるなど、日本への「感謝」が公の場で表明されています。これは、戦後日本の「自虐史観」とは異なる、現地の歴史認識が存在することを示す好例です。
インド国民軍のパラバイ・デサイ博士の主張
インド独立運動を日本と共にしたインド国民軍の法曹界の長老、パラバイ・デサイ博士は、デリー軍事裁判で、戦勝国であるイギリスがインド国民軍を軍事裁判にかけることに対し、「インドはまもなく独立する。この独立の機会を与えてくれたのは日本である。インドの独立は日本のおかげで30年も早まった」と強く主張しました。彼はまた、「インドだけではない。ビルマもインドネシアもベトナムも、東亜民族は皆同じである。インド国民はこれを心に深く刻み、日本の復興には惜しまない協力をしよう」と述べ、日本の貢献を多角的に評価しています。
タイの元首相、ククリット・プラーモートの言葉
タイの元首相ククリット・プラーモート氏は、日本のことを「母なる日本」と呼び、東南アジアの国々が白人国家と同等の立場になれたのは日本のおかげだと語っています。「十二月八日は、母なる日本が我々に大切なことを教えてくれた日です。我々のために彼女自身の繁栄を危険にさらしてまで重大な決定を下し、我々のために彼女の命をかけてくれた日です」と、日本の戦いを自国のためだと感謝する言葉を残しています。
「感謝」の背景にある複雑な現実
これらの独立指導者たちの言葉は、日本の戦いが、単なる「侵略」という範疇に収まらない、多面的な歴史的意義を持っていたことを強く示唆しています。日本は、白人支配からの解放という「大義」を掲げ、実際にその後のアジア諸国の独立を促す大きなきっかけを作りました。これは、日本の戦いが、白人による有色人種国家に対する植民地からの解放という「戦争目的」を達成したという見方を裏付けるものです 。
しかし、前節でも触れたように、日本の統治下には資源の収奪や一部での軍規の乱れといった「罪」の側面も存在しました。独立指導者たちの言葉は、こうした「功」の側面を評価したものであり、現地のすべての人々が日本を無条件に歓迎したわけではない、という「葛藤」の現実も忘れてはなりません。
歴史の真実を多角的に捉える
戦後日本の歴史認識は、東京裁判史観や自虐史観によって、「日本が悪かった」という一元的な見方に偏りがちでした。しかし、アジアの独立指導者たちの生の声に耳を傾けるとき、大東亜戦争が「白人支配からの解放」という大きな潮流の中に位置づけられる、より複雑で多層的な歴史であったことが明らかになります。
私たちは、過去の歴史を「断罪」するだけでなく、当時の人々が何を思い、何を選択したのかを「理解」しようと努めるべきです。アジア諸国の独立指導者たちの言葉は、日本の戦いが、アジア全体の歴史において果たした役割を再評価するための重要な視点を与えてくれます。この多角的な視点こそが、未来へとつながる真の歴史認識を構築するための鍵となるでしょう。
20-2. 近代化と脱植民地化の視点から
「アジアの奇跡」と日本の影響
大東亜戦争後、アジア諸国は次々と独立を達成し、急速な経済成長を遂げて「アジアの奇跡」と呼ばれる発展を遂げました。この近代化と脱植民地化のプロセスにおいて、日本の戦いが果たした役割は、戦後の歴史認識において十分に語られてこなかった側面があります。
植民地支配の打破と民族意識の覚醒
日本の大東亜戦争は、欧米列強による植民地支配の絶対性を打ち破るものでした。わずか数カ月で広大な東南アジア地域から欧米勢力を駆逐した日本の戦果は、アジアの人々に「白人は不敗ではない」という認識を植え付け、長年抑圧されてきた民族意識を覚醒させました。イギリスの歴史学者H・G・ウェルズは、「大東亜戦争は大植民地主義に終止符を打ち、白人と有色人種の平等をもたらし、世界連邦の基礎を築いた」と述べています 。また、著名な文明論者であるアーノルド・トインビーも、「アジアとアフリカを支配してきた西洋人が過去200年の間信じられてきたような不敗の神でないことを西洋人以外の人種に明らかにした」と指摘しています 。
これは、日本の戦いが、アジア・アフリカ諸国の民族解放運動に大きな「起爆剤」となったことを示しています。例えば、インド独立運動の指導者ジャワハルラール・ネルーは、日本の日露戦争勝利がインド独立への決意を促したと語り、インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、日本の戦いを「私たちアジア人の戦争」と表現しています。ビルマのバー・モウ元首相も、「日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない」と述べています。これらの言葉は、日本の戦いが、アジアにおける脱植民地化の大きな流れに直接的に影響を与えたことを示しています。
日本の近代化モデルと新興国の模範
明治維新以来、日本は非西洋国家としては稀有な近代化に成功しました。短期間で欧米列強に肩を並べるほどの国力を築き上げた日本の経験は、第二次世界大戦後、独立を達成したばかりの新興諸国にとって、近代化を推進する上での重要な「モデル」となりました。韓国の朴正煕大統領、イランのパーレビ国王、シンガポールのリー・クアンユー首相などが、日本の近代化政策を参考にしました。
特に、日本の教育制度、官僚制度、軍事制度は、これら新興国の国家形成に多大な影響を及ぼしました。元日経連会長の桜田武が、「韓国の経済発展は、日本の統治時代の教育のおかげである。教育制度、官僚制度、軍事制度は日本が残した三つの功績である」と述べたことは、その一端を示しています 。
「脱亜入欧」と「アジア主義」の混在
日本の近代化は、単なる西洋の模倣ではありませんでした。夏目漱石は「日本の近代化は外発的で、西洋の成果を借用・模倣したものだった」と指摘しますが、ライシャワーは「日本は決して後進国ではなかった。よしんば西欧に遅れをとっていたとしても、それは科学技術の分野においてだけだった」と述べ、集団としての統制力や協調のための技量においては西欧のどの国よりも進んでいたと評価しています 。
日本は、西洋の技術を取り入れつつも、日本の精神や文化を大切にする「和魂洋才」の道を歩みました。この「和魂洋才」は、エズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で「和魂和才」と表現したように、西洋文化を日本的に修正して取り入れたことで、日本の成功に繋がったとされています 。この日本の独自の近代化の成功は、アジアの新興国にとって、西洋の模倣だけでなく、自国の文化や精神を大切にしながら発展していくことの可能性を示しました。
歴史の連続性:民族解放の源流
日清・日露戦争も、アジアの民族解放に寄与したという視点も重要です。日清戦争が朝鮮や台湾など東アジア諸民族を清の支配から解放したように、日露戦争もフィンランドや東欧、中央アジアの諸民族の独立を促しました 。トルコでは日本の活躍がケマル・アタテュルクによるトルコ革命を誘発し、「近代化の父」ケマルは日本と明治天皇を尊敬しました。エジプトでも「独立に成功したのは明治天皇のおかげ」といわれています。これらの事実は、日本の戦いが、白人中心の国際秩序に対する挑戦であり、アジア諸民族の自覚を促した「民族解放」の側面を持っていたことを示しています。
「感謝」と「葛藤」の多層性
しかし、日本の統治は、前節で述べたように、資源の収奪や一部での軍規の乱れといった「罪」の側面も存在しました。独立指導者たちの言葉は、こうした「功」の側面を評価したものであり、現地のすべての人々が日本を無条件に歓迎したわけではないという「葛藤」の現実も忘れてはなりません。
戦後、アジア各国はそれぞれが独自の道を歩み、近代化と脱植民地化を達成しました。その過程において、日本の戦いは、決して一面的に「侵略」として断罪されるべきものではなく、白人支配からの解放という大きな歴史的潮流の中に位置づけられるべきです。
未来への視点
戦後アジア各国から見た日本の戦いを検証することは、私たち日本人自身が、自虐史観を払拭し、自国の歴史を多角的かつ客観的に捉え直す上で不可欠です。それは、過去の過ちを矮小化することとは異なり、光と影の両方を見つめることで、初めて真の歴史認識を構築できます。そして、その上に立って、アジア諸国との未来志向の国際関係を築いていくことが、21世紀の日本に求められているのではないでしょうか。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。