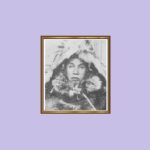第21回 東京裁判という“戦勝国の正義”
21-1. 判決は誰のためにあったのか?
正義の名のもとに裁かれた「敗戦国の罪」
1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて、東京市ヶ谷の旧陸軍士官学校で開かれた極東国際軍事裁判、通称「東京裁判」は、日本の戦争責任を裁き、戦後の国際秩序を形成する上で極めて大きな意味を持つ出来事でした。しかし、この裁判は「戦勝国の敗戦国に対する復讐劇」であり、「公平な裁判ではなかった」という批判が、当時から今日に至るまで根強く存在しています。果たして、この判決は本当に「正義」のためにあったのでしょうか?
「事後法」による裁きという根本的矛盾
東京裁判の最大の批判点の一つは、その法的根拠にあります。被告たちが問われた「平和に対する罪」「人道に対する罪」といった罪状は、戦争が始まる時点では明確な国際法として存在していませんでした。これらの罪は、戦争が終わった後に戦勝国が「急ごしらえ」で作ったものであり、過去に遡って法律を適用するという「事後法」の原則に反しています。
インド代表判事であるラダビノード・パール博士は、この点を厳しく批判しています。「法のないところに刑罰はなく、法のないところに裁判はない」という法の基本原則に反している以上、東京裁判そのものが無効であると主張しました 。彼は、この裁判を「復讐の欲望を満たすために、単に法律的な手続きを踏んだにすぎない」「儀式化された復讐」とまで断じています 。
「復讐」と「洗脳」の道具としての裁判
東京裁判の真の目的は、単に戦争犯罪者を処罰することだけではなかったと言われています。ケント・ギルバートは、「裁判の大きな目的は、戦争を起こした日本人に、その罪の意識を徹底的に刷りこむこと。そして二度と白人国家に対して戦争など起こそうと思わせない事にあった」と指摘しています。
つまり、東京裁判は、日本人に「自虐史観」を植え付け、愛国心や家族愛、道徳心といった日本の美徳を奪い、自己中心的な人間へと変えるための「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」の一環として位置づけられていたのです。このプログラムは、日本人がアメリカに対する憎悪の矛先を「昔の日本は悪い国だった」という自己否定へと変えるという、恐るべき効果を発揮しました。
「公正」とは何か?――戦勝国のダブルスタンダード
パール判事は、東京裁判が戦勝国だけが裁くという「不公正」を厳しく指摘しています。彼は、「戦勝国の国民であっても、かような裁判に付せられるべきである」と述べ、法の下の平等が貫かれない限り、真の世界平和の実現は不可能であると訴えました 。
実際、第二次世界大戦中、アメリカによる広島・長崎への原子爆弾投下、ドイツや日本への無差別都市爆撃など、戦勝国側も「人道に対する罪」と見なされうる行為を行っていました。パール判事は、原子爆弾の使用を「悲惨な決定」と強く批判し、「もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においてはこの原子爆弾使用の決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の指令、および第二次世界大戦中におけるナチ指導者たちの指令に近似した唯一のものであることを示すだけで十分である」とまで述べています。しかし、これらの行為は東京裁判では一切裁かれることはありませんでした。
この「ダブルスタンダード」こそが、東京裁判が「戦勝国の正義」に過ぎなかったという批判の核心にあります。
「歴史の捏造」と「共同謀議」の虚構
東京裁判の検察側は、日本の戦争が「満洲事変以来の『侵略戦争』のための『共同謀議』であった」と主張しました 。しかし、パール判事はこれを「もっとも奇異にしてかつ信ずべからざるものの一つ」と断じ、事実の寄せ集めにすぎず、共同謀議は存在しないと判定しています 。
東京裁判は、日本の過去の歴史、特に近代化の歩みを「侵略」と結びつけることで、日本の国際的地位を貶め、戦後の日本の行動を制限するという政治的な意図を持っていました。
マッカーサーの「本音」と日本の「無知」
ダグラス・マッカーサー連合国最高司令官自身も、戦後の証言で東京裁判の「不当性」を認める発言をしています。彼は1951年5月3日、米国議会の上院軍事外交合同委員会において、「彼ら(日本)が戦争を始めた目的は、主として安全保障上の必要に迫られてのことだった」と証言し、大東亜戦争を「自衛戦」であったと認識していました。彼はさらに「あんな裁判はやるべきではなかった」とも語っています。
しかし、このマッカーサーの重要な証言は、当時の日本のマスコミにはほとんど報じられることはありませんでした。それは、戦後日本の言論がGHQの「プレスコード」によって統制され、日本人に「自虐史観」を植え付けるという占領政策に協力していたためです。
「記憶のねじれ」と「真実の探求」
東京裁判は、日本の戦争責任を一方的に断罪することで、日本人の心の中に深い「罪悪感」を植え付けました。これにより、日本人は自国の歴史や文化に誇りを持つことをためらい、自虐的な歴史観が蔓延する結果となりました。
しかし、パール判事の意見書や、マッカーサーの証言、そして当時の国際情勢を多角的に検証するとき、東京裁判が「戦勝国の正義」という名のもとに行われた政治的裁判であり、その判決が必ずしも歴史の真実を反映したものではないことが明らかになります。
東京裁判の真の目的がどこにあったのかを問い直すことは、戦後日本が抱え続けてきた「記憶のねじれ」を解きほぐし、私たち日本人自身が、自国の歴史を客観的に、そして多角的に見つめ直すための重要な第一歩となります。
21-2. 法的根拠とその曖昧さ
法の支配を逸脱した「事後法」の適用
1946年(昭和21年)から始まった極東国際軍事裁判、通称「東京裁判」は、日本の戦争犯罪を裁くという名目のもとで行われました。しかし、この裁判は、その法的根拠の曖昧さから、今日に至るまで「戦勝国の正義」あるいは「政治的裁判」であるという批判を免れていません。特に問題視されるのは、刑法の基本原則である「事後法の禁止」を無視して、新たな罪状を適用した点にあります。
「平和に対する罪」という新設罪名
東京裁判で多くの被告に適用された「平和に対する罪」(A級戦犯の根拠)は、当時の国際法には存在しない、新しく創設された罪名でした。これは、ドイツのニュルンベルク裁判で、ナチスの指導者たちを裁くために考案されたもので、それを東京裁判にも当てはめたに過ぎません。
法の世界では、「法律のないところに刑罰はない(Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali)」という原則があります。これは、ある行為が行われた時点に、その行為を犯罪とする法律が存在しなければ、その行為を処罰することはできないという大原則です。しかし、東京裁判は、この原則を無視し、戦争が終わった後に「侵略戦争を計画し、準備し、開始し、遂行して、世界の平和を攪乱した」という罪を創設し、過去に遡って日本の指導者たちを裁きました。
インド代表判事のラダビノード・パール博士は、この「事後法」の適用を厳しく批判し、東京裁判そのものが無効であると主張しました。彼は、「法の根源はすべて国際法にあるはずだ。戦勝国だけが集まって、裁判のやり方をどうするかということを決めるのはまだしもとして、法の根源である国際法までもねじ曲げ、勝手な解釈や定義を下すことは許されない」と訴えています。
「殺人の罪」「人道に対する罪」の曖昧な定義
「殺人の罪」(B級戦犯の根拠)もまた、条約違反の罪から引き出されたものであり、宣戦布告せずになされた敵対行為を「殺人」と見なすという、当時の国際法にはない新しい罪名でした。また、「人道に対する罪」(C級戦犯の根拠)は、ニュルンベルク裁判でナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺などを罰するために新設されたもので、日本の戦争に当てはめることには無理がありました。
パール判事は、日本の指導者たちがナチスの指導者たちのような大規模な残虐行為を命令した証拠は全くないと指摘し、ナチと日本を同一視したところに東京裁判の大きな誤りがあるとしています。
「戦勝国の正義」の論理
このような法的曖昧さにもかかわらず、東京裁判が強行されたのは、それが「戦勝国の正義」という政治的論理に基づいて行われたからです。アメリカの首席検察官ジャクソン判事自身が、「われわれは、審理なしに彼らを処刑もしくは処罰しようと思えばできる。しかし公平な方法によって、到達した的確な有罪の判定なしに、無差別に処刑もしくは処罰することは、アメリカの良心に顧みて、あまりやましくないことはなく、かつまたわれわれの子孫たちが、誇りをもって記憶することのできるものではあるまい」と述べているように、形式的な「裁判」の体裁を整えることで、復讐を正当化しようという意図が見え隠れします。
東京裁判は、日本に「先の戦争への罪悪感」を徹底的に刷り込み、愛国心や道徳心といった日本の美徳を奪う「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」の一環として行われました。これにより、戦後の日本人は「昔の日本は悪い国だった」と信じ込まされ、自虐的な歴史観が蔓延することになりました。
マッカーサーの「自衛戦」発言の軽視
ダグラス・マッカーサー連合国最高司令官は、1951年(昭和26年)5月3日、米国議会の上院軍事外交合同委員会において、「彼ら(日本)が戦争を始めた目的は、主として安全保障上の必要に迫られてのことだった」と証言し、大東亜戦争を「自衛戦」と認識していました。彼はさらに「あんな裁判はやるべきではなかった」とも語っています。
しかし、このマッカーサーの重要な証言は、当時の日本のマスコミにはほとんど報じられることはありませんでした。GHQによるメディア統制(プレスコード)が敷かれ、日本人に「自虐史観」を植え付けるという占領政策に日本のメディアが協力したためです。これは、真実が国民に伝えられず、歴史認識が歪められていった典型的な例と言えるでしょう。
「共同謀議」の虚構と歴史の歪曲
東京裁判の検察側は、日本の戦争が「満洲事変以来の『侵略戦争』のための『全面的共同謀議』であった」と主張し、それを立証するために膨大な証拠を提出しました。しかし、パール判事はこの主張を「信ずべからざるものの一つ」と断じ、相互に独立した関連のない諸事件を寄せ集めたに過ぎず、共同謀議は存在しないと結論付けています。
この「共同謀議」の虚構は、日本の戦争を、特定の少数の人間による陰謀として描くことで、日本国民全体から戦争責任を切り離し、同時に日本の過去の行動を「悪」とすることで、戦後の日本の国づくりに制約を課すという政治的な意図を持っていました。
歴史の真実を問い直す意味
東京裁判が、法的な曖昧さと政治的な意図に基づいて行われた「戦勝国の正義」であったことは、パール判事の意見書や、マッカーサーの証言、そしてその後の歴史研究によって明らかになっています。この裁判の判決を絶対的なものとして受け入れることは、歴史の複雑性を無視し、私たち自身の歴史認識を歪めることに繋がります。
東京裁判の「法的根拠とその曖昧さ」を深く検証することは、戦後日本が抱え続けてきた「記憶のねじれ」を解きほぐし、私たち日本人自身が、自国の歴史を客観的に、そして多角的に見つめ直すための重要な一歩となります。それは、過去を断罪することではなく、過去から真に学ぶこと、そして未来へと活かすための視点を提供してくれるでしょう。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。