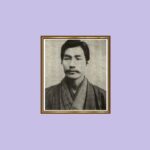
「佐久の大杉」──千年を越す神の柱(茨城県石岡市)
🟤佐久の大杉ー室町時代すでに千年杉との伝承
推定樹齢1300年ー佐久の大杉
鹿島神社(茨城県石岡市)
茨城県石岡市佐久。ここに鎮座する鹿島神社のご神木「佐久の大杉」は、ただの巨木ではない。伝承によれば、大化の改新(645年)の頃、大和朝廷からこの地に派遣された国司の後裔が植えたとされ、室町時代の応永34年(1427年)に神社が創建された当時、すでに「千年近い杉」と語られていたという。
その後、元禄16年(1704年)には武甕槌命(たけみかづちのみこと)を迎えて鹿島神社となり、佐久の大杉は神の宿る柱として人々の信仰を集め続けた。
昭和41年(1966年)には台風により上部約10mが倒壊。以降も落雷や風害に耐え、半身は枯死しながらも残る大枝にはいまなお青葉が芽吹き、悠然と生命を紡ぎ続けている。
環境省の巨樹調査からはなぜか漏れてしまったが、その威容と歴史は県指定天然記念物として正式に認められており、地域の誇りとして今も大切に守られている。
訪れた者は、この大杉がまさに鹿島神社の御神体そのものであることを体感するだろう。その荘厳な姿は、まるで柱のように天へと真っすぐ立ち、静かに“神域”の空気を放っている。
【所在地】
〒315-0117 茨城県石岡市佐久622(鹿島神社境内)
【アクセス】
・JR常磐線「石岡駅」より車で約20分
・常磐自動車道「千代田石岡IC」から約25分
・駐車スペースあり(境内付近)
歴史と自然の交差点──神秘なる佐久の大杉を、ぜひその目で。
<現地説明文>
茨城県指定天然記念物 佐久の大杉
昭和十六年三月三十一日指定
樹高 三十八・六m
幹周り 八・九m
推定樹齢 千三百年
この大杉は、鹿島神社の御神木として、長い歳月にわたり地域の人々に親しまれ崇拝されてきました。伝承によれば、神社が創建されたといわれる応永期(1394〜1428)には、「すでに千年に近 い杉」として知られていたといわれています。
度重なる落雷や台風等の被害によって、樹勢の衰退が目立つようになったことから、平成九年から十二年にかけて、茨城県・八郷町・佐久の大杉保存会・樹木医が一丸となり、樹勢回復の治療に取り 組みました。土壌改良、大枝の落下防止のための銅管支柱の取り付け、樹幹の亀裂部分への特殊な樹脂の注入などが施され、現在は着葉量も増加し、緑もますます濃くなってきました。
また、土壌改良により発根した多数の細根を保護するために、樹木医の橋本憲二氏から見学者用の歩廊が寄贈されました。この巨木を後世に残すためにも、歩廊から見学されますようご協力をお 願いいたします。
平成二十一年三月
佐久の大杉保存会
石岡市教育委員会
県指定天然記念物 佐久の大杉
指定年月日 昭和十六年三月三十一日
所在地 石岡市佐久
杉は湿潤な日本の風土に適した、日本固有の樹種である。古代より住居、日用品等に活用されてきた。稲作が伝来した際用水の管理等に大きく貢献した。
当大杉は鹿島神社の神木として地域の人々の厚い信仰をうけ、長年月にわたりかつ稀にみる丁重さで余命を保ってきた。
経、樹齢等、東日本を代表する巨樹である。数次にわたる落雷、台風等の損傷を受けながら、数本の大枝になお緑の活力を保っている姿は、御神木にふさわしい尊さである。
昭和六十年三月 石岡市教育委員会
🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より
🟤ご紹介した千年杉・大杉のある場所

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)
単行本 – 2022/10/27
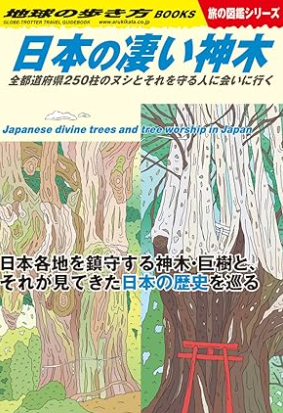
旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。
(C)【歴史キング】×【御神木マニア】





