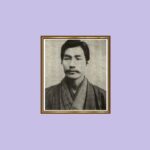
大阪・能勢の神域に立つ千年の巨木「野間の大ケヤキ」【国指定天然記念物】
🟤関西最大級 ー樹齢1000年以上│神域のケヤキ
推定樹齢1000年以上
野間の大ケヤキ(大阪府能勢町)
かつて“蟻無宮(ありなしのみや)”という神社があった地に、今もなお静かに聳え立つ――それが大阪・能勢町にある「野間の大ケヤキ」である。樹齢1,000年以上ともいわれ、昭和23年に国の天然記念物に指定されたこの巨木は、近畿を代表するケヤキであり、まさに“神域の象徴”といえる存在だ。
その幹回りは13メートル、樹高は27メートルを超え、枝張りは東西約40メートル。かつて境内を覆い尽くしていた神木は、まるで神の息吹を宿したような威厳と、静寂の中に響く存在感を放っている。旧・蟻無神社のご神木であったことから、“神が宿る木”として今も地元で崇められ続けている。
蟻無神社の創建は鎌倉時代中期・承久2年(1220年)と伝えられ、その社庭の砂にはアリ除けの霊験があるという伝承も残る。明治時代に野間神社へと合祀された後も、大ケヤキは変わらずこの地を守り続けてきた。
地元では、この御神木の新芽の出方によって農作物の豊凶を占ったとも伝えられている。神社跡地には現在、けやき資料館が設置され、ケヤキと能勢の自然・文化を学ぶ場としても親しまれている。
樹勢回復のための手当も丁寧に施され、今もなお静かに生長を続けるこの御神木。幹を見上げ、枝の広がりに包まれれば、人智を超えた悠久の時間に触れたような感覚に誘われるだろう。
📍所在地:大阪府豊能郡能勢町野間稲地266
🚃アクセス:能勢電鉄「妙見口駅」→阪急バス「本滝口」下車、西へ徒歩5分/駐車場あり
<現地説明文>
国指定天然記念物 野間の大けやき
昭和二十三年一月十四日 文化財保護法により指定
この大けやきを中心とする一画の地は、もと、「蟻無宮」という神社の境内で、この樹はその神の憑り代、すなわち御神体ともいうべき神木であったと思われる。
樹齢千年以上と推定されるこの樹は、目通りの幹回り約十四メートル、高さ三十メ ートル、枝張り南北三十八メートル、東西約四十ニメートルあり、一樹にしてよく社叢をなし、けやきとして大阪府下で一番、全国的にも第四番目を誇る巨樹である。
古来よりこの大けやきにまつわる伝承を探れば、里人らは春さきに出る新芽の出具合によって、この年の豊凶を占ってきたと伝えている。
また、社庭の砂を請い受けて持ち帰り、はたけもの(野菜)や屋内に散布すれば、蟻が退散するといい、その効験は遠くまで知れわたっていた。おそらく社名蟻無によるものであろう。
さらに一説では、有無社は紀貫之を祭神としており、貫之が同じく三十六歌仙の一人である源公忠に贈った歌により社名を付したという。すなわち
『手にむすぶ水にやとれる月影の あるかなきかの世にこそありけれ』
又经房遺書(安徳天皇ご潜幸の伝承)の一節に「・・・河合にいとおほきなる沢ありて水よどめり、さハ(わ)の中じまに市女が笠てふものに似たるいとうるはしき木の紅葉せしあり・・・」(原文)、奥書きは、「建保五丑年」とあり、なにか大けやきを連想させるものがある。
当社の創祀は、承久二庚辰三月十五日とあり、遠く鎌倉時代にさか上るが、明治四十五年当社祭神は野間神社に合祀された。以後、神木の保全・境内の清浄化に蟻無会 (前身は蟻無講中)をはじめ、郷民こぞって奉仕してきたところである。
とくに最近樹勢回復のため治療を施し、ようやく往時の姿によみがえろうとしている。
平成十年三月
文化庁
大阪府教育委員会
能勢町教育委員会
🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より
🟤ご紹介した{国指定天然記念物・大ケヤキ}のある場所

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)
単行本 – 2022/10/27
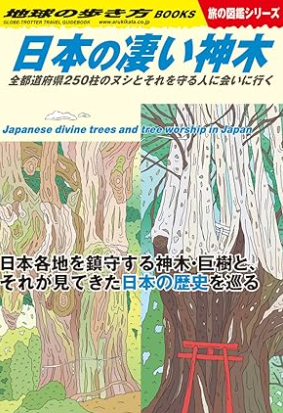
旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。
(C)【歴史キング】×【御神木マニア】





