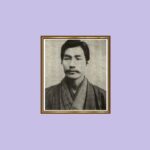
第27回 歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと
27-1. 歴史教育の課題と可能性
「作られた歴史」からの脱却と、真の歴史教育の探求
戦後日本における歴史教育は、GHQ(連合国軍総司令部)による占領政策の影響を強く受け、特定の歴史観を国民に植え付ける役割を担ってきました。この結果、多くの日本人の心に「自虐史観」が深く根付き、自国の歴史や文化に対する健全な誇りを持つことが難しい現状があります。しかし、歴史を学ぶ真の意味は、過去を一方的に断罪したり、美化したりすることではありません。過去の出来事を多角的かつ客観的に理解し、そこから得られる教訓を未来に活かすことこそが、歴史教育の本来の目的です。現在の日本の歴史教育は、どのような課題を抱え、そしてどのような可能性を秘めているのでしょうか。
日本の歴史教育が抱える「戦後の宿題」
戦後の歴史教育は、「二度と戦争をしない」という強い平和への願いに基づいて構築されました。その理念自体は尊いものですが、その過程で、歴史の複雑性や多面性が失われ、特定の「日本像」が強調されるようになりました。
- 「自虐史観」の固定化: 教科書やメディアを通じて、日本の近代史が「侵略の歴史」として描かれ、日本の「加害責任」が強く強調されました。東京裁判の判決内容が絶対的なものとして伝えられ、日本がなぜ戦争へと向かわざるを得なかったのかという複雑な背景や、日本の「生存権」をめぐる苦悩、そしてアジアにおける「白人支配からの解放」という大義名分については、十分に語られることがありませんでした。この結果、多くの日本人は、自国の過去を一方的に「悪」と認識し、過度な「反省」を強いられることになりました。
- 「軍部悪玉論」の単純化: 戦前の日本が「軍部の暴走」によって戦争へと突き進んだという単純な図式が教科書の主流となり、当時の複雑な社会状況や国民の意識、国際環境による「追い詰められた選択」という側面が軽視されました。これにより、国民は主体的に歴史を考える機会を失い、特定の誰かに責任を押し付けることで思考停止に陥りやすい傾向が生まれたと言えるかもしれません。
- 「日本人としての誇り」の喪失: 自虐史観は、日本人から自国の歴史や文化に対する健全な「誇り」を奪い、国家というものに対する意識を希薄にさせました。愛国心を持つことすら、どこか後ろめたい感情を抱くようになり、自国の防衛や主権に対する関心も薄れてしまうという弊害も指摘されています。多くの日本人が「日本人とは何か」という問いに明確な答えを見出せない状況は、戦後教育が残した大きな課題です。
「作られた常識」を乗り越える可能性
しかし、GHQによる占領はとっくに終わり、私たちは自らの手で未来を築く時代に生きています。今こそ、戦後教育によって作り上げられた「常識」を批判的に見つめ直し、真に多角的で客観的な歴史教育を追求する時です。
- 多角的な視点の導入: 歴史を学ぶ際には、日本国内の視点だけでなく、欧米諸国、そして何よりもアジア諸国の多様な視点から出来事を捉えることが不可欠です。例えば、アジアの独立指導者たちが、日本の戦いを「白人支配からの解放」のきっかけとして評価していた事実など、これまで十分に語られてこなかった側面に光を当てることで、歴史の複雑性と多面性を理解することができます。
- 一次資料に基づく探求: 教科書の記述を鵜呑みにするだけでなく、当時の新聞、文書、手記、証言、映像といった一次資料に自ら触れる機会を提供することが重要です。これにより、生徒たちは、歴史が「作られた物語」ではなく、様々な事実や解釈の上に成り立つものであることを実感し、主体的に歴史を考察する力を養うことができます。
- 「なぜ」を深掘りする教育: 歴史の出来事を単に暗記するのではなく、「なぜその出来事が起こったのか」「当時の人々は何を考え、どのように行動したのか」という「なぜ」を深く問い続ける教育が求められます。経済的要因、国際関係、社会心理など、多岐にわたる側面から歴史を分析する力を育むことで、過去の教訓を現代に活かすことができるようになります。
- 「反省」と「誇り」の両立: 歴史教育は、過去の過ちを真摯に「反省」する心を育むと同時に、自国の歴史や文化に対する健全な「誇り」を持てるようにすることも重要です。過度な自己否定は、むしろ真の反省を妨げます。自国の「功」と「罪」の両方を見つめ、それを次世代へと伝えることで、初めて私たちは未来に責任を持つことができるのです。
- 対話を通じた学び: 歴史認識の相違は、国際関係における摩擦の原因となります。教育の場において、異なる歴史認識を持つ国々の見解を学び、その背景にある「なぜ」を理解しようと努めることで、未来の国際社会で活躍するための「対話力」と「共感力」を養うことができます。
歴史を学ぶことは、未来を選ぶこと
歴史を学ぶことの真の意味は、過去を単に知ることではありません。それは、過去から得られた教訓を活かし、より良い未来を「選ぶ」ための力を身につけることです。GHQが作り上げた「作られた常識」の呪縛から解放され、多角的で客観的な歴史認識を国民全体で共有すること。
そして、その上に立って、日本人としての健全な誇りを取り戻し、国際社会の平和と発展に主体的に貢献できる人材を育成すること。これこそが、未来を担う子どもたち、そして私たち大人自身に課せられた、歴史教育の最大の「可能性」であり、「もう一つの昭和史」を語り継ぐ意味となるでしょう。
27-2. 民主主義社会と歴史の関係性
「作られた歴史」が民主主義を蝕むとき
戦後、日本は「民主主義国家」として再出発しました。民主主義とは、国民一人ひとりが主体的に考え、議論し、自らの意思で未来を選ぶ社会です。しかし、この民主主義社会が健全に機能するためには、国民が過去の歴史を正しく理解し、そこから教訓を得ることが不可欠です。残念ながら、戦後日本に深く根付いた「自虐史観」は、民主主義社会における国民の歴史認識を歪め、主体的な意思決定の妨げとなってきました。この「作られた歴史」が、いかに民主主義を蝕むのか、そして歴史と民主主義の健全な関係とは何かを考えてみましょう。
「戦後の宿題」が残した民主主義の影
GHQ(連合国軍総司令部)による占領政策は、日本に民主主義を導入するという名目で行われました。しかし、その過程で、GHQは東京裁判やメディア統制、教育改革を通じて、日本人の心に特定の歴史観を植え付けました。これは、日本人を「過去の罪人」として位置づけ、自国の歴史や文化に対する誇りを奪うことで、二度と白人国家に逆らわない、従順な国民を作り出すという政治的な意図が隠されていました。
この結果、戦後日本の民主主義社会には、いくつかの「影」が落とされました。
- 主体性の欠如: 「日本は悪かった」「侵略国家であった」という自己否定の歴史観が強調されたことで、多くの日本人は、自国の過去を主体的に考えることを放棄し、与えられた歴史像をそのまま受け入れてしまう傾向が強まりました。民主主義社会では、国民一人ひとりが批判的思考を持ち、自らの判断で行動することが求められますが、歴史に関する議論においては、その主体性が失われがちになったのです。
- 責任の所在の曖昧化: 東京裁判が、一部の指導者に戦争責任を押し付けることで、国民全体から戦争責任を切り離したことは、国民の間に「自分たちには責任がない」という意識を生み出しました。しかし、民主主義社会では、国民が国家の意思決定に最終的な責任を負うべきです。この責任の所在の曖昧化は、過去の過ちから真に学び、未来に活かすという民主主義の健全なサイクルを妨げました。
- 「愛国心」の否定と防衛意識の希薄化: 「愛国心」が「軍国主義」と同一視され、タブー視されたことで、日本人は自国を愛し、守るという健全な感情を育むことが難しくなりました。民主主義社会において、国民が自らの意思で国を守る気概を持つことは、国家主権を維持する上で不可欠です。しかし、戦後教育の影響で、自国を守る意識が希薄になり、国の安全保障に関する議論が深まりにくいという課題も生じています。
- 国際社会における対話の困難: 自虐史観に囚われることで、日本は国際社会で自国の主張を堂々と行うことが難しくなりました。過去の過ちを謝罪することは重要ですが、同時に自国の正当性や貢献を語ることができなければ、真の対等な対話は成り立ちません。これは、日本の国際的な発言力を弱め、民主主義国家としての責任を十分に果たせない状況を生み出しました。
歴史を学ぶことこそが民主主義の根幹
では、民主主義社会において、歴史を学ぶことの真の意味は何でしょうか。それは、国民一人ひとりが「知る権利」を行使し、過去を批判的に検証することで、未来を「選ぶ」ための判断力を養うことにあります。
- 批判的思考力の育成: 歴史を多角的に学ぶことで、私たちは一つの情報源や一つの見方に固執せず、様々な視点から物事を分析する批判的思考力を養うことができます。これは、現代社会においてフェイクニュースやプロパガンダを見抜く上でも不可欠な能力であり、民主主義社会の健全性を保つ上で極めて重要です。
- 未来への責任を自覚する: 過去の出来事から学ぶことで、私たちは同じ過ちを繰り返さないための知恵を得ます。歴史上の成功と失敗を理解することは、未来の政策を立案し、より良い社会を築くための指針となります。国民が歴史を通じて未来への責任を自覚し、積極的に社会参加することで、民主主義はより強固なものとなります。
- 多様性の尊重と共生: 異なる国の歴史認識や、国内の多様な声に耳を傾けることは、他者の文化や価値観を尊重する心を育みます。歴史を通じて多様性を理解することは、民主主義社会における共生を促進し、国際社会での平和的な共存にも繋がります。
- 健全なナショナリズムの形成: 自国の歴史の光と影の両方を受け止め、健全な誇りを持つことは、排他的ではない「健全なナショナリズム」を育みます。自国を愛し、その発展を願うことは、他国を尊重し、国際協調に貢献するための基盤となります。これは、民主主義社会において、国民が主体的に国家運営に関わる上で不可欠な感情です。
- 「戦後の宿題」を乗り越える: GHQが作り上げた「作られた常識」の呪縛から解放され、多角的で客観的な歴史認識を国民全体で共有すること。これこそが、民主主義社会における「戦後の宿題」を乗り越え、真に主体的な国民を育成するための鍵となります。
歴史が照らす民主主義の未来
歴史を学ぶことは、過去を断罪するためではなく、未来を選ぶためです。特に民主主義社会においては、国民一人ひとりが歴史を深く理解し、自らの意思で判断する力が、国の進むべき道を決定します。
私たちがGHQによる占領から既に長い時を経てもなお、その影響から抜け出せないとすれば、それは私たち自身が、歴史を主体的に学び、自らの手で「歴史認識」を構築する努力を怠ってきた証拠なのかもしれません。
今こそ、私たちは「もう一つの昭和史」を語り継ぐ意味を深く考え、歴史教育を通じて、未来を担う若い世代が、過去の教訓を活かし、真の民主主義社会を築き上げていけるように導くべきです。歴史を学び、未来を選ぶこと。それは、私たち日本人にとって、最も大切な「宿題」であり、希望に満ちた未来への第一歩なのです。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。




