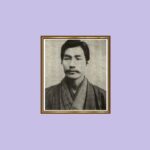
有名すぎる偉人のひとり。『東洋のシンドラー』と呼ばれた外交官・杉原千畝(1900年~1986年)
かつて『東洋のシンドラー』と呼ばれた日本人外交官がいました。
『シンドラー』と言えば第二次世界大戦中にナイス・ドイツのホロコーストという大量虐殺が国ぐるみ政策で行われる中で1000人を超えるユダヤ人の命を救ったという偉大な人物です。
その功績を称え、あのスピルバーグ監督の指揮のもとで
映画『シンドラーのリスト』が作られ、1994年にはアカデミー賞を受賞し
世界中の視聴者の大きな感動をよびました
では『東洋のシンドラー』とは誰のことでしょう?
ちなみにこちらのシンドラーも2015年に唐沢寿明さん主演で映画になりました
そう
杉原千畝(すぎはらちうね)さんです
杉原さんも、本家シンドラーと同じように多くのユダヤ人を救いました
しかしなぜ杉原さんはそのような行動をしたのでしょうか
杉原さんの信念やポリシー、行動の源泉・・その答えになるようなエピソードを
息子さんである杉原伸生さんが語っています
父・千畝さんに
「なぜユダヤ人を助けたの?」と素直に聞いたことがあるそうです
返ってきた返事はすごくシンプル
「かわいそうだから。」
杉原さんの信念やポリシー
行動の源泉は一体何だったのでしょうか
小さい頃、杉原さんは父親から将来は医師になるように進められていました。
令和の今でこそ、自身の道は当たり前のように自分で決めていますが、当時は親の敷いたレールに乗らないのはそう簡単なことではありませんでした。杉原さんは自分が得意であった英語を活かそうと英語教師の道を志しました。しかし、当然、父の怒りに触れ、金銭的援助も応援も得られない状況に陥りました。そんな中で『外務省の官費留学制度』の存在を知ることとなります。
杉原さんは直ぐに応募し見事合格となります。
{国からのお金で異国の地へ留学ができる}というこの制度は、杉原さんにとって大きなチャンスであり、躊躇することなく海を渡りまずは異国の地・ハルビンへ赴きます。
ここから杉原さんの活躍はいくつも挙げられ昇進までも見えたいたらしいですが、ご本人は帰国することを選びます。
杉原さんの手記に当時の心境が記されています。
「軍人たちの狭い了見による判断を目の当たりにして、嫌気がさした」
1939年(昭和14年)杉原さんは再び海を渡ります。
北ヨーロッパのリトアニア共和国、その首都カウナスに日本領事館・領事代理として赴任します。
第二次世界大戦前の混沌とした世の中であり、また国境を接している旧ソ連がリトアニアを併合しようとしている大変な時期でした。赴任直後であるのに直ぐ「危険だからリトアニアを脱出するように」と外務省本省から通達が出ていたくらいです。
そんな中で日本領事館の周りに群がっていたのが、後に杉原さんが救ったユダヤ人たちでした
その人達はナチス・ドイツにポーランドを占領され、逃げてきたのです。
この状況を放っておくとどうなるのか結末は誰しもに見えていました。
皆、直に拘束され収容所に送られてしまうという結末です。
「なんとか救う手立てはないのか」
杉原さんは思考を巡らせましたが、例えば数名程度のビザであれば、杉原さん1人の判断で可能ですが、ビザを必要としている人たちは軽く100人を超えていたので外務省の許可が必要です。
この現状を伝え、相談したものの返ってきた返答はノー
『ドイツとは同盟関係にある』という重い理由でした。
仕方がないという言葉だけで整理してはいけないかもしれませんが、普通に考えると、国と国との関係・自身が外務省の人間であるという立場・戦争前の混沌とした中で、自身に危険が及ぶということから、外務省本省から通達どおりに大抵の人がすぐに国を脱出するでしょう。
後ろ髪をひかれるような思いがあっても皆そうすると思います。
しかし杉原さんが出した結論は違いました。
なんと、領事館に残り難民一人一人と面談をしてビザ発給種類を作成したのです。ただし、苦難は続きました。
旧ソ連がリトアニアの正式併合を決定し、安全のために一刻も早く国を出る必要がありました。
しかしそこから約20日間杉原さんはリトアニアを出ることをせず期限ギリギリまでビザ発給のために一人で書類を書き続けます。
一説には自身が電車で移動しなくてはいけないという本当にそのギリギリまでビザ発給をし続けたと言われています。
結局、杉原さんが作成したビザは2000を超えました。
戦争による空襲で公式記録は残ってませんが、家族用のビザも含まれていたので、杉原さんのおかげで
脱出できたユダヤ人は6000人にもなると考えられています。
杉原さんは無事に日本へと帰ってくることができましたが、本国の外務省に復帰後、しばらくして個人判断での大量ビザ発給の責任を追求され外務省を解雇されることとなります。
異国の地で確かな実績を残し、外務省・外交に貢献してきましたが、国に背いての行動は失職覚悟のものであったと後に判明しています。
杉原さんが外務省を去り、月日は経過します。それから彼は民間企業に務めながら年月を重ねていました。随分と時間が経過し世間でも杉原さんの存在が忘れた頃、国外から杉原さんを探しているという電話がなります。1968(昭和43)年の事でした。
相手は、名前をニシェリと言い、イスラエル大使館の書紀・参事官でした。
彼は、かつて杉原さんのビザ発給のおかげで命を救われたユダヤ人の一人でした。
恩人・杉原さんをずっと探し続けていたのです。
ほどなくして感動の再会を果たし、その翌年には招待を受けてイスラエルを訪れます。
そこで杉原さんを出迎えたバルフティック宗教大臣もまた杉原さんにビザ発給してもらった一人でした。1985(昭和60)年イスラエル政府から、杉原さんに対して諸国民の中の正義の賞(ヤド・バシェム賞)
が贈られます。この功績を語る上で多角的な視点も重要であると考えています。
日本人初の栄誉に賞賛の声と共に、国の訓命に反したことに対して批判の声があったのも事実です。
実際、杉原さん自身が、自分のしたことが外交官として間違っていたかもしれないと語っています。
しかし、自分を頼ってきた難民たちは女性や老人、子供もおり
その何千もの命を見殺しにすることはできなかったとも話しています。
杉原さんの信念やポリシー、行動の源泉・・
杉原さんは決して英雄になりたかったわけではありません。
ただ、藁にも縋るような思いで自分を頼ってくる人を、凝り固まった考えで閉ざしてしまっては
『人の道に反する』と思ったわけです。
ご本人は「当たり前のことをした」と仰っていますが、心底本音なのでしょう。
立場の違いや、人生観や宗教観、ちょっとしたボタンの掛け違いによって、人間は様々な決断や行動をします。もしかしたら『いくつもの正解』が存在するのかもしれません。
杉原さんの発給したビザは「命のビザ」と言われその勇気と人道性は高く評価されています。
当サイトも『ひとつの正解』として、その賞賛に深く共鳴いたします




