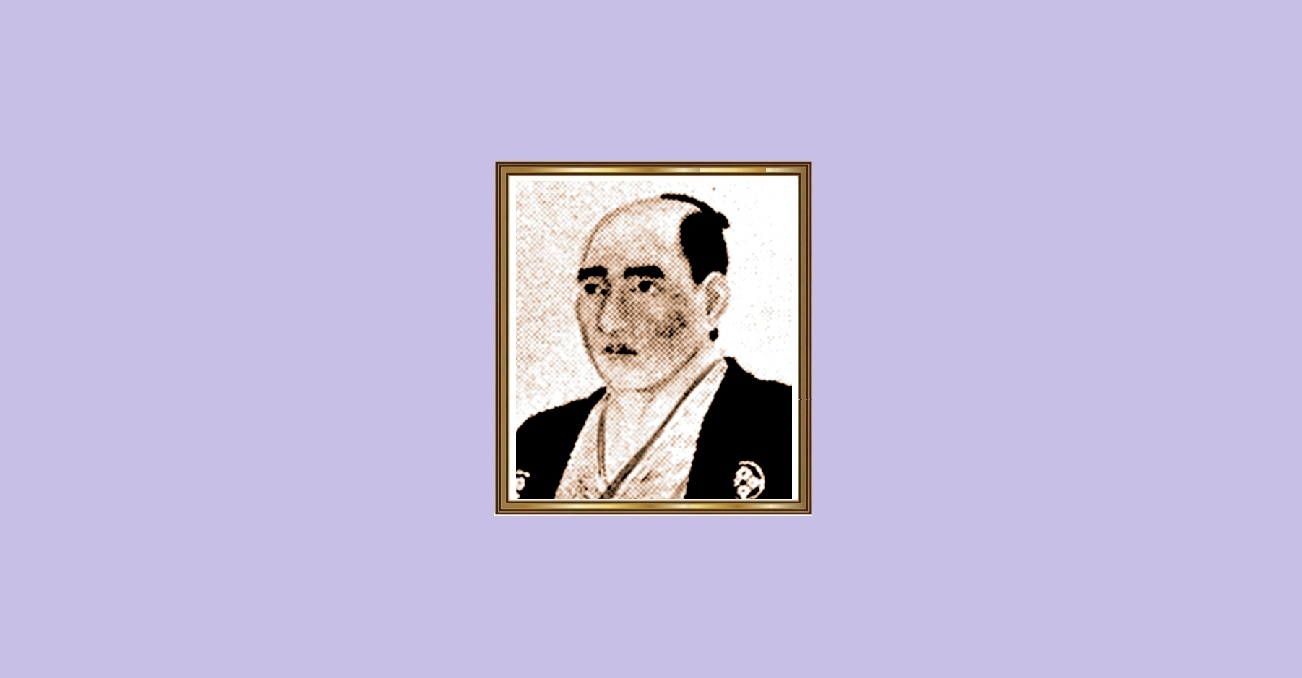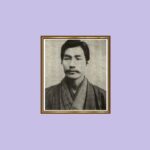
茨城県の偉人:間宮林蔵 — 鎖国日本の空白を埋めた、不屈の「探検の鬼」

茨城県
「この海峡の発見は、地理学上のみならず幕府の北方経営に多くの利益をあたえることは確実であった」
この言葉が示す通り、江戸時代後期に日本の北の果て、樺太を探検し、世界地図の空白を埋めたのが、茨城県つくばみらい市(旧・伊奈町)に生まれた間宮林蔵(まみや りんぞう)です。
農民の子から身を起こし、測量家、探検家、そして幕府の隠密として日本の国防に尽くした彼の生涯は、まさに不屈の精神と探究心に満ちています。「文政の三蔵」の一人にも数えられ、日本人でただ一人、海峡にその名を残した偉大な功績は、現代を生きる私たちに、未知の領域に挑む勇気と、真実を追求する知恵を教えてくれます。
測量家としての目覚め:伊能忠敬との出会い
間宮林蔵は、1775年(安永4年)頃、常陸国筑波郡上平柳村(現在の茨城県つくばみらい市)の農家に生まれました。幼い頃から地理や算術に才能を見せ、特に利根川の支流である小貝川の堰止め工事に加わった際、その利発さが幕府の役人・村上島之丞の目に留まり、江戸へ出て下級役人となります。
彼の人生の大きな転機は、1800年に初めて蝦夷地(現在の北海道)に派遣された際に、測量調査に来ていた伊能忠敬(いのう ただたか)と出会ったことです。忠敬は、若き林蔵の才能を見抜き、測量技術を直接指導しました。この師弟関係を通じて、林蔵の測量技術は飛躍的に向上し、後の探検や地図作成において不可欠な武器となりました。
林蔵はその後、伊能忠敬が測量できなかった蝦夷地や南千島の測量に従事し、その成果は忠敬の『大日本沿海輿地全図』の蝦夷地部分に大きく貢献することになります。
樺太が島であることを発見し、世界地図に名を残す
当時の日本では、樺太(サハリン)は大陸と陸続きの半島であると広く信じられていました。しかし、蝦夷地を脅かすロシアの南下政策に対し、幕府は樺太の実態を正確に把握する必要に迫られていました。
1808年(文化5年)、林蔵は幕府の命を受け、松田伝十郎と共に樺太を探検します。しかし、確証を得られなかった林蔵は、帰着後わずか20日ほどで再び樺太へ出発。今度は単身で、アイヌの協力者と共に西海岸を北上し、樺太北部と大陸の間に海峡があることを確認しました。この大発見によって、樺太が半島ではなく独立した「島」であることが証明されたのです。
この海峡は、後にドイツ人医師・シーボルトによって『日本』という著書の中で「マミアノセト(間宮海峡)」と名付けられ、ヨーロッパに紹介されました。これにより、間宮林蔵の名は世界地図に刻まれ、日本人でただ一人、地理上の大発見に名を残す偉業を成し遂げたのです。
さらに彼は、鎖国下の国禁を破る覚悟で、アイヌの助けを借りて海峡を渡り、シベリアの黒竜江下流にある清国の役所「デレン」にまで赴き、ロシアの動向や北方情勢を探るという、命がけの諜報活動を行いました。この記録は『東韃地方紀行』として幕府に提出され、国防の基礎資料となりました。
隠密としての後半生とシーボルト事件
樺太探検後、林蔵は幕府の普請役となり、その卓越した調査能力は「隠密(おんみつ)」としての諜報活動に活かされることになります。彼は、全国各地を巡り、外国船の動向や密貿易の実態を探るなど、日本の国防に尽くしました。
「密告者」としての誤解と真実
彼の名が歴史に残るもう一つの有名な出来事が、1828年(文政11年)のシーボルト事件です。当時、外国との文通はご法度でしたが、林蔵宛にシーボルトから届いた手紙の包みを、彼は法に従って開封せずに上司の勘定奉行に提出しました。これがきっかけとなり、シーボルトと幕府天文方・高橋景保の交流が発覚し、高橋は獄死、シーボルトは国外追放という大事件に発展しました。
これにより、世間では林蔵が「密告者」として非難され、その名声は失墜したという誤った見方が広まりました。しかし、シーボルト自身は帰国後、著書『日本』の中で林蔵を「大旅行家、学者として有名なばかりでなく、卓越した武人として名誉の者」と称賛し、「間宮海峡」の名を世界に紹介しています。林蔵の行動は、幕府の役人として職務を全うしたものであり、その真実を知る人々からは高く評価されていました。
彼の晩年は身体の衰弱から隠密活動も困難になったとされますが、死の直前まで水戸藩主・徳川斉昭(とくがわ なりあき)に北方情勢の意見を求められるなど、その知識と経験は日本の国防にとって不可欠なものでした。
間宮林蔵ゆかりの地:探検家の足跡を辿る旅
間宮林蔵の生涯は、彼の生まれ故郷である茨城から、探検の地である北海道、そして終焉の地である東京へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、その不屈の精神と偉大な功績を肌で感じることができます。
茨城県つくばみらい市:生誕の地と記念館
- 間宮林蔵生家・記念館(茨城県つくばみらい市上平柳):林蔵が生まれた農家が復元されており、隣接する記念館では、彼の生涯や探検の軌跡、関連資料が展示されています。
- 専称寺(せんしょうじ)の墓所(茨城県つくばみらい市上平柳):林蔵が樺太探検に出発する決意を固めた際、自ら建立したと伝えられる墓が、故郷の菩提寺に残されています。この墓は、彼が故郷に帰れないかもしれないという覚悟を物語るものです。
- 間宮林蔵立像(茨城県取手市 小貝川岡堰):小貝川の堰を見つめる林蔵の像は、彼が幕府の役人として認められるきっかけとなった場所です。
北海道稚内市:旅立ちの地と顕彰の地
- 間宮林蔵渡樺出港の地碑(北海道稚内市第二清浜地区):宗谷岬から西へ3kmほどの海岸には、林蔵が樺太探検に出発したとされる場所があり、墓石の碑が建てられています。
- 間宮林蔵立像(北海道稚内市宗谷岬):日本最北端の宗谷岬には、樺太の彼方を見つめる林蔵のブロンズ像が建ち、その偉業を称えています。
東京:終焉の地
- 間宮林蔵墓所(東京都江東区平野 本立院):晩年を過ごし、その生涯を閉じた場所の近くに墓所があります。墓石には、水戸藩主・徳川斉昭が選した文字が刻まれています。
間宮林蔵の遺産:現代社会へのメッセージ
間宮林蔵の生涯は、私たちに「探検家精神」の重要性を教えてくれます。彼は、当時誰も知らない未踏の地に進み、その真実を明らかにするために命がけで挑戦しました。彼の「貧弱な装備でも、工夫と勇気があれば不可能はない」という姿勢は、現代の私たちに、困難な課題に直面したときに、安易に諦めるのではなく、知恵と勇気を持って挑むことの大切さを教えてくれます。
また、彼の生涯は、単なる探検家としてではなく、国の将来を真剣に憂い、そのために自身の知識と能力を惜しみなく捧げた「愛国者」としての側面も強く示しています。彼の功績は、日本が鎖国という時代を終え、世界へと目を向けていく上で不可欠な礎となりました。
「間宮海峡」という、世界地図にただ一つ残された日本人の名。それは、一人の農民の子が、探究心と不屈の精神で成し遂げた、奇跡の物語の証です。間宮林蔵の遺した功績は、日本が世界に誇るべき偉大な歴史であり、私たち自身の可能性を信じるための、力強いメッセージを放ち続けています。
(C)【歴史キング】

(講談社文庫 よ 3-27) 文庫 – 2011/10/14
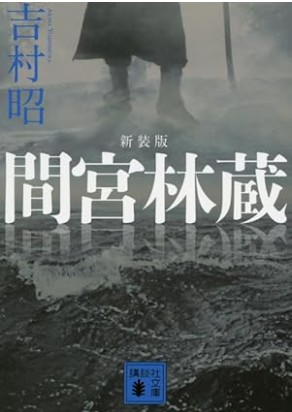
19世紀初頭、世界地図の中で樺太は唯一謎の地域だった。樺太は島なのか、大陸の一部なのか。樺太調査に挑んだ間宮林蔵は、苛酷な探検行の末、樺太が島であることを確認する。その後、シーボルト事件に絡んで思いがけない悪評にさらされ、さらには幕府隠密として各地を巡った、知られざる栄光と不運の生涯を克明に描く。(講談社文庫)
19世紀初頭、世界地図の中で樺太は唯一謎の地域だった。樺太は島なのか、大陸の一部なのか。樺太調査に挑んだ間宮林蔵は、苛酷な探検行の末、樺太が島であることを確認する。その後、シーボルト事件に絡んで思いがけない悪評にさらされ、さらには幕府隠密として各地を巡った、知られざる栄光と不運の生涯を克明に描く。