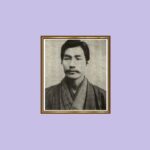
第28回 私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的
28-1. 「アジア解放」という理念の核心
「侵略」のレッテルに隠されたもう一つの大義
第二次世界大戦後、日本の大東亜戦争は、主に「侵略戦争」として語られ、日本はアジア諸国に多大な苦痛を与えた「加害者」であるという歴史認識が深く根付いてきました。東京裁判やGHQ(連合国軍総司令部)による徹底的な情報統制と教育改革は、この「侵略」の物語を国民の「常識」として定着させ、日本の戦争目的の真の姿を覆い隠してきました。しかし、この戦争が、白人による有色人種国家に対する植民地からの解放という、もう一つの壮大な「大義名分」を持っていたことを忘れてはなりません。この「アジア解放」という理念の核心に迫ることは、戦後日本の「自虐史観」を乗り越え、私たちが真に受け継ぐべき歴史的遺産を見出す上で不可欠です。
白人支配という「世界の現実」
大東亜戦争が始まる直前の世界は、白人列強による植民地支配が当たり前の「世界の現実」でした。イギリスは広大なインド帝国を擁し、マレー半島やビルマを支配していました。フランスはインドシナを、オランダは石油資源豊かな東インドを、アメリカはフィリピンをそれぞれ植民地としていました。これらの地域では、現地住民の意思とは無関係に、宗主国の利益が最優先され、資源は本国に吸い上げられ、教育や政治は宗主国の都合の良いように運営されていました。人種差別も公然と行われ、アジアの人々は「二級市民」として扱われていたのです。
日本は、明治維新以降、非西洋国家としては稀有な近代化を成し遂げ、欧米列強に肩を並べる国力を築き上げました。しかし、世界恐慌後のブロック経済化の中で、資源に乏しい日本は、欧米列強によって経済的な生命線を断たれ、国家存亡の危機に瀕していました。石油の全面禁輸を含むABCD包囲網は、日本を「戦うか、滅びるか」という究極の選択に追い込んだのです。
「大東亜共栄圏」に込められた「解放」の理念
このような状況下で、日本が掲げたのが「大東亜共栄圏」という理念でした。これは、単なる日本の勢力圏拡大を意味するものではなく、日本の建国精神である「八紘一宇」に基づき、アジア諸民族を白人支配から解放し、共存共栄の秩序を築くという壮大な構想でした。当時の日本の指導者たちは、この戦争を、欧米列強による不当な植民地支配を打破し、アジアに真の独立と繁栄をもたらす「聖戦」であると位置づけていました。
日本の進出は、確かに自国の「生存権確保」という現実的な国益と、アジアにおける日本の主導権確立という思惑が混在していました。しかし、その行動が、長年白人支配に苦しんできたアジアの人々に「解放」への希望を与えたことは、多くの独立指導者たちの言葉が証明しています。
アジア独立指導者たちの「感謝」の言葉
大東亜戦争後、次々と独立を達成したアジア諸国の指導者たちは、日本の戦いが自国の独立に果たした役割を高く評価しています。
- インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、「大東亜戦争は私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものだ」と述べ、日本の戦いをアジア解放の観点から高く評価しました。彼は、日本がインドネシア語の公用語化を推進し、民族意識を植え付け、後の独立運動の母体となる軍事訓練を提供したことを感謝しています。
- ビルマのバー・モウ元首相は、「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない」と断言し、日本の戦いがビルマの真の独立をもたらしたと評価しました。
- マレーシアのラジャー・ダト・ノンチック元上院議員は、日本軍のマレー半島進撃を「歓呼の声」で迎え、日本の統治がマレーシアの民族意識形成に貢献したことを感謝しています。
- タイのククリット・プラーモート元首相は、日本を「母なる日本」と呼び、「すべてのアジアの国々が独立を得たのは日本のおかげです」と、日本の貢献に深い感謝の意を表しました。
- インド国民軍のパラバイ・デサイ博士は、「インドの独立は日本のおかげで30年も早まった」と強く主張し、日本の戦いがアジアの民族解放に果たした役割を強調しました。
これらの言葉は、日本の戦いが、単なる「侵略」という範疇に収まらない、多面的な歴史的意義を持っていたことを強く示唆しています。日本の大義名分が、戦後にアジア諸国の独立を促す大きな潮流を生み出したことは、歴史の皮肉な側面として認識されるべきです。
「戦争目的」は達成されたのか?
日本は戦争に敗れ、国土は焦土と化し、多くの尊い命が失われました。しかし、大東亜戦争の「戦争目的」、すなわち「白人による有色人種国家に対する植民地からの解放」という大義名分は、結果的に達成されたと言えるでしょう。日本の敗戦後、欧米列強は再びアジアの植民地を支配しようとしましたが、日本軍の進出によって一度覚醒したアジアの民族意識は、もはや抑えつけることができませんでした。
インドネシア、ベトナム、マレーシア、ビルマなど、多くの国々が独立を勝ち取り、アジアは「白人の世紀」から「アジアの世紀」へと転換する大きなきっかけを得ました。これは、日本の戦いが、アジア全体の歴史において果たした、決して小さくない役割です。
語られなかった「大義」を受け継ぐ意味
戦後、この「アジア解放」という日本の戦争目的は、東京裁判史観や自虐史観の中でほとんど語られることがありませんでした。日本は「侵略者」としてのみ描かれ、その行動の背後にあった「大義」は封印されてきたのです。
しかし、私たちは今、この「語られなかった戦争目的」を再考すべき時を迎えています。それは、過去の過ちを矮小化したり、戦争を美化したりすることではありません。むしろ、歴史の複雑性を理解し、光と影の両方を見つめることで、真の歴史認識を構築することです。
「アジア解放」という理念の核心を理解することは、私たち日本人自身が、自虐史観の呪縛から解放され、自国の歴史に健全な誇りを取り戻す上で不可欠です。そして、その上で、アジア諸国との真の友好関係を築き、国際社会の平和と発展に貢献していくことこそが、未来へとつながる「もう一つの昭和史」を語り継ぐ意味となるでしょう。
28-2. 今こそ再考すべき“戦争目的”
「東京裁判史観」からの脱却と、真の戦争目的の探求
第二次世界大戦後、日本の大東亜戦争の「目的」は、東京裁判やGHQによるメディア統制、教育改革によって「侵略」という言葉に集約され、それ以外の側面はほとんど語られることがありませんでした。これにより、多くの日本人の心に「自虐史観」が深く根付き、過去の戦争に対する一方的な罪悪感を抱き続けてきました。しかし、この戦争が本当に「侵略」だけを目的としていたのでしょうか。今こそ、戦後日本に押し付けられた歴史観から脱却し、語られなかった真の“戦争目的”を再考すべき時が来ています。
「自存自衛」という切実な理由
大東亜戦争が始まった背景には、日本の「自存自衛」という切実な理由がありました。1929年の世界恐慌以降、世界各国が排他的なブロック経済を形成する中で、資源に乏しく、輸出に頼る日本は、経済的に追い詰められていました。アメリカによる石油の全面禁輸を含むABCD包囲網は、日本の国家の生存そのものを脅かすものであり、このままでは国が滅びるという切迫した危機感がありました。日本の指導層は、外交交渉による解決の道が閉ざされていく中で、「戦うか、滅びるか」という究極の選択を迫られたのです。
この視点に立てば、日本の戦争は、自国の生存権を守るための「自衛」の側面を持っていたと考えることができます。当時の日本の指導者たちは、この戦争を「やむを得ない選択」として位置づけていました。しかし、戦後の歴史認識では、この「自存自衛」という切実な側面はほとんど語られることがありませんでした。
「アジア解放」という壮大な大義
そして、もう一つの重要な戦争目的として「アジア解放」という壮大な大義名分がありました。当時のアジアは、イギリス、フランス、オランダ、アメリカといった白人列強による植民地支配下にあり、現地住民は差別と圧政に苦しんでいました。日本は、日露戦争での勝利によって、アジアの人々に「白人も倒せる」という希望を与え、民族意識を覚醒させました。
日本が掲げた「大東亜共栄圏」という理念には、白人支配からアジア諸民族を解放し、共存共栄の秩序を築くという壮大な構想が込められていました。日本の進出は、確かに自国の「生存権確保」という現実的な国益と、アジアにおける日本の主導権確立という思惑が混在していましたが、その行動が、長年白人支配に苦しんできたアジアの人々に「解放」への希望を与えたことは、多くの独立指導者たちの言葉が証明しています。
- インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、「大東亜戦争は私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものだ」と述べ、日本の戦いをアジア解放の観点から高く評価しました。
- ビルマのバー・モウ元首相は、「真のビルマの解放者は東条大将と大日本帝国政府であった」と断言し、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はないと述べました。
- タイのククリット・プラーモート元首相は、日本を「母なる日本」と呼び、「すべてのアジアの国々が独立を得たのは日本のおかげです」と感謝の意を表しました。
これらの言葉は、日本の大東亜戦争が、結果的に白人による有色人種国家に対する植民地からの解放という「戦争目的」を達成したという見方を裏付けるものです。日本の敗戦後、欧米列強は再びアジアの植民地支配を試みましたが、日本軍の進出によって一度覚醒したアジアの民族意識は、もはや抑えつけることができませんでした。多くの国々が独立を勝ち取り、アジアは「白人の世紀」から「アジアの世紀」へと転換する大きなきっかけを得たのです。
語られなかった「大義」がもたらした「自虐」
戦後、東京裁判やGHQのメディア統制、教育改革によって、この「自存自衛」や「アジア解放」といった日本の戦争目的の核心は、ほとんど語られることがありませんでした。代わりに、「日本は一方的な侵略国家であり、アジアに多大な苦痛を与えた」という「侵略」の物語が国民の記憶に深く刻み込まれました。
この結果、日本人は自国の歴史に誇りを持てなくなり、「反省」という名のもとに自己否定を繰り返す「自虐史観」に囚われてきました。この自虐史観は、日本人から自国を愛し、守る「健全な愛国心」や「気概」を奪い、国際社会における日本の発言力を弱める弊害をもたらしてきました。
今こそ「戦争目的」を再考する意味
今、私たちが大東亜戦争の“戦争目的”を再考することには、大きな意味があります。
- 歴史の真実を多角的に理解する: 単純な「侵略」論では語りきれない、日本の戦争の複雑な背景と、それがアジアにもたらした多面的な影響を理解することができます。これは、歴史の光と影の両方を見つめ、客観的な歴史認識を構築する上で不可欠です。
- 自虐史観を克服し、健全な誇りを取り戻す: 日本の行動に「大義」があった側面を認識することは、日本人が自国の歴史に健全な誇りを取り戻し、過度な自己否定から解放されることにつながります。「反省」すべき点は真摯に反省しつつも、自国の果たした役割を正しく評価することが、未来への前向きな姿勢を生み出します。
- アジア諸国との真の対話を進める: アジアの独立指導者たちの言葉に耳を傾け、彼らが日本に感謝し、尊敬の念を抱いている事実を認識することは、アジア諸国との真の友好関係を築く上で極めて重要です。歴史認識の共有は、一方的な「謝罪」や「賠償」だけでなく、相互理解に基づいた対話によって進められるべきです。
- 未来の日本が進むべき道を考える: 大東亜戦争の真の目的を再考することは、戦後の日本の平和と繁栄が、過去の「大義」の延長線上にあることを認識させます。これにより、私たちは「日本人として何を受け継ぎ、未来に何を残すべきか」という、国家としてのアイデンティティと使命を再確認することができます。
大東亜戦争は、日本が敗戦という形で終焉を迎えましたが、その目的の一部は、皮肉にも達成されたのです。この「語られなかった戦争目的」を今こそ再考し、歴史の真実を多角的に見つめることこそが、私たち日本人自身が、自虐史観の呪縛から解放され、未来を切り開くための大切な一歩となるでしょう。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。




