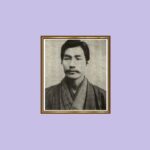
第29回 日本人が知るべきアジアからの声
29-1. インド・インドネシア・ビルマ・フィリピンの記憶
「侵略者」のレッテルを超えた、アジアの真実
戦後、日本人は大東亜戦争の歴史について、主に「侵略者」としての側面を強調する「自虐史観」を植え付けられてきました。しかし、この戦争がアジア諸国にもたらした影響は、決して一面的に語れるものではありません。特に、長年欧米列強の植民地支配に苦しんできたアジアの人々の間には、日本に対する「感謝」と「尊敬」の念が深く根付いていることを、私たちはもっと知るべきです。インド、インドネシア、ビルマ、フィリピンといった国々の指導者や民衆が、大東亜戦争と日本についてどのような記憶を持っているのか、その声に耳を傾けてみましょう。
インド:「日本のおかげで独立が早まった」
インドは、かつて大英帝国の広大な植民地であり、その独立運動は長く苦しいものでした。しかし、インド独立の父の一人であるジャワハルラール・ネルー首相は、日本の存在がインドの独立に大きな刺激を与えたと語っています。彼は、日露戦争でアジアの小国である日本が白人大国ロシアに勝利したことが、アジア全体に「白人も倒せる」という希望を与え、インドの独立運動の決意を強めたと回想しています。これは、日本の戦いが、直接的な武力介入とは異なる形で、アジアの人々の民族意識を覚醒させた何よりの証拠です。
インド独立運動を日本と共に戦ったインド国民軍の長老、パラバイ・デサイ博士は、戦後、イギリスによる軍事裁判で、日本の貢献について力強く主張しました。「インドの独立は日本のおかげで30年も早まった」と述べ、日本がインド解放のために可能な限りの軍事援助を提供したことに深い感謝を表明しています。彼の言葉は、日本の戦いが、インドの独立運動に直接的、間接的に貢献した紛れもない事実を示しています。
インドネシア:「アジア解放の戦いを日本が代表してくれた」
インドネシアは、350年もの長きにわたりオランダの過酷な植民地支配下にありました。日本の大東亜戦争は、このオランダ支配を短期間で打ち破り、インドネシアの人々に独立への希望を与えました。インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、日本の大東亜戦争を「私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものだ」と表現し、日本の戦いをアジア解放の観点から高く評価しています。
さらにナチール元首相は、日本がインドネシア語の公用語化を徹底的に推進し、インドネシア国民としての連帯感を植え付けたこと、そして若者に民族意識を育み、後の独立戦争の母体となる軍事訓練を提供したことを感謝しています。特に、日本軍が組織した祖国防衛義勇軍(PETA)の存在は、インドネシア革命において極めて重要であり、これなくしてインドネシアは独立できなかったとまで指摘されています。これらの事実は、日本の存在がインドネシアの独立に直接的、間接的に貢献したことを明確に示していると言えるでしょう。
ビルマ:「真の解放者は日本であった」
ビルマ(現ミャンマー)もまた、長らくイギリスの植民地であり、日本の進出はビルマ独立の大きな転機となりました。ビルマのバー・モウ元首相は、自著の中で日本の貢献について率直に語っています。「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない」と述べ、真のビルマの独立は日本占領下で宣言されたものであり、「真のビルマの解放者は東条大将と大日本帝国政府であった」とまで断言しています。
彼はまた、日本が多くの事柄に対して手本を示したにもかかわらず、その諸民族から誤解を受けていると指摘しており、戦後の一方的な「侵略者」としての評価に異を唱える立場を示しています。バー・モウの言葉は、日本の戦いが、ビルマの独立に直接的なきっかけを与えたことを明確に物語っています。
フィリピン:「日本によって目覚めさせられた」
フィリピンは、スペイン、アメリカと長きにわたり外国の支配下にありました。日本軍のフィリピン占領は、現地に多大な苦難をもたらした側面がある一方で、フィリピンの人々の民族意識を覚醒させ、独立への機運を高めるきっかけともなりました。
戦後、フィリピンのホセ・ラウレル元大統領は、東京裁判で証人として出廷した際に、「日本はフィリピンを植民地にするために戦争をしたのではない」と証言し、日本の戦争目的は「アジアの民族自決」にあったと擁護しました。彼は、日本がフィリピンの人々に独立を宣言させたこと、そして、独立国としての自覚を促したことを評価しています。フィリピンは、戦後も日本との賠償問題などを抱えましたが、現在では親日国として知られています。その背景には、戦争がもたらした苦難とともに、日本がアジアの植民地支配を終わらせるきっかけを作ったという記憶が、少なからず存在していると言えるでしょう。
記憶の多層性と未来への対話
これらのアジア諸国の指導者や民衆の声から読み解けるのは、日本の大東亜戦争が、単純な「侵略」という言葉だけでは語り尽くせない、多層的な歴史であったということです。そこには、白人支配への抵抗、民族自決への希望、日本の近代化への貢献への評価、そして一部の行動への反発や苦難が複雑に絡み合っています。
私たちは、過去の歴史を「断罪」するだけでなく、当時の人々が何を思い、何を選択したのかを「理解」しようと努めるべきです。アジア諸国の多様な声に耳を傾け、日本の戦いが、アジア全体の歴史において果たした役割を多角的に評価することこそが、戦後日本の「自虐史観」を乗り越え、より客観的で健全な歴史認識を持つための第一歩となるでしょう。
日本人が、自国の過去の光と影の両方を受け止め、アジアの人々の多様な記憶に敬意を払うこと。それが、真の相互理解を深め、未来志向の国際関係を築くための基盤となるのです。
29-2. 未来志向の国際関係を考える
「自虐史観」を超え、アジアとの真の友情を築く
前節では、インド、インドネシア、ビルマ、フィリピンといったアジア諸国の指導者や民衆が、大東亜戦争と日本に対して抱いている複雑な記憶、特に「白人支配からの解放」への感謝の念が存在することを見てきました。これらの声は、戦後日本に深く根付いた「自虐史観」だけでは捉えきれない、歴史の多面性を示しています。これからの日本が、アジア諸国と真に信頼し合える関係を築き、持続可能な平和と繁栄を追求していくためには、過去の「作られた記憶」の呪縛から解放され、未来志向の国際関係を構築することが不可欠です。
「謝罪」と「賠償」だけでは足りない真の理解
戦後の日本は、過去の戦争責任に対して「謝罪」と「賠償」を繰り返し行ってきました。これは、被害国との和解を進める上で重要なステップであり、今後も真摯な対応が求められることに変わりはありません。しかし、それだけでは「真の理解」や「心の通った友情」は生まれません。アジア諸国との関係においては、彼らが日本に対して抱いている「感謝」や「尊敬」といった、もう一つの側面にも目を向け、それを共有していく努力が不可欠です。
特に、白人支配からの解放という日本の「大義名分」が、結果的にアジアの民族独立に果たした役割については、これまで日本国内で十分に語られてきませんでした。アジアの指導者たちが、日本の戦いを自国の独立のきっかけと捉え、感謝の念を抱いていたという事実は、日本の歴史認識において「光」の部分として、もっと積極的に共有されるべきです。これは、過去の過ちを矮小化することとは異なり、歴史の複雑性を直視し、多角的な視点から物事を捉える姿勢を意味します。
未来志向の国際関係構築への道
では、日本はどのようにして、アジア諸国と未来志向の国際関係を構築できるのでしょうか。
- 歴史の「真実」を多角的に学ぶ: 私たち日本人は、まず自国の歴史を多角的かつ客観的に学ぶべきです。東京裁判史観やGHQによるメディア統制によって作られた「自虐史観」の呪縛から解放され、日本の戦争が持っていた「自存自衛」や「アジア解放」といった側面にも光を当てることで、歴史の全体像を把握することができます。この多角的な視点こそが、他国の歴史認識を理解し、真の対話を進めるための土台となります。
- アジア諸国との相互理解を深める: アジア諸国が日本に対して抱いている感情は、感謝、尊敬、そして一部での苦難や批判といった、非常に複雑で多層的なものです。私たちは、彼らが日本をどのように見ているのか、その多様な声に真摯に耳を傾け、彼らの歴史的経験や文化、価値観を尊重する姿勢を持つべきです。政府レベルだけでなく、民間レベルでの交流を促進し、文化や教育、観光を通じて相互理解を深めることが重要です。
- 経済協力と技術支援の継続: 戦後、日本はアジア諸国の復興と経済発展に大きく貢献してきました。日本のODA(政府開発援助)や技術協力は、アジア諸国のインフラ整備や産業育成に寄与し、「アジアの奇跡」と呼ばれる経済成長を支える大きな力となりました。これは、単なる経済的支援に留まらず、アジア諸国からの信頼と友情を築く上で重要な役割を果たしました。今後も、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた協力や、環境問題、防災といった地球規模の課題解決に向けた連携を強化していくべきです。
- 平和と安定への貢献: 日本は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできました。アジア太平洋地域の平和と安定に貢献することは、日本の国際社会における重要な役割です。紛争の予防や解決、人道支援、民主主義の推進など、国際協力の分野で積極的に貢献することで、アジア諸国からの信頼をさらに高めることができます。
- 「日本人としての誇り」の再構築: 自虐史観の呪縛から解放され、日本人本来の心と健全な誇りを取り戻すことは、未来志向の国際関係を築く上で不可欠です。自国の歴史や文化に自信を持ち、それを世界に発信できるようになった時、日本はより魅力的なパートナーとして、アジア諸国から尊敬される存在となるでしょう。「反省」すべき点は真摯に反省しつつも、自国の果たした役割を正しく評価することが、真の「誇り」を生み出すのです。
歴史の教訓を未来に活かす
歴史を学ぶことは、過去を断罪するためではありません。それは、過去の出来事から教訓を得て、より良い未来を「選択する」ための力を身につけることです。アジア諸国との関係においては、過去の苦難や対立を乗り越え、共通の未来を築くための「知恵」と「勇気」が求められます。
日本人が、自国の歴史の光と影の両方を受け止め、アジアの人々の多様な記憶に敬意を払うこと。そして、過去の経験から得られた教訓を活かし、経済、文化、安全保障といったあらゆる分野で、アジア諸国と真のパートナーシップを築き上げていくこと。これこそが、未来へとつながる「もう一つの昭和史」を語り継ぐ意味であり、日本が世界の中で輝くための道となるでしょう。
(C)【歴史キング】

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。




