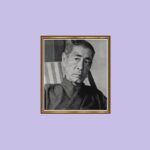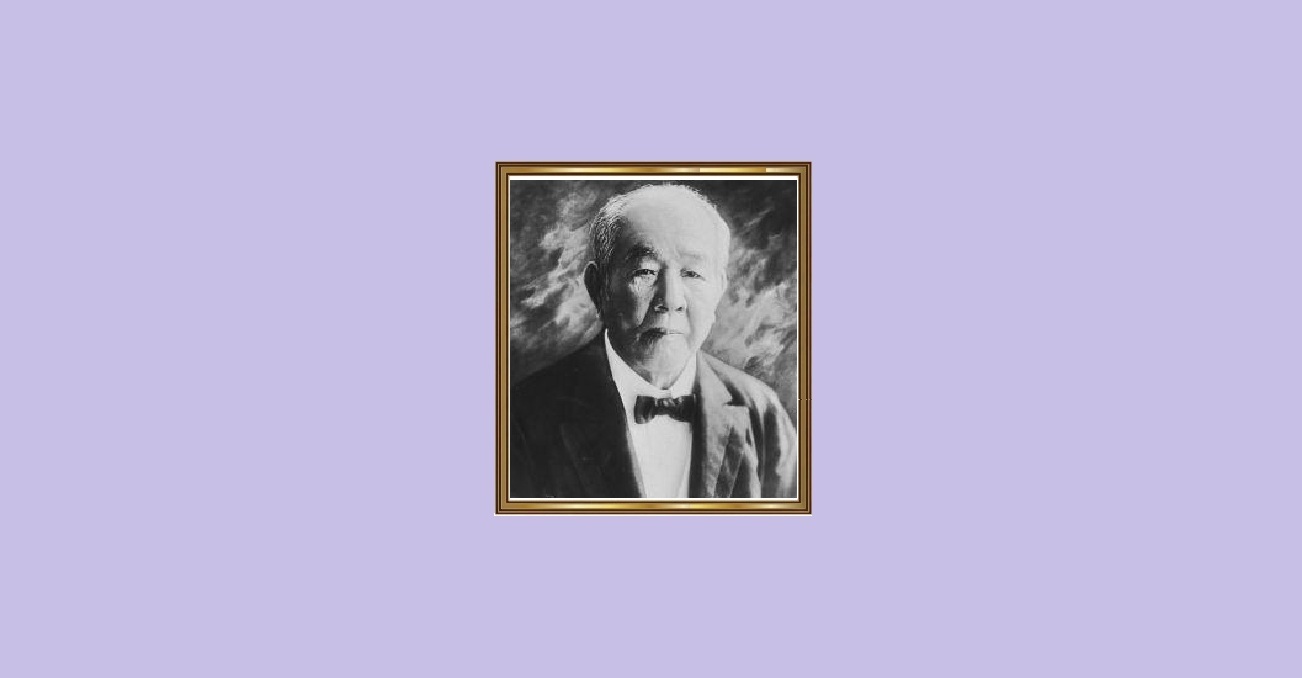新・1万円札{近代日本資本主義の父}渋沢栄一をはじめとする資本主義の父たち│前島密│松方正義│武藤山治│高橋是清│後藤新平etc…
近代日本資本主義の父――渋沢栄一
「率直にいって私は、経営の『社会的責任』について論じた歴史的人物の中で、かの偉大な明治を築いた偉大な人物の一人である渋沢栄一の右に出るものを知らない。彼は世界のだれよりも早く、経営の本質は『責任』にほかならないということを見抜いていた」
これは、「経営の神様」ピーター・ドラッカーが名著『マネジメント』の序文で渋沢について述べたものです。経営の神様をして、いち早く経営の本質を見抜いていたと言わしめた渋沢栄一(1840~1931)は、近代日本の産業界のありとあらゆる分野に及ぶ企業を興し、「近代日本資本主義の父」といわれた大事業家です。
渋沢は、武蔵国榛沢郡血洗島村(はんざわぐんちあらいじまむら・現埼玉県深谷市)の農商業を営む家に生まれ、6歳頃より教育熱心な父親から学問の手ほどきを受けました。7歳からは従兄弟の漢学者尾高惇忠(おだかあつただ)に「四書五経」、漢学、陽明学を学ぶかたわら家業を手伝い、14歳で単身仕入をするほどになり、商才を発揮したといいます。
22歳で江戸へ遊学し、尊王攘夷思想に目覚め、高崎城乗っ取り計画を立てますが、これを中止し、京都に逃亡して徳川慶喜(よしのぶ)公に仕えます。その後、慶喜公が将軍となったため幕臣となり、27歳の時、慶喜の弟昭武(あきたけ)の随行員としてパリ万国博覧会を訪れ、約二年間、ヨーロッパ諸国で見聞を広めます。
帰国後は、静岡で謹慎中の慶喜公の下で「商法会所」(出資を一般に公募した日本最初の株式会社といわれています)を成功させた後、新政府へ移り大蔵省へ出仕します。大隈重信、井上馨らの下で大蔵省の組織・財政改革に務め、三三歳で大蔵省を辞めて第一国立銀行を創設しました。
ここまでが渋沢の前半生です。幼少時からの学問や商売の経験はもちろん、攘夷派から一転して幕臣となり突然の洋行という役が回ってきたり、謹慎中の前将軍の下から一転して新政府へ出仕したりといった劇的な経験は、渋沢の後半生に大きく影響したことでしょう。この後、渋沢が91年の生涯を終えるまで携わった事業は、実業が500あまり、社会福祉、教育などの社会公共事業が600あまりに及ぶといわれています。
●渋沢栄一(1840~1931)
渋沢は、事業理念の範を、資本家とは一見不釣り合いな『論語』に求め、「事業と道徳の一致」(「論語と算盤」)を唱えました。そして、「士農工商」の最下位に置かれてきた商人を、国家を裕福にする実業家と位置づけ、事業が正業であるならば公益と私益とは一致すると主張し、かつこれを実践しました。一例を挙げるだけでも、第一国立銀行、日本興業銀行、東京海上保険会社、東京瓦斯、東洋製鉄、王子製紙、帝国ホテル、東京商工会議所、東京株式取引所の設立と、日本の近代産業のありとあらゆる分野に及んでいます。
一方で、非営利の社会事業にも力を注ぎ、東京府養育院、結核予防協会、聖路加国際病院などの社会福祉事業や医療事業のほか、商法講習所、日本女子大学の設立などの教育事業にもかかわっています。34歳で実母を亡くしてからは、「慈悲深かった母を亡くし、母に対するせめてもの恩返しとして社会福祉に力を入れるようになった」と渋沢自身が後年語っているように、経済活動で得た富を惜しみなく社会福祉事業に還元しました。
実業にせよ社会福祉事業にせよ、終止一貫しているのは「公益の追求」です。それは、近代人としての「独立自尊」の精神であり、強い倫理観と「公の精神」から生み出されたものでした。
渋沢の子息の秀雄は、渋沢が亡くなってしばらく経ってから、短歌誌『アララギ』のなかに「渋沢栄一翁の逝去を悼む」という前書きのついた一首を発見したそうです。
「資本主義を罪悪視する我なれど 君が一代は尊くおもほゆ」
秀雄は、「父が誠実に働き通した幅の広い一生は、人生観・社会観・国家観のちがう若い人にも、この歌のような例外的な共感をよびおこしたのであろう」と述べています。単に財界人という枠を超えて、渋沢が「近代日本資本主義の父」と呼ばれるゆえんがここにあります。
近代日本郵便の父――前島密
江戸幕府は、日本全体として外国との往来を閉ざすという鎖国の下、幕藩体制が敷かれていたわけですが、この制度は藩単位の自由な往来をも閉ざすものでした。日本の近代化において、まずこの諸藩の間の壁を取り払い、日本全国を自由に行き交う通信制度を実現することが不可欠でした。
明治になっても江戸時代の飛脚制度が存続していましたが、配達の不備も多く料金も高かったことから、全国的な郵便制度の創設を決意し、これを確立したのが、「一円切手」でおなじみの前島密(まえじまひそか・1835~1919)です。
●前島密(1835~1919)
越後国高田藩(新潟県上越市)の豪農の次男に生まれた前島は、13歳で江戸に出て蘭学と医学を学び、ペリー来航を機に砲術や航海術などを学びます。維新後は新政府に出仕し、駅逓権正(えきていごんのかみ)に就任。イギリスやアメリカで郵便制度を調査し帰国後、東京・京都・大阪間に国営の近代的郵便制度を開始しました。
1872年(明治5)には郵便網を全国に広げ、初めは地域ごとに異なっていた郵便料金を全国均一にしました。また、アメリカと郵便交換条約を結び、外国為替や郵便為替、郵便貯金といった諸制度を開始します。「郵便」や「切手」などの名称を考案したのも前島です。逓信省が設置されると、逓信次官として電話の開設にも尽力しています。
このように前島は、わが国近代郵便のあらゆる制度の確立に尽力したことこら、「近代日本郵便の父」と称さているのです。
租税分野の父――松方正義と神田孝平
明治新政府の下で日田(ひた)県(現大分県)知事に任命された薩摩藩出身の松方正義(1835~1924)は、実績を認められて中央政府入りし、内務卿大久保利通の下で地租改正事業に従事します。
●松方正義(1835~1924)
1878年(明治11)、パリ万国博覧会に出席した際、ベルギーなどの財政事情を学んで帰り、「明治十四年の政変」後は大蔵卿となり、当時国家財政を脅かしていた不換紙幣の整理を断行するほか、煙草税や酒造税などの増税や政府予算の圧縮策などの財政政策、またこれらを実行する日本銀行の創設、さらに官営模範工場の払い下げなどによって、財政収支を大幅に改善します。しかし、これらの施策が深刻なデフレーションを招いたため、「松方デフレ」と呼ばれて世論の反感を買うことになります。
松方は、一連の緊縮財政と増税が世論の反感を買うことを承知していました。紙幣整理を行う前、明治天皇に「これしか方法はないが、これをやれば世間は大変不景気になり反対論も出ます。もし、途中で政府の腰が砕けたり、陛下の考えが変わるならやらないほうがいい。やる以上は徹底的にやる必要があるが、約5年の歳月をいただきたい」と報告します。この時明治天皇に「お前の言うとおりにやれ。お前がいいと言うまで黙って見ている」と言われ、着手したといいます。
1881年(明治14)に大蔵卿となってから、内閣制度実施(1885年)後も続けて大蔵大臣を務め、以来1900年(明治33)に大蔵大臣を辞すまで、大蔵卿を含めた大蔵大臣在職期間は、14年半にも及びました。この間、二度、内閣総理大臣として松方内閣を組閣しますが、いずれも大蔵大臣を兼任しています。
「松方財政」を推進して財政基盤を立て直し、わが国の近代的財政金融制度の基礎を確立した松方は、国家財政一筋の生涯を送り、「近代日本租税の父」「近代日本財政の父」と称されています。
その松方が大久保利通と手を携え断行した1873年(明治6)の大改革「地租改正」は、それ以前に土地を所有できなかった農民に土地の所有権を認める進歩的なものでした。すべての土地に「地券」を交付して、地価の3%を地租として納税させる、つまり金銭で納税するという制度です。この近代的制度の先覚者が、美濃国不破郡(現岐阜県不破郡)出身の神田孝平(たかひら・1830~1898)です。
神田は、洋学者として幕府蕃書調所(ばんしょしらべしょ)教授、開成所教授、さらに頭取も務めました。数学に精通し、『経済小学』を翻訳してヨーロッパの経済制度を日本に初めて紹介した屈指の西洋経済学者の彼は、後に兵庫県令も務め、1874年(明治7)には全国に先駆けて兵庫県会を開くなど「天下の三県令」といわれたほどの人物です。
兵庫県令赴任前に文部大輔・江藤新平の下で文部大丞として地租改正に取り組み、1870年(明治3)、「田租改革建議」を建白。これが明治政府の土地および租税政策の理論的な光明となり、それを頼りに政府の地租改正事業が進められたといわれています。
地租改正は、現在の土地システムへ移行させる近代的な制度であり、神田は「近代日本の土地の父」と称されています。
「近代経営の父」と「職工の父」
「日本資本主義史上において、数少ない立派な実業家」と評価された大原孫三郎(まごさぶろう・1880~1943)は、岡山県倉敷の大地主で倉敷紡績を営む家に生まれますが、若い頃は放蕩三昧。謹慎中に、後に「児童福祉の父」「孤児の父」と称された石井十次(じゅうじ)と知り合い、彼の人生は大きく変わります。
石井の活動に感動した大原は、倉敷紡績入社後、工員の教育支援や労働環境の向上に努めるかたわら、貧民、孤児の救済や美術館の建設などの社会事業にも貢献します。大原の残した文化事業で最も有名な大原美術館は、倉敷の町を救ったともいわれています。
1932年(昭和7)、満州事変調査のために来日したリットン調査団の団員が大原美術館を訪れ、そこにエル・グレコやクロード・モネなどの名画の数々が並んでいることに仰天しました。以降、「クラシキ」の名が世界に知られるようになり、太平洋戦争下も世界的な美術品を焼いてはならないと、倉敷の町は爆撃を逃れたともいわれています。真偽の程はともかく、倉敷が空襲を免れたことは歴史的な事実です。
社会・労働問題の解決を一貫して提唱した近代経済学者福田徳三は、労働問題に関する経営者の姿勢を批判していますが、大原だけは例外として評価しています。また、福田とは対極的な立場のマルクス経済学者の大内兵衛(ひょうえ)も、「金を儲けることにおいて大原よりも偉大な財界人はたくさんいたが、金を散ずることにおいて高く自己の目標をかかげてそれに成功した人物として日本の財界人でこのくらい成功した人はなかった」と評しました。大原は、当時の専門家から「近代経営の父」ともいうべき高い評価を得ているのです。
実業家としては、倉敷紡績をはじめ現中国銀行、現中国電力などの社長を務め、大原財閥を築き上げ、社会事業としては、大原美術館のほかにも研究所、大病院、社会福祉施設などを現在に残し、社会や地域に多大な貢献をした大原は「企業メセナの父」とも呼ばれます。「企業メセナ」とは、企業が資金を提供して文化、芸術活動を支援することですが、この点につき作家の城山三郎は、「バブルにつれて生まれ、バブルとともに消えたメセナなどというやわなものとは、まるでちがう。(大原孫三郎の残した社会貢献は)正真正銘の力強い〝企業文化〟であった」と述べています。大原は、渋沢栄一と同様、財界人という枠を超えて「企業文化の父」と呼ぶにふさわしい文化遺産を後世に残しました。
渋沢栄一や大原孫三郎と同様に財界人という枠を超えて、日本資本主義の育成と発展に尽くした紡績業界の巨人がいます。鐘紡をわが国有数の大企業に育て上げ、「紡績王」「鐘紡中興の租」といわれた武藤山治(むとうさんじ・1867~1934)です。
●武藤山治(1867~1934)
慶応義塾で福沢諭吉に直接の薫陶を受けた武藤は、アメリカ留学などを経て、経営の悪化していた鐘淵紡績の再建に努めます。明治20年代に起きた職工争奪問題では、職工がよりよい賃金を求め工場移動をする自由意志を認めるなど、当時過酷極まりないといわれていた職工の優遇を唱え実行した武藤は「職工の父」と称されました。後に1919年(大正8)にワシントンで開催された第一回国際労働会議に資本家代表として推薦されるほど、武藤は労働者から絶大な信頼を得た経営者でした。
武藤は、近代的な経営手法と家族主義に基づき、女子工員らの悲惨な労働環境を改善し、工場の近代化や従業員の福利厚生の向上を図り、寮や保養施設、娯楽場、女学校まで完備した鐘紡は模範工場として「女工の天国」と評されるまでになります。また、日本初の共済組合設置、注意箱(投書箱)の設置と雑誌の発行により社内のコミュニケーションを改善するなど、当時の紡績工場で働く女工たちの過酷な生活が克明に記録されたことで知られる細井和喜蔵(わきぞう)著の『女工哀史』ですら、武藤率いる鐘紡に対する賞嘆の声が随所に見られるほどです。
ヒューマニズムに基づく「家族主義」「温情主義」で従業員を優遇し、人道的な労務管理を実践した武藤は「日本の労務管理の父」ともいうべき稀有な経営者でした。
後に武藤は、政界に進出し衆議院議員を三期務め、1932年(昭和7)、時事新報社社長として、帝人事件で政財界の腐敗を糾弾中、凶弾に倒れました。
「日本のケインズ」と「近代経済学の父」
1913年(大正2)に第一次山本権兵衛内閣の大蔵大臣となって以来、大正から昭和にかけて、原敬【はらたかし】、高橋是清(兼務)、田中義一、犬養毅、斎藤実(まこと)、岡田啓介の各内閣でそれぞれ大蔵大臣を務め、日露戦争や昭和の大恐慌などの国家存亡の危機に、財政面で救ったのが高橋是清(これきよ・1854~1936)です。
のんきで善良そうなダルマに似た風貌から、「ダルマ宰相」と呼ばれ庶民からも親しまれた高橋ですが、政界に入るまでの経歴がまさに「七転び八起き」そのものでした。
●高橋是清(1854~1936)
アメリカで奴隷になり、芸妓のヒモになり、相場詐欺に引っかかり、ペルーで銀山開発の詐欺に遭う――これらのことはすべて高橋の前半生に実際に起きた出来事でした。後年、自伝には、「自分は幸福者だ、運のいい者だ。……窮地に陥っても自分にはいつかよい運が転換してくる」と書いており、楽観主義者ぶりがうかがえます。
高橋はペルーの銀山開発が失敗し帰国した後、川田小一郎(こいちろう)日銀総裁に認められて日本銀行に入り頭角を現し、日露戦争の戦費を調達するため、政府からイギリスに派遣されて外債募集に成功し、日銀総裁まで登りつめます。政界入りしてからは、1927年(昭和2)の金融恐慌では銀行取付けの最中に金融界の救世主として蔵相に就任、モラトリアムを施行して恐慌を沈静させます。この時、「ダルマさんが出てきたから大丈夫だ」と庶民のあいだでささやかれたといいます。
1930年(昭和5)から翌年にかけての昭和恐慌では、大不況に陥り金の流出が続くなか、望まれて蔵相となり、金輸出再禁止を断行。続いて大量の国債を発行して、財政資金を呼び水にして景気にてこ入れし、国債の市場操作を通じる景気調節政策を導入して、恐慌からの脱出に成功、「日本のケインズ」とも称されました。晩年は、軍事費抑制方針を示したことから軍部と対立し、二・二六事件で暗殺されます。
財政家としては「日本のケインズ」と最大級の評価で称されていますが、実は高橋には、組織や職名は異なりますが、現在の特許庁長官に当たる農商務省専売特許局および特許局の初代局長であったという一面があります。現在の特許庁でも「初代特許庁長官」として高橋を紹介しています。
高橋は、1874年(明治7)頃、文部省に教育制度確立のため雇われていたモーレー博士の通訳をしていた時、博士から「日本には著作を保護する版権はあるが、発明・商標を保護する規定がない。……日本でも発明・商標は版権と共に保護する必要がある」と聞いて工業所有権の重要性を痛感し、以後研究を進め、1885年(明治18)施行の「専売特許条例」をはじめ、日本の特許法の起源とされる1888年(明治21)成立の「特許条例」など、商標制度や特許制度の制定に尽力しました。高橋が、近代日本の「特許制度の父」とも称されるゆえんです。
日本の金融政策を担った高橋が「日本のケインズ」と称される一方、日本の近代経済学分野において基礎をつくり、「日本の近代経済学の父」と称された東西両雄がいます。東の福田徳三(1874~1930)、西の高田保馬(やすま・1883~1972)です。
福田は、高等商業学校(現一橋大学)研究科を卒業後、ミュンヘン大学で博士号を取得、母校の東京商科大学(現一橋大学)教授として、日本にいち早くドイツ歴史学派の経済学を普及させ、近代経済学の基礎をつくった経済学者であることから「日本の近代経済学の父」と呼ばれています。大正デモクラシー期には吉野作造らと黎明会を結成し、民本主義の啓蒙に努めました。第一次世界大戦後はマルクス主義に対する批判的立場で、政府による社会・労働問題の解決を提唱したことから、日本における福祉国家論の先駆者とも評されています。研究の集大成『厚生経済研究』は、経済学研究者のバイブルとなっています。
他方の高田は、佐賀県小城郡三日月村(現小城市三日月町)に生まれ、第五高等学校(現熊本大学)の医科に入学しますが、社会科学のほうが自分に向いていると、同校の文科に再入学します。その後、京都帝国大学(現京都大学)で社会学を専攻し、貧富の差をなくす社会をつくるため社会学の研究に没頭して大著『社会学原理』を著し、階級や分業現象への関心から勢力説を提唱します。また、経済学のなかに社会学的要素を取り込んだ「勢力経済学」を提唱し、経済理論のほぼ全領域をカバーしたわが国最大の体系書と言われた『経済学新講』を著すなど、一般均衡理論、独占理論など近代経済学のわが国への導入に大きな役割を果たしました。
社会学と経済学の両面で壮大な体系を展開し、多くの優秀な学者を育て、さらに、優れた歌人としても知られ、まさに当代随一の「巨人」と仰がれた高田は、「日本の近代経済学の父」であると同時に、「日本社会学の父」とも称されました。
後藤新平:七つの称号
「自由民権運動の父」板垣退助が、「板垣死すとも自由は死せず」との名言を残したのは、1882年(明治15)演説に訪れた岐阜で暴漢に襲われた時ですが、この時板垣の手当てをしたのが、愛知県医学校(現名古屋大学医学部)で病院長兼医学校長をしていた弱冠25歳の後藤新平(1857~1929)でした。
ショッキングな事件に慌てふためく者が多いなか、後藤は冷静かつ適切な治療を行い、「ご負傷なさって、ご本望でしょう」と板垣に声をかけました。板垣は、後藤を頼もしく思い、「医師にしておくのは惜しい。政治家になれば、かなりのものになる」とつぶやいたといいます。
板垣の予言どおり、後藤は、明治から昭和にかけての近代日本の激動期に100年先の未来と世界全体を見渡す視野を持って、内政から外交まで幅広い業績を残します。後年、後藤に与えられた「父」なる称号の数々が、それらを物語っています。
医師として出発した後藤ですが、その後内務省に入り、ドイツ留学を経て内務省衛生局長に就任したものの「相馬事件」に連座し職を辞します。ところが日清戦争後、帰還兵の大量検疫での行政手腕が上司の児玉源太郎の目にとまり、児玉の台湾総督就任に伴い、台湾民政局長(後の民政長官)に大抜擢されるのです。植民地台湾の近代化に尽くし、現在に至る台湾発展の基礎を築いたことから、「台湾近代化の父」と称されています。
●後藤新平(1857~1929)
台湾での後藤の功績を認めた児玉は、満州の近代化を後藤にゆだねます。当時の満州は日本の植民地ではなかったのですが、日露戦争の勝利によって権益を獲得した南満州鉄道(満鉄)設立時の予算は約二億円と、当時の国家予算の四割にも達する膨大な額でした。満鉄と附属地の経営を任された後藤は、直後に児玉が急死したことから、その遺志を継ぐ決意で満鉄初代総裁に就任します。
児玉の「満州経営唯一の要訣は、陽に鉄道経営の仮面を装い、陰に百般の施設を実行するにあり」という信念を引き継ぎ、広軌鉄道・雄大な都市計画・学術文化施設などの「文装的武備」と呼ばれる経営を展開し、満州の社会基盤を整備します。このことから、後藤は、「満州開発の父」と称されました。
その後、第二次・三次桂太郎(かつらたろう)内閣の逓信大臣兼鉄道院総裁として、速達・内容証明郵便の開始、国鉄の電化・広軌化を進め、寺内正毅(まさたけ)内閣では内務大臣、外務大臣、第七代東京市長を務めるなど、まさに板垣の予言どおり大政治家としての道を歩みました。
1923年(大正12)9月1日、関東大震災で東京が焦土と化すなか、後藤は、第二次山本権兵衛(ごんべえ)内閣の内務大臣兼帝都復興院総裁として、震災復興計画を立案します。大規模な区画整理と公園・幹線道路の整備を伴い、30億円という破格の予算(国家予算の約一年分)のため猛反対に遭い、計画は縮小を余儀なくされますが、幅44メートルの昭和通りをはじめとする道路網、隅田川の鉄橋、大小百にも及ぶ公園・公共施設など、都心周辺部に近代都市基盤が整備され、市街地が拡大して現在の東京の都市骨格をつくったといわれています。計画の規模の大きさから「大風呂敷」と揶揄されますが、既成市街地における都市改造事業として世界最大規模であり、世界の都市計画史に残る快挙とも評価されるこの復興事業を立案した後藤は、「帝都復興の父」「都市開発の父」と称されました。
晩年の後藤は、少年団(ボーイスカウト)日本連盟初代総裁、拓殖大学総長、東京放送局(現日本放送協会)初代総裁などを歴任しました。特に少年団の活動には熱心で、会合には制服着用で出席し、「人のお世話にならぬよう。人のお世話をするように。そして、報いを求めぬよう」という標語をつくりました。日本の少年団を世界的組織の一つに育て上げたことから、「ボーイスカウトの父」と称され、また、東京放送局の放送開始日にマイクの前で挨拶を行い、日本でラジオ電波に乗った最初の声を発したことから、「放送の父」とも称されています。
後藤は1929年(昭和4)71年の生涯を閉じますが、1941年(昭和16)には後藤の一三回忌に当たって、故郷水沢に日本最初の公民館(現後藤伯記念公民館)が建設されました。後藤の生涯の根底にあった「自治」と「公共」が形になったことから、後藤は、死後、「公民館の父」と称されました。
日本の都市計画を生み、育て、見守った先駆者
内務官僚の池田宏(1881~1939)は、後藤のブレーンとして都市計画の実務に当たった人物です。1918年(大正7)、後藤内務大臣が創設した内務省大臣官房都市計画課の初代課長に任命された池田は、「都市計画調査会」の実質的リーダーとして、わが国の都市計画行政の基本路線を固めます。当時数少ない都市計画の専門家で、大阪市助役に転じていた後の「大阪の父」関一(せきはじめ)も調査会のメンバーに参加しています。
池田は調査会で、都市計画法案、市街地建築物法案を起草し、理解者が少なかった「都市計画」の概念を定型化し、一九一九年(大正8)の立法化にこぎつけました。その後、後藤が東京市長に就任すると助役に招かれ、関東大震災後に後藤が内務大臣兼帝都復興院総裁に就任すると内務省社会局長官兼帝都復興院計画局長に招かれたように、まさに後藤の右腕として尽くしました。当時、画期的な広さを持った昭和通りは、後藤の「大風呂敷」によるものと思われていますが、実際は池田のつくったものでした。
内務省を退官した後は、京都帝国大学(現京都大学)で教鞭をとるかたわら、都市問題全般の評論家として、都市計画の進展を見守り、時には積極的な社会的発言も行いました。
京都帝国大学の卒業論文から、没後刊行された『池田宏都市論集』に至るまで、生涯に241件もの著作を残した池田は、日本の都市計画の成立過程において、この制度を生み、育て、見守った先駆者です。その生涯は、まさしく「日本近代都市計画の父」「市政学の父」と呼ぶにふさわしいものでした。
(つづく)
「資本主義の父」11人の墓所
渋沢栄一墓所(谷中霊園・東京都台東区谷中)
前島密墓所(浄楽寺・神奈川県横須賀市芦名)
松方正義墓所(青山霊園・東京都港区南青山)
神田孝平墓所(谷中霊園・東京都台東区谷中)
大原孫三郎墓所(鶴形山大原家墓地・岡山県倉敷市鶴形)
武藤山治墓所(舞子墓園・兵庫県神戸市垂水区舞子陵)
高橋是清墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
福田徳三墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
高田保馬墓所(高田家墓地・佐賀県小城市三日月町)
後藤新平墓所(青山霊園・東京都港区南青山)
池田宏墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)