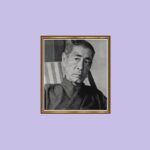北海道の「父」たち part.7 ~建築の「父」たち~│山本怡仙│久保兵太郎

北海道
山本怡仙──北海道レンガの父
赤レンガは明治時代の象徴ともいえる建材で、北海道庁旧本庁舎やサッポロファクトリーなど、札幌にもその美しい姿を残しています。日本のレンガ製造のルーツは、幕末の長崎にありますが、その技術を札幌に伝えたのが山本怡仙(やまもと いせん・1828~1880)です。
越前国府中(現福井県越前市)の酢製造業を営む家に生まれた山本は、私財を投じて藩校創設に尽力するなど、郷里の発展に貢献しました。維新後、北海道の開拓使工業局に出仕し、不燃・耐寒の家屋建築に不可欠なレンガの製造を任されます。月寒村にレンガ工場を建て、郷里から専門の職人を呼び寄せて技術指導を行いました。わずかな期間でしたが、札幌におけるレンガ製造の基礎を築いた功績から、山本は「北海道レンガの父」と称されています。
久保兵太郎──江別レンガの父
札幌の隣町、江別市も古くからレンガの町として栄えましたが、その地場産業を育て上げたのが久保兵太郎(くぼ ひょうたろう・1864~1933)です。阿波国(現徳島県)で生まれ育った久保は、家業の傍ら役場の職員としても優秀な働きぶりを見せます。その後、北海道の江別に移住し、1897年(明31)に江別野幌のレンガ製造所の経営を任されます。
レンガは、鉄道や港湾などの建築材料として需要が増加し、久保の経営は軌道に乗ります。道内6か所のレンガ工場を経営するまでに事業を拡大し、全国10数か所に販売所を設けて「レンガの久保」として名を馳せました。札幌の北海道庁旧本庁舎にも久保の工場で作られたレンガが使用されています。
久保はレンガの改良に熱心に取り組み、土質の厳選と製造技術の研究を重ね、レンガの質をさらに高めました。また、燃料として工場周辺の農家から資材を買い入れるなどして、住民の生活を支えました。野幌の名物として知られる「煉化もち」も久保の考案によるものです。レンガ製造を江別の地場産業に育て上げた久保は、「江別レンガの父」と称されています。