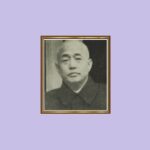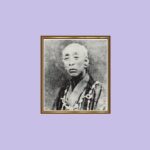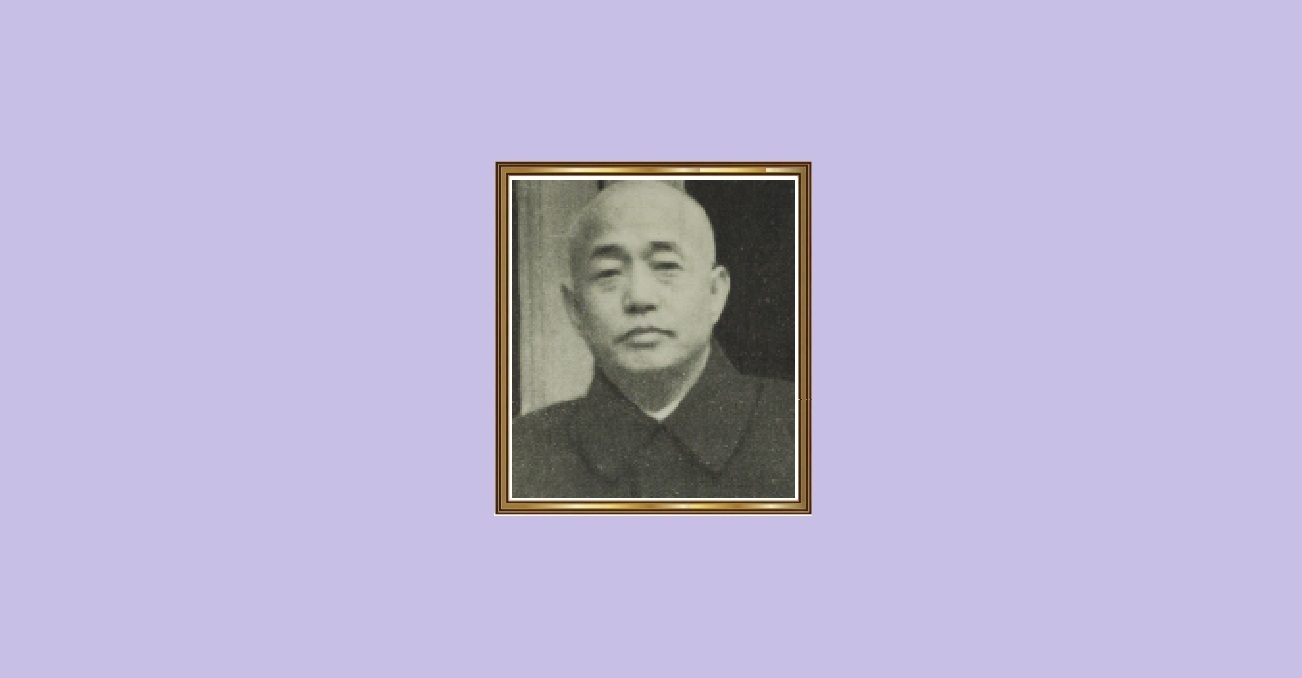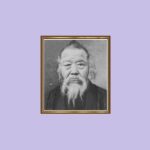
山形県の偉人:石原莞爾 — 「世界最終戦」を予言し、満州国建国を主導した天才軍略家

山形県
「国は悪によっては亡ばず、愚により亡ぶ」
この言葉は、昭和初期の日本陸軍で、異端の天才として知られた石原莞爾(いしわら かんじ)が残したものです。
山形県鶴岡市に生まれた彼は、日蓮宗の信仰とヨーロッパの戦史研究から、日本とアメリカが戦う「世界最終戦」という独自の軍事思想を構築。その思想に基づき、満州事変を主導し満州国建国を推進しました。その先見性あふれる戦略思想は、後の日本の運命を大きく揺るがすことになります。剛直な性格で権威を嫌い、上官の東條英機をも「上等兵」と罵倒した彼の生きざまは、まさに「帝国陸軍の異端児」と呼ぶにふさわしいものでした。
天才の萌芽:庄内からドイツへ
石原莞爾は1889年(明治22年)、警察官の次男として山形県鶴岡市に生まれました。幼い頃から利発な一方で、天衣無縫で枠にはまらない性格でした。1902年(明治35年)に仙台陸軍地方幼年学校に入校すると、常に首席を維持するなど、その学才は抜きん出ていました。
彼の思想形成に大きな影響を与えたのは、まず青年期に出会った日蓮宗への信仰でした。日蓮が予言したとされる「大闘諍(だいとうじょう)」という世界を巻き込む大戦争の記述に、彼は強い関心を抱きます。そして、1922年(大正11年)から3年間のドイツ留学が、彼の思想を決定づけることになります。ナポレオンやフリードリヒ大王の戦史を研究する中で、彼は戦争の形態が「殲滅戦争(せんめつせんそう)」と「消耗戦争」を交互に繰り返しながら歴史的に進化しているという思想を構築。この戦史研究と日蓮宗の予言を結合させ、やがて日本とアメリカが戦う「世界最終戦」という、独自の世界観・戦争観を完成させました。
満州事変と満州国建国の主導
石原は、日米最終戦に勝利するためには、満州を日本の戦略的・経済的拠点として確保する必要があると考え、1927年(昭和2年)に「関東軍満蒙領有計画」を立案します。
そして1931年(昭和6年)、関東軍作戦主任参謀であった石原は、板垣征四郎らと共に柳条湖事件とそれに続く満州事変を主導。わずか1万数千の関東軍で、23万の中国軍を打ち破り、満州を占領するという、軍事史上でも驚異的な作戦を成功させました。
彼は当初、満州を「領有」する構想でしたが、国内外の情勢変化を受けて、満州を中国人自らの手で運営させる「満州国独立論」へと転向。満州を「五族協和の王道楽土」とし、日米最終戦に備えるための「東洋のアメリカ」を建設しようという、彼の壮大な理想が満州国建国へと繋がっていきました。
権力との対立と予備役編入
石原は、その天才的な軍才と独自の思想ゆえに、軍部中枢から疎まれることも少なくありませんでした。
二・二六事件での剛毅な行動
1936年(昭和11年)の二・二六事件では、参謀本部作戦課長であった石原は、戒厳参謀として反乱軍の鎮圧に貢献しました。このとき、彼は反乱軍にピストルを突きつけられてもひるむことなく、「何が維新だ。陛下の軍隊を私するな」と一喝。当時の軍中枢が反乱軍にどう対処すべきか迷う中、冷静かつ強硬に鎮圧を主張し、実行しました。
しかし、その一方で、石原は宇垣一成(うがき かずしげ)の組閣を阻止するために陸軍を動かすなど、軍人として政治に深く介入しました。彼はこの行動を「人生最大級の間違い」と後に反省しています。
東條英機との決定的な対立
石原は、日中戦争の拡大には一貫して反対の立場でした。彼は、中国大陸での戦線拡大は、将来の対ソ・対米戦に備えるための国力を無駄に消耗する「時期尚早な愚策」であると主張しました。この不拡大方針を巡り、彼は関東軍参謀長であった東條英機と激しく対立します。
満州国を「満洲人自らに運営させる」ことを理想とした石原に対し、東條は軍部主導の支配体制を重視しました。石原は、東條の官僚的で視野の狭い思考を徹底的に嫌い、「東條上等兵」と呼んで馬鹿呼ばわりしたため、両者の関係は決定的に悪化。ついに石原は、参謀本部から関東軍参謀副長へと左遷され、最終的には1941年(昭和16年)、東條陸軍大臣によって予備役に編入(事実上の退役)されることになりました。
晩年の活動と今日的意義
予備役編入後、石原は立命館大学で国防学の講師を務める傍ら、「東亜連盟運動」を指導し、日本の主導で日・満・支が連携するアジアの連盟結成を訴え続けました。
太平洋戦争中は、「油がないからとて戦争を始めるとは、馬鹿か」と開戦を厳しく批判。敗戦後は戦犯指定を免れ、東京裁判には証人として出廷。満州事変は「自衛行動であり侵略ではない」と主張する一方で、無辜の民間人を原爆で殺したトルーマン大統領こそが「最大の戦争犯罪者」だと糾弾しました。また、東條英機を「私には些細ながら思想がある。東條という人間には思想はまったくない」と評し、終生その対立姿勢は変わりませんでした。
晩年は故郷の山形県鶴岡市に移住し、農業に勤しむ中で、日米最終戦論を修正。「日本国憲法第9条を武器に、米ソ間の争いを阻止し、最終戦争なしに世界が一つになるべきだ」と、絶対平和論へと転向しました。
彼の生涯は、満州事変を引き起こした戦争指導者という「負の側面」と、来るべき戦争の形態と日本の行く末を予見した「戦略家」という「正の側面」が複雑に絡み合っています。彼の思想は、現代の私たちが、日本の歴史と国際情勢を深く考える上で、多くの示唆を与えてくれます。
石原莞爾ゆかりの地:歴史の舞台を訪ねる旅
石原莞爾の生涯は、彼の故郷である山形県鶴岡市から、軍人としてのキャリアを積んだ仙台、そして思想を確立させたドイツ、満州へと広がっています。彼の足跡をたどることで、日本の近代史の重要な局面を肌で感じることができます。
山形県鶴岡市:生誕と終焉の地
- 石原莞爾生誕の地碑(山形県鶴岡市日和町):石原莞爾が生まれた場所に立つ記念碑です。
- 鶴岡市郷土資料館(山形県鶴岡市家中新町):石原莞爾に関する資料が保存・展示されており、彼の多岐にわたる思想と活動の全貌を知ることができます。
- 西山農場跡碑(山形県飽海郡遊佐町):晩年、同志と共同農場を営み、絶対平和論へと思想を転向させた場所です。
- 石原莞爾墓所(山形県飽海郡遊佐町菅里):遊佐町に彼の墓所があり、その最期を偲ぶことができます。
石原莞爾の遺産:未来への教訓
石原莞爾の生涯は、私たちに「時代の流れを巨視的に見通すこと」の重要性を教えてくれます。彼は、第一次世界大戦後の世界の動向から、将来の戦争の形態を予見し、日本が生き残るための戦略を構想しました。彼の「世界最終戦論」は、その予見が的中した側面もあれば、結果的に日本を泥沼の戦争へと引きずり込んでいった側面もあります。
しかし、彼の思想から学ぶべきは、その結論の正誤ではなく、いかにして時代を深く分析し、未来へのビジョンを描くかという、その思考のプロセスにあります。
また、彼の反骨精神は、権威や既成概念に盲目的に従うのではなく、自らの頭で考え、正しいと信じたことを貫くことの大切さを教えてくれます。特に、強大な権力を持つ東條英機に対しても臆することなく異を唱え続けた彼の姿勢は、現代社会においても、勇気を持って意見を表明することの重要性を示しています。
石原莞爾の物語は、日本の近代史における光と影を映し出すと同時に、私たち一人ひとりが、自らの頭で考え、行動し、未来を創っていくための、
(C)【歴史キング】

石原莞爾 アメリカが一番恐れた軍師 若き男たちの満州建国 (双葉新書) / 早瀬 利之 (著)
新書 – 2014/8/6
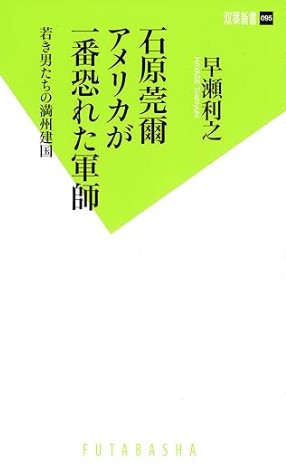
関東軍作戦主任参謀・石原莞爾は、稀代の軍師だった。その卓抜した戦略眼と歯に衣着せぬ言動から、彼は陸軍内にあって異端児であった。
軍内でその実力を発揮できず、不遇を囲っていた石原に転機が訪れる。日本が権益を手ににしていた満州への赴任である。
かの満州の地で、軍師・石原は「日本の未来」を見つけた!!