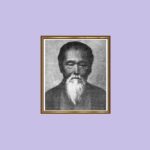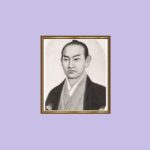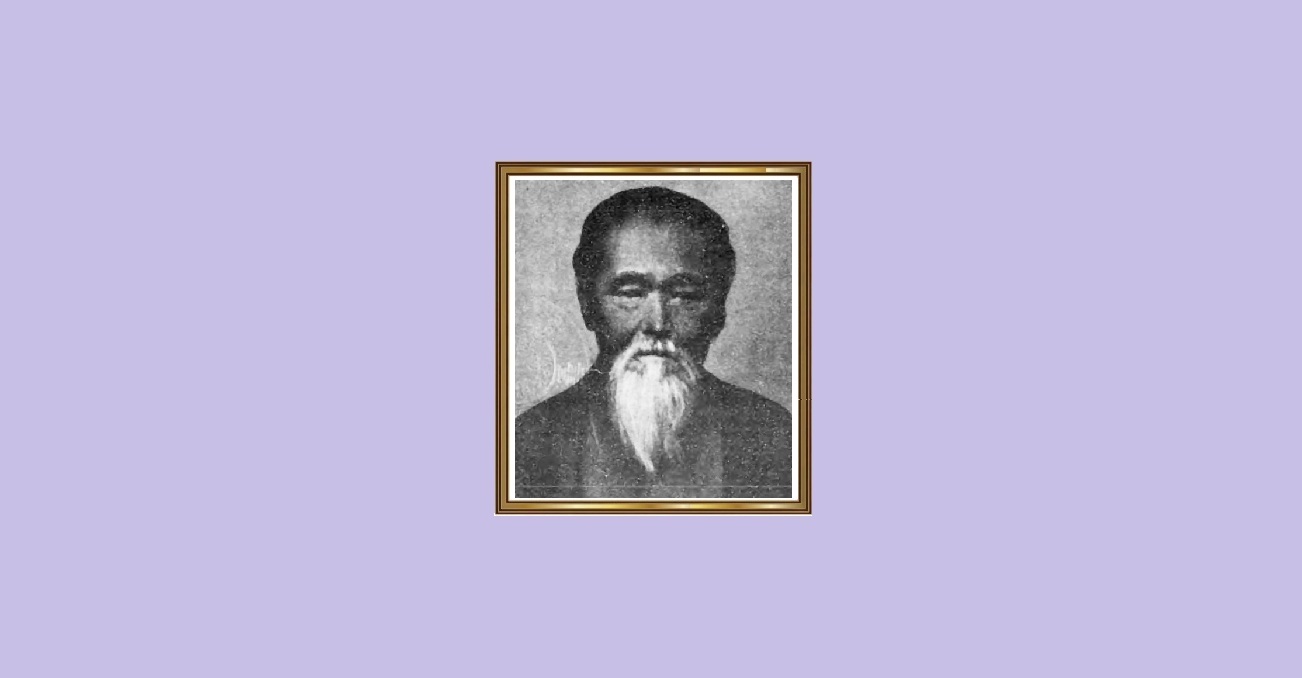奈良県の偉人:中村直三 — 「命の親」を増やし、日本農業の礎を築いた「明治の三老農」

奈良県
「全く農事ニ不行届より右様ニ立至り候」(農事をおろそかにしたから、このような事態になった)
──この言葉は、江戸時代末期から明治にかけて、農業改良に生涯を捧げた中村直三(なかむら なおぞう)が、天保の大飢饉を目の当たりにして抱いた強い危機感を表しています。
大和国山辺郡永原村(現在の奈良県天理市)に生まれた彼は、群馬の船津伝次平、香川の奈良専二と並び称される「明治の三老農」の一人。
農民を救い、「国益」の実現を目指した彼の活動は、後の日本の農業近代化に大きな影響を与え、明治後期の奈良県が全国一の米の収穫量を誇る「奈良段階」の基礎を築きました。
飢饉が植え付けた使命感:農事改良への道
中村直三は1819年(文政2年)、大和国永原村の貧農の長男として生まれました。彼が10代後半に経験した天保の大飢饉は、彼の人生を決定づける出来事となります。食糧不足により多くの人々が餓死していく悲惨な状況を目の当たりにした彼は、その根本原因が「農業の不徹底」にあると見抜き、農事改良こそが民を救う唯一の道であるという強い使命感を抱きました。
幕末に入り、開港による物価騰貴や綿業の打撃で農民の生活はさらに苦しくなります。村では一揆が起こりかねない不穏な状況でしたが、直三は村民たちに冷静に増産の重要性を説き、自らその先頭に立ちました。
彼の活動は、主食である米、すなわち「命の親」の品種改良に注力されました。諸国を歩いて優れた稲の種籾(たねもみ)を集め、自らの試作田で比較実験を行い、その成果を農民に伝えました。
独自の指導書と「老農」ネットワーク
直三の優れた点は、彼の指導法にあります。彼は、専門的な知識を持たない農民にも分かりやすく農法を伝えるために、様々な工夫を凝らしました。
- 指導書の工夫: 1862年(文久2年)に刊行した『勧農微志(かんのうびし)』を始め、多くの指導書を著しました。これらの書は、漢字にふりがなを付け、絵や図を豊富に使い、稲の品種ごとの収穫量を力士の番付表のように分かりやすく示すなど、農民が楽しみながら学べるように作られていました。
- 普及の工夫: 広告や宣伝の先駆けともいえる「ビラ」の形式で農法を配布するなど、新たな手法も積極的に取り入れました。
- 「老農」のネットワーク: 彼の活動は、永原村だけでなく大和国中へと広がり、志を同じくする多くの「老農」(農業指導者)たちに支えられました。直三は、このネットワークの中核として、各地から集まる良品種の情報を一手に集め、さらに改良を進めていきました。
明治の農業近代化と「奈良段階」の礎
明治時代に入ると、直三の名声は全国に知られるようになります。彼は、大和の各藩に招かれて農事改良を指導し、廃藩置県後には奈良県勧業下用掛などの役職に就き、積極的な活動を展開しました。
1877年(明治10年)の第1回内国勧業博覧会では、76種もの優良稲種を提出。さらに1881年(明治14年)の第2回博覧会では、実に740種の稲種を出品し、全国の品種改良家から尊敬を集めました。彼の指導は、秋田や宮城、石川、福井、大分など全国各地に広がり、その功績は全国的なものとなりました。
彼の活動が特に実を結んだのが、故郷である奈良県です。直三が亡くなった後、奈良県は明治後期から昭和初期にかけて、米の単位面積当たりの収穫量が全国一となる「奈良段階」と呼ばれる時代を迎えます。この驚くべき成果は、中村直三が蒔いた種が大きく育った結果であり、彼の功績がなければ成し得なかったものです。
1882年(明治15年)、コレラにより64歳で急逝。その生涯は、農民の苦しみと向き合い、その生活を豊かにするためにすべてを捧げた、まさに「農事改良の鬼」と呼ぶべきものでした。
中村直三ゆかりの地:農業の歴史を辿る旅
中村直三の足跡は、彼の生まれ故郷である奈良県天理市を中心に、彼が指導に訪れた全国各地へと広がっています。
- 中村直三農功之碑(奈良県奈良市):奈良県庁東交差点の北東に、彼の功績を称える大きな石碑が建っています。
- 中村直三生誕の地(奈良県天理市永原町):直三が生まれ育った場所です。現在、生家跡に特筆すべき史跡や記念施設は確認されていませんが、地元では彼の功績が語り継がれています。
中村直三の遺産:現代社会へのメッセージ
中村直三の生涯は、私たちに「課題を根本から解決する力」と「共感を呼ぶコミュニケーション」の重要性を教えてくれます。彼は、飢饉という深刻な社会問題に対し、安易な対処療法ではなく、農業生産力を向上させるという根本的な解決策を追求しました。
また、彼の指導法は、専門家と一般の人々の間にあった知識の壁を取り払い、多くの農民が自ら学び、実践できるような工夫に満ちていました。これは、現代の教育や情報発信においても、相手の目線に立って分かりやすく伝えることの重要性を示唆しています。
中村直三の物語は、一人の篤農家が、強い使命感と工夫によって、地域の、そして日本の未来を変えることができることを証明しています。彼の「命の親」である米への深い愛情と、農民への共感は、食料自給率や食の安全が問われる現代社会においても、私たちに多くの示唆を与えてくれるでしょう。
(C)【歴史キング】

大和の国のリーダーたち(奈良県立大学ユーラシア研究センター学術叢書シリーズ2 vol.2) / ユーラシア研究センター編 (編集)
単行本(ソフトカバー) – 2023/3/31

▼奈良(大和)を代表するリーダーたちの紹介で、作中、{農業のリーダー}として中村直三が登場
本書では、奈良の発展や変化の「分岐点」に立つ人物を「大和の国のリーダーたち」と呼ぶことにした。ある時点で「せーの」で一斉に取りかかったのではない。分野も活躍年代も同じではない。お殿さまもいれば、農民や商人もいる。顔見知りのお仲間ではないのだ。 共通項は、たったひとつ。「志」だ。 浅田松堂―大和絣の発明者/ 大和高田の豪商村島氏と長州藩―繰綿と塩の交易をめぐって/ 豊井紡績所と前川迪徳/ 柳澤保申と士族授産事業/ 農業のリーダー―中村直三の足跡/ 奥田木白と赤膚焼/ 大和売薬の発生と発展―米田家が果たした役割/ 土倉庄三郎―「不動」の人