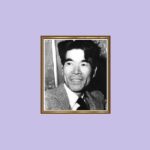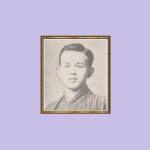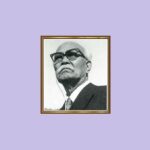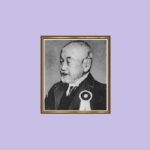
第1回 1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?│『もう一つの昭和史──静かなる日本再発見の旅』~語られざる真実と、未来への希望をつなぐ30章~

1-1. 世界恐慌という“外圧”がすべての始まりだった

1929年10月、アメリカ・ニューヨークのウォール街で起きた株式大暴落──「世界恐慌」の始まりである。この経済的激震は、ただの金融市場の崩壊にとどまらず、あらゆる国々の政治や外交のあり方をも変える転機となった。特に、日本の進路に与えた影響は決定的だった。
世界恐慌は、米国発の危機であったにもかかわらず、瞬く間に世界中へ波及した。輸出依存型経済であった日本はその影響をもろに受け、特に生糸を主とする外貨獲得手段が壊滅的な打撃を受けた。国内では失業者が急増し、農村では「娘を身売りして家族が生き延びる」ほどの困窮が現実のものとなった。
この未曾有の経済的混乱に対して、世界各国が取り始めた対応策は「自国第一主義」だった。関税障壁を高くし、輸入を制限し、自国の産業と雇用を守る。これが「ブロック経済」の台頭であり、日本にとってはまさに“扉を閉ざされた世界”の始まりを意味した。
経済的閉塞感と外交的孤立
イギリスは英連邦経済圏を、フランスはフラン圏を、アメリカはラテンアメリカ諸国との経済圏を強化する。いずれも植民地を背景とした自給自足型の経済ブロックであり、日本のような資源に乏しい、輸出入に頼る経済構造の国にとっては「入る場所のない世界」が完成しつつあった。
外交面でも、日本の立場は年々厳しくなっていく。国際連盟の場では、軍縮問題や中国との関係などでたびたび非難され、国際社会における日本の発言力は後退していった。かつて日露戦争に勝利し、一等国の仲間入りを果たしたかに見えた日本が、再び“周縁”に追いやられる感覚は、政治家のみならず国民にも共有されていく。
このような環境のなか、「満蒙(満州と蒙古)は日本の生命線」という論が台頭してくる。これは、経済的自立を目指すうえで、満州を日本の資源供給地とし、対中国貿易の要とする発想だった。実際、関東軍など現地軍は、満州における日本の権益拡大を既定路線と見なして行動を開始していた。
「暴発」ではなかった満州事変
1931年9月18日、柳条湖事件が起きる。南満州鉄道の線路が爆破され、それを口実に関東軍が中国軍を攻撃、「満州事変」が勃発した。この事件は、しばしば日本軍の「暴走」や「クーデター的行動」として描かれることが多い。
だが、背景には前述のような経済的・外交的孤立があったことを忘れてはならない。つまり、満州事変は決して突発的な「暴発」ではなく、追い詰められた日本が選ばされた“唯一の出口”だったという側面もある。政府は事後的にこれを黙認し、国民もまた好意的に受け止めた──それは、「ここしか生き残る道がない」という深刻な危機意識の反映だったのだ。
世界恐慌と「対外進出」の因果関係
このように見ていくと、日本の「対外進出」──すなわち戦争へ向かうプロセスは、決して日本一国の野心や軍部の暴走だけで説明できるものではない。むしろ、世界恐慌という外的要因によって、日本が国際社会の中で「選択肢を奪われた」ことが出発点にある。
当時の世界は今で言う“サプライチェーンの断絶”に等しいブロック経済下で、日本は文字通り「息の根を止められる」状況に追い込まれていた。しかも、植民地をもたず、資源にも乏しく、人口が急増する日本にとって、生き残りを図るには「新たな経済圏」の確保が不可避だった。
これこそが、後の「大東亜共栄圏」構想の原型であり、単なる軍国主義的野望とはまったく異なる論理から出てきた発想である。
外圧によって動かされた国家
世界恐慌という“外圧”によって、日本は次々と「非選択的な選択」を強いられていった。外交交渉による打開も、国際社会の理解も得られぬまま、日本は自らの生存と発展の道を求めて、対外進出に踏み出していく。
これが、戦争国家への第一歩だった。
だが、ここで忘れてはならないのは、「戦争国家」とは本来、日本自らが望んでなった姿ではなかったということだ。むしろ、世界経済と国際政治という大きな力の流れのなかで、“そうならざるを得なかった”という歴史の構造が存在する。これを無視して、単純に「軍部の暴走」や「天皇制の専制」を語ることは、歴史の本質を見誤ることにほかならない。
1-2. 「戦争国家」へのレッテル――誰が日本をそう呼んだのか

1930年代の日本を語るとき、「戦争国家」という言葉が頻繁に登場する。だが、果たしてそれは誰が、どのような文脈でそう名付けたのか。そこには日本自体の行動だけではなく、当時の国際社会の思惑と報道、さらには戦後に形成された価値観の影響が強く反映されている
まず明確にしておきたいのは、「戦争国家」というレッテルは、少なくとも当時の日本国内では一般的に使われていた表現ではないという点である。むしろ、この表現が本格的に定着したのは戦後、連合国の占領政策とともに再構築された歴史観の中においてであった。
欧米メディアと国際世論が作り上げた“危険な国”日本
1931年の満洲事変をきっかけに、日本は国際社会、とくにアメリカやイギリスなど欧米諸国のメディアで急速に“攻撃的”あるいは“軍国主義的”な国家と見なされ始める。国際連盟脱退に至った1933年の一連の外交的決断や、日中戦争の長期化も、日本のイメージを悪化させていった。
なかでも重要なのが、当時の報道とその構図である。リットン報告書を含め、欧米メディアは一貫して「日本=侵略者」「中国=被害者」という構図を描いた。日本の国内事情や、満洲における在留邦人の安全、さらには中国内部の軍閥抗争など、複雑な背景を排除したうえで、“悪役”としての日本像が固定されていったのである。
アメリカではこの時期、日系移民への差別が続いていた。西海岸を中心とした反日感情は政治家の発言や新聞の論調にも色濃く表れ、日本の行動は「黄禍論」の延長線上にあるものとして扱われた。つまり、「戦争国家」というレッテルは、単なる事実の指摘ではなく、政治的・文化的な背景とともに“貼られた”ものであった。
戦後教育と占領政策が作った“自己否定”の歴史観
さらに注目すべきは、戦後の占領政策の一環として行われた歴史教育の再構築である。GHQ(連合国軍総司令部)は、日本を民主主義国家へと導くため、徹底した戦争責任教育を行った。その中心にあったのが、「日本は侵略的な戦争国家であった」という自己否定の物語である。
このとき導入された教育方針は、単に戦前の“軍国主義”を否定するだけでなく、日本人に「自国の過ち」を刻み込むことを目的としていた。新しい教科書からは天皇、靖国神社、忠誠、名誉といった言葉が削除され、かわりに“戦争の悲惨さ”と“加害責任”が強調された。
このような枠組みの中で、「戦争国家・日本」というレッテルは、歴史的事実というよりも“教育による価値観”として定着していったのである。そして、それが現代においてもなお日本の国際イメージや外交姿勢に影響を与えている。
なぜ日本は自己主張しなかったのか?
もちろん、日本政府もすべてを黙認していたわけではない。とくに1930年代後半から1940年代前半にかけては、国際社会に向けて自国の立場や正当性を説明しようとする努力もあった。たとえば、松岡洋右外相が国際連盟の場で見せた反論は、当時としては異例の積極外交であった。
しかし、その訴えが届くことはほとんどなかった。英語での情報発信力、国際宣伝戦の経験不足、さらに当時のメディア環境の非対称性もあり、日本の主張は欧米の大きな報道のうねりに呑まれていった。
また、日本国内においても“国際世論に訴える”という発想は乏しかった。「外圧」に対しては断固たる姿勢で臨むという“内向き”の発想が強く、国際舞台でのイメージ戦略という概念はほとんど存在していなかったといえる。
「戦争国家」の実態とそのズレ
ここでもう一度、冷静に問い直してみたい。1930年代の日本は本当に“戦争国家”だったのか。
確かに満洲事変以降、日本の軍事行動は増加し、国家予算における軍事費の割合も拡大していた。だが同時に、日本は当初、世界恐慌による経済的苦境を打開するため、満洲の安定化を目指したに過ぎないともいえる。実際、軍部内部にも対外拡張に消極的な勢力は存在していたし、一般国民の意識も、むしろ「生きるため」「国を守るため」にやむをえず選択していた側面が強い。
このように考えると、「戦争国家」という表現が、当時の実情をどこまで正確に反映していたのかには大いに疑問が残る。むしろ、それは“事後的”に形成されたイメージであり、戦後の歴史教育やメディア報道によって増幅されてきたものではなかったか。
「戦争国家」という言葉がもたらす功罪
そして最後に、私たちがこの言葉をどう扱うべきかという問題が残る。戦争の反省や教訓は必要だ。しかし、レッテル貼りによって過去を単純化し、「だから日本は悪かった」という結論に誘導するのであれば、それは歴史の真実からは遠ざかってしまう。
歴史とは、常に複雑な背景と文脈の中にある。誰が、なぜ、何のために“戦争国家”と呼んだのかを問うことは、単に過去を知るだけでなく、私たちが今後どのような価値観を持ち、世界とどう向き合うかを考えるうえで極めて重要なのである。
このように、「戦争国家」という言葉の出所と使われ方を検証すること自体が、まさに“歴史を学ぶ”という行為の核心なのである。
1-3. 満州事変の衝撃とリットン報告書の“偽善”

1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)で発生した南満洲鉄道の爆破事件――いわゆる「柳条湖事件」を契機に、日本軍が満洲へと進軍を開始した。この一連の行動は、後に「満洲事変」と呼ばれ、国際社会との対立を深めていく象徴的な出来事となる。そしてこの事変が、日本が「戦争国家」のレッテルを貼られていく出発点として描かれることが多い。
しかし果たして、それはどれほど真実を突いた評価だったのだろうか。満洲事変を「侵略」と断じた国際連盟の姿勢、そしてその評価の根拠となった「リットン報告書」の内容には、果たして中立性と公平性があったのか。今回は、その構図を見直していきたい。
■ 満洲事変とは何だったのか──「日本の暴発」か、「中国側の挑発」か
公式には、南満洲鉄道の線路が中国軍によって爆破されたとして、日本軍がこれに対し自衛的措置として出兵したと説明された。後年の調査では、この爆破が日本側によって仕組まれたものであったことがほぼ定説となっている。
しかし、ここで注目すべきは、当時の満洲がいかに不安定かつ混乱した地域であったかという事実だ。張学良による東北統治の不安定性、匪賊の跋扈、共産党勢力の浸透など、日本の生命線と見なされていたこの地域は、安全保障上の重要課題だった。
事変直後、関東軍は中央政府の指示を待たずに独自に軍事行動を拡大し、結果として満洲全域を制圧することに成功する。昭和天皇や政府高官はこれを追認せざるを得ず、現地での「既成事実化」が中央を動かす構図となった。
■ 国際連盟の対応──リットン報告書の成立とその「正義」
国際社会はすぐに反応した。中国側の訴えに応じて、国際連盟は調査団を派遣し、現地を訪れたのがイギリス人リットン伯爵を団長とする「リットン調査団」である。
彼らは現地調査を行い、最終的にリットン報告書をまとめ上げた。報告書は、日本の軍事行動を「自衛」とは認めず、「侵略」であるとし、満洲国の建国を認めなかった。日本はこの内容に強く反発し、1933年、ついに国際連盟を脱退する。
ここで注目したいのは、リットン調査団の調査期間が非常に短かったこと、またメンバー構成に偏りがあったこと、さらに欧米列強自身が中国市場をめぐって利権を争っていた利害関係者であったという点だ。
日本が建国を支援した「満洲国」には、一応の住民自治が存在していたにもかかわらず、リットン報告書はそれを「傀儡政権」と断定。欧米がアジアにおいて築いていた植民地や支配地域と比べても、その判断基準は明らかに二重であった。
■ 欧米列強の“偽善”──自らの植民地支配とどう違ったのか?
イギリスは香港を、フランスはインドシナを、アメリカはフィリピンをそれぞれ支配下に置いていた。中国の一部である上海には、各国の「租界」が存在し、列強の治外法権が堂々と行使されていたのである。
こうした状況下で、「日本だけが侵略者」とされたリットン報告書の論調に、日本人が納得できなかったのは当然であった。実際、当時の日本国内では「リットン報告書は植民地主義者による偽善の塊だ」といった論調が支配的だった。
しかも、報告書が出された1932年から1933年にかけての国際情勢を見ても、欧米諸国は満洲に対して具体的な介入を行わず、最終的には日本の満洲統治を暗黙に認めるかたちとなっていった。
■ 日本の孤立と国民の意識──「正しさ」が伝わらなかった国際構造
リットン報告書の発表と、それに続く日本の国際連盟脱退。この一連の流れは、「日本が暴走した」という一面的な理解で語られることが多い。
だが、当時の日本国民の感情はどうだったのか。新聞各紙は連盟の姿勢に激しく反発し、全国的な「連盟脱退支持」の世論が形成された。「日本の正義が通らないなら、そんな連盟にいる意味はない」という考え方が広く共有されていた。
こうした国内の空気を無視して、「国際的には日本は加害者だった」とだけ語ることは、歴史の多面性を無視した見方である。戦後の視点からは、日本の行動は批判されるべき点も多いが、当時の人々が感じていた「正しさ」と「孤立感」は、やはり理解されるべきである。
■ 満洲事変の本質──地政学と安全保障の視点から
そもそも日本にとっての満洲とは何だったのか。それは単なる経済利権の場ではなく、ソ連の脅威に備える「緩衝地帯」であり、国防上の死活的拠点だった。
日露戦争以降、日本は莫大な人命と財政を投じて満洲の鉄道、鉱山、インフラ整備を行ってきた。これを「一方的な侵略」とみなすのは、あまりに表面的な理解であり、欧米のアジア支配の歴史を考えれば、当時の日本の判断には一定の説得力があったといえる。
もちろん、満洲事変における日本軍の独走や、政府のコントロール不能状態は批判されるべき点だ。しかしそれも含めて、国際社会が日本の立場や背景をほとんど考慮せず、「加害者」として断罪したことは、冷静な国際関係の処理とは言えなかった。
■ 「満洲事変」はなぜ語られなくなったのか
今日、学校教育の場では「満洲事変=侵略の始まり」という単純な構図だけが語られがちである。だがそこに至る背景、当時の国際秩序、日本人の安全保障観や経済事情、すべてを含めて捉えなければ、真の歴史理解にはならない。
本稿では、「満洲事変とリットン報告書」を通じて、歴史がいかに“勝者の論理”によって作られてきたかを改めて確認した。今後、私たちが歴史と向き合う際に必要なのは、「あの時代に生きていた人々の感覚に立ってみること」である。
一面的な“断罪”ではなく、背景を知り、違う立場を理解すること。そこにこそ、「もう一つの昭和史」を学ぶ意味があるはずだ。
1-4. 経済制裁という“見えない宣戦布告”

序章:宣戦布告なき戦争の始まり
1930年代、日本は世界の潮流から孤立しつつあった。だが、当時の国民も政府も、まだ本格的な戦争へと突き進む覚悟を持っていたわけではない。むしろ多くの人々は、外交的解決と平和の道を模索していた。しかし、その背後で静かに、そして確実に日本を締めつけていった力があった――それが「経済制裁」という名の“見えない宣戦布告”である。
世界恐慌とブロック経済の圧力
1929年の世界恐慌は、先進諸国に深刻なダメージを与えた。各国は自国の経済を守るため、関税障壁を強化し、植民地や勢力圏での経済ブロックを形成。イギリスの「スターリング・ブロック」、フランスの「フラン・ブロック」、アメリカの「モンロー主義的孤立」などが、日本に対して経済的な壁となって立ちはだかった。
日本は天然資源に乏しく、輸出入に依存する経済構造だったため、こうしたブロック化は致命的だった。とりわけ繊維製品などの輸出が締め出され、満州事変以降はますます排除が強まり、日本の経済は外圧によって急激に冷え込んでいった。
アメリカの対日政策と禁輸措置
当時、アメリカは中国との関係を重視しつつ、日本の拡張政策を警戒していた。満州事変以降、アメリカは日本に対し次第に敵意を強め、経済的な圧力を強化していく。石油、鉄、ゴムなど、日本にとって不可欠な戦略物資の輸出規制が始まり、1940年には「対日航空機用燃料の全面禁輸」などが実施される。
1941年に入ると、いわゆるABCD包囲網(アメリカ、イギリス、中国、オランダ)による経済封鎖が完成。これにより、日本は事実上、戦略物資の調達手段を失い、国家存亡の危機へと追い詰められていく。
経済制裁の裏にあった「外交戦争」
経済制裁は、国際法上では戦争行為と見なされないが、実質的には「宣戦布告なき戦争」と言える。特に日本にとって、資源の流れを断たれることは、軍事力の低下だけでなく、日常生活に直結する大打撃であり、民衆の間にも「我慢の限界」が広がっていった。
当時の新聞や雑誌には、資源の確保や自給自足の必要性を説く記事が多く見られ、国民の意識も「自立」から「自衛」へ、そして「対抗」へと移行していく。戦争への道は、軍部だけが描いたものではなく、こうした国際的な圧力と民意の変化が生み出した結果でもあった。
「追い詰められた日本」という視点
当時の政府内部でも、「交渉による打開」を求める声は根強かった。外務省や一部の閣僚は、日米交渉や日中和平交渉に望みをつないでいた。しかし、経済制裁が強化されるなかで、次第に「戦わざるを得ない」という空気が支配的になっていく。
外交という選択肢が消え、経済的包囲が進行するなかで、日本は“暴発”したのではなく、むしろ“追い詰められて”開戦へと向かったという見方ができる。実際、当時の記録には「資源封鎖によって日本が窒息死するのを待つ」という対日政策の明言すら見られる。
制裁は武力を使わない戦争だった
こうしてみると、1930年代から1941年までの日本は、戦争に「追い込まれていった」のであり、自ら好戦的に突き進んだわけではないという側面が浮かび上がる。経済制裁という“見えない宣戦布告”は、静かに、しかし確実に日本を開戦へと導いた。
本来、外交的に解決すべき対立が、経済という武器で仕掛けられたとき、その矛先が向けられた国家はどう応じるべきなのか。歴史は、今を生きる私たちにも重い問いを投げかけている。
1-5. 「選択肢のない時代」にいた日本人の声
1930年代の日本に生きた人々にとって、日々の暮らしや国際情勢の変化は、個々の「選択」によって動かせるようなものではなかった。戦争への道を選んだのではなく、他に道がなかった――。それが、この時代を生きた日本人の実感であった。
「戦争を望まない国民」と現実との乖離
新聞や雑誌の世論調査を見ると、開戦前夜の日本において、国民の多くは戦争を望んでいなかったことがわかる。たとえば、昭和初期の新聞アンケートでは、約7割が「戦争は避けるべき」と回答している。しかし、こうした世論は、軍部や政治の動きに対して大きな影響力を持つには至らなかった。
当時の情報統制もまた、国民の「選択肢」を狭める要因であった。新聞やラジオでは国策に沿った報道が優先され、異なる視点の情報に触れることが困難だった。自分たちの国が置かれた立場を冷静に考える材料が、そもそも与えられていなかったのだ。
経済的苦境のなかでの「支持」
また、日本人が軍事行動に一定の支持を示したように見えるのは、生活苦からの脱出を願う心情も背景にある。昭和恐慌により失業者があふれ、農村では「娘の身売り」が社会問題となった時代。そんな中、満洲への進出が「開拓」「希望」として報じられると、多くの若者が満洲移民として現地に渡った。生活の安定を求めての選択だった。
これは積極的な「戦争支持」とは異なる。追い詰められた末の「選択」だった。実際、多くの国民は、軍部の暴走や外交の失敗を冷静に批判する力も時間も持ち合わせていなかった。
「国民精神総動員運動」と同調圧力
1937年に始まった「国民精神総動員運動」は、一般市民の生活や思考に対しても国家の意向を強く押しつけるものであった。「ぜいたくは敵だ」「欲しがりません勝つまでは」という標語が生まれ、人々の行動や意見が「戦争協力か、非国民か」といった二項対立の中に押し込まれていった。
このような空気の中で、たとえ戦争に疑問を持っていたとしても、それを表に出すことは難しかった。社会的な同調圧力が強く働き、反対意見は「非国民」として弾かれる時代だったのである。
地方の声、庶民の声
当時の農村記録や個人の日記などを読むと、庶民の暮らしぶりと心情がよりリアルに伝わってくる。ある農村青年は「村には仕事がなく、兵隊になるしかなかった」と記している。また、ある主婦は「戦争はこわい。だが、兵隊に行く息子を止められない」と日記に綴った。
これらは「国家の選択」ではなく「個人の現実」であり、「戦争国家」とされた日本の実態を、より人間的な側面から浮き彫りにしてくれる。
教育と戦争の内面化
教育制度もまた、国家と個人の関係において大きな役割を果たしていた。「修身」教育では、天皇への忠誠と国家への奉仕が最も重視され、「個人の幸福」や「平和への希求」は副次的なものとされた。幼いころから「お国のために尽くす」ことが美徳とされ、それが「自然な選択」として内面化されていった。
このようにして、戦争の構造は、単なる軍事や外交のレベルを超えて、庶民の価値観や倫理観、さらには人生設計にまで深く浸透していったのである。
「国家の暴走」ではない、「時代の空気」
1930年代の日本を「戦争国家」として語るとき、しばしば「国家の暴走」として一括りにされがちである。しかし、より正確には「選択肢のない時代に生きた人々の集合的な流れ」として捉えるべきではないか。
戦争を選んだのではない。選ばざるを得なかったのだ。
その背景には、国際情勢の激変、経済的困窮、情報統制、教育の在り方、社会的同調圧力など、複合的な要因が存在した。それを理解せずに、当時の日本人を単に「軍国主義者」と決めつけるのは、あまりにも表層的な見方である。
私たちは今、あの時代を生きた人々の「声なき声」に耳を傾けながら、歴史を静かに問い直す必要がある。
(第1回 完)
(C)【歴史キング】
『もう一つの昭和史──静かなる日本再発見の旅』
副題:語られざる真実と、未来への希望をつなぐ30章
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
- {第1回}1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?
→ 今、このコラムを読まれています - {第2回}世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”
- {第3回}満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?
- {第4回}経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本
- {第5回}日独伊三国同盟――なぜ日本はこの道を選んだのか?
- {第6回}山本五十六の苦悩――「戦争では国が滅びる」
- {第7回}皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?
- {第8回}ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造
- {第9回}北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化
- {第10回}南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?
- {第11回}日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談
- {第12回}アメリカの暗号解読――すべては読まれていた?
- {第13回}松岡の誤算とヒトラーの誘惑――“世界再編の夢”とその代償
- {第14回}チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず
- {第15回}ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力
- {第16回}山本五十六、真珠湾を選んだ日
- {第17回}なぜ日本は東南アジアに進出したのか?
- {第18回}白人支配からの解放――「大東亜共栄圏」という理念
- {第19回}現地の証言から読み解く「感謝」と「葛藤」
- {第20回}戦後アジア各国から見た日本の戦い
- {第21回}東京裁判という“戦勝国の正義”
- {第22回}戦後教育に埋め込まれた価値観とは?
- {第23回}GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?
- {第24回}特攻精神と武士道の再評価
- {第25回}「反省」と「誇り」は両立するのか?
- {第26回}歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較
- {第27回}歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと
- {第28回}私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的
- {第29回}日本人が知るべきアジアからの声
- {第30回}100年後も読み継がれるために――「もう一つの昭和史」総まとめ
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。