
新潟県の偉人──河井継之助:最後のサムライが貫いた信念と独立精神
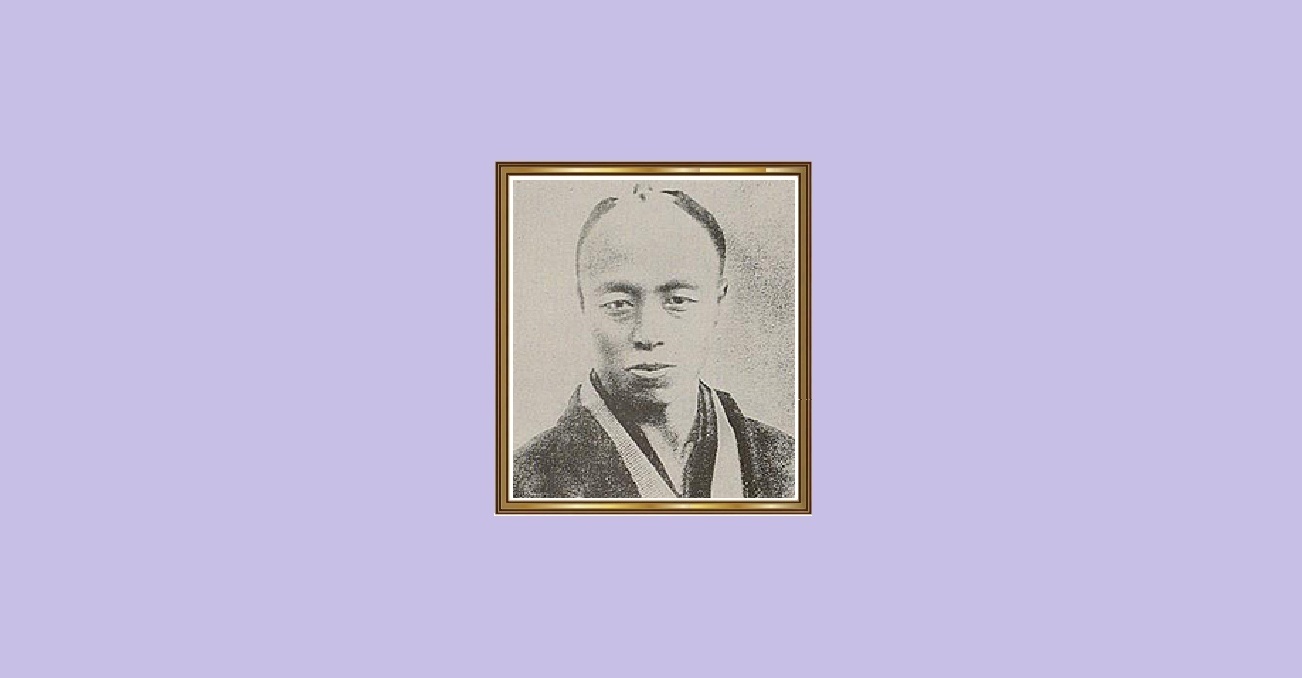
🔵幕末動乱に現れた、越後・長岡の俊才

新潟県
河井継之助(かわい つぎのすけ/つぐのすけ)
画像出典:今泉鐸次郎『河井継之助伝』目黒書店 昭和6 【610-113】
国立国会図書館デジタルコレクション
幕末期の越後長岡藩にあって、時代に先駆けた思想と胆力をもって藩政改革を推し進めた家老である。その生涯は、単なる武士の枠を超え、政治家、経済人、思想家、そして軍略家として多面的な才覚を発揮した“最後の理想主義者”とも言える。
彼が育った河井家は中堅家柄の一角に位置し、民政・財政の要職を歴任してきた有能な役方の家系だった。その伝統と才知を受け継ぎ、幕末の激動期に「独立自尊」の理念を貫いた彼の足跡をたどることは、現代の日本人にとっても深い示唆を与えてくれる。
河井継之助の出自と少年時代:風流と理知の家系に育つ
継之助は文政10年(1827年)、越後長岡藩(現在の新潟県長岡市)で、藩士・河井代右衛門の長男として誕生した。幼名は秋義、号は蒼龍窟。家禄は120石で、河井家は代々能吏として藩の財政や町政に関わっていた中堅の家柄であった。父・代右衛門秋紀は新潟町奉行や郡奉行を歴任した実務派であり、同時に僧・良寛と親交を持つなど風流人としても知られた。
この家系には諸説あるが、近江・膳所藩からの本多家の家臣にルーツをもつ説と、地元・蒲原郡の地侍から出たとする説がある。いずれにせよ、藩政において能力を評価された役方の系譜であり、その実績と信頼が継之助の藩政進出の下地を作ったことは間違いない。
幼少より才気煥発であった継之助は、藩校・崇徳館などで朱子学を学びながらも、のちに陽明学へと傾倒していく。その転機となったのが江戸や西国での遊学経験であった。
佐久間象山から山田方谷へ──継之助の学問的原点
安政6年(1859年)初春、継之助は再び江戸に上り、儒学者・古賀謹一郎の私塾「久敬舎」に入門。幕末の知の最前線であった久敬舎で経世済民の思想を磨いた彼は、さらに学びを深めるため、西国へと旅立つ。
このとき訪れたのが備中松山藩(現・岡山県高梁市)である。ここで彼は、日本屈指の藩政改革者として名高い山田方谷(やまだ ほうこく)を訪ねる。
当初、農民出身の方谷に対して継之助は「安五郎」などと通称で記すなど、どこか軽んじた態度を見せていたが、方谷の清廉な人格と驚異的な改革成果を目の当たりにし、深く心を打たれる。学識と実務の一致──知行合一の精神に基づいた方谷の改革は、継之助の理想に決定的な影響を与えた。
方谷が多忙な中で十分な指導ができなかった時は、門人である三島中洲が応対にあたった。継之助は方谷から『王文成公全集』を譲り受け、その中に方谷直筆の訓示を記してもらっているが、後年それを守れなかったことを悔いたとも伝わる。
この松山滞在の後、継之助は長崎、佐賀、熊本藩などを訪問し、西洋技術や軍事事情に見聞を広めていく。そして翌年、横浜に滞在後、長岡へ帰郷した。
この西国遊歴は、継之助にとって単なる視察ではなく、理想の国家像を模索する知の巡礼であった。
長岡藩の改革者として──理想の独立国家を目指して
帰藩後、継之助は次第に藩政の中枢に登用されていく。評定方随役から外様吟味役、郡奉行、町奉行を兼任し、ついに「御奉行格加判」として藩政全般に関わる立場に就任。これにより、名実ともに長岡藩の実権を握ることとなった。
彼の改革は徹底していた。
🚫賄賂・賭博の禁止
🚫遊郭の廃止
🚫河税・株の特権解消による商業の自由化
🚫農民救済策
🚫藩士の禄高の是正
🚫教育制度の刷新
🚫兵制改革による近代武装
こうした急進的な改革は保守派からの反発を招きながらも、「他力に頼らず、冒されず、己の力で生きていく」国家像を具現化するため、継之助は全身全霊で邁進していった。
彼が手に入れた兵器には、最新の「ミニエー銃」や、手動機関銃「ガトリング砲」も含まれる。これらは横浜の外国商人から独自に購入したものであり、長岡藩の軍事力を飛躍的に高めた。
戊辰戦争──中立から徹底抗戦へ
慶応3年(1867年)、幕府が政権を朝廷に返上すると、時代の潮流は一気に倒幕へと動いた。新政府は諸藩に兵や資金の供出を求めるが、継之助は中立を掲げ、これを拒む。
しかし、長岡にも新政府軍の進軍が迫る。継之助は小千谷会談で非戦の意志を伝えるも、新政府側の若き参謀・岩村精一郎はこれを一蹴。和議は決裂し、長岡藩は奥羽越列藩同盟に加盟して戦端を開くこととなる。
新政府軍2万に対し、同盟軍はわずか8千。劣勢のなか、継之助は榎峠や朝日山を奪還し、さらに奇襲により長岡城を奪回するという奇跡を演出。しかしその最中、継之助は左足を銃撃され、重傷を負う。
疲弊と離反が重なり、長岡城は再び落城。継之助は会津を目指し敗走するが、福島県只見町・塩沢村で力尽きた。享年42。
河井継之助を訪ねる──歴史と記憶の地
継之助の生涯は多くの地に刻まれている。長岡市には河井継之助記念館、長岡城跡、大黒古戦場、八丁沖古戦場、そして墓所のある栄凉寺がある。敗走の果てに亡くなった福島県只見町にも墓と記念館があり、彼の志を今に伝えている。
河井継之助記念館(長岡市)
栄凉寺(長岡市)
塩沢医王寺・記念館(只見町)
長岡城跡、大黒・八丁沖古戦場、光福寺ほか
小説・ドラマ・書籍で読み継がれる河井継之助
継之助の名を一躍世に知らしめたのは、司馬遼太郎の歴史小説『峠』である。司馬は彼を「木戸孝允の三倍の器量」と称え、「薩長に生まれていれば紙幣になっていた」とまで評した。NHKの大河ドラマ『峠』では、俳優・役所広司によって継之助が演じられ(映画版:2022年)、再び注目が集まった。
Amazonでも現在以下の書籍が人気である:
『峠(上・下)』司馬遼太郎(新潮文庫)
『河井継之助: 武士の矜持』童門冬二(PHP文庫)
彼の思想は現代に何を遺したのか
河井継之助の理想は、単なる藩政改革ではなく、日本という国家の未来に対する提言であった。他力に頼らず、自らの力と信念で生き抜く──その思想は現代社会においても普遍の価値を持つ。
経済格差、官僚主義、安全保障の混迷──こうした課題を前にした日本人にとって、継之助の「独立自尊」の精神は再び見直されるべき指針ではないか。
彼が詠んだ詩に、その真意が表れている:
十七誓天擬補国(十七天に誓い 補国に擬す)
春秋廿九宿心(春秋二十九 宿心たおる)
千載此機可得難(千載この機得ること難かるべし)
世味知来長大息(世味知り来って 長く大息す)
最後のサムライ──河井継之助。その生涯は「どう生きるか」を我々に問い続けている。
以上
(C)【歴史キング】






