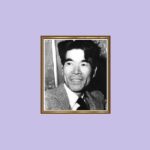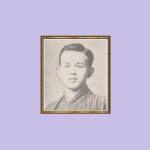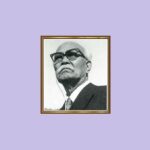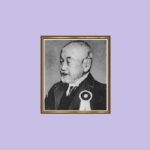
第4回 経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本

4-1. アメリカの資源制限措置とその意図
1930年代末から1940年代初頭にかけて、日本は国際的な孤立を深めていった。その一因が、アメリカを中心とする英米諸国による資源供給の制限である。とくに日本が経済的に大きく依存していた石油・屑鉄・ゴムなどの物資を止められたことは、まさに生命線を断たれるに等しい制裁措置だった。
当時の日本は、国内に十分なエネルギー資源を有しておらず、とくに石油に関しては、その大半をアメリカからの輸入に頼っていた。こうした状況で石油が止められれば、軍艦も飛行機も動かず、国家の防衛そのものが立ちゆかなくなることは火を見るより明らかだった。
資源制限の背景――「ABCD包囲網」の形成
アメリカによる資源制限は、単なる貿易摩擦ではなかった。それは中国大陸における日本の行動、南進政策、三国同盟締結といった日本の対外政策への警戒と敵意を反映していた。1940年、日本が仏印に進駐すると、その直後にアメリカは日本に対する屑鉄の全面禁輸を通告。さらに1941年7月、南部仏印への進駐が決定的となると、アメリカは在米日本資産の凍結を発表。わずか1週間後の8月1日、ついに石油の対日輸出全面禁止が通告され、日本はアメリカから一滴の石油も得られなくなった。
この措置はイギリス、オランダ、さらにはフィリピン、ニュージーランドも同調し、いわゆる「ABCD包囲網」(アメリカ、イギリス、中国、オランダ)という形で日本を包囲する国際的な制裁体制が出来上がっていった。
なぜアメリカは資源を止めたのか
アメリカの対日資源制限措置は、表向きは「中国の主権と領土保全」「国際秩序の回復」を名目としたものであったが、その真意は日本の膨張主義を抑えこむための戦略的な封じ込め政策である。実際、当時のアメリカ国内ではすでに「日本にこれ以上資源を与えることは、戦争の継続を助けることになる」という認識が広がっていた。
アメリカは日本との戦争を避けようとしながらも、経済的手段によって圧力をかけ、日本を譲歩させようとした。だが、その強硬策が、かえって日本にとっての「死活的危機」となり、追い詰められた日本は「生き残りのための戦争」に傾いていくことになる。
経済制裁は“見えない戦争”だった
日本にとって石油は、軍需のみならず民需においても不可欠であった。制裁によって国家の存続が脅かされるほどの危機に直面したとき、それを「経済戦争」と見なすのは自然な反応だった。実際、1928年に締結されたケロッグ=ブリアン条約では、「侵略戦争は禁止されるが、自衛戦争は合法」とされていた。アメリカのケロッグ国務長官自身も「重要な経済的打撃を与える政策も、侵略にあたる可能性がある」と議会で答弁している。
つまり、日本から見れば、経済制裁は軍事力を伴わない侵略であり、それに対抗する行動は“自衛”という認識であった。これが後の「大東亜戦争は自衛戦争である」との主張につながっていく。
米国は自給国、日本は依存国という現実
アメリカは資源大国であり、自国でエネルギー資源をまかなえる。対して日本は、石油・ゴム・鉄・アルミニウムといった工業国として不可欠な物資の多くを海外に依存していた。この構造的な弱点が、日本の選択肢を著しく制限した。
とくに南方にある資源地帯への依存は致命的であり、アメリカによってその補給路を閉ざされれば、日本は「生きるために戦わざるを得ない」状況に追い込まれていった。仏印進駐は、まさにその布石であり、南進政策の始動でもあった。
「資源封鎖=開戦」の等式
石油が止められれば、いずれ国が動かなくなる──この現実を前に、日本は早晩決断を迫られることになる。とくに海軍にとっては死活問題であり、「石油を止められれば戦争だ」と語った海軍将校の言葉は象徴的である。
それでも日本政府や軍部の一部には、「アメリカが本気で戦争を仕掛けてくるはずがない」「交渉で妥結できるはずだ」といった楽観論が存在し、対米戦争回避の可能性を模索していた。しかし、アメリカの姿勢は一貫して強硬であり、対話の余地はほとんど残されていなかった。
資源の制限は「静かな宣戦布告」だった
アメリカによる資源制限措置は、単なる経済政策ではなく、外交戦争の一環であり、日本に対する“見えない宣戦布告”ともいえるものであった。国家の存立を根本から揺るがすこうした動きに対して、日本がどのように対応すべきだったのか――これは現代の私たちにとっても大きな問いである。
この危機に直面した日本は、いかにして外交的選択肢を模索し、同時に“追い詰められた国”としての尊厳をどう守ろうとしたのか。次節以降、その苦闘と決断の過程を丁寧にたどっていきたい。
4-2. 石油・ゴム・鉄──封じ込められる生命線
封じ込められた資源、窒息寸前の日本経済
1941年夏、日本は経済の命綱を断ち切られた。とりわけ、アメリカが対日石油輸出の全面禁止を通告したことは、海軍・空軍をはじめとする国家の全エネルギー戦略を根本から揺さぶる事態となった。そもそも当時の日本は、石油の8割以上をアメリカからの輸入に依存していたため、これはまさに「国家の呼吸を止められた」ともいえる非常事態だった。
この措置は、アメリカが日本の南進──とりわけ南部仏印進駐──を「挑発的行動」とみなし、その対抗措置として発動したものである。しかもこの直前には、アメリカは日本の在米資産を凍結し、すでに屑鉄の輸出も禁止していた。資源供給の大動脈を一気に締め上げられた日本は、政治的にも経済的にも追い詰められた状況に陥っていたのである。
石油なき軍隊──戦えぬ軍艦、飛ばぬ戦闘機
資源制限の深刻さは、何より軍部が痛感していた。軍艦や飛行機を動かすには膨大な石油が必要であり、備蓄では到底まかなえない。木戸内大臣の日記には「海軍は二年分の備蓄があっても、戦争が始まれば一年半しかもたない」「陸軍は一年で限界」との記述がある。つまり、持久戦はもとより、短期戦ですら危うい状況だったのだ。
このため、海軍内では「いま戦わねばジリ貧になる」との焦燥が広がり、山本五十六をはじめとする現場指揮官らが中央の判断に強く異議を唱える場面も出てきた。一方で、軍令部総長・永野修身は「政府が決めたことだから」と述べ、開戦への覚悟を滲ませた。彼は天皇にも「物がなくなり、逐次貧しくなるので、どうせいかぬなら早いほうがよい」と語ったという。
ゴム、鉄、スズ──他にも奪われた資源たち
石油だけではない。アメリカやイギリスが供給していたゴムや鉄といった重要資源もまた、日本にとっては不可欠な「産業の血液」だった。とりわけゴムは、軍用車両や航空機のタイヤ、兵器の可動部品などに用いられ、鉄は武器生産とインフラ整備の要であった。こうした資源が次々と封鎖されるなか、日本は「南方資源地帯」へと手を伸ばさざるを得ない状況に追い込まれていった。
南方には石油、ゴム、スズ、タングステンといった資源が豊富に存在しており、とくにオランダ領東インド(現インドネシア)は世界有数の産油地であった。この地を押さえれば、アメリカやイギリスに依存せずとも戦争を継続できる――そんな思惑が政府・軍部に根を張っていった。
南進の論理と破綻──「窮鼠、猫を噛む」戦略
だが、こうした資源獲得のための「南進」は、必然的に英米との衝突を意味した。木戸幸一は手記に「資源の貧弱なる我が国が南方の石油、ゴム、鉄を入手する為の施策をなすは、何ら差し支えなきところであるが、これはあくまでも平和的に行なわれるべき」と書き残している。
一方で、現実には「平和的進出」は空想に過ぎなかった。すでにアメリカは対日経済封鎖の姿勢を強めており、日本が一歩動けば、その分だけ包囲網が狭まるという構造になっていた。南進とは、外交による解決を放棄し、「窮鼠猫を噛む」ような力技の解決に向かう危険な賭けでもあった。
なぜ日本は、戦争回避の道を選べなかったのか?
ここで大きな疑問が残る。「なぜ日本は、アメリカに妥協するという選択肢をとれなかったのか」という問いだ。ひとつには、すでに国際的な孤立と経済的圧迫のなかで、後戻りできない状況に追い詰められていたことが挙げられる。もうひとつには、「石油が尽きる前に何とかしなければならない」というタイムリミットが、戦争の決断を加速させたという側面がある。
さらに、当時の日本には「南方資源を手に入れさえすれば、米英と対等になれる」という幻想が根強く存在した。その背後には、近代化以降の植民地経験の欠如や、資源ナショナリズム的な発想も潜んでいた。
生命線を絶たれた国の「選択肢」とは何か
アメリカによる石油禁輸と資源封鎖は、単なる「経済措置」ではなかった。それは、明確な戦略的意思を持った「戦争なき戦争」の一形態であり、日本にとっては事実上の宣戦布告にも等しいものだった。日本は孤立を深め、追い詰められ、残された「選択肢」はますます狭まっていった。
それでも日本は、最後まで外交による打開を模索しつつ、「資源を奪われたまま沈黙するわけにはいかない」という国民的情念にも突き動かされていたのである。次回は、こうした封じ込めに誰が加担し、どのような意図で日本を経済的に締め上げたのか──その構図に迫っていく。
4-3. 誰が日本の孤立を望んだのか?
国際社会の建前と本音──「協調外交」の裏側
日本が孤立していった背景には、国際社会が掲げる「平和の維持」や「協調外交」という建前とは裏腹に、実際にはそれぞれの国益が最優先されていた現実がある。特に大戦後の世界秩序を主導していた英米仏の列強諸国は、アジアにおける自らの植民地利権を守るため、満洲における日本の影響力拡大を警戒し、牽制しようとしていた。
国際連盟の場では「侵略を許さない」という正義の言葉が繰り返されたが、その裏では日本の排除を通じて自国の影響力を維持しようという思惑が交錯していた。
英米仏ソの利権構造──日本の台頭は「脅威」だったのか?
満洲における日本の動きに対して、最も強い反応を見せたのが英米仏、そしてソ連であった。イギリスは中国大陸に広範な経済利権を有しており、アヘン戦争以来の影響力を守るために日本の軍事的進出を問題視した。アメリカもまた、中国市場の「門戸開放」政策を提唱していたことから、満洲における排他的支配を快く思わなかった。
一方でソ連にとっては、満洲は極東の安全保障に関わる生命線でもあり、日本軍の南下は直接的な脅威と受け止められていた。こうした列強の利権構造と日本の行動は、表面上の「国際協調」とは別の次元でぶつかっていたのだ。
国内の「孤立」論と現実的な打開策
国際連盟からの脱退、経済制裁、そして報道での孤立批判──これらの状況が重なる中、日本国内では「国際社会から見放された」という論調が強まっていく。しかし、果たしてそれは真実だったのか。
例えば東南アジアや中東の新興国家群、そして一部の中立国では、日本の行動を理解しようとする動きもあった。また、日本政府内でも外交による打開を模索する議論は根強く存在しており、「孤立」という言葉の一人歩きこそが、本当の孤立を招いていった側面もあった。
報道と外交の乖離──誰が「正しさ」を語ったのか?
日本の孤立が深まる中、マスメディアは連日のように「国際的非難」や「制裁強化」の報道を続けた。これにより国民の不安が煽られ、外交的な柔軟性も失われていく。一方で、外務省の一部では、アジア諸国との新たな連携や、中立国とのパイプ構築を試みる動きもあった。
だが、こうした外交努力は報じられることもなく、国民の目に触れることはほとんどなかった。「日本が悪い」「日本は孤立した」という単純な物語が広まり、冷静な判断が置き去りにされていったのである。
日本の孤立を誰が決めたのか?──問い直されるべき視点
日本の孤立は、果たして不可避だったのか。それとも意図的に「演出された」ものだったのか。歴史を振り返ると、日本がアジアの新秩序を模索する中で、既存の国際秩序から排除されていく構図が見えてくる。
「国際社会の総意」という言葉の背後には、各国の思惑と戦略が潜んでいる。日本の孤立は、単なる外交的失敗ではなく、戦略的な排除の結果でもあった。そのことを見落としては、歴史の本質はつかめない。
4-4. アジアに広がる緊張と日本の「選択肢」
白人列強の影に揺れるアジア諸国
1930年代のアジアは、単なる植民地という枠を超え、列強同士の覇権争いと民族の目覚めが交錯する緊張の坩堝だった。イギリスはインドやビルマ、オランダは東インド、フランスはインドシナを掌握し、いずれも強固な支配体制を敷いていた。しかし、その支配の背後には、圧政や差別によって押し殺されてきた民衆の不満が潜在していた。
日本が掲げた「東亜新秩序」という言葉には、こうしたアジアの現状を打破しようという意図があった。だが、アジアの現地では、まだ日本が「侵略者」なのか「解放者」なのか、その評価は定まっていなかった。現地の人々にとって、日本の動向は希望であると同時に、新たな支配者の登場なのではという不安も伴っていたのである。
この時期、日本は単なる経済封鎖への対処だけでなく、「アジアでの自国の立ち位置」を真剣に考えねばならない岐路に立たされていた。
民族解放か侵略か──二律背反のスローガン
当時の日本は、汪兆銘政権との提携を通じて「反蒋・親日」体制を固め、中国の内戦構造において一定の立場を築こうとしていた。これは一見すると、平和的秩序を追求するように見えるが、欧米列強はそれを「侵略」と決めつけ、国際世論を操作しようとしていた。英米系メディアは日本の行動を意図的に歪曲し、国際社会の「共通敵」として日本を孤立させる構図をつくり上げたのである。
だが、このような報道の背後には、アジア全体の主導権を日本に奪われたくない列強の思惑が潜んでいた。日本の行動は、列強の植民地秩序に対する「挑戦」であり、それが彼らにとっての「脅威」だったのだ。
日本に残された「選択肢」の実像
経済封鎖が進行するなかで、日本政府は、従来の国際協調路線を貫くのか、それともアジア主導の新秩序を志向するのか、という根源的な選択を迫られていた。つまり、「現状維持」か「構造転換」か──である。
前者はワシントン体制を維持し、西洋列強と協調を図る道であり、後者はアジアの自立と共栄を志す理想の道であった。理想と現実のはざまで、日本は「理想」を口にしながらも、国際的孤立という「現実」に徐々に追い込まれていった。
東南アジアに漂い始めた「解放」の空気
植民地支配下のアジア諸国では、日本の動きを注視する知識人や青年たちが存在した。インド、ビルマ、インドネシアなどの独立運動家たちは、日本の対欧米戦略を「自分たちの戦い」と重ね合わせ始めていた。
「日本が白人列強に挑んでいる」という事実そのものが、彼らにとっては精神的な支柱となった。例えばインドネシアのモハメッド・ナチールは「日本は私たちの戦争を代わりに戦ってくれた」と語り、若きインドのネルーも日本の姿勢に独立への刺激を受けたと述懐している。
ただし、これらの反応も一枚岩ではなかった。「日本が来たら本当に自由になるのか?」という疑念も常に付きまとっていたのである。
英米の「包囲網」がアジアを利用した構造
イギリスは中国への支援を強化し、日本に対する情報戦を積極的に展開していた。なかでも、インドやビルマ、オランダ領東インド(現インドネシア)においては、日本の動きを徹底的に「侵略者」と位置づけ、そのイメージを広める工作を続けていた。
一方で、欧米の新聞や通信社(ロイターなど)は、反日的な報道を多角的に繰り返し、日本の孤立化を国際的に固定化しようとしていた。もはやこれは単なる外交ではなく、「情報戦」と呼ぶべき様相を呈していた。
残された最後の交渉可能性──それもまた封じられた
当時、日本国内にはまだ「交渉による解決」を模索する動きも残っていたが、それは次第に力を失っていった。とくにアメリカのルーズベルト政権は、経済封鎖を段階的に強化しつつ、日本をじわじわと「行き止まり」に追い込む戦略を採っていた。
日本に残された「選択肢」は、もはや外交上のカードとしてはほとんど力を持たず、選択とは名ばかりの「追い詰められた決断」へと変質していた。
緊張の中に芽吹いた「希望」──新秩序構想の始動
アジア諸国の一部には、日本の新秩序構想に共感を示す動きもあった。それは、列強による搾取と差別からの解放を象徴する理念として捉えられたからである。たとえば、「東亜新秩序」という言葉に期待を寄せた人々もいた。
もちろん、それは現実としての秩序というよりも、「今よりましな未来を託す理念」としての希望に過ぎなかったかもしれない。しかし、それすらも無視された時、日本が掲げる「共栄圏」はますます孤独な道へと進まざるを得なかった。
道なき時代に「道」をつくるということ
この時代の日本は、決して攻撃的な選択を積極的に望んだのではなかった。むしろ、あらゆる扉が外から順に閉じられていくなかで、「残された道を選ばざるを得なかった」というのが、当時の実相であろう。
経済制裁によって孤立し、外交では裏切られ、メディアでは悪役に仕立てられながらも、それでも日本は、アジアの未来を託される存在であろうとした。その試みは、未熟さと勇気の狭間にあった。私たちは、あの時代の「選択」に、今あらためて光を当てる必要があるのではないだろうか。
4-5.「開戦前夜」の日本人の声
焦燥と動揺、しかし表には出ない覚悟
1941年12月8日――この日を境に、日本は世界大戦の渦中に飛び込んだ。だが、そこに至るまでの数週間、日本の政界・軍部・官僚・そして民間に至るまで、さまざまな思いが交錯していた。「戦争は避けられない」という空気が漂う一方で、「なんとか外交で打開を」という最後の望みも捨てきれずにいたのだ。
昭和天皇自身もまた、開戦決定直前の御前会議で「日米交渉の打開を極力図ってほしい」と重ねて言葉を発していた。それは、戦争への流れを止める最後の意志表明であったが、すでに状況は切迫し、逆転の余地は乏しかった。
ハル・ノートという「最後通牒」
アメリカが11月26日に提示した「ハル・ノート」は、日本にとって青天の霹靂だった。これを受け取った東郷外相や嶋田海軍大臣らは、「日本の存立を脅かす最後通牒」と受け取ったという証言が残る。政府内でこれを受諾すべきだと主張する者は皆無であり、日本の外交努力が完全に否定されたと受け止められた。
この通牒によって、戦争は事実上不可避となった。パール判事も後に、「日本のような国でなくとも、あのような通牒を受けたなら戦わざるを得ない」と述べている。
開戦決定と天皇の沈黙
12月1日、第四回御前会議が開かれ、正式に「対米英開戦」が決定される。このときの会議はわずか1時間ほどで終了した。すでに議論は尽くされていたのである。天皇は「運命というほかはない」と語ったという記録も残されている。
開戦命令は「ニイタカヤマノボレ一二〇八」。すでに日本の機動部隊は出撃していた。外交による打開の可能性は閉ざされ、歴史の歯車は音を立てて動き始めた。
外交官の悲劇と国民の知らぬ現実
開戦直前、外交交渉を担当していた野村吉三郎大使は、アメリカとの最終交渉に力を尽くしていた。しかし、外務省内の非協力的な空気、そして通告文の送達の遅延など、失策が重なった。真珠湾攻撃の直前に通告が届かなかったことで、日本は「だまし討ち」の汚名を被ることとなる。
この裏側で、日本国民は、まだ開戦の決意が固められているとは知らなかった。報道も規制され、「国難に一致団結」のスローガンが響くなか、人々は不安を抱えながらも、なんとなく日常を送っていた。
軍の本音と山本五十六の覚悟
12月5日、山本五十六は岩国で機動部隊の指揮官たちに向かって演説を行った。その場で山本は「万一、前日に交渉が成立した場合には即座に中止して帰還せよ」と命じたが、反発の声もあがったという。山本は静かに、しかし厳しく言い放った。「百年兵を養うは、国の平和を護るためである。帰れぬなら、今すぐ辞表を出せ」。
それは、開戦を命じる者の、最も重い責任感から出た言葉だった。
記憶に刻むべき「声なき声」
開戦当日の朝、日本全国にラジオ放送が流れる。「帝国は、米英両国と戦争状態に入れり」――。この一報を聞いたとき、日本人の心は震えただろう。しかしそれは、覚悟というよりも、不安と困惑の入り混じった、まさに「声なき声」であったはずだ。
開戦に至る過程で、声を上げることが許されなかった多くの庶民、反戦を唱えて左遷された官僚、複雑な思いで従軍していった青年たち。彼らの声は、表には出てこなかったが、確かに存在していた。その「沈黙の記憶」こそ、今、改めて耳を傾けるべき日本人の歴史的財産である。
(第4回 完)
(C)【歴史キング】
『もう一つの昭和史──静かなる日本再発見の旅』
副題:語られざる真実と、未来への希望をつなぐ30章
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
- {第1回}1930年代、日本はなぜ「戦争国家」とされたのか?
- {第2回}世界恐慌とブロック経済――追い詰められた“選択肢なき日本”
- {第3回}満州事変とリットン報告書――国際社会は本当に中立だったのか?
- {第4回}経済制裁という名の外交戦争――孤立していく日本
→ 今、このコラムを読まれています - {第5回}日独伊三国同盟――なぜ日本はこの道を選んだのか?
- {第6回}山本五十六の苦悩――「戦争では国が滅びる」
- {第7回}皇室の葛藤――「死なばもろともだね」の意味とは?
- {第8回}ソ連とヒトラーの密約――独ソ不可侵条約と裏切りの構造
- {第9回}北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化
- {第10回}南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?
- {第11回}日ソ中立条約の舞台裏――スターリンと松岡洋右の電撃会談
- {第12回}アメリカの暗号解読――すべては読まれていた?
- {第13回}松岡の誤算とヒトラーの誘惑――“世界再編の夢”とその代償
- {第14回}チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず
- {第15回}ルーズベルトの炉辺談話とABCD包囲網の圧力
- {第16回}山本五十六、真珠湾を選んだ日
- {第17回}なぜ日本は東南アジアに進出したのか?
- {第18回}白人支配からの解放――「大東亜共栄圏」という理念
- {第19回}現地の証言から読み解く「感謝」と「葛藤」
- {第20回}戦後アジア各国から見た日本の戦い
- {第21回}東京裁判という“戦勝国の正義”
- {第22回}戦後教育に埋め込まれた価値観とは?
- {第23回}GHQとメディア統制――日本人の記憶は誰が作ったのか?
- {第24回}特攻精神と武士道の再評価
- {第25回}「反省」と「誇り」は両立するのか?
- {第26回}歴史認識はなぜ揺れるのか――世界各国との比較
- {第27回}歴史を学ぶことの意味――それは未来を選ぶこと
- {第28回}私たちは何を受け継ぐのか――語られなかった戦争目的
- {第29回}日本人が知るべきアジアからの声
- {第30回}100年後も読み継がれるために――「もう一つの昭和史」総まとめ
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。