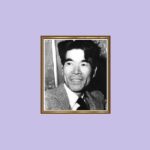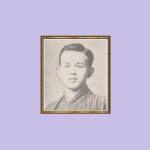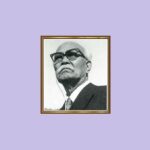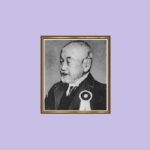
第9回 北部仏印進駐とアメリカの経済制裁強化

9-1. 仏印進駐の決定と現地対応
追い詰められた日本の新たな「活路」
1939年8月の独ソ不可侵条約締結は、日本の外交戦略に大きな衝撃を与えました。特に「北進論」、すなわちソ連を主敵とする戦略は事実上不可能となり、「南進論」へと大きく舵を切るきっかけとなりました。この南進論の中心にあったのが、仏領インドシナ(以下、仏印。現在のベトナム、ラオス、カンボジア)への進駐でした。しかし、この進駐は単なる領土的野心からではなく、当時の日本が直面していた経済的・軍事的な「活路」を求める切実な選択であったことを理解する必要があります。
中国戦線の泥沼化と「援蒋ルート」
日中戦争が長期化し、泥沼化する中で、日本軍は中国国民党の蔣介石政権を追い詰めることに苦戦していました 。その原因の一つが、アメリカやイギリス、フランスなどが中国国民党に物資や武器を供給していた「援蒋ルート」の存在でした 。特に、仏印を通るルートは重要な補給線となっており、これを遮断することが中国戦線の早期解決につながると考えられていました 。日本としては、中国を早期に屈服させ、その資源を活用することで、欧米列強との対立に備えるという戦略的意図があったのです 。
しかし、フランスは1940年5月のドイツ軍による電撃戦で本国が陥落し、ヴィシー政権が成立していました 。これにより、仏印総督府は本国からの指示が曖昧になり、事実上、ドイツの意向に左右される状態にありました。日本はこれを好機と捉え、仏印への進駐交渉を開始したのです 。
平和的進駐のはずが…現場の「暴発」
日本政府と軍部は、仏印への進駐を「平和的」に行うことを目指し、仏印総督府との交渉を進めました 。しかし、現地の日本軍の一部には、交渉がスムーズに進まないことに苛立ちを覚える者がいました。特に、当時の陸軍の若い参謀たちは、「武人が敵地に乗り込むのにおめおめ両刀を収めて玄関から上がるのですか」とまでいきり立ち、一気に仏印軍を撃破しようと突入したといいます 。
その結果、1940年9月23日、北部仏印への進駐作戦において、日本軍は仏印軍と銃火を交えることになりました 。これは、平和的な進駐を望んでいた日本政府の意図に反する、現地の「暴発」とも言える行動でした 。これにより、日本は国際社会から「侵略者」として全面的に非難を浴びることとなり 、その国際的信用は大きく失われました。現地責任者からは「統帥乱れて信を中外に失う」という痛烈な電報が東京に打たれたほどです 。
日本軍内部の「空気」と「無責任」
この事件は、単なる「事故」として片付けられるものではありません。当時の日本軍内部には、独ソ不可侵条約でドイツがソ連と手を組んだことへの不満 や、ノモンハン事件での苦戦を経て「何としても戦果を上げたい」という焦り がありました。また、陸軍全体に「根拠なき自己過信」や「驕慢な無知」 、そして「底知れぬ無責任」 が蔓延していたことも背景にあります。参謀たちは、自らの作戦計画がいかに無謀であっても、勇戦敢闘させるようなものであれば、失敗しても責任が問われないと考えていました 。
この「空気」が、仏印進駐における現場の「暴発」を許容し、結果として国際的な非難を招くことになったのです。日本陸軍は、日中戦争の頃から天皇へのきちんとした報告を怠り、自分たちの独断で事を運ぶ傾向にありました 。これは、組織として学ぶべき教訓を学ばず、同じ過ちを繰り返す体質を示していました 。
南進論の加速と海軍の苦悩
北部仏印への進駐は、援蒋ルートを遮断するという軍事的な目的を達成した一方で、日本の南進政策を本格化させることにもなりました 。これにより、ゴムや錫、そして何よりも石油の確保を目指して、オランダ領東インド(現在のインドネシア)など、さらに南方の資源地帯への関心が強まります 。
しかし、この南進は必然的にアメリカ、イギリス、オランダといった列強との全面衝突を意味しました 。特に海軍は、軍艦や飛行機を動かすのに不可欠な石油の多くをアメリカに依存していたため、資源が尽きれば国が動かなくなるという危機感を強く抱いていました 。山本五十六連合艦隊司令長官は、この事態を「言語道断だ」と憂慮し、戦争となれば「東京あたりは三度ぐらいまる焼けにされて、非常なみじめな目にあうだろう」とまで語っています 。
海軍内部には、山本のように開戦回避を訴える者もいましたが、多くの強硬派が台頭し、「バスに乗り遅れるな」という時流に乗って南進論が加速していきます 。そして、1940年11月15日には、いざという時にすぐ出動できるよう「出師準備」を発動。これは日露戦争以来のことであり、ある種の戦争決意とも言える段階に入ったことを示していました 。
「自己過信」と「無責任」の連鎖
北部仏印進駐における現地の「暴発」と、その後の国際的信用失墜は、当時の日本が抱えていた構造的な問題を浮き彫りにしました。それは、軍部の独走を許す統制の甘さ、短期的な成果にとらわれ長期的な視野を欠く戦略、そして何よりも国際社会における自己の立場を客観的に見ることができない「自己過信」と「無責任」の連鎖でした 。
この時点において、日本はすでに後戻りできない道へと足を踏み入れていました。仏印進駐は、中国戦線の泥沼化、独ソ不可侵条約の衝撃、そして資源確保という複合的な要因が絡み合った結果であり、日本が自らの意思で戦争へと突き進んだというよりも、「選択肢を失い、追い詰められていった」という側面が強いのです。
9-2. アメリカの対日姿勢の硬化と輸出制限
日本の南進とアメリカの警戒
1940年9月、日本が北部仏印(フランス領インドシナ北部)へ進駐したことは、アメリカの対日姿勢を決定的に硬化させることにつながりました 。これまでも満洲事変や日中戦争の拡大に対し、アメリカは日本を警戒してきましたが、この仏印進駐は、日本の勢力圏が東南アジアへと拡大し、アメリカの植民地であるフィリピンや、オランダ領東インド(現在のインドネシア)の石油資源に接近する動きと見なされたのです。アメリカにとって、太平洋の安定と自国の国益を守る上で、日本の南進は看過できない脅威へと変わっていきました。
屑鉄禁輸から石油全面禁輸へ
アメリカはまず、1940年9月には屑鉄(スクラップ)の対日全面禁輸を通告しました 。これは日本にとって大きな打撃でした。当時の日本は、鉄鋼生産の多くを屑鉄に依存しており、軍事産業の維持に不可欠な資源だったからです。この措置は、日本への経済的圧力を一段と強める「警告」であり、次なる制裁として石油の禁輸が来ることを強く示唆するものでした。
そして、その懸念は現実となります。1941年7月、日本が南部仏印への進駐を決定すると、アメリカのルーズベルト政権は、ついに在米日本資産の凍結を発表 。これは、日本がアメリカ国内に持つすべての金融資産や貿易資金を、自由に使えなくするという極めて厳しい措置でした。この凍結発表からわずか1週間後の8月1日、アメリカは石油の対日輸出全面禁止を通告しました 。
「ABCD包囲網」の完成と日本の生命線
このアメリカの石油禁輸措置には、イギリス、オランダ、そして中国が同調しました。これにより、日本はアメリカ(America)、イギリス(British)、中国(China)、オランダ(Dutch)の頭文字をとって「ABCD包囲網」と呼ばれる完全な経済封鎖下に置かれることになります 。
特に石油は、当時の日本の国家運営、特に軍事行動にとって、文字通り「生命線」でした 。石油の8割以上をアメリカからの輸入に依存していた日本にとって、この全面禁輸は、軍艦も飛行機も動かせなくなることを意味し、国家の防衛そのものが立ち行かなくなる死活問題でした 。木戸幸一内大臣も、「海軍は二年分の備蓄があっても、戦争が始まれば一年半しかもたない」「陸軍は一年で限界」と、石油不足の深刻さを記録しています 。
経済制裁は「宣戦布告なき戦争」だった
アメリカが日本に対して行った一連の輸出制限措置は、国際法上は「戦争行為」とは見なされませんでした。しかし、その実質は、武力を使わない「宣戦布告なき戦争」に等しいものでした。ケロッグ=ブリアン条約で侵略戦争が禁止される一方で、自衛戦争は合法とされていた時代において、アメリカのケロッグ国務長官自身が「重要な経済的打撃を与える政策も、侵略にあたる可能性がある」と議会で答弁していたことは重要です。
日本から見れば、アメリカによる資源封鎖は、国家の生存権を脅かす「経済的侵略」であり、これに対抗する行動は「自衛」であるという認識が強まっていきました 。この認識は、後の太平洋戦争を「自衛戦争」と位置づける日本の大義名分へと繋がっていくことになります。
外交交渉の限界と「追い詰められた日本」
アメリカの強硬な経済制裁は、日本政府内の外交による解決を模索する勢力を追い詰めました。野村吉三郎駐米大使は、日米関係をなんとか元に戻そうと懸命な交渉を続けますが、その努力は実を結びませんでした 。外務省内の一部のエリート官僚の反感や非協力的な態度も、交渉の足を引っ張った一因とされています 。
ルーズベルト大統領は、日本の要求をほとんど無視した「ハル・ノート」(1941年11月26日)を提示し、日本を「行き止まり」へと追い込みました 。この最終通牒は、日本の中枢部に「外交交渉は完全に失敗した」という認識を決定づけるものでした 。
当時の日本の指導者たちは、「石油が尽きる前に何とかしなければならない」という明確なタイムリミットに直面していました。この「ジリ貧」状態からの脱却、すなわち「ドカ貧」になる前に戦いを始めるべきだという論調が、海軍内部でも強まっていきます 。山本五十六は最後まで開戦に反対していましたが、ひとたび開戦が決定されると、短期決戦に持ち込むための真珠湾攻撃作戦の立案に全力を傾けました 。彼の言葉からは、戦争を避けられなかったことへの苦悩と、それでも「勝てる方法」を模索する軍人としての覚悟が読み取れます。
情報戦と日本の「甘さ」
興味深いことに、アメリカは日本の外交暗号を「パープル(紫)」と名付けて解読しており、日本の秘密電報はすべて傍受・解読されていました 。日本政府は、自国の外交情報がアメリカに筒抜けになっていることに全く気づいていませんでした 。これは、日本が情報戦において完全に劣勢にあったことを示しており、アメリカが日本の弱みを正確に把握し、その上で経済制裁を強化していった背景でもあります。
この情報格差は、日本が国際社会の動向を正確に読み解くことを困難にし、結果として「誤った楽観論」や「根拠なき自己過信」を生む土壌となりました 。アメリカは、日本が「戦わずして日本の国力を消耗せしめる」という対日政策の根幹を進めていたことを、日本の指導層は見抜けていなかったのです 。
「選択肢なき」決断への道
北部仏印進駐とそれに続くアメリカの経済制裁強化は、日本にとっての「選択肢」を著しく狭める結果となりました。資源の乏しい日本が、世界の主要市場と資源供給ルートを閉ざされた時、残された道は、武力によって資源を確保するか、あるいは国家として存立を諦めるかの二者択一に近い状況でした。
これは、日本が自ら望んで好戦的な道を選んだというよりも、世界恐慌後の国際的な経済秩序の変化と、白人列強の自国優先主義、そして日本の外交力・情報力の限界が複合的に作用し、「戦争以外に生き残る道はない」と追い詰められていった結果であると言えるでしょう。
次章では、この南進論が具体的にどのような戦略的意味を持っていたのか、そして、それが当時の日本社会と世論にどのように受け止められたのかについて、さらに深く掘り下げていきます。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。