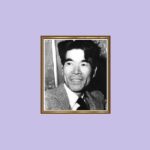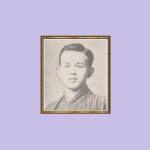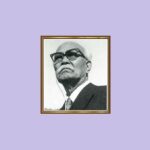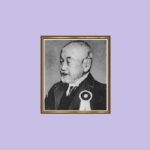
第10回 南進論と援蒋ルート遮断――仏印への進駐は侵略だったのか?

10-1. 援蒋ルート遮断という戦略的意味
中国戦線の泥沼化と日本の焦り
1937年(昭和12年)に始まった日中戦争は、当初日本の軍部が想定していた「一撃論」とは裏腹に 、長期化し、泥沼化の一途を辿っていました。首都南京を陥落させても 蔣介石は重慶へ逃れ抗戦を続け 、中国軍は広大な国土を利用した巧妙なゲリラ戦を展開し、日本軍を疲弊させていきました 。日本国内では、「いつまで戦争が続くのか」という国民の不満や不安が募り始めており 、軍も政府も、この事態を打開するための新たな方策を模索していました。
この状況下で、日本が注目したのは、蔣介石の重慶政権に対する欧米からの援助物資の流れでした。特に、フランス領インドシナ(仏印)を通る道路や鉄道は、イギリスやアメリカが中国国民党に武器や物資を供給する重要な補給路、いわゆる「援蒋ルート」となっていました。日本軍は、この援蒋ルートを遮断することが、中国戦線を早期に終結させ、対日抗戦の意思をくじく上で極めて有効な戦略だと考えたのです。
援蒋ルート遮断がもたらす複数の効果
援蒋ルートの遮断は、日本にとって複数の戦略的意味を持っていました。
まず第一に、中国戦線の早期解決です。援蒋ルートからの物資供給が止まれば、蔣介石政権の抗戦能力は著しく低下し、日本が有利な条件で和平交渉を進められる可能性がありました。これにより、日本の国力消耗を抑え、長期的な国際戦略に集中できると期待されました。
第二に、経済的圧力の強化です。当時、日本はアメリカやイギリスなどによる経済制裁と資源供給の制限に苦しんでいました。特に石油、鉄、ゴムなどの戦略物資の輸入が困難になる中で、援蒋ルートの遮断は、欧米列強への牽制となり、日本への経済的圧力を緩和させる効果も期待されました。援蒋ルートを遮断することで、中国大陸における日本の優位性を確立し、同時に欧米列強の東南アジアにおける利権を揺さぶることが可能になると考えられたのです。
第三に、南進政策の足がかりです。援蒋ルートの遮断は、仏印への進駐を伴うものでした。これにより、日本は東南アジア地域への軍事的な足がかりを得ることになります。この地域には石油、ゴム、錫など、日本が喉から手が出るほど欲していた資源が豊富に存在しており、日本の国家存続にとって死活的に重要でした。南進政策は、単なる領土拡張ではなく、経済的な自立と安全保障を確保するための「生き残り戦略」としての側面が強かったのです。
仏印進駐の決定プロセス
1940年、ドイツがフランスを電撃的に破り、ヴィシー政権が成立すると 、仏印の宗主国であるフランスは日本に対して弱腰になりました。日本はこれを好機と捉え、援蒋ルートの遮断と仏印への進駐をフランス政府に求めました。
日本政府と軍部の間では、この仏印進駐の是非について議論が交わされました。近衛文麿首相は、当初、仏印進駐を平和的に行うことを目指し、仏印総督府との交渉を進めました 。しかし、陸軍の強硬派、特に作戦を推進する参謀たちは、交渉が遅々として進まないことに苛立ちを募らせていました。彼らは、日本の国際的孤立と資源不足の現状を打破するためには、断固たる行動が必要だと考えていたのです 。
その結果、交渉の最中にもかかわらず、現地の日本軍の一部が独断で武力を行使し、仏印軍と衝突する事態が発生しました 。これにより、平和的な進駐という当初の日本の意図は損なわれ、国際社会からは「侵略行為」として激しく非難されることになります。この現場の「暴発」は、日本軍内部の統制の乱れと、結果を急ぐあまりの「拙速」さを示していました。
「侵略」か、「自衛」か──歴史の問いかけ
仏印進駐を「侵略」と断じる見方は、確かにその結果として日本の軍事力が拡大し、現地に武力介入が行われたという事実に基づいています。しかし、当時の日本の状況、すなわち、世界恐慌後のブロック経済による経済的圧迫、中国戦線の泥沼化、そして欧米列強からの資源封鎖という多重的な苦境を考慮すれば、仏印への進駐は、日本が自国の生存と安全保障を確保するために、「援蒋ルート遮断」という戦略的意味合いを持って行われた側面が強かったと言えます。
もちろん、武力行使を伴った点や、現地での「暴発」があったことは批判されるべき事実です。しかし、その行為の背後には、日本を追い詰めた国際社会の動きや、国の存亡をかけた切羽詰まった状況があったことを忘れてはなりません。
この「援蒋ルート遮断」という戦略的判断が、その後の太平洋戦争へと繋がる大きな一歩となったことは間違いありません。それは、日本が自ら望んで選んだ道というよりも、多くの選択肢が閉ざされた中で、国家が生き残るために「選ばざるを得なかった」道であったという見方もできるのです。
10-2. 南進の是非と世論の動向
「南進」は「侵略」か、「生き残りの道」か?
北部仏印への進駐、そしてそれに続くアメリカの経済制裁強化は、日本の外交・軍事戦略を大きく「南進」へと傾かせました。この「南進論」は、単に軍部の独断的な拡張主義として語られることが多いですが、当時の日本の置かれた状況を冷静に見つめ直すと、それは非常に複雑な背景を持った、「侵略」とも「生き残りのための選択」とも言える多面的な意味合いを帯びていたことが見えてきます。
資源なき日本の苦境と「生命線」の思想
日中戦争の長期化、そしてアメリカによる石油をはじめとする戦略物資の禁輸措置は、日本経済を根底から揺るがしました。日本は自国に資源が乏しく、石油の8割以上をアメリカからの輸入に頼っていたため、この経済封鎖は国家の存続に関わる死活問題でした。軍艦も航空機も動かせなくなるという現実を前に、日本は新たな資源供給源を確保しなければ、国力が枯渇し、いずれ滅びるという危機感に直面していました。
このような状況下で、豊かな石油やゴム、錫などの資源が眠る東南アジア(南方資源地帯)は、日本にとって魅力的な「活路」として浮上しました。この地域への進出は、単なる領土拡張ではなく、日本の産業と軍事を維持するための「生命線」を確保するという、切実な目的があったのです。
南進をめぐる国内の「是非」論
しかし、南進政策が決定されたからといって、国内が一枚岩だったわけではありません。政府、軍部、そして国民の間では、その「是非」をめぐって様々な議論が交わされました。
陸軍の強硬派は、中国戦線の打開と資源確保のためには、武力による南進もやむなしという立場でした。彼らは、ヨーロッパでのドイツの電撃戦の成功を見て、「今こそ世界情勢は大きく動いている。この機を逃してはならない」という焦燥感を抱いていたようです 。
一方、海軍内部には、山本五十六のように、アメリカとの戦争を避けたいという強い思いを持つ者もいました。山本は、南進がアメリカとの全面衝突を招くことを予見しており、「戦争となれば、最初の半年や一年は暴れてみせる。しかし二年、三年となれば、私は保証しない」と、日本の国力の限界を冷静に見抜いていました。海軍大臣の米内光政や、海軍次官の山本五十六、軍務局長の井上成美といった穏健派は、三国同盟や南進に対して強く反対し、あくまで対米協調の路線を維持しようと奮闘しました 。しかし、彼らの声は、軍部内の強硬派、そして「バスに乗り遅れるな」という当時の世論の潮流の中で、次第に埋もれていきました 。
国民世論の「揺れ」と「同調」
一般国民の間では、南進論に対してどのような感情があったのでしょうか。当時の新聞や雑誌の論調を見ると、必ずしも「侵略への熱狂」一辺倒だったわけではないことがわかります。確かに、マスメディアは「ABCD包囲網」といった言葉を使い、アメリカの経済制裁が日本を追い詰めていることを繰り返し報じました。これにより、「このままでは日本は滅びる」「自存自衛のためには戦うしかない」という切迫感が国民の間に広がっていったのは事実です 。
しかし、同時に、戦争への不安や生活苦に対する不満の声も存在しました。昭和14年(1939年)末の雑誌のアンケートでは、「日米戦争は避けられる」と考える国民が約3分の2を占めていたという記録もあります 。これは、国民が積極的に戦争を望んでいたわけではなく、むしろ平和的解決への期待がまだ残っていたことを示唆しています。
それでも、南進への動きが加速する中で、国民は「贅沢は敵だ」「欲しがりません勝つまでは」といったスローガンのもと、国家総動員体制へと組み込まれていきました 。言論統制が強化され、異なる意見が封殺される中で、国民は「国策」に同調せざるを得ない状況に置かれていました。「国家が生き残るためなら仕方がない」という諦念と、メディアが作り出す「やむを得ない戦争」という雰囲気が、南進を容認する大きな力となったのです。
南進政策の「功罪」とアジアの視点
仏印進駐を含む南進政策は、結果的に日本を太平洋戦争へと導き、アジアにおける日本の行動を「侵略」と批判される根拠となりました。しかし、当時のアジアには、白人列強による植民地支配に苦しむ多くの人々がいました。日本が「大東亜共栄圏」という理念を掲げ、白人支配からの解放を訴えたことは、一部の独立運動家にとっては希望の光でもありました。インドネシアのモハメッド・ナチール元首相が「日本は私たちインドネシア人が独立のために戦うべき戦争を日本が代表して敢行したものだ」と語ったように、日本の行動がアジアの民族独立に与えた影響は無視できません。
南進は、日本が白人優位の国際秩序に挑戦し、アジアに新たな秩序を築こうとした試みでもありました。それは、自国の生存権確保という切実な問題と、アジアの解放という理想が混在した複雑な行動だったのです。
歴史の教訓――「選択肢なき時代」の重み
南進の是非を問うことは、単なる過去の評価にとどまりません。それは、国家が「選択肢なき時代」に追い詰められた時、いかにして「生存」と「倫理」のバランスを保つかという、現代にも通じる普遍的な問いを投げかけます。仏印への進駐が「侵略」であったという側面を否定することはできません。しかし、同時に、その行動が当時の日本にとって「やむを得ない選択」であったという背景もまた、歴史の真実の一部として見つめる必要があるでしょう。
歴史を学ぶとは、単純な善悪二元論に陥ることなく、多様な視点から当時の状況を理解し、その複雑さに思いを馳せることでもあります。南進政策の「是非」を問い直すことは、私たち日本人自身が、自国の歴史とどう向き合い、未来へとどう繋いでいくべきかを考える上で、避けては通れない課題なのです。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。