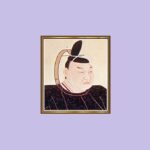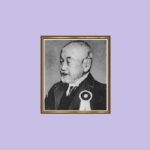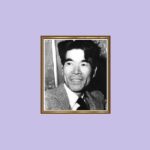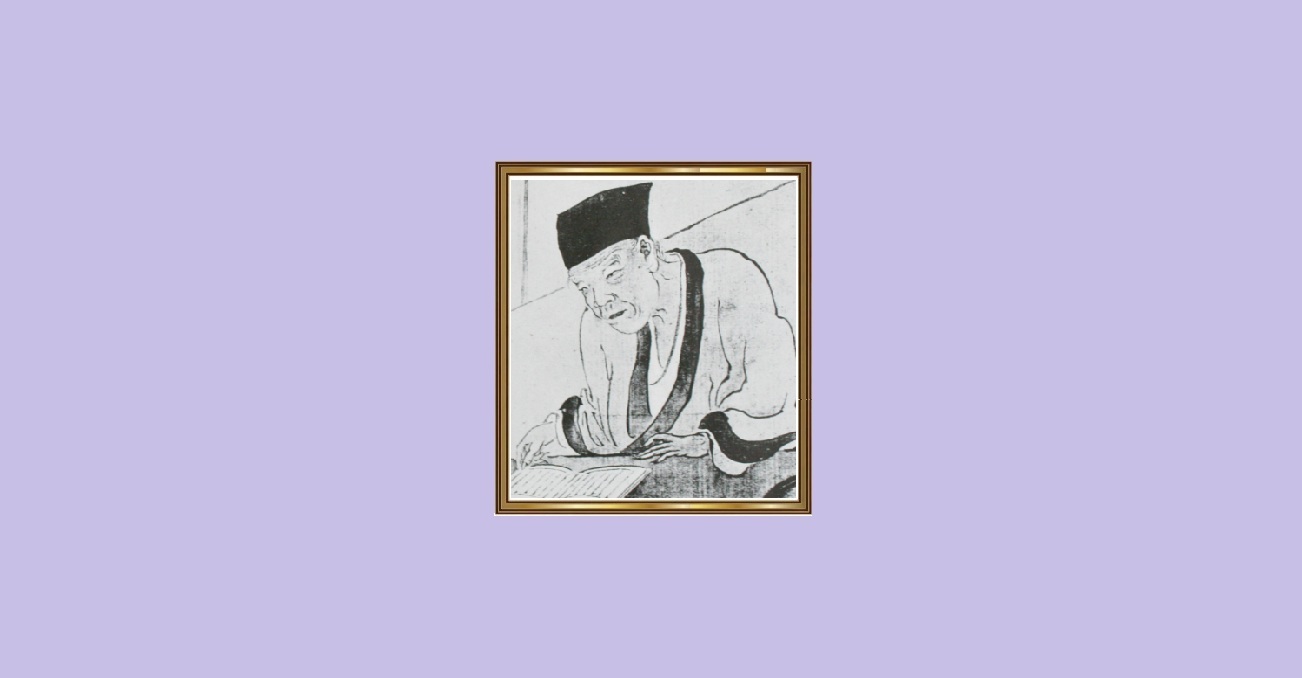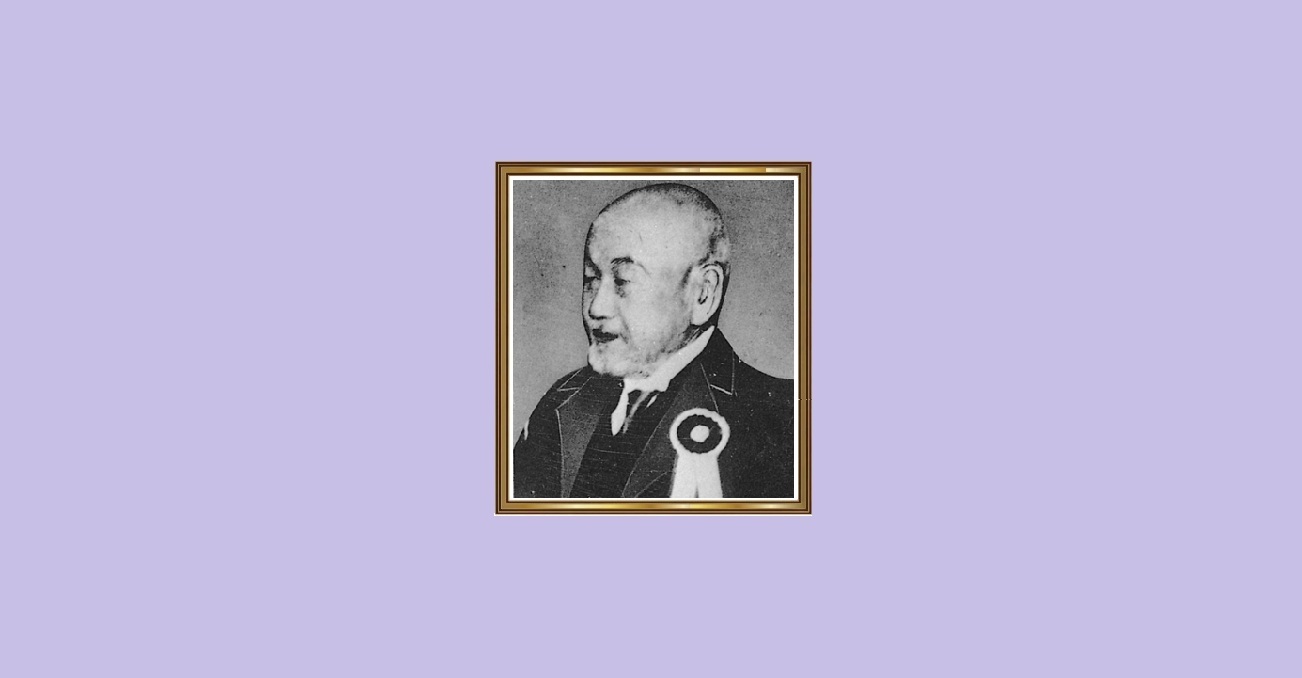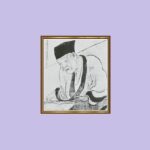
宮城県の偉人:吉野作造 — 大正デモクラシーを牽引した「日本民主主義の父」
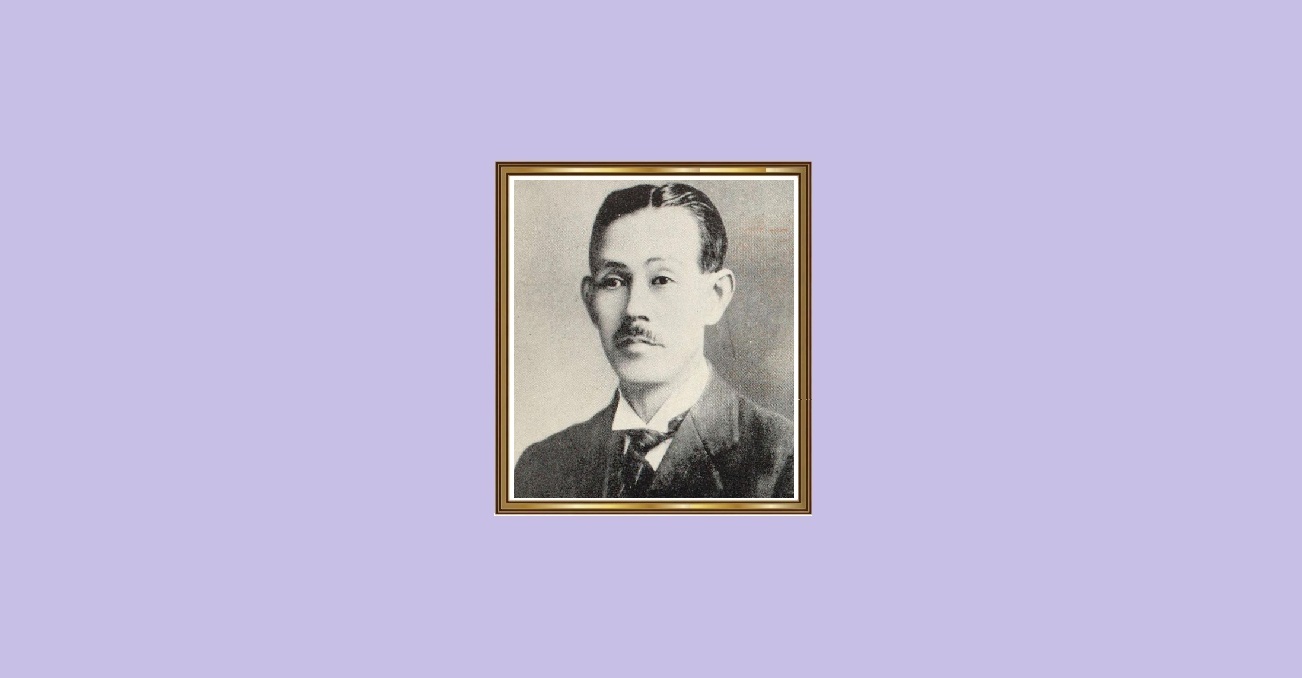

宮城県
「政治の目的は一般民衆の利福に在るべし」
この力強い言葉は、大正時代に日本の政治思想に革命をもたらした吉野作造(よしの さくぞう)が唱えた「民本主義」の核心です。宮城県大崎市(旧古川市)に生まれた彼は、旧弊な政治体制に対し、普通選挙の実現と政党政治の確立を訴え、「日本民主主義の父」として知られています。その思想と行動は、当時の日本社会に大きな変革のうねりを生み出し、現代の私たちの民主主義の基盤を築きました。吉野作造の生涯は、まさに「路行かざれば到らず、為さざれば成らず」という言葉を体現した、挑戦と実践の日々でした。
思想の原点:故郷から世界へ、そしてキリスト教との出会い
吉野作造は1878年(明治11年)、宮城県志田郡大柿村(現在の大崎市古川十日町)に糸綿商を営む家の長男として生まれます。家業を継ぐことなく、仙台の宮城県尋常中学校(現:仙台第一高等学校)、旧制第二高等学校を経て、東京帝国大学法科大学政治学科へと進学します。
彼の思想形成に大きな影響を与えたのは、第二高等学校時代に出会ったキリスト教です。自由と平等を重んじるキリスト教の教えは、吉野の心に深く根差し、後の「民本主義」の根幹をなすことになります。また、大学では政治学者の小野塚喜平次に師事し、首席で卒業するなど、学究の道を究めました。
卒業後、彼は1906年(明治39年)に清国の袁世凱の長男・袁克定の家庭教師として中国に赴任。その後、政治史および政治学の研究のため、約3年間のヨーロッパ留学を経験します。この海外での経験を通じて、彼は大きく変化しつつある世界の潮流、特に社会を動かすためには民衆の力が不可欠であることを肌で学び、自身の思想をより深めていきました。
「民本主義」の提唱と大正デモクラシーの牽引
帰国後の1914年(大正3年)、吉野は東京帝国大学法科大学教授に就任し、本格的な言論活動を開始します。彼の名を一躍有名にしたのは、1916年(大正5年)に雑誌『中央公論』に発表された論文「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」でした。
この論文の中で、吉野は「民本主義」という独自の訳語を提唱し、当時日本で主権在民を直接主張することが難しかった時代状況において、「政治の目的は一般民衆の利福に在るべし」「政策の決定は一般民衆の意向に拠るべし」と力強く主張しました。これは、天皇主権という明治憲法下の制約の中で、「Democracy(デモクラシー)」という世界的な潮流を日本の国体に即した形で理論化した画期的なものでした。
吉野の「民本主義」は、当時の知識人や民衆に広く受け入れられ、大正デモクラシーの理論的支柱となります。彼は、普通選挙の実施や政党内閣制の確立を訴え、その後の1925年(大正14年)の普通選挙法制定に大きな影響を与えました。彼の主張は、官学の最高峰である東京帝大教授という立場から発せられたこともあり、大きな説得力を持って時代を動かす原動力となったのです。
行動する政治学者:理論と実践の融合
吉野作造は、書斎にこもるだけの学者ではありませんでした。彼は自身の「民本主義」の理念を社会に浸透させるため、精力的な言論活動と社会実践を行いました。
普通選挙、労働運動、そして国際協調
吉野の活動は多岐にわたり、政治学者・松尾尊兌氏によれば、主に以下の4つの面で大きな実績を残しています。
- 民本主義の鼓吹と普通選挙・政党政治の実現への寄与: 普通選挙の実現と政党政治の発展を理論的に指導し、大正デモクラシーを主導しました。
- 労働運動の発展支援: 友愛会や新人会といった団体を通じて、労働者の権利向上を訴える労働運動を支援しました。
- 国際協調と民族自決の尊重: 当時、日本政府と対立関係にあった中国や朝鮮のナショナリズムをいち早く直視し、これと連帯する道を探りました。民本主義の理念を国際関係にも適用し、相互理解に努めたことは、彼の国際的な視野の広さを示すものです。例えば、関東大震災時の朝鮮人虐殺事件については、その真相究明に奔走し、批判論文を発表するなど、人権擁護の立場を貫きました。
- 日本近代史研究の開拓: 民本主義を歴史的に根拠づけるため、明治文化研究会を組織し、『明治文化全集』の刊行に尽力するなど、日本近代史研究の道を開きました。在野の学者や文化人を含む多様なメンバーを集めたことは、吉野の広い視野と包容力を表しています。
関東大震災での壮絶な行動と「路行かざれば到らず」
1923年(大正12年)の関東大震災では、彼の研究室と図書館が火災に見舞われます。貴重な資料を守ろうと、燃え盛る図書館に二度も突入を試みるも果たせず、炎を見上げながら立ち尽くす吉野の頬には涙が光っていたという逸話が残されています。これは、彼の学問への情熱と、自己の信念を貫くひたむきな姿を象徴する出来事でした。
彼はまた、「路行かざれば到らず、為さざれば成らず」という言葉を信条とし、どんなに正しい理論や価値観を持っていても、実際に行動に移さなければ何も達成できないと説きました。この言葉通り、彼は多くの雑誌に寄稿し、全国各地で講演を行い、市民と直接対話する機会を積極的に設けることで、自身の思想を社会に根付かせようと努力しました。
吉野作造ゆかりの地:民主主義の足跡を辿る旅
吉野作造の生涯は、彼の生まれ故郷である宮城県から、東京、そして彼が国際的に活躍した中国やヨーロッパへと広がっています。彼の足跡をたどることで、その思想と行動の軌跡を深く知ることができます。
宮城県大崎市:生誕の地と記念館
- 吉野作造記念館(宮城県大崎市古川十日町):吉野作造の功績を顕彰するために1995年(平成7年)に設立された市立の記念館です。遺族から寄贈された貴重な遺品や資料が展示されており、吉野作造の思想と活動を深く学ぶことができます。NPO法人古川学人が運営しており、市民大学講座や小・中学生向けの教育活動も活発に行われています。
東京:学びと活動の拠点、そして終焉の地
- 吉野作造墓所(東京都府中市 多磨霊園):吉野作造が眠る墓所があり、その功績を偲ぶ人々が訪れます。
- 旧制第二高等学校跡(仙台市青葉区):彼がキリスト教の洗礼を受け、民本主義の思想の基礎を築いた学び舎の跡地です。
- 東京帝国大学(現:東京大学):彼が教授として教鞭を執り、「民本主義」を発表した、日本の最高学府です。
- 早稲田大学:晩年に講師を務めた大学です。
吉野作造の遺産:現代社会へのメッセージ
吉野作造が亡くなった1933年(昭和8年)は、日本が軍国主義へと傾斜し、民主主義が抑圧されていく時代でした。しかし、彼は死の直前まで民主主義の進歩を信じ、その理念を語り続けました。
「私たちが最も心がけるべきことは、今現在正しいとされることを守り続けることよりも、常により正しいことを追求する向上的な態度をもつことでなければなりません」。
この吉野の言葉は、現代社会を生きる私たち一人ひとりへの呼びかけとして、今もなお色あせることなく輝きを放っています。
情報化が進み、多様な意見が飛び交う現代において、私たちは何を「正しい」とし、どのように社会をより良くしていくべきでしょうか。吉野作造の生涯は、単に政治学の理論を学ぶだけでなく、自身の信念を行動に移し、社会変革のために尽力することの重要性を教えてくれます。民主主義の担い手である私たちにとって、彼の「民本主義」の精神、そして「路行かざれば到らず、為さざれば成らず」という実践の哲学は、未来を切り拓くための羅針盤となるでしょう。
(C)【歴史キング】