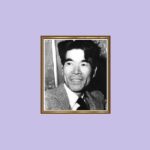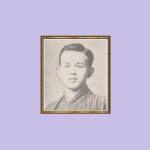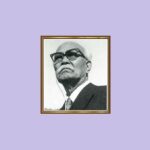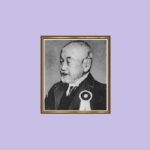
第14回 チャーチルの忠告と日本の決意――「まだ間に合う」の声は届かず

14-1. 英米からの和平示唆と日本の反応
迫りくる開戦と最後の和平の兆し
1941年(昭和16年)後半、太平洋における日米間の緊張はかつてないほど高まっていました。アメリカによる対日経済制裁、特に石油の全面禁輸は、日本の国家存亡を脅かす深刻な状況を生み出し、日本は「戦うか、滅びるか」の瀬戸際に立たされていると感じていました。このような状況下で、日本は南進政策を加速させ、アメリカとの衝突が避けられないという空気が支配的になっていました。
しかし、この緊迫した状況の中でも、まだ外交による解決の可能性を模索する動き、そして日本への「和平示唆」とも受け取れるメッセージが、英米側から発せられていたことを忘れてはなりません。果たして、日本はその声に耳を傾け、歴史の針を巻き戻すことができたのでしょうか。
チャーチルからの「冷静な忠告」
注目すべきは、イギリスの首相ウィンストン・チャーチルが、日ソ中立条約締結のためモスクワに滞在中の松岡洋右外相に送った書簡です(1941年4月12日付) 。この書簡は、チャーチルの深い洞察と、国際情勢を冷静に見極める戦略眼に裏打ちされたものでした。チャーチルは、直接的かつ具体的に、日本の対米英強硬路線がもたらす危険性を忠告しています。
ドイツの勝利は幻想ではないか?: チャーチルは、ドイツがイギリスを征服し、ソ連も叩き潰すという日本の楽観的な見方を牽制し、「ドイツが敗北すれば、日本の生産高七百万トンでは、日本単独の戦争には不充分ではないのですか」と問いかけました 。これは、日本の指導層が抱いていた「ドイツは無敵」という幻想を打ち砕き、日本の国力の限界を直視させるものでした。
アメリカの介入は避けられない: 「日独伊軍事同盟への日本の加入はアメリカの参戦を容易にしたのではないですか、あるいはかえって困難にしたのでしょうか」 。「アメリカがイギリスに味方し、日本が独伊枢軸に参加するとして、英米の優秀な海軍はヨーロッパの枢軸国を処分するとともに、日本をも処分することを可能にしたのではないですか」 と、英米が協力すれば日本も簡単に潰せるという厳しい現実を突きつけました。これは、日独伊三国同盟が対米牽制の切り札になると信じていた日本の思惑を、真っ向から否定するものでした。
アメリカの圧倒的生産力: チャーチルは、具体的な数字を挙げてアメリカの工業生産力の優位性を示しました。「1941年には、アメリカの鋼鉄の生産高は七千五百万トンになり、イギリスでは千二百五十万トンになり、合計しておよそ九千万トンになるというのは事実ではありませんか」 。これは、日本のわずか七百万トンという生産高と比較し、長期戦になれば日本に勝ち目がないことを示唆するものでした。
松岡の「侮辱」と決意
しかし、松岡洋右は、このチャーチルの忠告を「侮辱」と受け止めました。彼は、「日本の外交政策は、たえず偉大な民族的目的と八紘一宇に具現した状態を地球上に終局的に具体化することを企図し、日本の直面する事態のあらゆる要素をきわめて周到に考慮して決められたものであるから、ご安心くだされたい」と返答し、日本の決意を誇示しました 。松岡にとって、日本の行動は「八紘一宇」という壮大な理念に基づいた正義の行為であり、外部からの批判は、その理念を理解しない者の「余計なお世話」と映ったのかもしれません。
この松岡の反応は、当時の日本の指導者層に共通する「客観性の欠如」と「自己過信」を象徴していました。自国の国力や国際情勢を冷静に分析するよりも、自らの「理想」や「信念」に固執する傾向が強かったのです。
ルーズベルトの「和平への努力」と「断固たる姿勢」
アメリカのルーズベルト大統領もまた、開戦を避けつつ日本の行動を抑え込むための外交努力を続けていました。1940年11月には、ウォルシュとドラウトという二人の神父を通じて、「ルーズベルト大統領と近衛首相が太平洋沿岸で会談し、日米間の懸案を一挙に調整する」という「日米国交打開策」を日本に提示しています 。
これは、日米のトップが直接会談することで、貿易問題や中国問題といった懸案事項を話し合い、戦争を回避しようという提案でした。当初、日本政府はこれに好意的であり、特に陸軍軍務局長の武藤章少将は乗り気だったとされています 。しかし、松岡外相の帰国と強硬な反対によって、この「日米諒解案」は事実上、流れてしまいます 。松岡は、「神父がもってきたような、正常なルートでもない案をどうして信用するのか。愚劣にもほどがある。これは陸軍の陰謀だ」とまで言って、この和平案を突っぱねました 。
その後も、アメリカはハル国務長官を通じて交渉を続けましたが、日本の中国からの撤兵や三国同盟からの離脱といった原則的な要求を頑として譲りませんでした。これは、アメリカが「日本の膨張を武力ではなく経済的・外交的圧力で抑え込む」という明確な対日戦略を持っていたためです。
「戦機は後には来ない」という日本の決意
日本は、アメリカの資源制限措置によって経済的に追い詰められる中で、「ジリ貧になる前に、短期決戦で一気に活路を見出すしかない」という「戦うなら今しかない」という空気が強まっていきました 。山本五十六連合艦隊司令長官も、アメリカの圧倒的な生産力を熟知し、長期戦になれば勝ち目がないことを認識しながらも、「戦機は後には来ない」と、ハワイ作戦(真珠湾攻撃)の立案と実行を推し進めました。
1941年9月6日の御前会議では、「対英米戦を辞せず」という最終決定がなされ、11月5日の御前会議では、11月29日までに日米交渉が不成立の場合は開戦を決意するという最終的な方針が固められました 。この時、昭和天皇は再び「日米交渉を極力続けて目的が達しえられない場合は、米英と開戦しなければならないのかね」と悲痛な表情で問いかけましたが、すでに時遅しでした。
なぜ「まだ間に合う」の声は届かなかったのか
チャーチルの忠告やルーズベルトの和平示唆は、確かに「まだ間に合う」可能性を秘めていました。しかし、それが日本に届かなかった、あるいは届いても受け入れられなかったのは、以下のような複合的な要因があったと考えられます。
情報戦における日本の劣勢: アメリカが日本の暗号を解読し、日本の外交・軍事の動きを把握していた一方で、日本は相手の意図を正確に読み解く情報収集・分析能力を欠いていました。
指導者層の自己過信と現実認識の甘さ: 松岡洋右に代表される一部の指導者たちは、自らの理想や信念に固執し、国際情勢を客観的に見ることができませんでした。また、「ドイツは無敵」といった希望的観測が、冷静な判断を阻害していました。
国内の「空気」と世論の圧力: 国際的孤立や経済制裁による閉塞感、そして「やむを得ない戦争」という国民感情が、強硬路線を支持する「空気」を作り出し、平和的解決を模索する声を圧殺しました。
軍部の独走と統制の欠如: 天皇や一部穏健派の懸念にもかかわらず、軍部は独自の論理で南進政策を推進し、外交交渉の余地を狭めていきました。
「まだ間に合う」という声が届かなかったのは、日本が自ら招いた部分もあれば、国際情勢という抗しがたい大きな流れに巻き込まれていった側面もあります。この歴史の局面は、国家が危機に直面した際に、いかに冷静かつ客観的に情報を見極め、国内外の意見に耳を傾けることの重要性を示唆しています。この教訓を胸に刻むことこそが、未来へとつながる歴史認識の第一歩となるでしょう。
14-2. 決断を迫る時間との戦い
迫りくる「Xデー」と日本の焦燥
1941年(昭和16年)後半、アメリカによる石油禁輸を始めとする経済制裁は、日本を国家存亡の淵へと追い込んでいました。特に石油の備蓄が枯渇する「タイムリミット」が迫る中、日本政府と軍部には「戦うか、滅びるか」という切迫した選択肢しか残されていないという認識が強まっていました。この「決断を迫る時間との戦い」こそが、日本の太平洋戦争開戦への道を決定づけた大きな要因となります。
軍部の「戦うなら今」という論理
アメリカによる経済制裁が強化される中で、日本の軍部、特に海軍内部では、「戦機は後には来ない。今こそがチャンスだ」という強硬論が台頭していました。海軍は、日米の軍事力比率を詳細に計算しており、1941年12月末までに日本の海軍兵力が対米7割に達するが、その後はアメリカの圧倒的な生産力によってその比率は急速に低下すると予測していました 。つまり、時間をかければかけるほど、日本の劣勢は明白になるという現実的な分析があったのです。
山本五十六連合艦隊司令長官も、アメリカの国力を熟知し、長期戦では勝ち目がないことを誰よりも理解していました。しかし、彼は「やるなら最初に一撃を」という、短期決戦による講和を目指す真珠湾攻撃作戦を立案し、軍令部の猛反対を押し切ってまでその実行を推し進めました。これは、彼にとって「戦争を早く終わらせるための攻撃作戦」であり、まさに「戦うなら今しかない」という切迫した時間意識の表れでした。
外交交渉の「名ばかり」と最終期限
日本政府は、対米開戦の決定を公式化しつつも、表面上は外交交渉の継続を模索していました。これは、国際社会への配慮や、最後の最後まで平和的解決の可能性を探るという建前もありましたが、実態としては、既に軍部内で開戦の時期が決定されていた中で行われる「名ばかりの交渉」でした。
1941年11月5日の御前会議では、日米交渉が11月29日までに不成立の場合は開戦を決意するという最終方針が固められました。この「Xデー」の設定は、外交交渉に与えられた最後の期限であり、この日までにアメリカが日本の要求を全面的に受け入れなければ、武力行使に踏み切るという日本の強い決意の表れでした 。
しかし、アメリカは日本の暗号を解読しており、この「Xデー」の存在も、日本の開戦への決意も、全て把握していました。アメリカにとって、この交渉は日本を「追い詰める」ための時間稼ぎであり、ハル・ノート(1941年11月26日)は、日本の要求をほとんど無視した内容で、交渉決裂を決定づける「最後通牒」としての性格を持っていました。
昭和天皇の葛藤と「やむを得ない」裁可
昭和天皇は、最後まで戦争回避を強く望んでいました。1941年9月6日の御前会議では、明治天皇の御製を詠み、「よもの海みなはらからと思ふ世に など波風の立ちさわぐらむ」と、平和への願いと戦争への憂慮を静かに示しました。11月5日の御前会議においても、「日米交渉を極力続けて目的が達しえられない場合は、米英と開戦しなければならないのかね」と、悲痛な表情で問いかけています 。
しかし、軍部や政府首脳は、石油の枯渇という現実的なタイムリミット、そして「戦機は今」という強い信念のもと、天皇の懸念を押し切る形で開戦へと突き進んでいきました。天皇は、憲法上は統帥権の総覧者でありながらも、実質的には軍部の独走を止められないという「微妙な距離感」の中にあり、最終的には「運命というほかはない」として、開戦を「やむを得ず」裁可することになります。この天皇の苦悩は、国家を率いる者としての責任と、止められない時代の流れとの間で引き裂かれた、深い孤独の表れでした。
重臣会議と「理想」と「現実」の対立
開戦直前の12月1日、昭和天皇は過去の総理大臣経験者を集めた「重臣会議」を開き、戦争突入を報告し、意見を聞きました。この会議では、若槻礼次郎、岡田啓介、米内光政といった穏健派の重臣たちが戦争に反対する意見を述べました。特に若槻礼次郎は、東条英機首相に対し、「理想のために国を滅ぼしてはならない」と強く主張しました。しかし、東条は「理想を追うて現実を離れるようなことはしない。が、理想をもつことは必要だ」と反論し、日本の決意を固めていました 。
このやり取りは、「理想」を追求することが、時に「現実」を直視できない「独善」へと繋がりうるという、当時の日本の指導層が抱えていた問題を象徴しています。経済的困窮と国際的孤立という厳しい現実の中で、国民の生活と国家の存続を守るためには、もはや武力行使しか道がないという「やむを得ない決意」が、最終的な開戦の選択へと繋がっていったのです。
情報格差がもたらした悲劇
この「決断を迫る時間との戦い」において、アメリカの情報戦における優位性は決定的でした。アメリカは日本の暗号を解読し、日本の外交交渉の「Xデー」や軍事計画を把握していました。しかし、日本は自国の情報が筒抜けになっていることに気づかず、相手の意図を正確に読み解くことができませんでした。この情報格差が、日本の「時間との戦い」をさらに不利なものにし、開戦へと向かう日本の選択肢を狭めていったのです。
日本の指導者層は、時間がない中で「戦うなら今しかない」という焦りに囚われ、チャーチルからの冷静な忠告やルーズベルトの和平示唆といった「まだ間に合う」かもしれない声に耳を傾ける余裕を失っていました。情報戦における日本の敗北は、単なる軍事的な敗北に留まらず、外交戦略全体の失敗へと繋がり、最終的に太平洋戦争という悲劇へと日本を導く大きな要因となったのです。
歴史は、私たちに「時間との戦い」の中でいかに冷静な判断を下すか、そして情報がいかに国家の命運を左右するかを教えてくれます。過去の過ちから学び、未来へと活かすために、この「決断を迫る時間との戦い」の真実を深く理解することが重要です。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。