
沖縄県の偉人:伊波普猷 — 故郷を深く掘り、誇りを灯した「沖縄学の父」
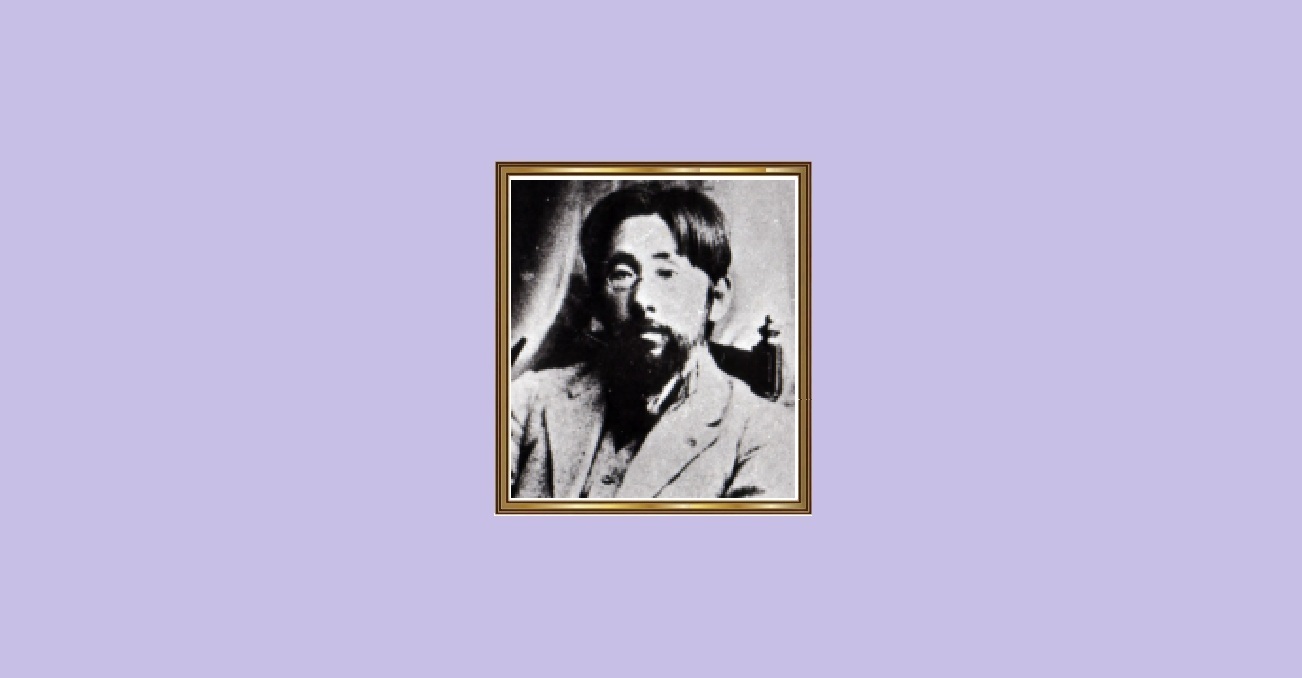

沖縄県
「彼ほど沖縄を識った人はいない。彼ほど沖縄を愛した人はいない。彼ほど沖縄を憂えた人はいない。彼は識ったが為に愛し、愛したために憂えた。彼は学者であり、愛郷者であり、予言者でもあった。」
この言葉は、友人である東恩納寛惇が、伊波普猷(いは ふゆう)の顕彰碑に刻んだものです。
沖縄県那覇市に生まれた伊波普猷は、激動の時代の中で、その生涯をかけて故郷・沖縄の歴史と文化を探究し、「沖縄学」という新たな学問分野を確立しました。「オモロと沖縄学の父」と称される彼は、沖縄の人々が失いかけていた誇りと勇気を呼び覚まし、その精神は、ニーチェの警句を翻案したという琉歌「深く掘れ己の胸中の泉 餘所たよて水や汲まぬごとに」(自分の立つ場所を深く掘れ、そこには泉がある)に象徴されています。
激動の時代に生まれた、知の探求者
伊波普猷は、1876年(明治9年)、琉球藩那覇西村(現在の那覇市西)に士族の長男として生まれました。彼が生まれたわずか3年後の1879年(明治12年)には、400年近く続いた琉球王国が「琉球処分」により解体され、沖縄県が設置されるという激動の時代に生を受けました。この時期、沖縄ではチョンマゲが切られ、標準語による教育が推進されるなど、日本本土への同化政策が進められ、沖縄の歴史や文化は否定されがちでした。
若き日の伊波は、16歳で入学した沖縄県尋常中学校(現:沖縄県立首里高等学校)で、日本人教師による差別や、日本より沖縄は劣っているという教育に直面します。この経験が、彼に沖縄の文化とアイデンティティを深く探求するきっかけを与えたのかもしれません。
彼は上京し、明治義会中学を経て、1900年(明治33年)に第三高等学校(現:京都大学の前身)に入学。1903年(明治36年)には東京帝国大学文科大学言語学科に入学し、橋本進吉、小倉進平、金田一京助、新村出といった当時の第一人者たちの講義を聴講しました。この帝大時代、彼は中学時代の恩師・田島利三郎の影響を受け、沖縄最古の歌謡集である『おもろさうし』の研究を志します。
「沖縄学」の創始と郷土への啓蒙活動
1906年(明治39年)に東京帝国大学を卒業した伊波は、故郷沖縄に戻ります。彼の専門領域は、言語学、民俗学、文化人類学、歴史学、宗教学など多岐にわたり、これらの研究が後に「沖縄学」という新たな学問分野へと発展したことから、「沖縄学の父」と称されるようになりました。
彼は、1910年(明治43年)に沖縄県立図書館の初代館長に就任。図書館を単なる書庫ではなく、「沖縄の歴史・文化の素晴らしさを沖縄の人にもっと知ってもらいたい」という強い思いのもと、県民に学びの場を提供する啓蒙活動の拠点としました。彼は、大人だけでなく子どもたちにも開かれた図書館を目指し、貴重な沖縄関連の研究資料を精力的に収集・保管しました。
さらに、伊波は県内各地で講演活動を積極的に行いました。当時、本土の同化政策によって否定されがちだった「ウチナーグチ(沖縄語)」を使い、沖縄の文化や歴史の素晴らしさを熱く語りかけました。彼の講演は評判を呼び、国内外の多くの沖縄県民に、失いかけていた「沖縄人としての自信と誇り」を回復させる大きな力となりました。彼の代表的著作である『古琉球』(1911年)などは、沖縄研究の古典的名著として知られています。
苦悩と「日琉同祖論」:アイデンティティの探求
伊波普猷は、生涯を通じて琉球人のアイデンティティの形成を模索し続けました。その探求の一つが「日琉同祖論」です。これは、日本人(ヤマトンチュ)と琉球人が同じ祖先を持つという考え方で、当時の沖縄が日本本土から差別されていた状況において、沖縄人が日本人と対等であることを主張する上で重要な意味を持っていました。
彼の研究は、『おもろさうし』の深く掘り下げられた分析を通じて、沖縄が日本とは異なる独自の特質を持つ地域であることを強調し、その独自性を日本の歴史の中に位置づけようとするものでした。それは、沖縄を日本の歴史に押しつぶされる状態から解放し、精神的な自治を目指す試みでもあったと言えるでしょう。
しかし、その一方で、伊波の思想には、近代日本が作り出した沖縄差別への批判が弱かったという指摘もあります。彼の「日琉同祖論」が、結果的に天皇制国家に沖縄を組み込むための同化政策に利用されたという批判も存在します。彼の思想は、故郷への深い愛情と、時代の制約の中で、沖縄のアイデンティティを確立しようとする複雑な葛藤の産物だったと言えるでしょう。
波瀾の後半生と最期の願い
1924年(大正13年)、49歳になった伊波は、沖縄県立図書館長を辞任し、司書を務めていた22歳年下の女性・真栄田マカト(後の伊波冬子)を追って東京に上京し、同棲生活を始めます。故郷も職も妻子も捨てての上京は、周囲に大きな波紋を呼びました。東京では豊富な資料や現地調査が困難な状況下でも、彼は冬子の支えのもと、精力的に沖縄研究を続け、多くの論文や著作を書き上げました。
1945年(昭和20年)の沖縄戦で故郷が焦土と化し、米軍の占領下に置かれるという悲劇に見舞われる中、伊波は初代沖縄人連盟の会長に就任し、沖縄の将来を深く憂い続けました。そして1947年(昭和22年)8月13日、東京の友人の仮寓で、沖縄の行く末を案じつつ、71歳で永眠しました。
彼の遺骨は、死後12年間東京に安置されていましたが、妻・冬子の帰郷に伴い、1961年(昭和36年)、伊波が研究にゆかりの深く、生前に「那覇の街が一眺され、東シナ海、慶良間列島がめるところ」と望んだという浦添城跡の地に墓が建立され、永遠の眠りにつきました。
伊波普猷ゆかりの地:沖縄学の足跡を辿る旅
伊波普猷の生涯は、彼の生まれ故郷である那覇、そしてその研究のゆかりの地である浦添を中心に、東京へと広がっています。彼の足跡をたどることで、沖縄の歴史と文化に捧げられたその情熱を感じることができます。
沖縄県那覇市・浦添市:生誕と研究の拠点
- 伊波普猷生誕地(沖縄県那覇市西):伊波普猷が生まれた那覇市西には、彼の生誕地を示す場所があります。
- 沖縄県立図書館(沖縄県那覇市泉崎):伊波普猷が初代館長を務め、沖縄研究資料の収集と啓蒙活動に尽力した場所です。現在も沖縄に関する貴重な資料が多数所蔵されています。
- 伊波普猷の墓・顕彰碑(沖縄県浦添市仲間 浦添城跡内):伊波の研究にゆかりの深い浦添城跡の西側の一画に、彼の墓と顕彰碑が建てられています。顕彰碑には、友人の東恩納寛惇による「彼ほど沖縄を識った人はいない」で始まる詩が刻まれています。
伊波普猷の遺産:未来へ繋ぐ沖縄の誇り
伊波普猷の生涯と功績は、単なる学術的偉業に留まりません。彼は、琉球処分後の混乱と差別の時代にあって、沖縄の人々が自らの歴史と文化に自信と誇りを持てるよう、その「アイデンティティ」の確立に尽力しました。
彼が愛した琉歌「深く掘れ己の胸中の泉 餘所たよて水や汲まぬごとに」は、他者に依存するのではなく、自らの足元を深く掘り下げ、内なる力を引き出すことの重要性を私たちに教えています。これは、現代社会において、グローバル化の中で自文化の価値を見失いがちな私たちにとって、普遍的なメッセージとなるでしょう。
伊波の研究は、沖縄が直面した苦難の歴史の中で、いかにしてその精神性や文化を守り、発展させていくかという問いに対する、彼の生涯をかけた答えでした。「自覚しない存在は悲惨である」という彼の言葉は、歴史を学び、自らのルーツを深く理解することの重要性を、私たちに訴えかけています。
彼の残した「沖縄学」は、今日でも多くの研究者によって引き継がれ、沖縄の文化と歴史を未来へと繋ぐ大切な役割を担っています。伊波普猷の「愛郷者」としての情熱と「預言者」としての先見性は、故郷への深い愛と、未来への希望を私たちに与え続けています。
(C)【歴史キング】








