
【京都・亀岡】龍神と繋がる古社 走田神社 〜天皇家の祖神と神聖なるナギの木〜

🟤天皇家 秘めたる社
推定樹齢不明【ナギ】
走田(ハセダ)神社(京都府亀岡市)
古都京都の亀岡盆地にひっそりと佇む走田神社(はせだじんじゃ)。奈良時代初期に創建され、平安時代の歴史書『延喜式』にもその名が記される、まごうことなき由緒ある古社です。境内を包む深い森と厳かな雰囲気は、まるで時が止まったかのよう。これまでに『鬼平犯科帳』や『十三人の刺客』など、数々の時代劇のロケ地としても選ばれるほど、その神秘的な情景は見る者を魅了し続けています。
走田神社の御神木は、境内にそびえる神聖なるナギの木です。ナギは、和歌山県や山口県、四国、九州などに分布する常緑高木で、亀岡には自生しないものの、数少ない植栽されたものの中でも特に大きな存在感を放っています。残念ながら2018年の台風で幹の一部を損壊しましたが、その威厳は今もなお健在。古くから神社の境内に植えられ、神聖な木として崇められてきたナギは、その葉脈が縦に通ることから、縦方向に裂けにくく、「縁結び」や「夫婦円満」のお守りとしても親しまれてきました。この大木は、走田神社が持つ悠久の歴史と神聖な力を象徴する存在と言えるでしょう。
この地の魅力は、ナギの木だけにとどまりません。走田神社のご祭神は、古事記に登場する「海幸・山幸」の物語で知られる、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)、その妃である豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、そしてお二人の御子である彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)の三柱の神々です。特に彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊は、初代天皇である神武天皇の父神にあたり、走田神社が皇室の直系祖先神を祀る極めて重要な社であることを物語っています。
亀岡盆地はかつて巨大な湖であったという伝説があり、出雲神話の大国主神が保津峡谷を開拓したと伝えられます。また、ご祭神の豊玉姫命は龍宮に住む海の神の娘とされ、境内には「垂乳味池(たらちみいけ)」と呼ばれる清水が湧き、子孫繁栄の御利益があるとされています。これらの伝承は、この地が水と深く結びつき、古代から人々の生活と信仰の中心であったことを示唆しています。
江戸時代には歴代亀山藩主からも厚く尊崇され、地域の氏神として崇められてきた走田神社。境内を流れる不鳴川(ならずがわ)の伝承や、鳥居や灯籠に見られる亀の意匠など、随所にユニークな発見が隠されています。
走田神社は、ただの古社ではありません。神話と歴史、そして自然が織りなす神秘的なエネルギーに満ちた場所です。特に、悠久の時を見守り続けてきたナギの御神木は、この地の神威を最も強く感じさせる存在。映画やドラマのロケ地として選ばれるのも納得の、その厳かでスピリチュアルな空間で、あなたも古代からのメッセージと生命の息吹を感じてみませんか。

🌳亀岡の名木 三十七│走田神社のナギ
樹種 ―ナギ・・・イヌマキ科
常緑高木。本州(和歌山県・山口県)・四国・九州・琉球・台湾に分布する。暖地では神社の境内に植え、また民家の庭木としても利用される。亀岡には自生しないが植栽されたものが数本確認されている。その中でもこの樹が一番の大木である。材は年輪が不明瞭、黄褐色で緻密。家具材・器具材・彫刻材などにもちいられる。果期は十月中旬。二〇一八年の台風により幹を折損する被害に遭う。
<調査日1995年11月14日>
胸高幹周=一・四メートル
樹高=十六メートル
「亀岡の名木」八八ページ所載
亀岡市・(公財)亀岡市都市緑花協会
🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より
🟤ご紹介したナギの木のある場所

📍所在地・アクセス情報
走田神社(はせだじんじゃ)
住所: 京都府亀岡市余部町走田1
アクセス:
バス停「国道穴川」より徒歩4分
JR「亀岡駅」より車で約10分
電話番号: なし
境内参拝: 自由
駐車場: 有
関連する書籍のご紹介

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)
単行本 – 2022/10/27
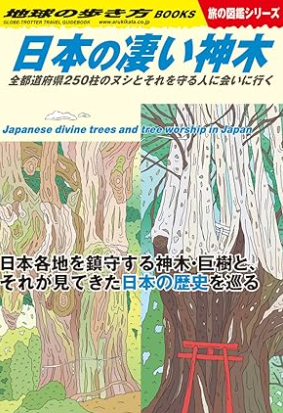
旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。
(C)【歴史キング】×【御神木マニア】







