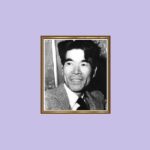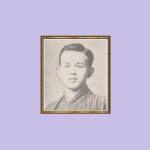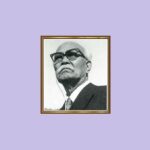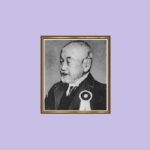
『日本人が知らない「空気」の正体: 山本七平『戦争責任と靖国問題』を読み解く』

第1回:なぜ靖国問題は終わらないのか? 戦犯合祀と日本人の「固定観念」
靖国神社と日本人の「固定観念」が引き起こした国際問題の落とし穴
「靖国」という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。多くの日本人にとって、靖国神社は国のために命を捧げた英霊を祀る神聖な場所であり、その存在は日本人の心に深く根ざしています。しかし、この靖国神社が、なぜ中国や韓国、そして欧米諸国から度重なる批判を浴びるのか、その根本的な理由を正確に知っている人は、意外と少ないかもしれません。
その最大の原因は、昭和53年(1978年)に行われた「A級戦犯の合祀」です。
軍国主義の象徴とされた東條英機をはじめとする、いわゆるA級戦犯14名が、無名戦士として祀られていた他の戦没者と同じように合祀されたことで、靖国神社は国際的な政治問題へと発展しました。
しかし、不思議なことに、この「戦犯合祀」は当時の日本国内でほとんど話題になりませんでした。政治ジャーナリストの伊藤達美氏が、この合祀の事実が発表されたのが昭和54年(1979年)4月で、新聞・テレビ等のマスコミが一斉に報道したと記しているにもかかわらず、です。
山本七平氏もまた、1986年にカナダで行われたシンポジウムで、欧米の知日家から「靖国公式参拝」への猛烈な批判を受けながらも、その問題が「戦犯合祀」にあるとは全く思い至らなかったと記しています。彼の念頭には「東條英機」という言葉はなく、「ヤレヤレ助かった」とすら感じていたと言います。
なぜ、これほど重要な出来事が、多くの日本人の記憶から抜け落ちているのでしょうか?
山本氏は、その理由を「靖国神社は名誉の戦死を遂げた人を祀る場所」という、戦前から続く日本人の「固定観念」が非常に強かったからだと指摘します。この「固定観念」は、たった一度の報道では簡単に覆るものではありませんでした。当時の総理大臣でさえ、靖国神社を「国に命を捧げた人に国民が感謝を捧げる場所」と述べており、そこには「A級戦犯」という存在が含まれているという意識は希薄でした。
この「固定観念」と、現実に起きた「戦犯合祀」との間に生まれたねじれこそが、靖国問題の根本的な落とし穴なのです。
なぜ火の手が上がるまで放置したのか?日本の後手外交
「ヤスクニ論争」は、確かに国内にも存在しました。しかし、それは主に信教の自由の問題であり、「戦犯合祀」の問題ではありませんでした。この問題が国際的な火種となったのは、昭和54年(1979年)に合祀の事実が公表されてからではなく、数年後に中国からの抗議が始まったことがきっかけでした。
山本氏は、この日本の対応を厳しく批判しています。
「火の手があがるまで放ってきた」という言葉は、まさにその状況を的確に表しています。中国からの抗議は、はじめから国際問題として提起されたものであり、本来であれば、火種が小さいうちに的確な説明と反論を行う必要がありました。
しかし、日本政府は対応を後手に回し、事態を放置した。その結果、欧米のマスメディアもこの問題を取り上げ、「日本は東條英機を神に祀り、その道を歩もうとしている」という、日本にとっては到底受け入れがたい論調で非難を繰り返すことになります。
この外交の難しさについて、山本氏は経済問題との違いを指摘しています。経済問題であれば、たとえば半導体戦争の際にも、アメリカのメーカーとユーザーが対立するように、相手の中に味方がいる可能性があります。しかし、「戦犯合祀」のような歴史や倫理に関わる問題では、日本を積極的に弁護してくれる国は世界中どこにもいません。これは、かつての友邦ドイツも同様です。一度火がつくと鎮火させるのが非常に難しく、日本は常に守勢に立たされることになったのです。
靖国問題は、決して過去の遺物ではありません。それは、我々が対応しなければならない、「現在」の問題なのです。
指揮官の「敗戦罪」と、失われた日本人の倫理観
この問題の根底には、日本人の独特な「責任」の捉え方が存在します。
山本氏は、日露戦争で多くの部下を失った乃木希典大将のエピソードを紹介しています。乃木大将は、戦勝祝賀会で人々の前に深々と頭を下げ、「皆様方の子弟を殺した乃木でございます」と語り、言葉を詰まらせたと言います。この言葉には、指揮官として部下を死地に追いやったことへの、計り知れない責任と悲しみが込められています。
一方、太平洋戦争で陸軍大臣、参謀総長、そして首相まで兼任した東條英機は、敗戦という惨禍をもたらしながら、このような「指揮官の責任」や「倫理観」が問われることはほとんどありませんでした。
当時の日本には、軍法会議で死刑を宣告されたロジェストウェンスキー中将(日露戦争時のバルチック艦隊司令官)の例にみられるように、敗戦の責任は指揮官が負うべきだという厳格な常識がありました。実際に、敗戦の責任を痛感し、自ら命を絶った軍人も少なくありませんでした。
しかし、GHQによる占領下で「戦犯」という概念が持ち込まれ、東京裁判が「平和に対する罪」という国際法にはない罪で日本の指導者を裁くと、事態は複雑化します。
この東京裁判は、日本の自国の法律である陸軍刑法で裁く機会を奪いました。代わりに「勝者の正義」という曖昧な基準で裁くことで、日本人の心から「自分たちの国が敗戦したことへの責任」という視点を奪ってしまったのです。
戦地でボロボロの『陸軍刑法』を読み、略奪や強姦殺人は死刑だと語り合っていた兵士たちは、自分たちを窮地に陥れた指導者たちにどのような思いを抱いたでしょうか。彼らが抱いたのは、「一体、東條はどうなんだろう」という、指揮官への素朴な疑問でした。
この「責任」の欠落が、戦後日本の歴史認識を歪める大きな要因となりました。
日本はなぜ二度「敗れた」のか?
敗戦後の日本人は、終戦の詔勅が下された日、皇居前で号泣し「陛下、お許しください」と叫びながら、玉砂利に額をこすりつけていました。その姿は、決して戦争の敗北を喜んだものではなく、苦難の末の悲痛な感情の表れでした。
しかし、その一方で、当時の新聞や世論は、一斉に「軍国主義は悪かった」と手のひらを返し、戦前の指導者たちを「国賊」と非難し始めました。これは、戦前の「戦争で勝って外交で負けた」という恨み節を、そのまま「戦争指導者」へと向けたにすぎません。
山本氏は、この一連の動きを「勝者の戦争目的を継承した戦後主義」と喝破します。
戦前の日本人が、「無敵皇軍」という神話を信じ、その成果を台無しにした「軟弱外交」を非難していたのと同じように、戦後の日本人もまた、GHQが掲げる「民主主義」という新しい価値観を無批判に受け入れ、戦前の指導者たちを「悪」と断罪しました。
日本人は一度、戦争に敗れました。そして二度目は、自分たちの歴史を勝者の価値観で語ることで、自らの精神を内側から否定するという形で「敗れた」のです。
靖国問題の本質は、単なる宗教や政治の問題ではありません。それは、戦後、私たちがGHQによって植え付けられた「固定観念」と、本来日本人が持っていた「責任」や「倫理観」との間に生じた、深い溝を象徴しているのです。
この「自虐史観」の呪縛から解放され、日本人本来の心を取り戻すこと。これこそが、未来へとつながる「もう一つの昭和史」を語り継ぐための第一歩となるでしょう。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

昭和史 1926-1945 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一べき1冊。
巻末に講演録『ノモンハン事件から学ぶもの』(28ページ)を増補。

昭和史戦後篇 / 半藤 一利 (著)
(平凡社ライブラリー) 文庫 – 2009/6/10

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために必読の1冊。
巻末に講演録『昭和天皇・マッカーサー会談秘話』(39ページ)を増補。