
北海道の偉人/三重県の偉人:松浦武四郎 — 「北海道」の名付け親、アイヌ民族を愛した旅の巨人
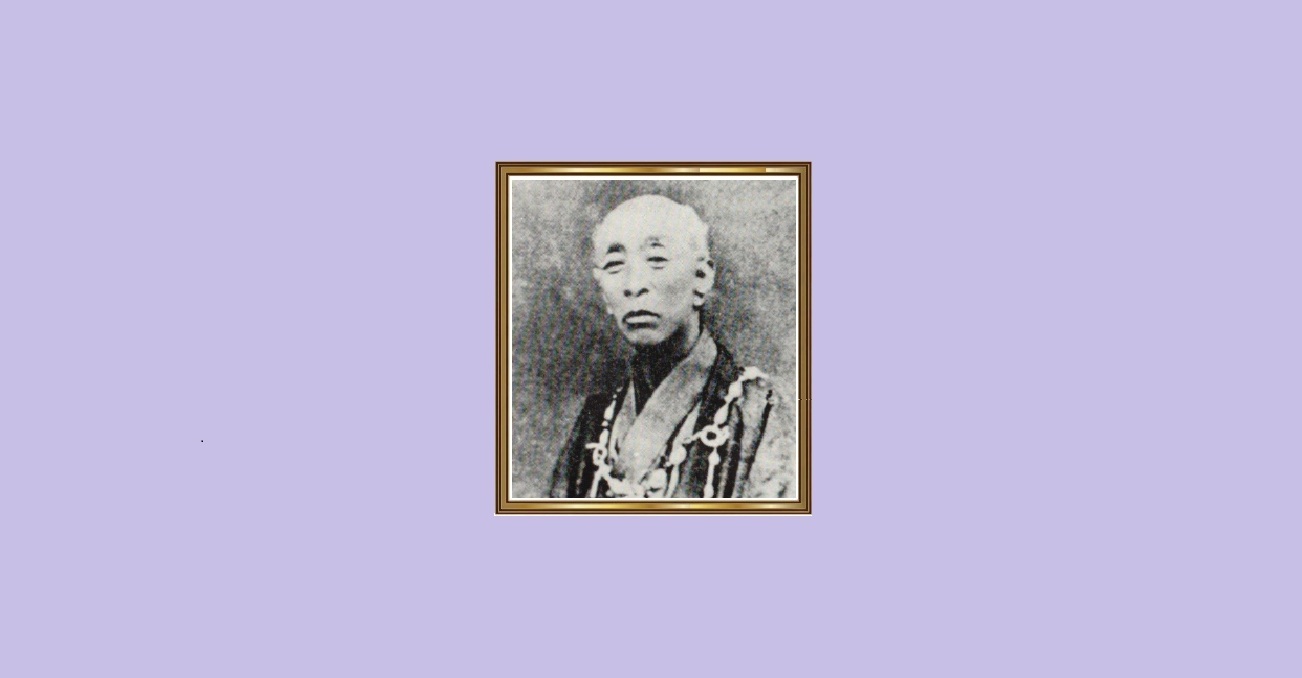

北海道│三重県
「北加伊道」
この名前を明治新政府に提案し、現在の「北海道」の礎を築いたのが、三重県松阪市に生まれた探検家、松浦武四郎(まつうら たけしろう)です。江戸時代から明治にかけて、日本中を旅し、特に蝦夷地(えぞち)を六度にわたって探査した彼は、単なる地理学者にとどまらず、アイヌ民族の文化と人権を守るために尽力した「旅の巨人」として知られています。その飽くなき好奇心と冒険心、そして何よりも他者を深く理解しようとする誠実な心は、現代に生きる私たちに、真の異文化共生とは何かを問いかけ続けています。
旅に魅せられた少年、志を抱いて北へ
松浦武四郎は1818年(文政元年)、伊勢国須川村(現在の三重県松阪市)で庄屋の四男として生まれました。彼の生家は、伊勢神宮へ向かう「おかげ参り」の旅人が行き交う街道沿いにあり、幼い頃から様々な人々や文化に触れて育ちました。この環境が、彼の類まれな好奇心と冒険心を育む土壌となりました。
16歳で初めて旅に出た武四郎は、その後27歳になるまで全国各地を巡り、名所旧跡や百名山に登るなどして見聞を広めました。しかし、長崎で北方の大国ロシアが蝦夷地をうかがっているという話を聞き、日本の国防に危機感を覚えた彼は、探検家として蝦夷地調査にその生涯を捧げることを決意します。
アイヌ民族との出会いと「北海道」の誕生
27歳になった武四郎は、生涯の使命と定めた蝦夷地探検へと向かいます。公私合わせて六度にわたる踏査は、原生林が生い茂り、道なき道を進む命がけの旅でした。この旅で彼を支えたのが、古くからその土地に住むアイヌ民族の人々でした。
武四郎はアイヌの人々と寝食を共にし、彼らの言葉を学び、文化や歴史、伝承を丹念に記録していきました。彼は、アイヌ民族の文化が決して劣ったものではなく、独自の素晴らしさを持つものであることを深く理解し、彼らが和人(わじん)による圧政に苦しめられている現状を目の当たりにして心を痛めます。
武四郎は、蝦夷地の地理、動植物、そしてアイヌ文化を克明に記録した『蝦夷日誌』や、アイヌ民族の生活をありのままに描いた『蝦夷漫画』など、膨大な数の著作を出版。アイヌの生活をありのままに記録した『近世蝦夷人物誌』は、そのルポルタージュ的な手法から、彼の存命中は出版が許されませんでしたが、彼の人間性を象徴する最高傑作として高く評価されています。
明治新政府が発足し、蝦夷地開拓が進められることになった際、武四郎は開拓判官として、蝦夷地に代わる新たな名称の選定を任されました。彼は六つの候補を提出しますが、その一つが「北加伊道(ほっかいどう)」でした。「加伊(カイ)」はアイヌ語で「人間」を意味する言葉であり、「北加伊道」には「北の大地に住む人々の国」という、先住民族への深い敬意と共生への願いが込められていました。この案が採用され、現在の「北海道」という名称が誕生したのです。
辞職と晩年の挑戦:旅に生きた人生
武四郎は、アイヌ民族の人権を守るため、彼らを酷使する「場所請負制度」の廃止を政府に強く訴え続けました。しかし、商人らの抵抗もあり、彼の意見は聞き入れられることなく、政府の開拓政策はアイヌの生活と文化を奪う方向へと進んでいきます。この状況に失望した武四郎は、明治政府の開拓使判官をわずか半年ほどで辞任し、官位も返上しました。
その後は、再び一旅人として全国を巡る自由な人生を送りました。好古家として縄文時代の古物から近代の美術品までを収集し、68歳から70歳にかけては、故郷である三重県と奈良県の県境に広がる大台ケ原を3度にわたって探査。登山道の整備や山小屋の建設に私財を投じました。70歳の時には富士山に登頂するなど、晩年まで彼の冒険心は衰えることがありませんでした。
彼は、1888年(明治21年)に東京の自宅で脳溢血により死去。享年71でした。彼の遺骨は、東京の染井霊園と、彼が最も愛した大台ケ原の西大台ナゴヤ谷に分骨されています。
松浦武四郎ゆかりの地:不屈の足跡を辿る旅
松浦武四郎の生涯は、彼の生まれ故郷である三重県から、探検の地である北海道、そして晩年の拠点となった東京へと繋がっています。彼の足跡をたどることで、その不屈の精神と偉大な功績を肌で感じることができます。
三重県松阪市:旅の原点と生家
- 松浦武四郎記念館(三重県松阪市小野江町):武四郎の生涯や功績を映像やパネル展示で分かりやすく学ぶことができる施設です。彼が全国の寺社から集めた古材で建てた書斎「一畳敷」の実寸模型は必見です。
- 松浦武四郎誕生地(三重県松阪市小野江町):築200年以上といわれる武四郎の実家が、伊勢参宮街道沿いに残されています。毎年2月には、アイヌ古式舞踊が披露される「武四郎まつり」が開催され、彼の偉業を称えています。
北海道:探検と命名の地
- 北海道命名之地記念碑(北海道音威子府村):武四郎がアイヌ語の地名から「北海道」と命名したことを記念する碑です。
- 松浦武四郎銅像(北海道天塩町、小平町など):道内各地に彼の功績を称える銅像や歌碑、顕彰碑が建てられています。特に天塩町の鏡沼海浜公園には、天塩川の風景を詠んだ歌碑が立っています。
- 松浦武四郎記念碑(北海道勇払郡厚真町):厚真町には、武四郎の功績を称える記念碑があります。
東京・神奈川:晩年の拠点
- 一畳敷書斎(東京都三鷹市 国際基督教大学構内):武四郎が晩年に自らの終の棲家として建てた書斎が、移築・保存されています。
- 松浦武四郎墓所(東京都豊島区 染井霊園):東京の染井霊園に、武四郎が眠る墓所があります。
松浦武四郎の遺産:多様性を受け入れる心
松浦武四郎の生涯は、私たちに「未知の分野への挑戦」と「他者の文化を尊重する心」の重要性を教えてくれます。彼は、誰にも知られていない北海道の全貌を明らかにすることに生涯を捧げ、その過程で出会ったアイヌ民族の文化を深く理解し、その人権を守るために身分を捨ててまで闘いました。
彼の「北海道」という命名に込められた「人間」を意味する「カイ」という言葉は、私たちにとって、多様な文化や価値観を持つ人々が共に生きる社会を築くことの大切さを示しています。これは、グローバル化が進む現代において、私たち自身の足元にある多様性を見つめ直し、それを尊重する心を持つことの重要性を教えてくれています。
武四郎の不屈の探検家精神と、アイヌ民族への深い愛情は、日本が世界に誇るべき偉大な歴史の一ページです。彼の遺した多くの著作や地図、そして「北海道」という名前は、私たちに、挑戦する勇気と、他者を愛し、共に生きる智慧を与え続けています。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

アイヌ人物誌 ーー松浦武四郎原著「近世蝦夷人物誌」/ 松浦 武四郎 (著), 山本 命 (その他), 更科 源蔵 (翻訳), 吉田 豊 (翻訳)
単行本(ソフトカバー) – 2018/9/26
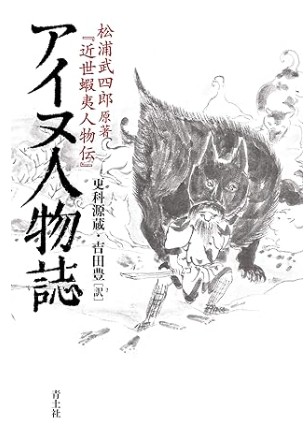
アイヌ民族が日本人からどのような立場に置かれていたのか。
時の為政者によって当時は出版禁止。アイヌの誠実にして剛毅な生き方を丹念に記録し続けた
稀有な日本人によるヒューマンドキュメント。
2019年春、松本潤が松浦武四郎役でNHKドラマ化決定! !
松浦の紀行文を読むと、単に一個の魅力的な人物というだけではない、
アイヌ民族の権利の、力強く、そして説得力ある擁護者としての姿が、文中から立ち現れて来る。
(「松浦武四郎北方日誌」(金関寿夫 訳)より)
ーードナルド・キーン
アイヌとの交流なしに未墾の大地は歩き回れなかっただろう。
彼らから聞く土地の名を文字にしていったことで、大きな島の地図が出来上がり歴史に組み込まれていく。
後に北海道と名付けられるその大地で、松前藩や請負商人に搾取され苦しむ先住民の姿を、
松浦武四郎は彼らに寄り添うように描き出している。
ーー奈良美智






