
【大阪・門真】奇跡の巨樹「薫蓋樟」三島神社の神威に触れるパワースポット〜千年の生命が紡ぐ物語〜

🟤奇跡の巨樹「薫蓋樟(くんがいしょう)」
推定樹齢1000年以上【薫蓋樟】
三島神社(大阪府門真市)
大阪府門真市、淀川水系の古川が流れる温暖な低湿地に、古くからこの地の氏神として崇められてきた三島神社(みつしまじんじゃ)が鎮座しています。その境内いっぱいに枝葉を広げ、圧倒的な存在感を放つ巨木こそ、国指定天然記念物であり「新日本名木100選」にも選ばれた「薫蓋樟(くんがいしょう)」です。推定樹齢1000年以上、高さ約24m、幹周り13.1m(資料によっては17m超)にも及ぶこのクスノキは、大阪府内で最大、そして日本国内でも有数の規模を誇る生ける伝説です。
「薫蓋樟」という名は、江戸時代後期の公家、千種有文(ちくさありふみ)がこの木を詠んだ歌碑に由来します。「村雨の雨やどりせし唐土(もろこし)の 松におとらぬ樟ぞこのくす」と刻まれた歌は、まるで中国の伝説の松にも劣らないほどの壮麗さを称えています。地元の人々からは親しみを込めて「クスノキさん」と呼ばれ、その存在は地域に深く根付いています。
この巨樹は、社殿に接するように根を下ろし、その枝葉はまるで神社全体をすっぽりと覆い隠すかのようです。幹の根元には不規則な凹凸が生まれ、黒ずんだ幹にはいくつもの大きなこぶが見られます。主幹からうねるように伸びる5本の大枝は、東西に約34m、南北に約33mもの広がりを見せ、その雄大さはまさに圧巻です。幹の高さ2m付近には注連縄が張られ、神聖な存在として敬われていることが伺えます。
薫蓋樟は、千年の長きにわたり、幾多の試練を乗り越えてきました。大正時代には電柱設置のために枝先を一部伐り落とされた際、伐った当人が木の祟りで腹痛を起こしたという言い伝えが残っています。1934年(昭和9年)の室戸台風では大きな被害を受け、昭和後半には周囲の宅地化や道路舗装の影響で地下水が涸れ、樹勢が衰え葉が黄ばむほどになりました。しかし、1974年(昭和49年)に地元の人々が保存会を結成し、境内に掘割を作るなどの対策を行った結果、見事に樹勢を取り戻したのです。この奇跡的な回復力は、この木が持つ計り知れない生命力と、人々との深い絆を物語っています。
三島神社は、天照皇大神、大己貴命、素盞嗚尊の三神を祀る由緒ある神社です。この地域がクスノキの生育に適した温暖で平坦な低湿地であったことから、古くから多くの巨木が育ってきました。門真市では、1973年(昭和48年)にクスノキを「市の木」に選定しており、薫蓋樟はそのシンボルとして、市の将来を象徴する存在となっています。
2012年には巨樹研究専門家による「神秘的な巨樹ベスト10」で第9位に選ばれるなど、その神秘性は全国的にも注目されています。幹のすきまにできた穴は、かつて子供たちの格好の遊び場であったというエピソードも、この木が地域の人々の生活に寄り添い、親しまれてきた歴史を物語っています。
千年の時を超え、数々の困難を乗り越え、今なお力強く生き続ける「三島神社の薫蓋樟」。その雄大な姿は、私たちに自然の偉大さ、生命の尊さ、そして地域の人々との深い結びつきを教えてくれます。ぜひ一度、このパワースポットを訪れ、悠久の歴史と神威、そして生命の息吹を肌で感じてみてください。
所在地・アクセス情報
名称: 三島神社の薫蓋樟(くんがいしょう/くんがいくす)
所在地: 大阪府門真市三ツ島1丁目15 三島神社境内
アクセス:
Osaka Metro長堀鶴見緑地線「門真南駅」より徒歩約15分
京阪電気鉄道京阪本線「門真市駅」よりタクシーで約10分
駐車場: 有
<現地説明文>
薫蓋(くんがい)クス(国指定天然記念物)
指定: 1945年5月30日 史跡名勝天然記念物保存法
薫蓋樟(くんがいしょう)の名で親しまれている三島神社の境内にある樹齢1千年といわれるクスノキの巨樹。
府内に4件しかない樹木の国指定の天然記念物の一つで、高さは約24mあり、 幹周りは13.1mで幹の中は空洞になっています。樹勢は旺盛で四方に大きく枝を広げています。
集落の中でこれほどの巨樹が生育しているのは非常に珍しいことです。
根元には、江戸時代後期の公家左近衛少将千種有文の歌碑
薫蓋樟 村雨の雨やどりせし唐土の 松におとらぬ楠ぞこのくす
があり、名称の由来となっています。
門真市教育委員会
🟤ユーチューブちゃんねる{御神木マニア}@goshinbokumania より
🟤ご紹介した御神木(クスノキ)のある場所
関連する書籍のご紹介

日本の凄い神木: 全都道府県250柱のヌシとそれを守る人に会いに行く / 本田不二雄 (著)
単行本 – 2022/10/27
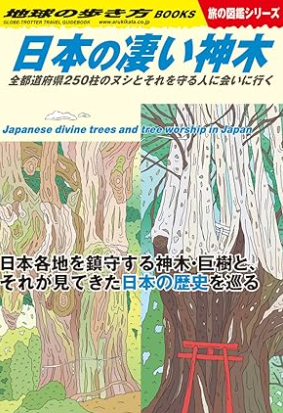
旅に新しい楽しみや見方を紹介する旅の図鑑シリーズ新刊。日本の全都道府県の、地元で信仰される神木や、歴史ある巨木を紹介。木の歴史や巨木が生まれる背景、人との生活との関わりなど、「木の旅」をテーマに、各地方の巨木・神木を240本以上紹介。また、木・人・旅に関するコラムなどの情報も充実。
(C)【歴史キング】×【御神木マニア】







