
愛媛県の偉人:二宮忠八 — ライト兄弟に先駆けた日本の空の開拓者【日本飛行機の父】
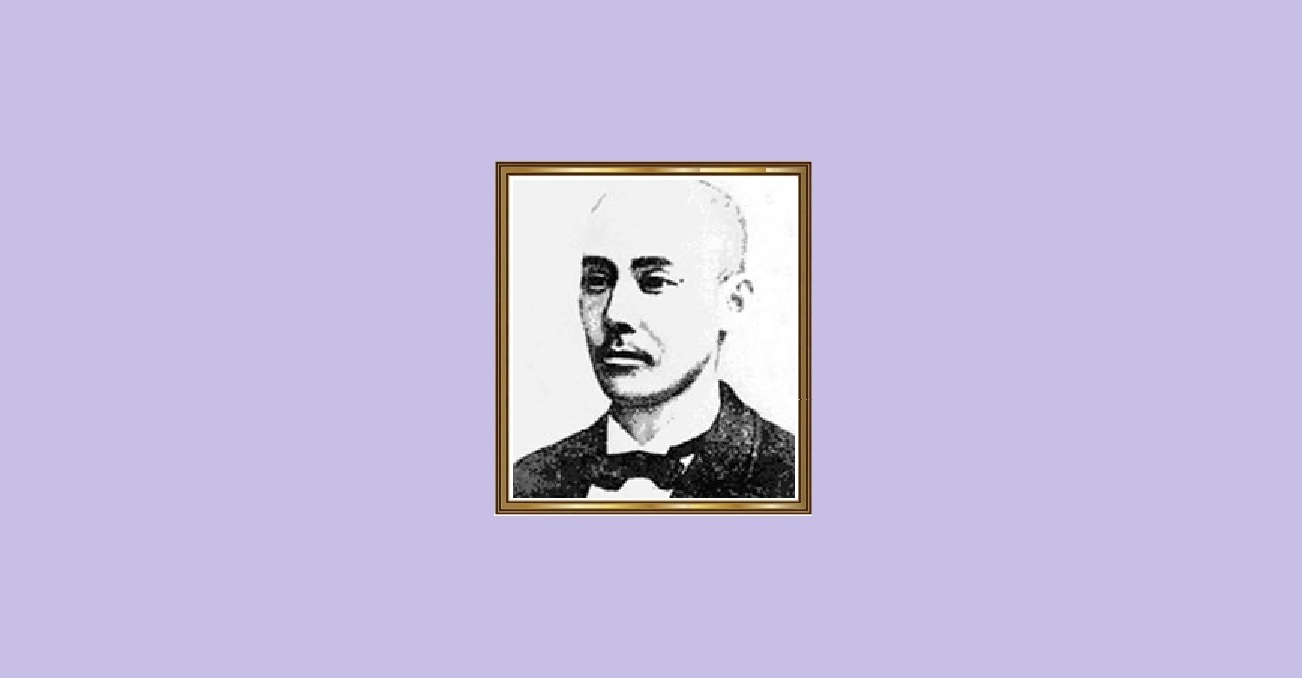
プロフィール
二宮 忠八(にのみや ちゅうはち)
1866年6月20日生│1936(昭和11)年4月8日没(69歳)
「飛行器」「模型飛行器」「日本飛行機の父」
「若かりし頃、毎晩のように飛行機に乗る夢を見たが、実際の飛行機はそれと少しも違わなかった」
この言葉は、日本人で初めて飛行原理を着想し、「日本飛行機の父」と称された二宮忠八(にのみや ちゅうはち)が、晩年に生涯一度だけ飛行機に乗ったときの感想です。
伊予国宇和郡八幡浜浦矢野町(現在の愛媛県八幡浜市)に生まれた彼は、ライト兄弟よりも12年も早く、動力飛行機の原理を発見しました。軍や国に理解されず、夢を挫折せざるを得ませんでしたが、その情熱と不屈の精神は、後の日本の航空界に大きな影響を与え、その功績は、故郷の愛媛や香川に今も語り継がれています。
幼少期の苦学から「飛行原理の発見」へ
二宮忠八は1866年(慶応2年)、八幡浜市の海産物問屋の家に生まれました。幼い頃は裕福な家庭でしたが、12歳の時に父を亡くし、家業が傾いたため、奉公に出て家計を支える苦学の日々を送りました。しかし、彼の探究心は衰えることはありませんでした。町の雑貨店や印刷所で働きながら、夜遅くまで物理学や化学の本を読み耽り、自ら考案した「忠八凧(ちゅうはちだこ)」を売って学資を得ました。この凧作りで培われた創意工夫と、錦絵で見た気球への憧れが、彼の空への夢の原点となります。21歳になった1887年(明治20年)、忠八は徴兵され、香川県丸亀の歩兵第12連隊に入隊します。そして、1889年(明治22年)11月9日、野外演習の帰途、香川県仲多度郡十郷村の樅ノ木峠で、運命的な出来事を経験します。昼食中に、群れをなして飛ぶカラスが、羽ばたかずに翼を広げただけで滑空している姿を目にしたのです。この観察から、忠八は「固定翼」が空気の圧力によって浮き上がる力(揚力)を生み出し、空を飛ぶことができるのではないか、という航空力学の原理を発見しました。これは、レオナルド・ダ・ヴィンチ以来、飛行機は鳥のように羽ばたいて飛ぶものと考えられていた時代において、世界的に画期的な着想でした。
「カラス型」「玉虫型」飛行器の製作と軍への上申
飛行原理の発見以来、忠八は寝る間も惜しんで研究に没頭します。そして、軍の聴診器のゴム管を動力源に、船のスクリューをヒントにしたプロペラを回す、最初の模型飛行器「烏(からす)型模型飛行器」を完成させました。1891年(明治24年)4月29日、丸亀練兵場でこの模型飛行器の飛翔実験に成功。自力滑走で約10メートル、手投げ発進では約36メートルを飛行しました。これは、アメリカでライト兄弟が有人動力飛行に成功する12年も前のことであり、動力による人工翼が空中を飛行した、日本最初の出来事でした。さらに彼は、人間が搭乗できる人力飛行機「玉虫型飛行器」の構想を練り、製作に着手します。これは、無尾翼の複葉機で、下の翼が操縦翼面として機能する、当時としては非常に先進的な設計でした。しかし、日清戦争が始まると、衛生卒として従軍していた忠八は、飛行器が戦場での偵察や通信に役立つと考え、軍に上申書を提出します。しかし、旅団参謀の長岡外史(ながおか がいし)大佐ら上官たちからは、「今は戦時中である」「本当に空を飛んだら聞いてやろう」と、その夢を一蹴されてしまいます。
挫折と再起、そして「飛行神社」の建立
軍の理解を得られなかった忠八は、独力で飛行機を完成させるしかないと決意し、軍籍を離れて実業家への道を選びます。大日本製薬株式会社に入社し、のちに自ら大阪製薬を設立して社長に就任するなど、薬業で成功を収め、飛行機製作のための資金を蓄えました。しかし、ようやく資金の目処がつき、研究を再開しようとした矢先、1903年(明治36年)、アメリカのライト兄弟が有人動力飛行に成功したというニュースが日本に報じられます。世界初の快挙を逃したことを知った忠八は、男泣きに泣き、製作中の飛行器をハンマーで破壊。飛行機の研究から一切身を引きました。その後、時代が飛行機の時代へと突入し、航空事故が多発するようになると、忠八は、事故犠牲者の慰霊こそが、飛行機開発に携わった者としての責任であると感じます。彼は、私財を投じて京都府八幡市に「飛行神社」を建立し、自ら神主となって、航空安全と犠牲者の慰霊に一生を捧げました。晩年、彼の功績は次第に評価されるようになり、1919年(大正8年)には、軍の専門家によって彼の飛行原理が「合理的な天才的考案」であることが証明されます。そして、かつて上申書を却下した長岡外史も、直接忠八のもとを訪れ、非礼を詫びました。
🎞️二宮忠八が登場する作品
二宮忠八の生涯は、ライト兄弟に先駆けた天才というロマンと、夢を挫折せざるを得なかった悲劇的な物語から、多くの作品で描かれています。
- 小説:
- 『虹の翼』(吉村昭):忠八の生涯を題材にした小説です。
- 漫画:
- 『シュマリ』(手塚治虫):北海道開拓の時代を舞台にした漫画で、主人公に人生の指針を示す人物として忠八が描かれています。
- 『日露戦争物語』(江川達也):日露戦争を題材にした漫画で、忠八の活躍が描かれています。
📍二宮忠八ゆかりの地:空への夢を辿る旅
二宮忠八の足跡は、彼の故郷である八幡浜市から、飛行原理を着想した香川、そして晩年の拠点である京都へと繋がっています。
- 二宮忠八生誕地(愛媛県八幡浜市):忠八が生まれた場所には石碑が建ち、彼の原点を今に伝えています。
- 二宮忠八飛行館・道の駅空の夢もみの木パーク(香川県仲多度郡まんのう町追上):忠八が飛行原理を着想した樅ノ木峠の近くにあり、「烏型」「玉虫型」模型飛行器の復元模型が展示されています。
- 飛行神社(京都府八幡市):忠八が航空殉難者の霊を慰めるために私財を投じて創建した神社です。自ら神主も務め、航空安全を祈願しました。
- 斐光園(ひこうえん)(愛媛県八幡浜市):忠八が故郷に想いを馳せて造った公園です。園内には彼の情熱を伝える記念碑が建っています。
- 八幡浜市民図書館(愛媛県八幡浜市):図書館内には「忠八コーナー」が設けられており、彼の功績や遺品が展示されています。

💬二宮忠八の遺産:挑戦と情熱の物語
二宮忠八の生涯は、私たちに「先見性と情熱が困難を乗り越える力となる」ことを教えてくれます。
彼は、ライト兄弟に先駆けて飛行原理を着想しましたが、軍や国に理解されず、資金難という壁に阻まれ、夢を挫折せざるを得ませんでした。しかし、彼はその挫折を乗り越え、実業家として成功を収め、晩年には飛行機の事故犠牲者の慰霊という、新たな使命を見出しました。彼の「飛行神社」は、単なる慰霊施設ではなく、空への夢を追い求めるすべての人々を支え、励ます精神的なシンボルとなりました。彼の物語は、新しい技術や発明がいかに先見的であっても、社会の理解や支援がなければ埋もれてしまう、という重要な教訓を私たちに伝えています。もし、当時の日本が彼の才能を認め、支援していたら、世界の航空史は全く違うものになっていたかもしれません。二宮忠八の生き方は、夢を追うことの尊さ、そして挫折を乗り越えて新たな使命を見出す強さを、現代に生きる私たちに力強く語りかけているのです。






