
鹿児島県の偉人:大久保利通 — 日本近代化の礎を築いた、冷徹なる独裁者
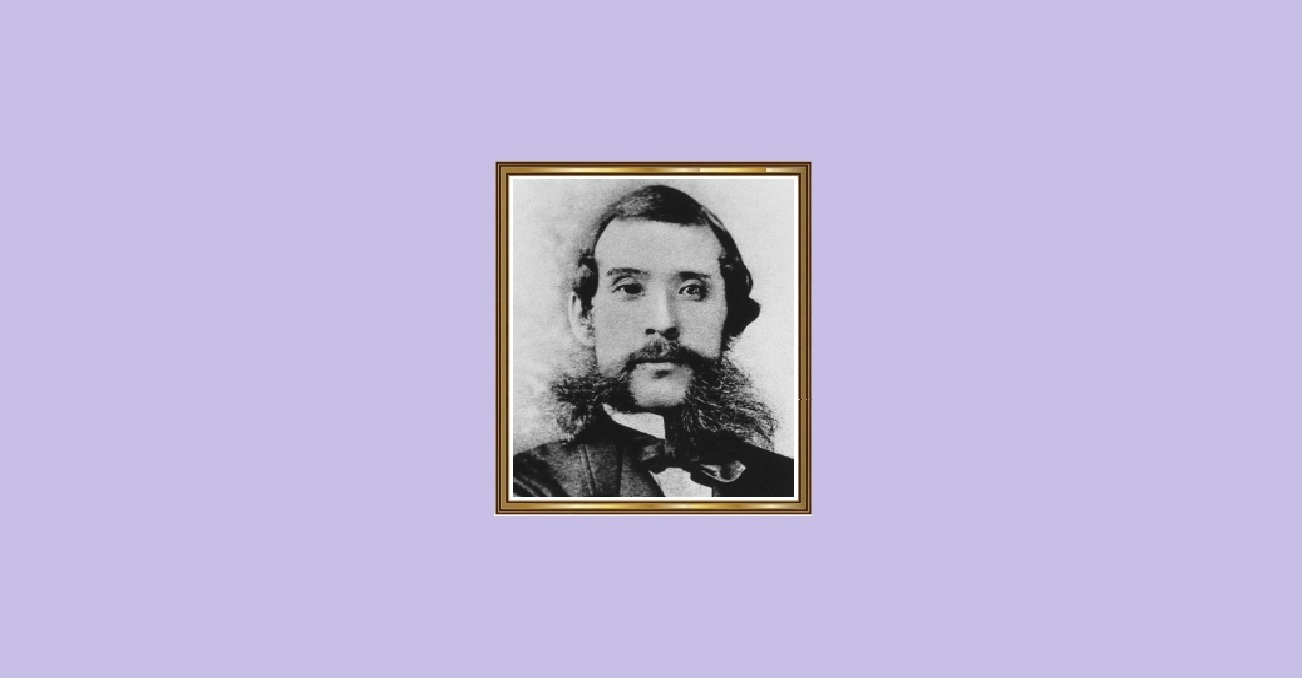
「為政清明」「堅忍不抜」
この言葉に象徴されるように、日本の近代化という壮大な国家ビジョンの実現に生涯を捧げたのが、薩摩藩の下級武士から明治政府の事実上のトップにまで上り詰めた大久保利通(おおくぼ としみち)です。同郷の親友・西郷隆盛と並んで「維新の三傑」と称された彼は、倒幕の立役者となり、維新後は独裁と批判されながらも強力なリーダーシップで近代日本の礎を築きました。しかし、その強引な手法ゆえに多くの反発を招き、志半ばで暗殺されるという悲劇的な最期を迎えます。大久保の生涯は、日本の近代化の光と影を映し出し、現代の私たちにリーダーシップと国家ビジョンのあり方を問いかけ続けています。
貧しい下級武士の少年時代と学問への没頭
大久保利通は1830年(文政13年)、薩摩藩の下級藩士の子として、鹿児島城下高麗町(現在の鹿児島市)に生まれました。幼名は正袈裟(しょうけさ)。家格は御小姓与(おこしょうぐみ)と呼ばれる下級藩士であり、裕福な家柄ではありませんでした。また、幼い頃から病弱で、長身で痩せていたことから「タケンツツボ(竹の筒)」とあだ名をつけられるなど、武術の訓練には向いていませんでした。しかし、彼はその分、勉学に没頭し、藩校「造士館」で頭角を現します。ここで、3歳年上の西郷隆盛や、後に明治政府で活躍する税所篤(さいしょ あつし)、吉井友実(よしい ともざね)らと出会い、生涯にわたる親友であり同志となりました。1850年(嘉永3年)、薩摩藩のお家騒動である「お由羅騒動」に巻き込まれ、父・利世は流罪、利通も職を罷免され謹慎処分となります。この間、一家は経済的に困窮を極めましたが、この苦難の経験が、大久保に現実を直視する冷静な視点と、藩政への強い関心を抱かせたと言われています。
久光への接近と「公武合体」路線の推進
島津斉彬(しまづ なりあきら)が藩主になると、大久保は謹慎を解かれ、藩の記録所で復職。西郷と共に、身分に関わらず才能ある若者を登用する斉彬のもとで頭角を現します。しかし、斉彬が急死すると、大久保は新たな実力者である斉彬の弟、島津久光(しまづ ひさみつ)に接近します。久光が愛好していた囲碁を通じてその信頼を得た大久保は、久光の側近に取り立てられ、31歳の若さで藩政に参与する立場となりました。この頃、西郷と並んで藩の御用取次役に抜擢された大久保は、久光が掲げる「公武合体」路線を推進するため、京都や江戸の政局に関わるようになります。しかし、幕府の権威が次第に低下していくのを目の当たりにした大久保は、公武合体の限界を悟ります。この頃、西郷隆盛も奄美大島から戻り、大久保と再会。二人は、公武合体路線から、武力による倒幕路線へと大きく舵を切ることを決意します。
倒幕への道と「維新の三傑」
大久保は、京都に潜伏していた公家の岩倉具視(いわくら ともみ)と結託し、長州藩との「薩長同盟」を成立させます。そして、1867年(慶応3年)、将軍・徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)が「大政奉還」を果たした後も、岩倉らと共に「王政復古の大号令」というクーデターを敢行し、新政府の樹立を成し遂げました。新政府では参与に任じられ、慶喜の辞官納地を主張。鳥羽・伏見の戦いに始まる戊辰戦争では、新政府軍の指揮官の一人として旧幕府軍を鎮圧し、明治新政府の礎を築きました。この功績により、大久保は西郷、木戸孝允(きど たかよし)と並び称される「維新の三傑」の一人として、その名を歴史に刻むことになります。
内務卿としての独裁と国家ビジョン
明治新政府の中枢を担うことになった大久保は、日本の近代化という壮大な国家ビジョンを掲げ、強力なリーダーシップでその実現を推し進めました。
欧米視察と「富国強兵」政策
1871年(明治4年)、大蔵卿(おおくらきょう)に就任した大久保は、岩倉具視を全権大使とする使節団の副使として、欧米各国を視察します。欧米の進んだ技術、文化、そして社会制度を目の当たりにした彼は、特にドイツの統一を成し遂げたビスマルクの国家運営に強い感銘を受けました。帰国後、彼は征韓論を唱える西郷らと対立し、明治六年政変で西郷らを失脚させると、自らが初代内務卿(ないむきょう)となり、政府の事実上のトップに君臨します。そして、「富国強兵」をスローガンに、殖産興業、地租改正、徴兵令といった近代化政策を矢継ぎ早に実行しました。彼は、海外で人気の高かった日本の生糸に着目し、官営工場として富岡製糸場を設立。殖産興業で得た資金で軍備を強化し、近代国家としての基盤を確立しました。大久保は、地方の行政制度を整備するために内務省を創設し、日本の官僚機構の基礎を築いた人物としても知られています。
士族反乱の鎮圧と台湾出兵
しかし、彼の強引な手法は多くの反発を招きました。特に、武士の特権を奪われた不平士族の反乱が各地で頻発します。1874年(明治7年)の佐賀の乱では、自ら鎮台兵を率いて鎮圧にあたり、首謀者の江藤新平(えとう しんぺい)らを厳しく処罰しました。また、台湾での琉球漁民殺害事件をきっかけに台湾出兵が行われると、大久保は清国との交渉に全権弁理大臣として臨み、清国に賠償金を支払わせることで、外交問題を有利に解決しました。そして、1877年(明治10年)、最後の反乱である西南戦争が勃発。大久保は、かつての親友である西郷が率いる旧士族軍と戦うことになり、新政府軍の総指揮を執ってこれを制圧。西郷を自刃に追い込みました。
大久保利通の人間性と評価
大久保は、寡黙で厳格な性格で、冷徹な独裁者として恐れられましたが、その内面には、国を思う強い情熱と、人間味あふれる一面も持ち合わせていました。
私財を投じた公正無私な仕事ぶり
彼は、金銭に潔白で、私財を蓄えることをせず、むしろ国家予算が不足する公共事業には、私財を投じてまで尽力しました。その結果、彼の死後には8,000円もの借金が残り、所有財産もすべて抵当に入っていたと言われています。また、出身藩に関わらず有能な人材を登用し、不正をはたらいた者に対しては、たとえ親しい者であっても容赦なく切り捨てるなど、公正無私な姿勢を貫きました。家庭では、子煩悩な優しい父親でした。仕事の忙しさから家族と夕食を摂ることもままなりませんでしたが、土曜日は必ず家族や妹たちを呼んで夕食を共にするなど、家庭を大切にする一面も持ち合わせていました。
時代を先行したビジョンと悲劇的な最期
大久保の政治家としてのビジョンは、時代を大きく先行していました。彼は、日本の近代化は30年を要すると考え、明治維新後の10年間を「創業の時期」、次の10年間を「建設の時期」、そしてその後の10年間を「後進に譲る発展の時期」という明確なロードマップを描いていました。そして、その建設の時期の真っただ中であった1878年(明治11年)5月14日、大久保は馬車で皇居へ向かう途中、東京・紀尾井坂付近で、西郷を敬愛する6人の不平士族に襲われ、49歳で暗殺されました。この事件は「紀尾井坂の変」と呼ばれ、ロンドンタイムズは「大久保利通氏の死は日本国の不幸である」と報じました。彼の死後、日本の政治の主導権は、彼が育成した伊藤博文や大隈重信へと引き継がれ、日本はさらに近代化の道を歩んでいきます。もし大久保が、自らが描いたロードマップ通りに生きて、帝国憲法の発布に関わっていたとしたら、その後の日本の歴史は、大きく変わっていたかもしれません。彼の独裁的な政治手法は、議会制民主主義とは相容れないものでしたが、彼がいなければ、明治初期の混乱を乗り越え、近代日本の礎を築くことは困難であったと考える歴史家も少なくありません。
📍大久保利通ゆかりの地:近代化の足跡を辿る旅
大久保利通の足跡は、彼の故郷である鹿児島から、政治の拠点となった京都、そして最期の地である東京へと繋がっています。
- 大久保利通生誕地(鹿児島市加治屋町):西郷隆盛の生誕地も近く、維新の英傑たちが生まれ育った場所です。
- 維新ふるさと館(鹿児島市加治屋町):大久保や西郷をはじめ、幕末から明治維新にかけて活躍した薩摩藩の偉人たちを紹介する資料館です。
- 大久保利通銅像(鹿児島市西千石町):没後100年を記念して建立された銅像で、馬車夫と馬の像も彫られています。
- 大久保利通旧邸跡(京都市上京区):京都での政治活動の拠点となった邸宅跡を示す石碑が建っています。
- 大久保利通哀悼碑(東京都千代田区清水谷公園):暗殺された場所に建つ石碑で、彼の功績を称えています。
- 大久保利通墓所(東京都港区青山霊園):彼の遺骨が眠る墓所です。
- 大久保神社(福島県郡山市):安積疏水計画を推進した大久保を水神として祀る神社です。
💬大久保利通の遺産:現代社会へのメッセージ
大久保利通の生涯は、私たちに「明確なビジョンと実行力」の重要性を教えてくれます。彼は、日本の将来を見据え、内政の整備と富国強兵という目標を掲げ、独裁と批判されながらもそれを断行しました。彼の政治手法は、現代の民主主義とは相容れないものでしたが、その根底にあったのは、私利私欲ではなく、国家の未来を案じる強い使命感でした。彼の「情を排した」政治は、多くの悲劇を生みましたが、それがなければ、日本の近代化は大きく遅れていたかもしれません。
©【歴史キング】






