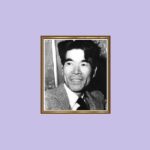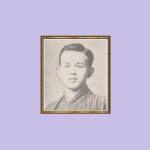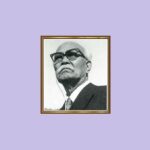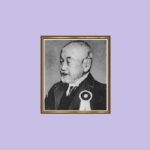
「民衆運動の父」│父と呼ばれた日本人

明治の義人――田中正造
明治時代初期に現在の栃木県と群馬県の間を流れる渡良瀬川(わたらせがわ)周辺で起きた足尾銅山鉱毒事件は、日本で最初の公害問題といわれています。この問題を提起し、生涯をかけてこれと闘ったのが、「明治の義人」田中正造(しょうぞう・1841~1913)です。1841一八四一年(天保12)、下野(しもつけ)国安蘇(あそ)郡小中村(現栃木県佐野市)の名主家に生まれた正造は、17歳で家を継ぎますが、不正を働く領主の退陣を求めて投獄されます。解放された1869年(明治2)、正造29歳のこの年、政府は版籍奉還を行い、時代は変貌期を迎えていました。縁あって江刺(えさし)県(現岩手県)庁附属補に採用された正造は、農民が困窮する状態をつぶさに調査し、彼の提案を受け入れた県はただちに1800人分の救援米を支給したといいます。ところが、またも試練が待ち受けていました。正造の直接の上司が殺害される事件が起き、殺人容疑の罪で逮捕されてしまうのです。1874年(明治7)、嫌疑は晴れますが、獄中生活は2年10カ月にも及びました。郷里に戻った正造は、38歳で政治の道を志します。その際、実父から、正造の政治家としての道を暗示するような狂歌を贈られたといいます。
「死んでから仏になるはいらぬこと、生きているうちよき人となれ」
明治10年代、自由民権運動が全国に広まるなか、正造は郷里の区会議員に選ばれます。民権運動の推進力となっていた新聞紙の創刊が全国各地で相次ぐなか、栃木でも栃木新聞が再刊され(第二次栃木新聞。現下野新聞)、編集長に就任した正造は国会開設の急務を説くかたわら、栃木県議会の指導者になっていきます。この時期、強引な土木工事を進めて「土木県令」「鬼県令」と呼ばれた福島県令の三島通庸(みしまみちつね)が栃木県令を兼任することになり、栃木市から宇都宮市への県庁移転を強行して官庁の建設や道路開削などが推し進められました。民権派が多数を占める県議会は三島の暴政に対抗し、正造は政府に訴えます。ところが、過激派による加波山(かばさん)事件が起き、正造は事件連累者として逮捕され、67日間に及ぶ三度目の獄中生活を送ります。民衆の立場に立って熱弁をふるう正造には、主要都市に置かれた鎮台(軍隊)にちなみ、「栃鎮(とっちん)」(栃木の鎮台)の渾名がつけられます。この異名から、正造がいかに精力的な活動を行っていたかをうかがい知ることができます。
栃木県議会議長を経て、1890年(明治23)の第一回総選挙で衆議院議員に当選し、活躍の舞台を国政に移すと、1891年(明治24)の第二回帝国議会で、農作物や魚に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を初めて取り上げ、政府や銅山側の責任を厳しく追及します。渡良瀬川沿いの人々を救うための闘いを続ける正造が提出した質問書は、300人の議員から提出された全質問書の一割強に当たる35件に及び、国政での奮闘によって、「たなしょう」の渾名で一躍名物代議士となります。当時、内村鑑三は、政界の暴れん坊として「押し通る」の異名を持つ星亨(ほしとおる)を引き合いに「一の田中は一〇〇の星に勝ります」と語ったほどで、黎明期の帝国議会で、正造の存在感がいかに大きかったかを物語っています。正造の追及により、政府は銅山側に一定の責任を認め、また、新聞各紙は徐々に被害地の惨状を報道したため、世論をつくり出すことに成功します。ところが1900年(明治33)2月13日、現地農民と警官隊が群馬の川俣村(現群馬県邑楽(おうら)郡明和町(めいわまち))で衝突し、農民多数が逮捕される川俣事件が発生。事件直後、正造は国会で事件に関する質問を行いました。これが、「亡国に至るを知らざれば、これすなわち亡国の儀につき質問書」で日本の憲政史上に残る大演説といわれるものです。しかし、時の首相・山県有朋の答弁は、「質問の旨、趣その要領を得ず、よって答弁せず」というものでした。以後、国の政策に、まったく改善は見られませんでした。それにもめげず、正造は国会での奮闘、各地での遊説に明け暮れますが、過労のため入退院を繰り返すようになります。すでに還暦を迎え、心身共に疲れ果てた彼は、1901年(明治34)10月、議員を辞職して11年間の代議士生活に終わりを告げました。
世論を揺り動かした正造の決死の行動
その二カ月後、正造は、足尾銅山鉱毒問題を解決するために数カ月前から準備してきた秘策を実行に移しました。当時、死刑を免れないといわれていた、明治天皇への直訴という手段に訴えたのです。もとより死を覚悟してのことでしょう。幸徳秋水(こうとくしゅうすい)執筆による直訴状を手にした正造は、第一六回議会開院式を終えて皇居に帰る途中の明治天皇が乗る馬車に近づき、取り押さえられます。1901年(明治34)12月10日午前11時20分、現在の東京都千代田区霞ヶ関一丁目の西幸門前交差点がその舞台でした。

🟣田中正造(1841~1913)│「民衆運動の父」
直訴は失敗したものの、新聞各紙が大々的に報道したことで、事件と直訴状の内容は広く知れ渡りました。足尾銅山鉱毒問題解決のために一気に世論を揺り動かすという、正造の目論見は的中したのです。世論を無視できなくなった政府は、翌年、鉱毒調査委員会を設置し、谷中村(現栃木県栃木市)に貯水池を設けて渡良瀬川の治水を図るという計画を立てます。それは、鉱毒問題の根本的解決には程遠いものでした。直訴による死刑を免れ、足尾銅山停止に向けてさらなる闘志を燃やす正造は、悲痛な思いで谷中村に住み、追いつめられた村を救うため、農民と共に鉱業停止と谷中村復活に取り組むなか、1913年(大正2)9月4日に73年の生涯を閉じました。結局、谷中村は廃村に追い込まれ、その跡地は渡良瀬遊水地に姿を変えました。足尾銅山鉱毒事件で、銅山を運営していた古河鉱業が加害の事実を正式に認め調停が成立したのは、正造の死から61年後のことでした。急激な近代化政策の一方で、大きな犠牲を払った一連の事件は、近代日本における公害問題の原点といわれます。正造の生家跡のある栃木県佐野市周辺の渡良瀬川流域には、記念館・博物館・資料館、記念碑、墓所など正造を偲ぶことができる場所が数多く存在しますが、壽徳寺(じゅとくじ・栃木県足利市野田町)にある正造翁顕徳碑には、「環境汚染公害対策国際運動之祖、渡良瀬川鉱毒災害民衆運動之父」と刻まれています。みずからの利益を顧みず、生涯不当な権力と闘い続け、近代日本の公害問題に挑んだ生涯でした。
労働組合運動の父――高野房太郎と片山潜
足尾銅山鉱毒事件の背景には、西洋列強に対抗するための殖産興業政策がありました。外貨を稼ぐ輸出品として殖産興業の柱となっていたのが銅です。なかでも足尾銅山は、1877年(明治10)に古河市兵衛(ふるかわいちべえ)が経営に着手して以来、富鉱脈の発見や生産技術の近代化によって生産量が急増し、20世紀初頭には日本の銅産出量の4分の1を担う大鉱山に成長しました。ところが、急激な鉱山開発により鉱滓(こうさい)が洪水で渡良瀬川に流出して農地を汚染、農業に大きな被害を及ぼし、下流域の住民を苦しめることになるのです。維新後の急速な工業化は、公害問題のみならず、労働者の生活を犠牲にするという問題も引き起こしました。1899年(明32)に横山源之助がまとめた『日本之下層社会』では、当時の社会のひずみが鋭く指摘されています。こうした社会情勢のなか、「労働組合期成会」を立ち上げ、1897年(明30)12月1日に日本最初の近代的労働組合「鉄工組合」を正式に発足させたのが、日本における労働組合運動の先駆者といわれる高野房太郎(ふさたろう・1868~1904)と片山潜(せん・1859~1933)です。
🟣高野房太郎(1868~1904)│「労働組合運動の父」
🟣片山潜(1859~1933)│「労働組合運動の父」
長崎に生まれ、東京・横浜で育った高野は、1886年(明治19)に実業家を目指して渡米し、働きながら英語と経済学を学びます。当時のアメリカでは労働運動が活発化しており、高野も1891年(明治24)に在米日本人の仲間たちと職工義友会を創立します。1894年(明治27)、アメリカ労働総同盟(AFL)会長のサミュエル・ゴンパースは、高野の熱意と才能に感銘を受け、彼をAFLの日本担当オルグに任命します。労働組合を日本に定着させるという志を持つ高野は、1896年(明治29)に帰国して職工義友会を再建すると、同年4月に日本最初の労働運動の宣伝パンフレット『職工諸君に寄す』を執筆刊行し、労働組合の結成を呼びかけました。同年6月には、職工義友会主催の労働問題演説会を大成功させ、7月に労働組合運動の宣伝啓蒙団体「労働組合期成会」を結成、さらに鉄工・機械工を組織して「鉄工組合」を結成します。高野は名刺の裏に、「労働は神聖なり、結合は勢力なり、神聖の労働に従う人にして勢力の結合を作らんか、天下また何者かこれに衝あたる者あらんや。我が日本の職工諸君の為すべきこと、ただそれ結合を為すにあるのみ、組合を設くるにあるのみ」というスローガンを刷り込んでいました。これは、労働運動の原点としての彼の志をよく表しています。一方、美作(みまさか)国久米南条郡羽出木村(現岡山県久米郡久米南町)に生まれた片山は、岡山師範学校(現岡山大学)に入学するも、向学心に燃え上京して働きながら漢学塾などに学びます。ところが、「アメリカは貧乏でも勉強のできるところ」と聞き、旅費のカンパと借金で1884年(明治17)に渡米しました。皿洗いなどをしながら苦学した足かけ13年、グリンネル大学で文学修士、エール大学で神学士の資格を得て、1896年(明治29)に帰国します。ほぼ同時期にアメリカに滞在していた片山も労働問題や社会問題に目覚めますが、彼の場合はアメリカでキリスト教に入信しており、帰国後はキリスト教社会主義の立場から社会運動の実践に入ります。1897年(明治30)3月、東京神田にセツルメント・キングスレー館を開設して社会改良運動をスタートさせた片山は、高野らの初期労働組合運動にも参加して、その先駆者として活躍。日本最初の本格的な労働運動機関紙である『労働世界』(労働組合期成会発行)の編集長として、労働者の権利意識の向上に尽くしました。しかし、労働組合を日本に定着させるという高野の労働組合主義と、労働組合期成会内部で政治運動化・社会主義化への傾斜を深めつつあった片山の考えは、徐々に対立していきます。その後、高野は引退して中国青島(チンタオ)で没しますが、片山は社会主義の指導者へと活躍の場を変えていきます。異なる道を歩んだ二人ですが、日本の労働運動黎明期において、片山抜きに高野を語れず、また高野抜きに片山を語れないほど、二人が中心的指導者であったことは間違いなく、このことから、両人共に「労働組合運動の父」と称されています。ただし、これについて、歴史教科書も含め多くの文献は、労働組合期成会の創設者として高野と片山の名を併記するものの、「労働組合期成会の創立者として第一に名を挙げなければならないのは、組織の構想者で、実践者であった高野房太郎です」(二村一夫『労働は神聖なり、結合は勢力なり―高野房太郎とその時代』岩波書店)というように、二人を対等に位置づけることはできないとしています。確かに、日本人が「労働組合」という言葉さえ知らなかった時代にいち早くその意義を理解して日本にこれを定着させるべく労働組合をゼロからつくり上げた高野の先駆者としての評価は不動のものといえるでしょう。一方、片山は、指導者としての影響力を持つに至ったとはいえ、労働組合期成会発足時までの活動については高野の一協力者にすぎなかったというのが真相のようです。若くして没し回想録を残さなかった高野に対し、片山は『自伝』(改造社)を残し、運動衰退後も発行を続けた『労働世界』などの豊富な資料があったことから、片山の評価が実際以上に高くなった面はあるでしょう。また、軍国主義の反省と称した戦後の左傾化の波のなかで、社会主義に反対する立場をとった高野に対し、片山は社会主義運動の先駆者としてコミンテルン(共産主義の国際組織)の指導者になったことも影響しているでしょう。さらに言えば、学術研究者が政治的立場による偏見を持たなかったとしても、みずからの専門外の研究においては過去の文献の影響を受けるということもあります。だとしても、片山が「労働組合運動の父」にふさわしい人物であることは事実です。なぜなら、本連載第一回で述べたように、先駆者たちが「父」と呼ばれる理由は、おのおのが活躍した分野で抜群の功績を挙げたことのほか、大きな志、日本人としての気概を持ち、彼らが属した地域や組織でかかわりを持った人々が、それらの「偉業と志を後世の人々に語り継がなければならない」という強烈な思いを持つからです。偏見にとらわれない歴史的事実の精査が必要な一方で、それだけが先駆者としての立場を確定させるものではありません。いかなる政治的背景があろうとも、後世に語り継ぐべきであるという人々の想いがある限り、「父」なる称号は存在意義があるのです。高野と片山に関する学術研究と「父」なる称号の関係は、このことを如実に表しています。
「大正デモクラシー」の理論的指導者、吉野作造
労働組合運動は、鉄工組合の財政悪化などで次第に衰退し、1900年(明治33)に治安警察法が制定されストライキが違法行為と定められると弾圧を受け、労働組合期成会は解散に追い込まれます。厳しい状況のなか、片山と共に資本の公有、軍備全廃、普通選挙実施、貴族院廃止などの主張を掲げた日本最初の社会主義政党「社会民主党」を結成したのが、キリスト教的人道主義者の安部磯雄(いそお・1865~1949)です。

🟣安部磯雄(1865~1949)│「日本社会主義の父」
片山と安部は、日露戦争真っ最中の1904年(明治37)には、オランダのアムステルダムで行われた第二インターナショナル第6回大会に日本代表として出席し、壇上でロシア代表と日露戦争反対の握手をしたことで国際的に注目され、共に「日本社会主義の父」と称されました。ちなみに安部は、早稲田大学で教鞭を執り、野球部を創設して早慶戦の端緒を開いたことから、「学生野球の父」という称号も与えられています。
🟣堺利彦(1870~1933)│「日本社会主義運動の父」
片山と安部が、日本の労働組合運動の指導者として「日本社会主義の父」と呼ばれたのに対し、「日本社会主義運動の父」と称されたのが、堺利彦(1870~1933)です。豊前(ぶぜん)国仲津郡(現福岡県京都郡みやこ町)出身の堺は、『萬朝報(よろずちょうほう)』の記者として社会改良を主張する論説や言文一致体の普及を図る一方で、社会正義を求めて1901年(明治34)に萬朝報社主・黒岩涙香(るいこう)、内村鑑三、幸徳秋水らと「理想団」を結成します。日露戦争の折、社会主義の立場から非戦論を主張しますが、『萬朝報』が主戦論に転換したため、堺は幸徳と共に退社して平民社を創立。週刊『平民新聞』を発刊して反戦運動を展開します。以来、明治、大正、昭和にわたり、社会主義運動の発展に力を注いだ堺は、マルクス思想をいち早く日本に紹介してことで知られています。その晩年に、無産政党運動で行動を共にした鈴木茂三郎(もさぶろう、後に日本社会党委員長)は、次のように堺を評しています。「堺利彦は、日本における社会主義運動の父である。なかには片山潜や安部磯雄とならべようとする人もあるであろうが、人の社会における『父』が一人であるように、社会主義運動の日本における『父』は一人の堺利彦であろう」(『中央公論』昭和40年6月号)日露戦争後、大正時代末年までの間、政治・社会・外交・文化の各方面で、明治憲法体制に対抗する自由獲得運動が勢いを増します。いわゆる「大正デモクラシー」です。具体的には、普通選挙制度や言論・集会・結社の自由を求める運動、困窮した国民への負担が大きい海外派兵の停止を求めた運動、社会面では男女平等、部落差別解放運動、団結権・ストライキ権などの獲得運動、また自由教育の獲得、大学の自治権獲得運動など、さまざまな方面からの運動が展開されました。その理論的指導者として知られるのが、「民本主義」を唱えた政治学者、吉野作造(1878~1933)です。

🟣吉野作造(1878~1933)│「日本民主主義の父」
宮城県志田郡大柿村(現宮城県大崎市古川)に生まれ、第二高等学校(現東北大学)を経て東京帝国大学法科大学政治学科を首席で卒業した吉野は、『中央公論』にキリスト教ヒューマニズムの立場から政治論文を発表し、そのなかで普通選挙の実施や貴族院の改革を伴う「民本主義」を唱えます。「民本主義」とは、Democracyの訳語で、国民全体の幸福を中心に考える政治、つまり、民衆を政治の根本に置くことです。天皇主権の明治憲法下で、主権在民(民主主義)を主張することはできませんが、吉野は「Democracyが世界の大勢である」と論じ、これを最大限追求するため、字義を整理・展開して「民本主義」という訳語を使ったのです。普通選挙のうえに成立する政党内閣制を主張し、大正デモクラシーの機運を盛り上げた吉野は「日本民主主義の父」と称されています。
「世界の三大偉人」とも称される、社会運動家・賀川豊彦
🟣中村太八郎(1868~1935)│「普選の父」「土地国有論の父」
大正デモクラシー自体は、明治憲法体制を一新できませんでしたが、1925年(大正14)、いわゆる普選(普通選挙)法が実施されるという大きな成果を生みました。これを推進し、「普選の父」と称されるのが、中村太八郎(たはちろう・1868~1935)です。信濃国筑摩郡大池村(現長野県東筑摩郡山形村)の豪農の家に生まれた中村は、自由民権運動の影響下に育ち、上京して法律などを学びます。帰郷後は、地価修正運動、中山道鉄道誘致運動、米穀取引所設置運動など地域の繁栄のための運動に尽力し、日清戦争後は、社会問題に鋭い関心を示し、1897年(明治30)7月、全国に先駆けて松本で木下尚江(なおえ)らと普通選挙期成同盟会を設立します。生涯のほとんどを普選運動に捧げた中村は、職業を聞かれると、「職業は普通選挙だ」と答えていたといいます。県議会選挙での恐喝取財の容疑で1年10カ月の獄中生活を強いられたりしましたが、出獄後すぐに貴族院・衆議院への普選請願書を提出したり、雑誌『普通選挙』を発行したりと、普選運動の先頭に立って活動します。中村らが普選運動を旗揚げして28年後の1925年(大正14)3月29日、普通選挙法案が衆議院、貴族院で可決成立します。同年5月5日に公布され、その翌日付の報知新聞は「三〇年の久しきにわたり、終始一貫献身的努力を普選の達成に捧げたる中村太八郎氏の功労を閑却してはならぬ」と報道しています。中村はまた、土地国有論者としても有名で、土地国有講究会を組織してこの問題に取り組んだことから、「土地国有論の父」とも呼ばれています。これに関連して、わが国では日露戦争の頃から、地主の土地所有が強大となり、小作地面積は全国総耕地の45%を超え、地主による圧迫と小作料の重圧により小作人は窮乏を極めます。さらに、第一次世界大戦後の1920年(大正9)に勃発した経済恐慌をきっかけに農民の生活が悪化するなか、日本で初めて全国組織としての小作人組合「日本農民組合」が設立されます。
🟣杉山元治郎(1885~1964)│「農民の父」
地主層との闘いの前面に立って組織的な農民運動を確立した先駆者が、この組織の設立者の一人で、「農民の父」と呼ばれた杉山元治郎(もとじろう)(1885~1964)です。大阪府日根郡下瓦屋村(現大阪府泉佐野市)に生まれた杉山は、16歳でキリスト教に入信し、伝道の道を歩むかたわらで農業にも従事し、多くの農民と接するうちに小作争議への関心を強めていきました。日本農民組合の委員長として小作争議を指導していた杉山は、無産政党結成の機運が高まるなか、1926年(大正15)に結成された労働農民党の初代執行委員長に就任します。1932年(昭和7)には第18回衆議院議員総選挙に全国労農大衆党公認で出馬して当選。以後、戦前・戦後を通じ九回の当選を果たしました。
🟣賀川豊彦(1888~1960)│「協同組合運動の父」「生協の父」
杉山と共に日本農民組合を設立した賀川豊彦(かがわとよひこ・1888~1960)は、農民運動はもとより、多くの社会運動を指導し、友愛・互助・平和の精神を唱え続けた不屈の伝道師として知られています。賀川は、結核などを病み、苦しみながら、当時の日本最大のスラム(貧民街)の一つ、神戸のスラムに住み込み、救済活動を続けた「貧民街の聖者」として世界的に知られています。海外布教は13回を数え、世界連邦建設運動の提唱など世界的に活動の幅を広げ、ノーベル平和賞候補にもなりました。評論家の大宅壮一氏は、賀川を「近代日本のナンバーワン」と評し、また、アメリカでは、「世界の三大偉人」として「賀川、ガンジー、シュバイツァー」を挙げる書籍があるほどです。賀川が指導した社会運動のなかで最も成功したといわれるのが、後の生協・農協・医療生協などへつながる協同組合運動です。相互扶助の精神による消費者のための消費協同組合、生産者のための生産協同組合を目指し、1920年(大正9)に神戸購買組合を創設、「一人が万人のため、万人が一人のため」の標語をつくり、その後も現在の生協(COOP)・大学生協・JA共済に結びつく数々の生活協同組合を立ち上げたことから、「協同組合運動の父」「生協の父」と称されています。賀川の社会運動を支えたのは著述業の収入でした。貧民街での救済事業、労働組合運動、農民組合運動などの体験に基づく自伝的小説『死線を越えて』(1920年・上巻)、『太陽を射るもの』(1921年・中巻)、『壁の声きく時』(1924年・下巻)の三部作は、累計400万部を売り上げ、大正期最大のベストセラーとなりました。大正デモクラシー期は、労働者の地位向上や福祉の増進を目指す運動が盛んに行われ、さまざまな団体が組織され社会的関心を呼び起こしました。
🟣鈴木文治(1885~1946)│「日本労働運動の父」
🟣豊原又男(1872~1947)│「わが国職業紹介事業の父」
🟣蒲生俊文(1883~1966)│「安全の父」「労災防止の父」
吉野や賀川のほかにも、現在の連合に繋がる労働運動の源流をつくった「日本労働運動の父」鈴木文治(ぶんじ・1885~1946)、職業紹介事業の基礎をつくった「わが国職業紹介事業の父」こと豊原又男(1872~1947)、労働災害防止運動の中心的存在として活躍し「安全の父」「労災防止の父」と呼ばれた蒲生俊文(がもうとしぶみ・1883~1966)などに、各分野の草分け的存在として「父」の称号が与えられています。
📍「民衆運動の父」人の墓所
田中正造墓所(阿弥陀堂境内・栃木県佐野市小中町/惣宗寺〔佐野厄よけ大師〕・栃木県佐野市金井上町/田中霊祠・栃木県栃木市藤岡町藤岡/寿徳寺・栃木県足利市野田町/雲龍寺・群馬県館林市下早川田町/北川辺西小学校敷地内・埼玉県加須市麦倉)
*正造の遺骨は生前ゆかりのあった六カ所に分骨された。
高野房太郎墓所(吉祥寺・東京都文京区本駒込)
片山潜墓所(赤の広場「クレムリンの壁」・ロシア/青山霊園・東京都港区南青山)
安部磯雄墓所(雑司ケ谷霊園・東京都豊島区南池袋)
堺利彦墓所(総持寺・神奈川県横浜市鶴見区鶴見)
吉野作造墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
中村太八郎墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
杉山元治郎墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
賀川豊彦墓所(多磨霊園・東京都府中市多磨町)
鈴木文治墓所(不明)
豊原又男墓所(金谷山宝祥寺・東京都新宿区若松町)
蒲生俊文墓所(不明)