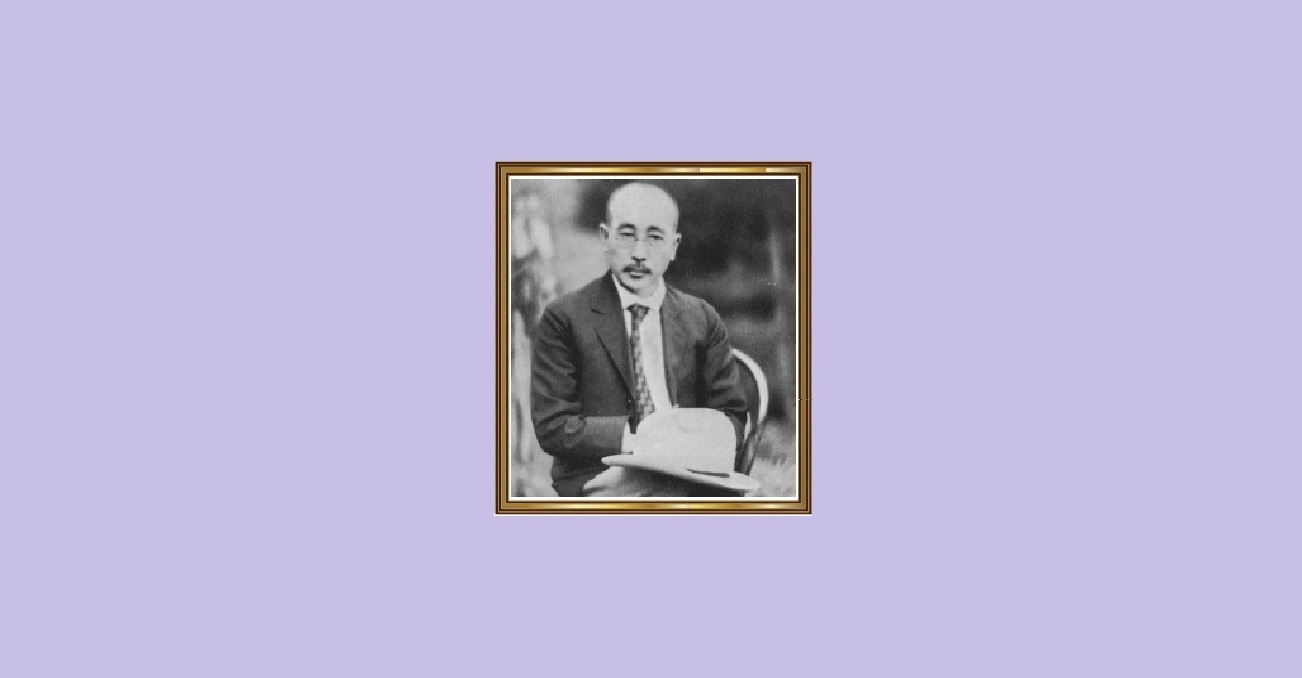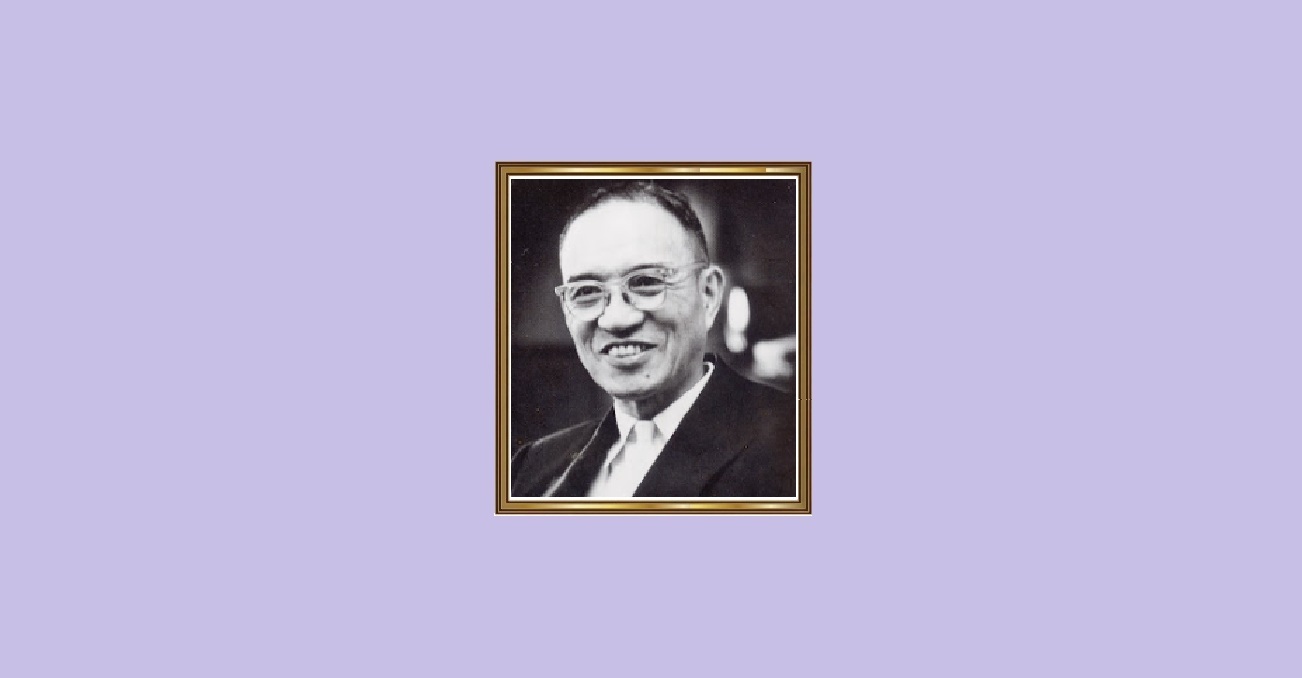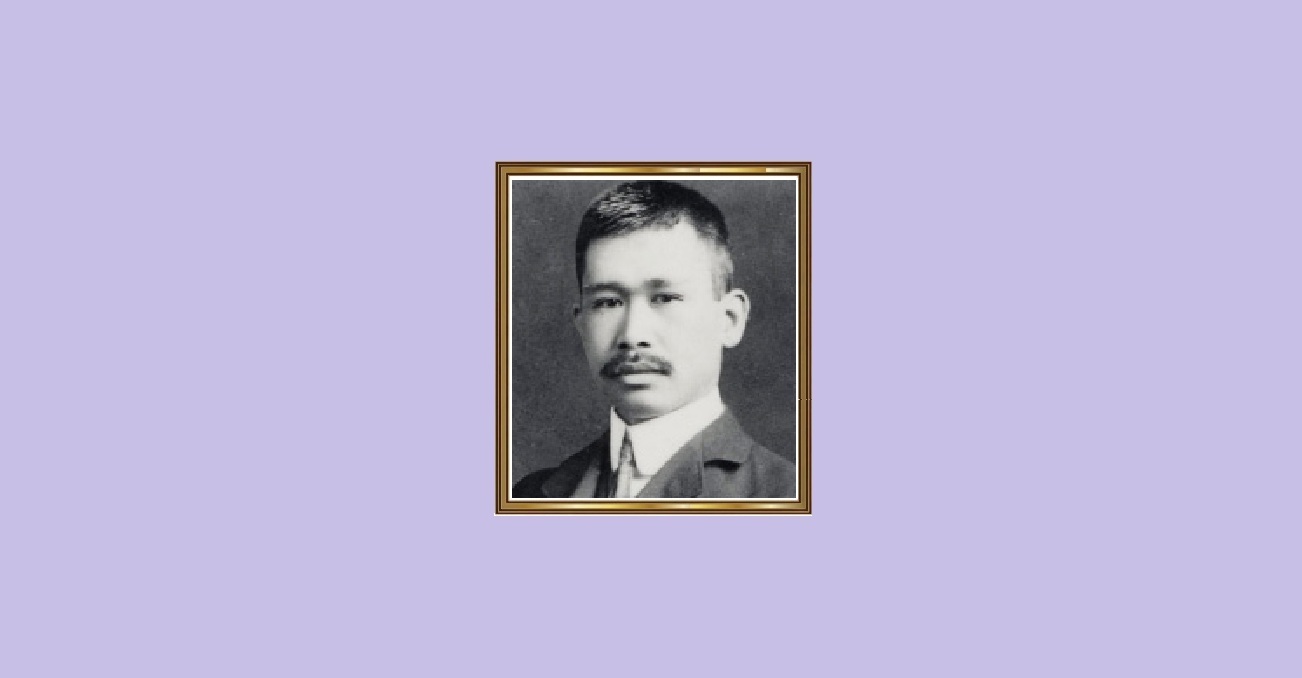和歌山県の偉人:南方熊楠 — 「日本人の可能性の極限」を体現した、知と情熱の巨人
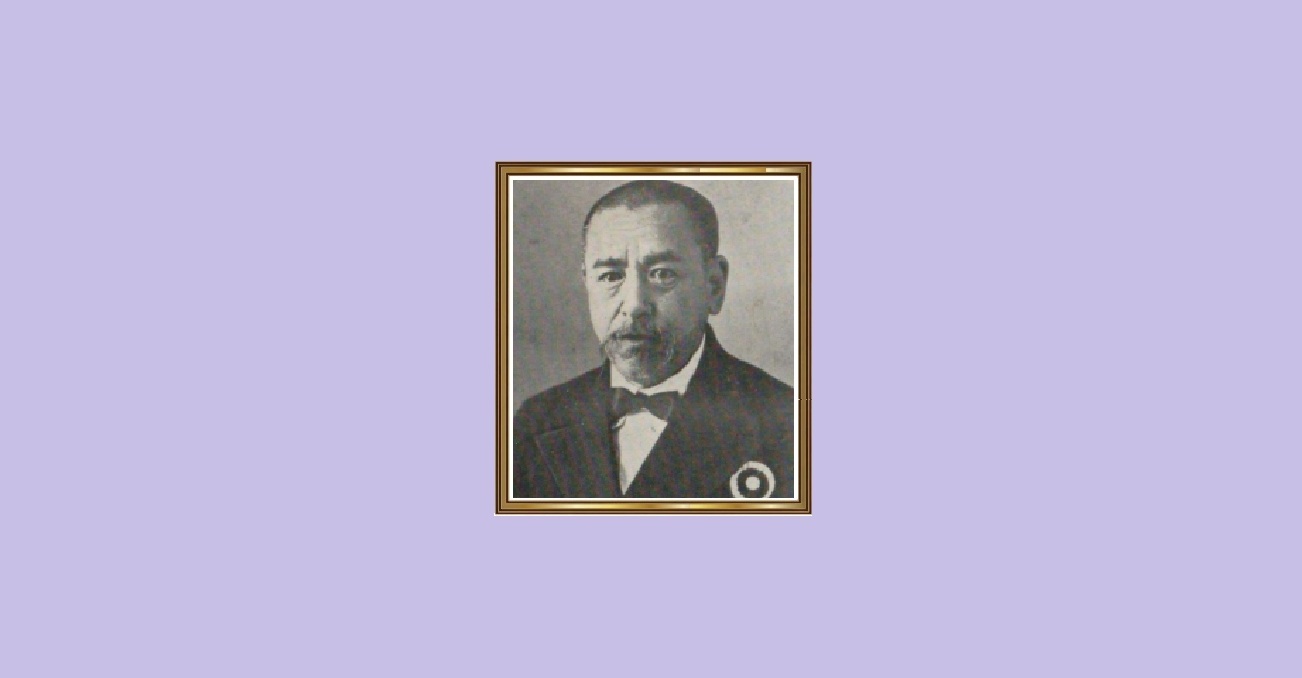

和歌山県
「雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ」
この御歌は、昭和天皇が熊楠の死後、彼が愛した和歌山の地を訪れた際に詠まれたものです。和歌山市橋丁に生まれた世界的博物学者、南方熊楠(みなかた くまぐす)は、その生涯を「森羅万象」(宇宙に存在する一切のもの)の解明に捧げ、「知の巨人」と呼ばれました。東京大学予備門を中退し、アメリカ、イギリスで15年におよぶ研究生活を送り、科学雑誌『ネイチャー』に日本人最多の論文を寄稿。帰国後は故郷・和歌山を拠点に、粘菌の研究や自然保護運動に尽力しました。彼が追い求めた学問は、民俗学、生物学、宗教学など多岐にわたり、柳田國男をして「日本人の可能性の極限」と言わしめたのです。
幼少期の神童から「和漢三才図会」の筆写魔へ
南方熊楠は1867年(慶応3年)、和歌山城下町の橋丁で、金物商「雑賀屋」を営む豪商の次男として生まれました。幼い頃から体が弱かったため、海南市にある藤白神社の信仰に基づき、大楠の「楠」と熊野の「熊」の二文字を名として授けられました。彼の学問への探究心は、幼少期から並外れていました。生家には商品の鍋や釜を包むために使われた反故紙が山と積まれており、熊楠はそれに書かれた文字や絵を貪るように読んでいました。学校に通う前から大抵の漢字の音訓を諳んじていたという彼は、小学校入学後、近所の産婦人科医の家で初めて『和漢三才図会』を目にし、その膨大な知識の世界に魅了されます。12歳までにこの大百科事典を筆写し始めた彼は、その後『本草綱目』『諸国名所図会』など、100冊を超える書籍を記憶しながら筆写するという、常人離れした学習方法を身につけました。この「筆写」という行為が、彼の驚異的な記憶力を培い、生涯にわたる学問スタイルの基礎を築いたのです。
学生生活の挫折とアメリカへの旅立ち
1883年(明治16年)、和歌山中学校を卒業した熊楠は、東京大学予備門(のちの旧制第一高等学校)に入学。同窓生には、夏目漱石や正岡子規といった後の文豪たちがいました。しかし、熊楠は大学の画一的な教育に馴染めず、興味のない科目には全く目を向けませんでした。学業そっちのけで菌類の採集や遺跡発掘に明け暮れ、学期末試験で苦手な代数に落第すると、あっさりと退学を決意します。「一度だけの命を賭けるのは馬鹿馬鹿しい」と大学教育に見切りをつけた彼は、自由な学問を求めて、海外留学を決心します。当時、莫大な費用がかかる留学に、父は当初反対していましたが、熊楠の熱意に理解を示し、その留学を後押ししました。1886年(明治19年)、熊楠は横浜港を出航し、単身アメリカへと渡ります。
大英博物館での研究と「東洋の知」
アメリカに渡った熊楠は、ミシガン、フロリダ、キューバを転々としながら、植物の採集と研究に没頭します。特に、シカゴの地衣類学者カルキンスに師事し、採集→整理記載→標本作りという、彼の研究スタイルの基礎を築きました。1892年(明治25年)、彼は、さらなる知見を求めてイギリスへ渡ります。留学中に父が亡くなり、仕送りが途絶えて窮乏した生活を送る中でも、彼は大英博物館の閲覧室に日夜通い詰め、人類学、考古学、宗教学、セクソロジーなど、あらゆる分野の書籍を読み漁りました。この大英博物館での研究生活で、熊楠は「ロンドン抜書」と呼ばれる膨大な筆写ノートを作成。このノートには、9言語に及ぶ書籍からの抜粋がびっしりと書き込まれており、熊楠の圧倒的な語学力と知識量がうかがえます。また、彼は科学雑誌『ネイチャー』に、和漢の知識を駆使した論文を多数寄稿しました。「東洋の星座」に始まり、「網の発明」「日本の発見」など、生涯で51本もの論文を掲載。これは現在に至るまで、日本人による単著での掲載本数の最高記録であり、彼の名声を確固たるものにしました。
孫文との友情と「神社の森」
ロンドンでは、亡命中の革命家・孫文と出会い、深い友情を育みました。二人は、仏教を中心とした宗教論や哲学論で熱心に語り合い、孫文は熊楠との友情の証として、筆で「海外逢知音(かいがいちおんにおう)」という言葉を書き贈っています。しかし、熊楠は、その奇抜な言動ゆえに、大英博物館の閲覧室でトラブルを起こし、追放されるという事件を起こします。この後、彼は金銭的な困窮も重なり、1900年(明治33年)、14年におよぶ海外研究生活を終え、帰国します。帰国後、熊楠は和歌山県田辺町(現在の田辺市)に居を構え、熊野の山中で粘菌や菌類の研究に没頭する傍ら、民俗学や伝説、宗教を、広範な世界の事例と比較して論じ始めます。この時期の論文は、民俗学の父・柳田國男との間で交わされた、東西の考証事例を縦横に用いた往復書簡として結実し、後の日本民俗学の誕生と発展に多大な影響を与えました。この頃、明治政府が「神社合祀令」を発令し、地域の神社を統廃合する政策を推し進めると、熊楠は、人々の心の拠りどころである神社や、そこに広がる鎮守の森が失われることを強く憂慮しました。彼は、自然保護運動の先駆者として、新聞や雑誌に反対意見を投稿し、粘菌の生態系を守るという科学的な視点から、田辺湾神島(かしま)の保護を訴え、その天然記念物指定に尽力しました。彼のこの運動が、後に世界遺産に登録される熊野の森を守る大きな力となったのです。
昭和天皇への「キャラメル箱の進講」
熊楠の生涯で最も有名なエピソードとして語り継がれているのが、1929年(昭和4年)に昭和天皇に神島で「進講(学問の講義)」を行った時のことです。生物学に深い関心を持っていた昭和天皇は、熊楠の存在を知り、紀南行幸の際に、田辺湾に停泊した戦艦「長門」の艦上へ熊楠を招きました。この時、熊楠は、最高級の桐箱ではなく、開けやすいようにとミルクキャラメルの空き箱に粘菌の標本を詰めて献上しました。この奇抜な行動に、周囲は驚きましたが、昭和天皇は熊楠の並外れた知識と、学問への情熱に感銘を受け、予定時間を延長して熱心に耳を傾けられました。熊楠の死後、昭和天皇は再び南紀を訪れた際に、熊楠との一期一会を懐かしみ、「雨にけふる神島を見て 紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ」という歌を詠まれました。これは、天皇が民間人を詠んだ最初の歌であり、彼の功績を称える御製碑(ぎょせいひ)は、現在、南方熊楠記念館の庭に立っています。
南方熊楠ゆかりの地:知の巨人の足跡を辿る旅
南方熊楠の足跡は、彼の故郷である和歌山市から、研究の拠点となった田辺市、そして彼が守ろうとした熊野の森へと繋がっています。
- 南方熊楠生誕地(和歌山市橋丁):熊楠が生まれた場所には胸像が建っています。
- 南方熊楠顕彰館・南方熊楠旧邸(和歌山県田辺市):熊楠が晩年の半生を過ごした旧邸宅が国の登録有形文化財として保存されており、隣接する顕彰館では、彼の膨大な遺品や著作を展示しています。
- 南方熊楠記念館(和歌山県西牟婁郡白浜町):昭和天皇の御製碑が建つ番所山にあり、熊楠の功績を称える資料を展示しています。
- 闘雞(とうけい)神社(和歌山県田辺市):熊野三山の別宮であり、熊楠の妻・松枝の生家でもあります。熊楠は境内の森を「熊野植物研究の中心基礎点」と定めました。
- 高山寺(和歌山県田辺市):熊楠の墓所がある真言宗の古刹です。
- 神島(和歌山県田辺市):熊楠が自然保護に尽力し、昭和天皇に進講を行った場所です。
南方熊楠の遺産:現代社会へのメッセージ
南方熊楠の生涯は、私たちに「知の探求に終わりはない」ということを教えてくれます。彼は、既存の学問体系や社会の枠組みにとらわれることなく、ひたすら自身の好奇心と情熱に従って、森羅万象の真理を追い求めました。彼の思想の核心である「南方マンダラ」は、科学と哲学、宗教といった異なる分野が、一つの真理へと繋がっているという、現代の学際研究にも通じる視点を与えてくれます。また、彼の「エコロジー」の思想は、環境問題が深刻化する現代社会において、人間と自然が共生するためのヒントを与えてくれるでしょう。熊楠の物語は、奇行と天才性が同居する彼の人間的な魅力とともに、一人の人間が、その情熱と知性によって、時代を動かし、人々の心に深い影響を与え続けることができることを証明しています。彼の遺した膨大な知の財産は、現代に生きる私たちに、自らの心の奥底にある「なぜ?」を追い求める勇気と、未知の世界へ踏み出す情熱を、力強く語りかけているのです。