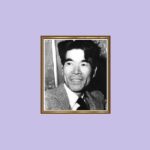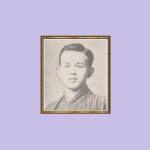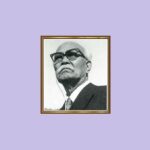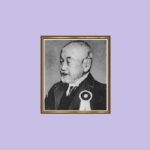
鳥取県の偉人:原勝 — 「砂丘はわが心の友」、鳥取砂丘を緑に変えた情熱の林学者
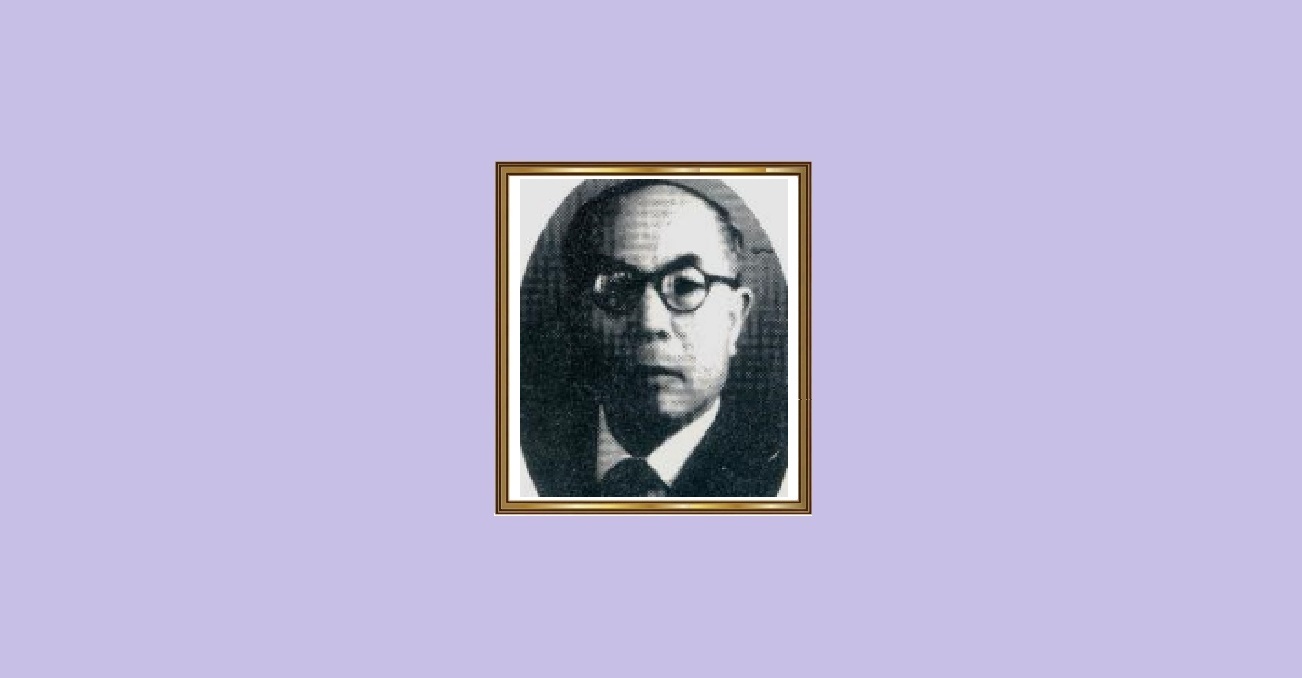

鳥取県│岐阜県
「砂丘はわが心の友」
この言葉は、鳥取砂丘の緑化と砂防の研究に生涯を捧げた林学者、原勝(はら まさる)の情熱と、砂丘への深い愛情を表しています。1895年(明治28年)に岐阜県に生まれた彼は、北海道大学農学部を卒業後、鳥取高等農業学校(現・鳥取大学農学部)の唯一の林学教官として鳥取の地に招かれました。当時、不毛の地と見なされていた鳥取砂丘を、彼の科学的な研究と不屈の精神が、豊かな緑の森へと変え、その功績は、鳥取県だけでなく、日本の砂丘地農業に多大な影響を与えました。
知の巨人:砂丘を愛し、砂丘に挑んだ林学者
原が鳥取の地に降り立った大正12年(1923年)、鳥取砂丘は、風によって砂が移動し、農地や家屋を埋没させるという、人々にとって深刻な脅威でした。しかし、彼はこの「不毛の地」を、研究者としての探求心を掻き立てる「心の友」と捉え、その緑化と砂防の研究に生涯を捧げることを決意しました。
文献なき研究への挑戦
原勝がまず直面したのは、研究文献の圧倒的な不足でした。当時の日本では、砂丘の科学的な研究はほとんど行われておらず、図書館にもドイツ語の原書が2冊あるだけという状況でした。彼は、この困難な状況を嘆くのではなく、自らの足で研究の道を切り開くことを選びます。
- 文献収集の旅: 彼は、東京や京都の大学や研究機関を訪ね、文献を持っている学者を探して借り受け、知識を貪欲に吸収しました。また、アメリカからは植物生態学の専門雑誌を取り寄せ、世界の最先端の研究動向を学びました。
- 私財を投じた現場主義: 研究費や機材、人手も不足する中で、原勝は私財を投じて研究を続けました。彼は、書斎にこもるだけでなく、県内各地の砂丘地を丹念に歩き回り、砂の動きや植物の生態を徹底的に調査。砂の性質を把握し、砂を防ぐ方法を研究するという、基礎から始める地道な努力を続けました。
論文「砂丘造林に関する研究」と林学博士の学位
8年におよぶ基礎研究を経て、1931年(昭和6年)に研究が一段落すると、翌1932年、彼はその成果をまとめた論文「砂丘造林に関する研究」で、林学博士の学位を受けました。この論文は、それまで経験と勘に頼っていた砂丘の緑化を、科学的な根拠に基づいた体系的な手法へと高めたものであり、彼の偉大な功績の第一歩となりました。
実用化への情熱:砂丘を緑に変えた改革者
博士号を取得した後も、原勝の砂丘造林への情熱は衰えることはありませんでした。彼は、砂丘地の農業を可能にするために、さらなる研究と実用化に取り組みます。
植林と砂防垣の実用化
- 品種改良と混交林: 砂丘地でも育つフランス海岸松や黒松の植林を推進。さらに、地力増進のために落葉広葉樹を混合して植林する方法を考案し、砂丘地の生態系をより豊かにすることを目指しました。
- 砂防垣の発明: 砂の移動を防ぐための「砂防垣(さぼうがき)」を考案し、その実用化に成功。これにより、植林した苗木を砂の埋没から守ることができるようになり、砂丘造林の成功率を飛躍的に向上させました。
これらの研究が土台となり、鳥取県内の砂丘造林は急速に進展。不毛の地であった鳥取砂丘は、緑豊かな森へと姿を変え、人々の生活と農業の基盤を安定させました。
全国への貢献と後世への遺産
原勝の研究は、鳥取県だけでなく、戦後の全国各地の砂丘造林を進める上でも、貴重な指針となりました。彼の研究は、砂丘地の農業への道を拓き、人々の暮らしを豊かにすることに貢献しました。彼の功績を称える記念碑が、鳥取砂丘の一角に建てられており、そこには「砂丘はわが心の友」という彼の言葉が刻まれています。これは、彼が砂丘を単なる研究対象ではなく、人生をかけて向き合った「友」と見なしていたことを物語っています。
原勝ゆかりの地:砂丘の歴史を辿る旅
- 原勝の言葉が刻まれた石碑(鳥取砂丘内):彼の砂丘への深い思いを伝える言葉が刻まれた記念碑です。
原勝の遺産:現代社会へのメッセージ
原勝の生涯は、私たちに「困難な課題に挑む情熱」と「基礎研究の重要性」を教えてくれます。彼は、誰も見向きもしなかった不毛の地を、独自の視点と地道な努力で研究し、その解決策を見出しました。彼の「砂丘はわが心の友」という言葉は、私たちに、目の前の困難を敵と見なすのではなく、真摯に向き合うことで、新たな可能性が開けることを教えてくれます。また、彼の研究は、鳥取県だけでなく、全国の砂丘地の緑化に貢献したように、基礎研究の成果が、社会全体に大きな恩恵をもたらすことを証明しています。原勝の物語は、一人の研究者が、その情熱と知性によって、地域の、そして日本の未来を創ることができることを示しています。彼の功績は、現代に生きる私たちに、地道な努力と、困難に立ち向かう勇気を、力強く語りかけているのです。