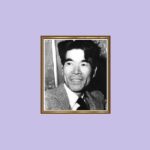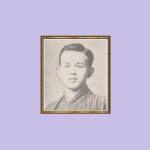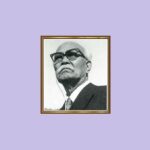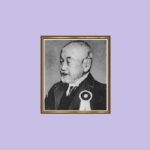
岩手県の偉人:原敬 — 爵位を固辞し、民衆の負託に応えた「平民宰相」
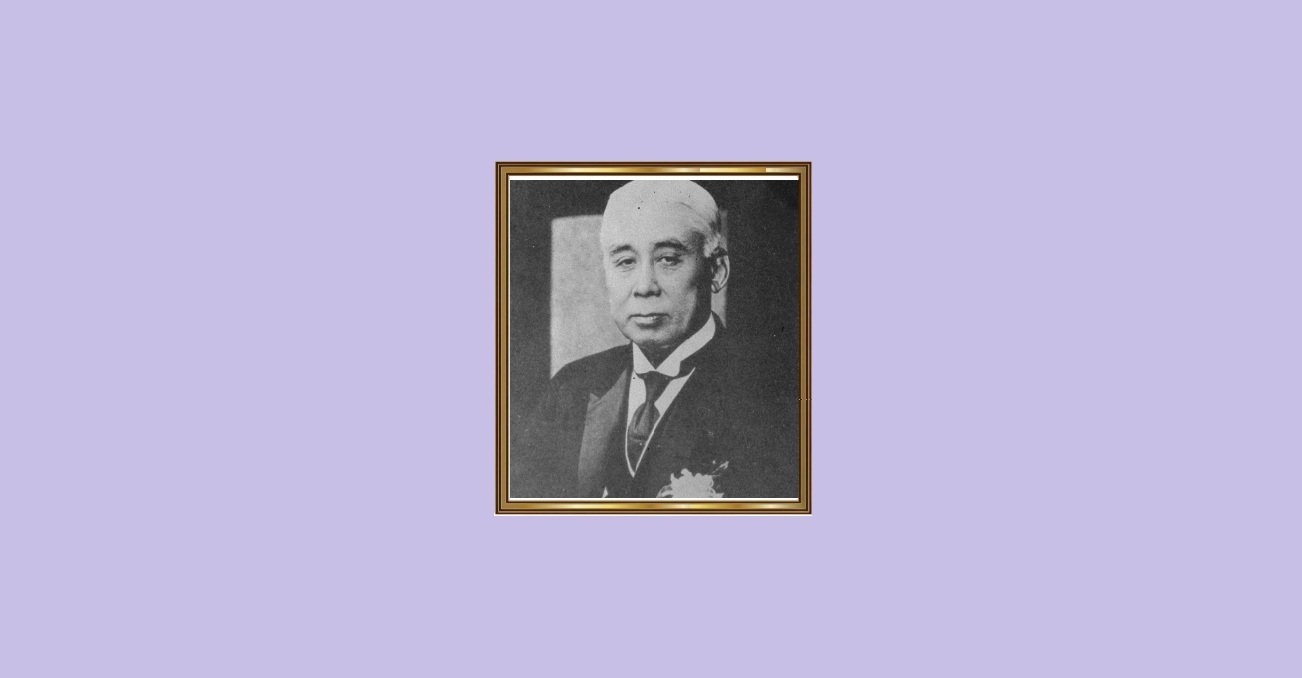

岩手県
「戊辰戦役は政見の異同のみ」
(戊辰戦争は、政治に対する考え方が違っていただけで、天皇に反抗したのではない)
この言葉は、第19代内閣総理大臣原敬(はら たかし)が、戊辰戦争の敗戦によって朝敵とされた故郷の盛岡藩士たちの名誉回復を願って語ったものです。岩手郡本宮村(現在の岩手県盛岡市)に生まれた彼は、爵位を固辞し、衆議院議員として初めて内閣総理大臣の座に就いたことから、「平民宰相」と称えられました。藩閥政治が支配する時代にあって、卓越した政治手腕で本格的な政党内閣を組織。しかし、志半ばで凶刃に倒れるという悲劇的な最期を迎えます。彼の生涯は、日本の近代化と民主化の歩みを象徴するものであり、現代の私たちに真のリーダーシップとは何かを問いかけ続けています。
貧しい下級武士の少年時代と学問への没頭
原敬、幼名・健次郎は1856年(安政3年)、盛岡藩士の上級武士の家に生まれました。祖父は家老、父は側用人を務める家柄であり、彼は裕福な環境で育ちました。しかし、9歳で父を亡くし、12歳の時に戊辰戦争で旧幕府軍に属した盛岡藩が敗北したことで、家は没落。家禄を10分の1に減らされ、生活は一気に困窮します。母・リツは、家財を売り払い、苦しい生活の中で子供たちの教育に尽力しました。「私利を求めず、正直かつ勤勉で、大局を見て行動する」という原の行動理念は、この母の教えから学んだと言って過言ではありません。原は、苦学の末、司法省法学校に104名中2番という優秀な成績で合格します。しかし、寄宿舎の待遇改善を求めた行動がもとで退学処分となり、その後は新聞記者として活躍。郵便報知新聞社、大阪毎日新聞社などで筆を執り、福沢諭吉系の言論人として、漸進的な民権拡張を求める論陣を張りました。外務省に入省後は、天津領事やパリ公使館書記官を務め、国際法やフランス語、欧州の国際政治を学び、外交官としての能力を開花させます。特に、日清戦争後の不平等条約改正に尽力した陸奥宗光(むつ むねみつ)にその才能を見出され、外務次官にまで昇進しました。
「政友会」での台頭と「平民宰相」の誕生
官界を退いた原は、1900年(明治33年)、伊藤博文が結成した「立憲政友会」に幹事長として入党します。藩閥の出身者が政治を牛耳る時代にあって、彼は爵位を固辞し、平民として衆議院議員選挙に出馬。盛岡市を地盤として初当選を果たし、以降8回連続当選を重ねるという、異例の出世を遂げました。彼の政治家としての才能が最も発揮されたのが、第1次西園寺公望(さいおんじ きんもち)内閣の内務大臣時代です。彼は、藩閥の牙城であった内務省の人事を刷新し、藩閥以外の若手官僚を積極的に登用。郡制の廃止を主張するなど、藩閥勢力の基盤を切り崩すための大胆な改革を断行しました。大正7年(1918年)、米騒動で寺内正毅(てらうち まさたけ)内閣が総辞職すると、元老・山県有朋(やまがた ありとも)や西園寺公望の推薦により、原のもとに内閣総理大臣就任の大命が下ります。爵位を持たず、衆議院議員から首相になった彼は、国民から親しみを込めて「平民宰相」と呼ばれ、日本で初めての本格的な政党内閣を組織しました。
原内閣の政策:国民の生活向上と民主化
原内閣の政策は、外交における対英米協調主義と、内政における積極政策をその特徴とします。
- 外交: 第1次世界大戦後の国際情勢を的確に捉え、対外的な強硬路線を改め、国際協調外交を展開しました。特に、アメリカとの協調を重視し、日英同盟の強化を図るなど、ブレない外交姿勢を貫きました。
- 内政: 「四大政綱」と呼ばれる「教育の改善」「交通機関の整備」「産業の振興」「国防の充実」を掲げ、強力なリーダーシップのもとで推進しました。特に、地方の鉄道建設に熱心で、公債を発行してまで鉄道網の整備を進め、地方の経済発展に大きく貢献しました。
- 民主化: 選挙権の納税資格を大幅に引き下げ、有権者の数を拡大しました。また、文官の任用制度を改正し、官僚派の拠点であった郡制を廃止するなど、反政党勢力の基盤を切り崩し、政党政治の確立に尽力しました。
悲劇的な最期と後世への遺産
原内閣は、教育改革やインフラ整備といった多くの功績を残しましたが、その強引な政治手法は、旧来の藩閥勢力や、普選運動を求める改革派双方からの批判を招きました。大正10年(1921年)11月4日、大阪での関西政友会大会に出席するため、東京駅に向かっていた原は、駅構内で国鉄大塚駅職員中岡艮一に刺殺されました。65歳の生涯でした。彼の死は、多くの人々に衝撃を与え、彼の死後、強力なリーダーを失った政党政治はまとまりを欠き、やがて軍部の台頭を許すことになります。
原敬ゆかりの地:平民宰相の足跡を辿る旅
原敬の足跡は、彼の故郷である盛岡から、政治の拠点となった東京へと繋がっています。
- 原敬記念館(岩手県盛岡市本宮):原敬の生家跡に建てられた記念館で、彼の遺品や日記など、貴重な資料を展示しています。
- 原敬墓所(岩手県盛岡市大慈寺):彼の遺言により、大慈寺に妻・浅と共に静かに眠っています。
- 原敬先生像(岩手県盛岡市岩手県公会堂前):彼の没後30年を記念して建立された銅像です。
- 盛岡城跡公園(岩手県盛岡市):原が、地元の発展のために南部家と交渉し、市民の憩いの場として整備させた公園です。
- 原敬別邸(介寿荘)跡(岩手県盛岡市):母・リツのために建てた別邸跡地です。
- 東京駅丸の内南口(東京都千代田区):原敬が暗殺された場所に、彼を悼むプレートが埋め込まれています。
原敬の遺産:現代社会へのメッセージ
原敬の生涯は、私たちに「真の民主主義とリーダーシップ」とは何かを教えてくれます。彼は、爵位や学閥といった既得権益に頼ることなく、自らの実力と信念で政治の世界を切り拓きました。彼の政治手法は、現代の民主主義とは相容れないものでしたが、その根底にあったのは、私利私欲ではなく、国家の未来を案じる強い使命感でした。彼の築いた鉄道網や教育制度は、戦後の高度経済成長を支え、現代の日本の礎となっています。原の物語は、一人の人間が、その知性と行動力によって、閉塞した時代を打ち破り、人々の暮らしを豊かにすることができることを証明しています。彼の死は、日本の歴史の転換点となりましたが、その遺した思想と精神は、現代に生きる私たちに、より良い社会を築くための指針を与え続けているのです。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

真実の原敬 維新を超えた宰相 (講談社現代新書 2583) / 伊藤 之雄 (著)
新書 – 2020/8/19
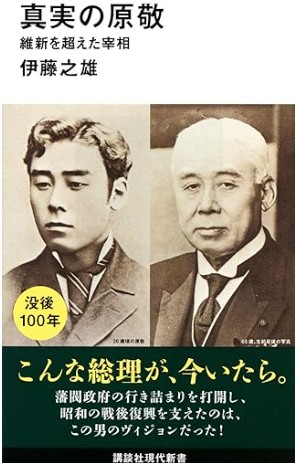
こんな総理が、今いたら!
藩閥政府の行き詰まりを打開し、昭和の戦後復興を支えたのは、この男のヴィジョンだった。
混乱の時代における政治家の役割とは何か。政治における優れたトップリーダーの資質とは何か。今まさに問われているこのテーマに、大きなヒントを与えてくれるのが、今年百回忌を迎えた「平民宰相」原敬である。厖大な史料を確かな眼で読み込み、伊藤博文や大隈重信、昭和天皇など近代日本をつくってきた人々の評伝を著して高い評価を得てきた著者は、原を「近代日本の最高のリーダーの一人」と断言する。
原は、朝敵・南部藩に生まれながら、明治新政府への恩讐を超え、維新の精神を受け継いでその完成を目指し、さらに世界大戦後のアメリカを中心とした世界秩序を予見して、日本政治の道筋を見すえていた。その広く深い人間像は、外交官、新聞記者、経営者と様々な経験と苦闘のなかで培われたものだった。志半ばで凶刃に倒れたことで、「失われた昭和史の可能性」とは何か。
著者にはすでに、選書メチエで上下巻930ページにおよぶ大著『原敬―外交と政治の理想』(2014年)があるが、その後の新史料と知見をふまえ、「今こそ改めて原の生涯と思想、真のリーダー像を知ってほしい」と書き下ろした新書版・原敬伝。