
群馬県の偉人:内村鑑三 — 「二つのJ」に生涯を捧げた、魂の独立者
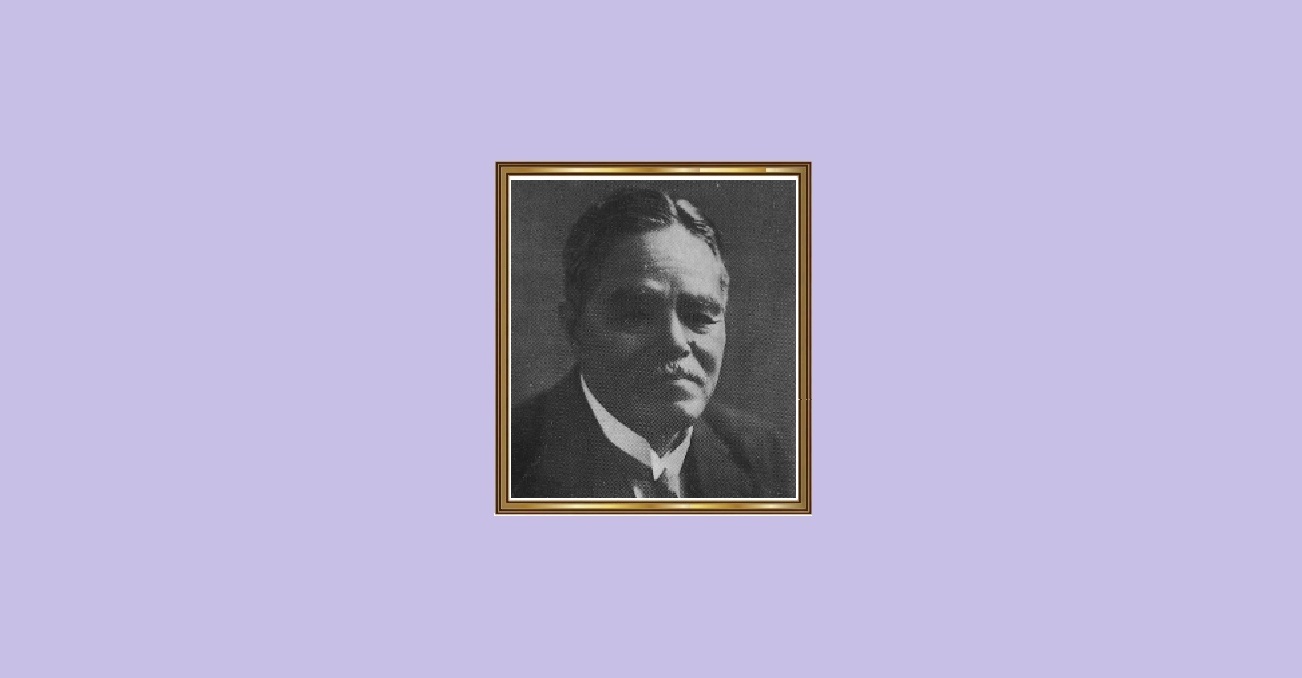
プロフィール
内村 鑑三(うちむら かんぞう)
1861(万延2)年3月23日生│1930(昭和5)年3月28日没(69歳)
「代表的日本人」
「I for Japan; Japan for the World; The World for Christ; And All for God」
この言葉は、武士の家に生まれながら、キリスト教の信仰に目覚め、生涯をかけて日本とイエス・キリストの双方に仕えた内村鑑三(うちむら かんぞう)が、その墓碑銘に刻んだものです。江戸小石川に生まれ、多感な青年期を高崎藩で過ごした彼は、札幌農学校での学びとアメリカでの回心を経て、日本独自のキリスト教思想「無教会主義」を創唱しました。日露戦争における非戦論や足尾鉱毒事件への関与など、その言動は常に時代の流れと対立し、多くの迫害と苦難を経験しました。しかし、その不屈の精神と、普遍的な愛の思想は、後の日本に深い影響を与え、今なお多くの人々の心の拠り所となっています。
幼少期の苦難と札幌農学校での回心
内村鑑三は1861年(文久元年)、高崎藩士・内村宜之(よしゆき)の長男として江戸小石川の武士長屋に生まれました。5歳の頃、父が意見の不一致で高崎に謹慎を命じられたため、一家は高崎へ移住。幼少期から父に儒学を学び、明治維新という時代の大きな転換期を多感な青年として経験しました。14歳で単身上京し、東京外国語学校に入学。ここで、後に終生の友となる新渡戸稲造(にとべ いなぞう)、宮部金吾(みやべ きんご)と出会います。そして、官費生という経済的な理由もあり、北海道開拓に携わる技術者を養成する札幌農学校に第2期生として入学しました。しかし、入学直後の彼らを待っていたのは、教頭ウィリアム・スミス・クラーク博士の感化によって、すでにキリスト教に改宗していた上級生たちでした。初めはキリスト教への改宗に強く反発していた内村でしたが、友人たちが次々と署名したことがきっかけで、ついに「イエスを信ずる者の契約」に署名し、洗礼を受けました。この回心は、彼の人生を根本から変えることになります。それまで神社や祠の前を通るたびに頭を下げていた苦労から解放されたと、内村はユーモラスに語っています。
「二つのJ」への誓いと在野の精神
内村は、札幌農学校を首席で卒業。卒業の際、彼は新渡戸、宮部と共に、自らの人生を「二つのJ」、すなわちJesus(イエス)とJapan(日本)のために捧げることを誓い合いました。卒業後、内村は開拓使御用係として水産を担当するなど、官僚の道を歩み始めます。しかし、当時の官僚組織が持つ立身出世主義と、彼の信じる福音主義信仰との間に葛藤を抱くようになり、やがて官職を辞し、自費でアメリカへ留学しました。アメリカでは、拝金主義や人種差別といったキリスト教国の現実を知って幻滅しますが、アマースト大学でJ・H・シーリー総長の感化により、真の回心を体験。これ以降、内村の思想は、イエスの教えと日本への深い愛によって、一貫して貫かれることになります。
「不敬事件」と「非戦論」:時代と戦った言論人
帰国後、第一高等中学校の教員となった内村は、1891年(明治24年)に、彼の人生を大きく変えることになる「不敬事件」を起こします。教育勅語奉読式で、最敬礼をせずに講壇を降りたことが「不敬」であると非難され、職を辞することになります。この事件により、内村は官職の道を閉ざされ、生涯を在野の言論人として生きることを決意しました。この頃から、内村は旺盛な執筆活動を開始します。キリスト教への信仰に至るまでの葛藤を綴った『余は如何にして基督信徒となりし乎』や、日本の偉人を海外に紹介した『代表的日本人』といった著作は、国内外で大きな反響を呼びました。また、新聞『万朝報(よろずちょうほう)』の英文欄主筆として、社会評論家としても名を馳せ、幸徳秋水(こうとく しゅうすい)、堺利彦(さかい としひこ)らとともに社会問題に取り組みます。特に、足尾銅山鉱毒事件では、鉱毒反対運動に深く関わり、田中正造を支えるなど、社会運動家としても活躍しました。しかし、日露戦争を機に、内村は「非戦論」を展開。幸徳、堺らが主戦論に転じると、彼らと共に『万朝報』を退社します。信仰に基づく平和主義を貫いた彼は、この非戦論によって、キリスト教界からも孤立し、さらなる苦難の道を歩むことになりました。
「無教会主義」の創唱と晩年の活動
内村は、日露戦争を機に、社会的活動から徐々に身を引き、聖書研究に内在的な関心を深めていきます。
- 無教会主義: 既存の教会組織や制度にとらわれず、信徒が直接聖書を読み、信仰を深めるという「無教会主義」を創唱。個人雑誌『聖書之研究』を創刊し、生涯をかけて聖書研究と執筆活動を続けました。
- 再臨運動: 晩年には、キリスト再臨信仰に基づく再臨運動を開始。無教会主義の同志たちと共に、北海道から岡山まで各地で講演会を開き、信仰を説きました。
彼の思想は、弟子の矢内原忠雄(やないはら ただお)らを通して、後の社会主義や教育界にも大きな影響を与えました。しかし、晩年には病に倒れ、1930年(昭和5年)、70歳でその生涯を閉じました。彼の死後も、その教えを学ぶために「天風会」などの団体が設立され、その思想は今に受け継がれています。
📍内村鑑三ゆかりの地:魂の軌跡を辿る旅
内村鑑三の足跡は、故郷の群馬県から、学びの地である北海道、そして晩年の活動拠点である東京へと繋がっています。
- 石の教会・内村鑑三記念堂(長野県軽井沢町):内村が晩年を愛した軽井沢にある教会です。彼の思想である「無教会主義」に共鳴するオーガニック建築で、信仰を持たない人も自由な祈りを捧げられる場所です。
- 多磨霊園(東京都府中市):内村鑑三の墓所です。彼の墓碑には、彼の人生哲学である「二つのJ」の言葉が刻まれています。
- 札幌農学校跡(北海道札幌市):彼が新渡戸稲造らと共に学んだ札幌農学校の跡地です。
💬内村鑑三の遺産:現代社会へのメッセージ
内村鑑三の生涯は、私たちに「信念を貫くことの尊さ」を教えてくれます。彼は、国家主義や教会組織、そして世論といった大きな流れに抗い、自らの内なる声に耳を傾け、信じる道を歩み続けました。彼の思想の核心である「無教会主義」は、組織や形式にとらわれず、個人の精神的な自立を促します。これは、現代社会において、多様な価値観が混在する中で、自分自身の心の拠り所を見つけることの大切さを示唆しているのではないでしょうか。内村鑑三の物語は、武士の子として愛国心を持ちながらも、キリスト者として平和を希求した彼の内なる葛藤と、その中で育まれた強靭な精神を伝えています。彼の遺した思想と精神は、現代に生きる私たちに、自らの魂に誠実に向き合い、真の豊かさを追求するための道標を、力強く示しているのです。
©【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

代表的日本人 (岩波文庫 青 119-3) / 内村 鑑三 (著), 鈴木 範久 (翻訳)
文庫 – 1995/7/17

内村鑑三(1861―1930)は、「代表的日本人」として西郷隆盛・上杉鷹山・二宮尊徳・中江藤樹・日蓮の五人をあげ、その生涯を叙述する。日清戦争の始まった一八九四年に書かれた本書は岡倉天心『茶の本』、新渡戸稲造『武士道』と共に、日本人が英語で日本の文化・思想を西欧社会に紹介した代表的な著作である。読みやすい新訳。

日本の偉人たちを紹介している名著「代表的日本人」の著書が内村鑑三さんですが、当サイトからすれば、内村鑑三さん!あなたも偉人です✨️






