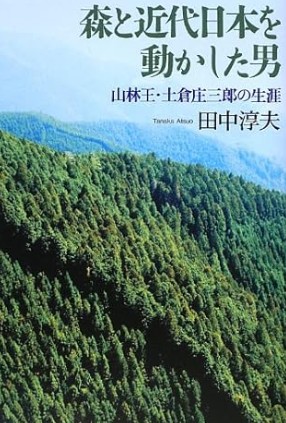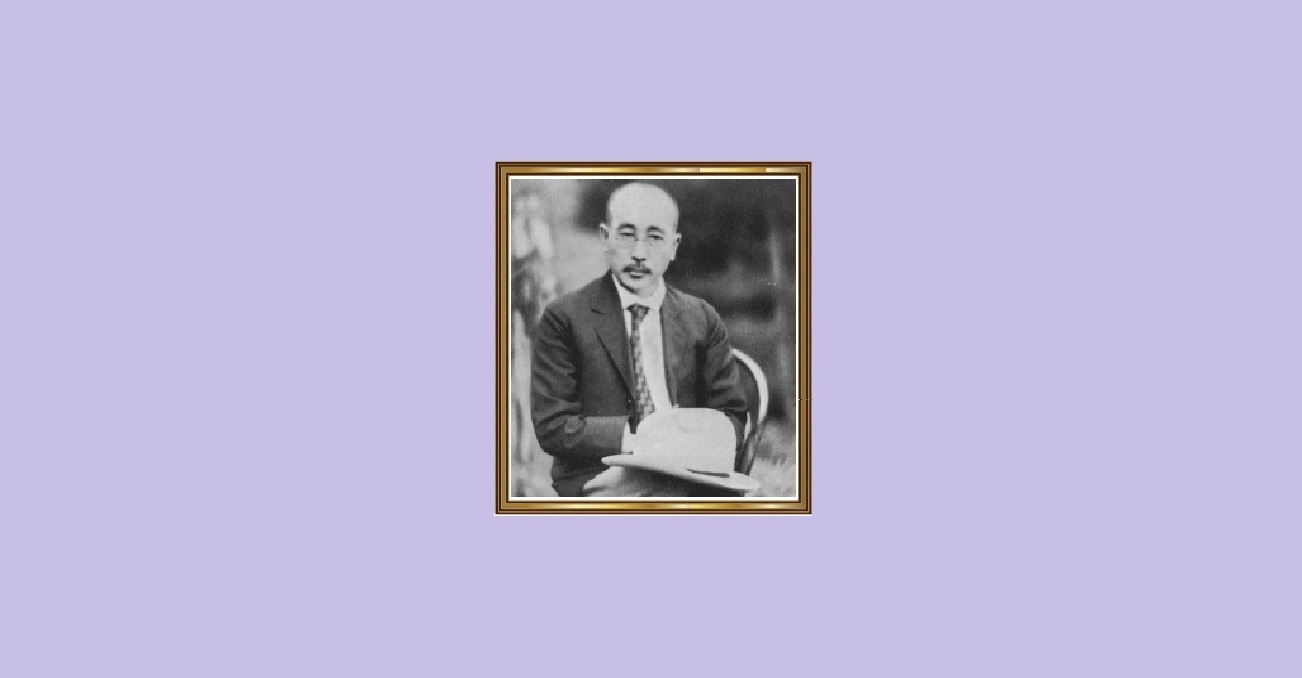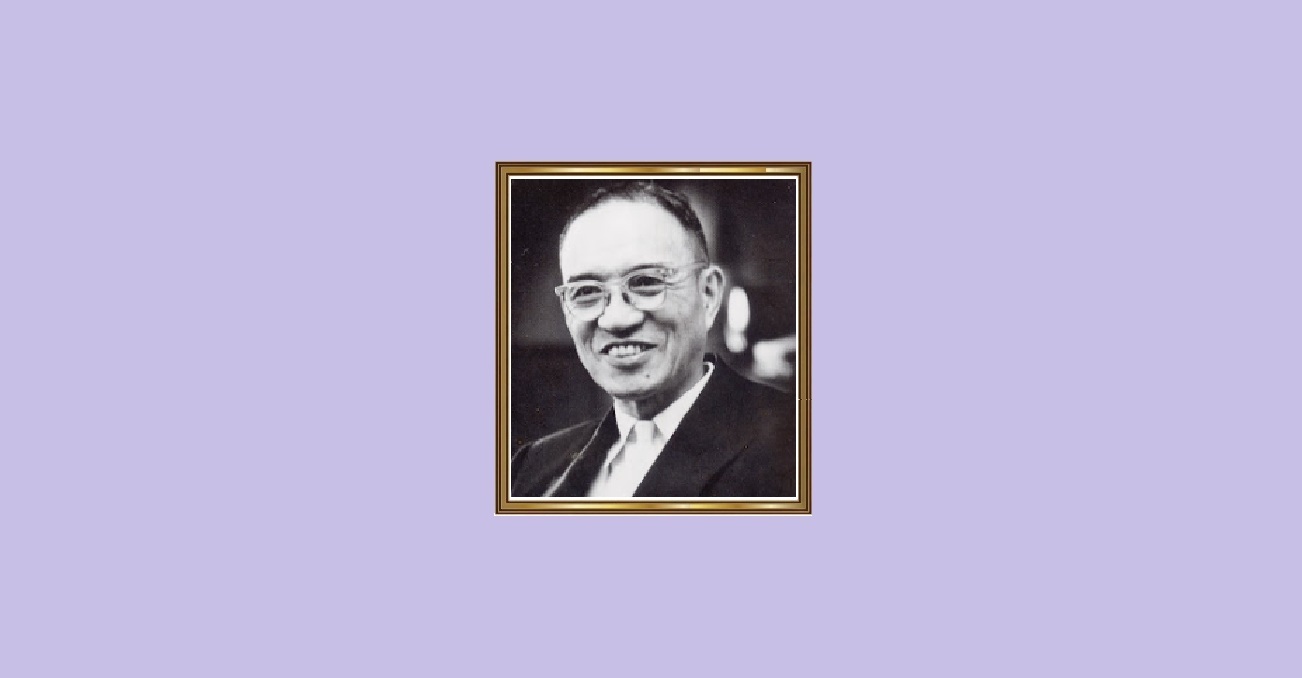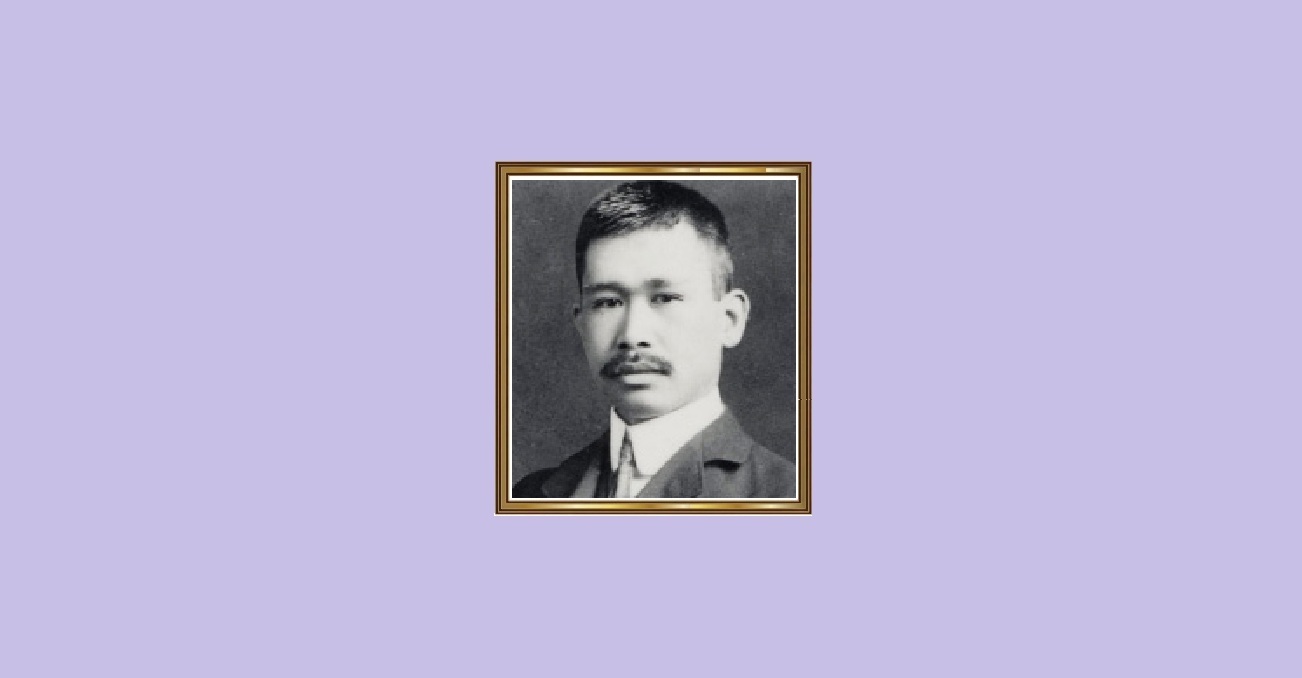奈良県の偉人:土倉庄三郎 — 「吉野美林」を築き、日本の近代政治を支えた「造林王」
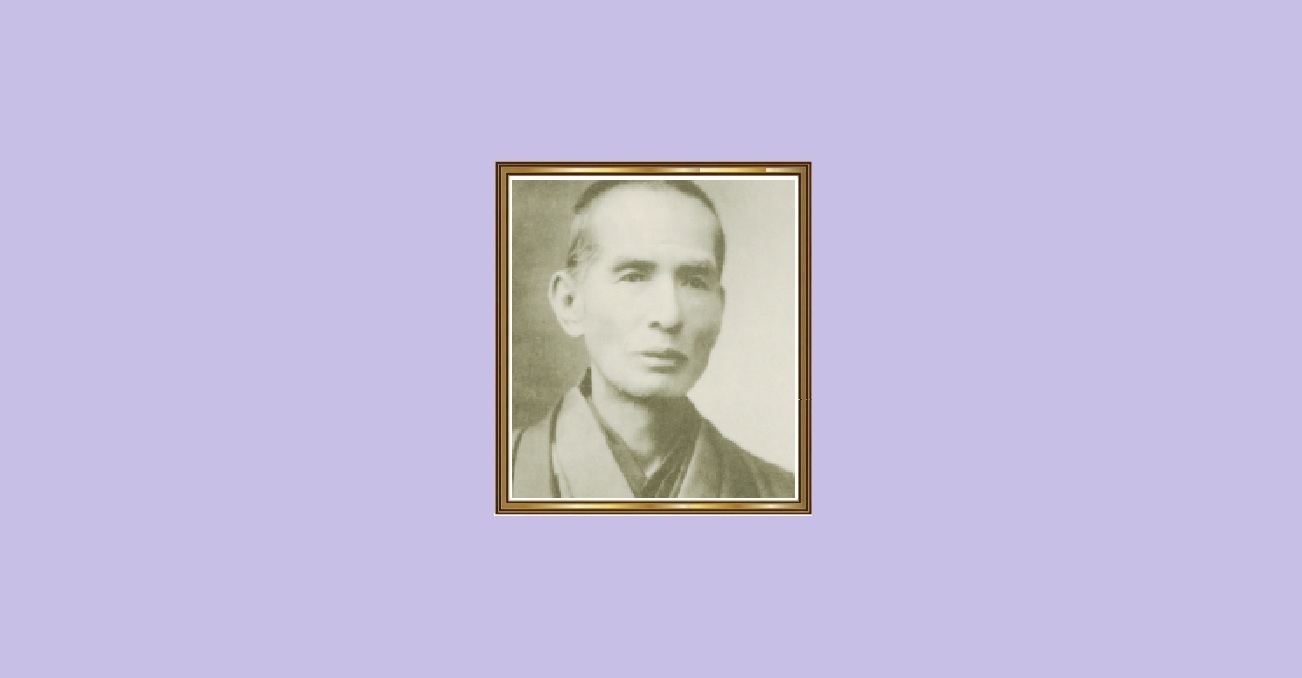

奈良県
「青山二十分の一」
この言葉は、自らが所有する山林の評価額の20分の1を、私財として道路建設に投じることを意味します。江戸時代末期から明治にかけての山林王、土倉庄三郎(どぐら しょうざぶろう)が、私利私欲を超えて公共の利益を追求した、その壮大な信念を表しています。吉野郡大滝村(現在の奈良県吉野郡川上村)に生まれた彼は、「吉野林業の中興の祖」として、伝統の技術に科学的な工夫を加え、日本三大美林の一つである吉野杉のブランドを確立しました。その功績は林業に留まらず、板垣退助の自由民権運動や同志社大学の設立を資金面で支え、まさに「林業と政治の父」として、近代日本の礎を築きました。
幼少期の聡明さと、林業への使命感
土倉庄三郎は、1840年(天保11年)、吉野郡大滝村(現在の川上村)の山林地主の家に生まれました。父・庄右衛門も山林経営に長けた人物であり、庄三郎は幼い頃から吉野の豊かな自然と林業技術に囲まれて育ちました。16歳で家督を継ぐと、彼はすぐに頭角を現し、吉野材木方の総代に就任します。これは、吉野林業地で最も多くの材を搬出する川上村から選出される習わしであり、若くして地域の林業の指導者としての実権を握ったことを意味します。庄三郎の人生のテーマは、山林から材木を効率的に運び出し、良質な木材を生産することでした。
「青山二十分の一」とインフラ整備
彼がまず取り組んだのは、林業発展の最大の課題であった「運搬」の改善でした。山深い吉野の奥地から材木を市場に送り出すため、庄三郎は私財を投じて壮大なインフラ整備に乗り出します。
- 吉野川の改修: 筏(いかだ)流しの水路を整備するため、吉野川の浚渫工事(しゅんせつこうじ)や川幅の拡幅工事を行いました。この水路整備は、後の吉野林業の発展に不可欠な基盤となりました。
- 東熊野街道の整備: 川上村から上北山村に通じる「東熊野街道」(現在の国道169号の原型)の建設を計画。その資金調達のため、沿道の山林地主たちに「青山二十分の一」という献金を呼びかけ、自らも莫大な私財を投入して道路を完成させました。
庄三郎は、林業の要は運搬にあると熟知しており、これらのインフラ整備を、地域の利益と自身の事業を直結させるための最優先事項として捉えていました。
土倉式造林法と「林業興国」の実現
庄三郎は、伝統的な吉野林業の技術に満足せず、科学的な考究を重ねて独自の造林法を確立しました。これが「土倉式造林法」です。
密植と高品質化の技術
従来の造林技術では密植は避けるべきとされていましたが、土倉式造林法はあえて密植を行い、頻繁な間伐(まばつ)を行うことで、良質な材木を生産することに成功しました。
- 無節・通直・完満: 彼の技術で育った吉野杉は、「無節」(節がない)、「通直」(真っ直ぐである)、「完満」(根元から末口までの太さがほぼ同じである)という特徴を持ち、酒樽や家具の材料として全国に知られるようになりました。
- 吉野林業全書: 1898年(明治31年)に刊行された『吉野林業全書』には、庄三郎の造林法が体系的にまとめられ、林業家のバイブルとして全国に普及しました。
庄三郎は、この造林育成の技術を地元の吉野だけに留めることなく、全国へ広めました。静岡県の天竜川流域、群馬県伊香保、兵庫県但馬地方など、各地で造林を指導し、日本の林業の生産性向上に貢献しました。
吉野の桜を守る信念
林業家としての庄三郎は、吉野山の桜の保護者でもありました。吉野山の桜が、薪にするため伐採される計画が持ち上がった際、庄三郎は自ら500円という大金を投じて桜の木を全て買い取り、伐採を阻止しました。彼は、「いずれ日本は世界の国々と交流するようになる。その時に、日本のシンボルである桜は必要だ」と考え、吉野山の桜景色を後世に引き継ぎました。彼の先見の明がなければ、吉野の桜は今日、世界遺産(紀伊山地の霊場と参詣道)の一部として外国人観光客を魅了することはなかったかもしれません。
政治と教育への貢献:「土倉詣で」の時代
庄三郎の非凡な才能と財力は、林業分野にとどまらず、当時の政治、教育、社会運動にまで及びました。
自由民権運動と明治の元勲たち
庄三郎は、自らの財産を「3分の1は国のため、3分の1は教育のため、3分の1は事業のため」と定め、私財を社会に還元するポリシーを貫きました。
- 自由民権運動のパトロン: 明治10年代から20年代にかけて、彼は自由民権運動に理解を示し、板垣退助の西欧視察の洋行費を援助したことは有名です。また、中島信行が新聞を発行する際にも資金を提供しました。
- 土倉詣で: 当時の政治家や社会運動家との交流も深く、伊藤博文、井上馨、山縣有朋、大隈重信といった明治の元勲たちが、庄三郎の支援を求めて、吉野の川上村まで「土倉詣で」をしたと言われています。
教育への多大な支援
庄三郎は、教育こそが国づくりの基本であると考え、私財を惜しみなく投じました。
- 同志社大学への支援: 新島襄の活動に賛同し、同志社大学の設立に際して、資金提供だけでなく、資金計画の面でも助言を行いました。
- 日本女子大学の設立支援: 女子の高等教育の必要性を説いた成瀬仁蔵の日本女子大学設立にも多額の寄付を行い、学校設立が実現しなかった際の「出資金返還保証」まで買って出るなど、女性教育の発展に貢献しました。
- 地域教育: 地元の川上村では、私費で小学校や私塾「芳水館」を設立し、漢学、算術、英語、武道といった中等教育を地域の青少年に提供しました。
晩年と「樹喜王」の称号
晩年、庄三郎は山縣有朋から「樹喜王(じゅきおう)」の称号を贈られました。これは、彼の林業に対する情熱と功績が、国家レベルで認められたことを示しています。庄三郎は1917年(大正6年)、78歳でその生涯を閉じました。彼の死後も、その精神は弟子や後継者に受け継がれました。大正10年(1921年)、東京帝国大学の農学博士本多静六(ほんだ せいろく)が中心となり、庄三郎の功績をたたえる「土倉翁造林頌徳記念」の碑文が吉野川右岸の鎧掛岩(よろいかけいわ)に刻まれました。この巨大な磨崖碑(まがいひ)は、彼の偉業が永遠に語り継がれるべきものであることを示しています。
土倉庄三郎ゆかりの地:吉野美林の足跡を辿る旅
土倉庄三郎の足跡は、彼の故郷である奈良県吉野郡川上村を中心に、彼が尽力したインフラと林業の地に点在しています。
- 土倉翁屋敷跡(奈良県吉野郡川上村大字大滝36-1):庄三郎の生家跡で、現在も銅像が建てられています。
- 土倉翁造林頌徳記念磨崖碑(奈良県吉野郡川上村大滝1071-1):吉野川右岸の鎧掛岩に、庄三郎の功績をたたえる巨大な碑文が刻まれています。
- 森と水の源流館(奈良県吉野郡川上村宮の平(迫1374-1)):川上村の豊かな森と水の恵みを体感できる施設。迫力あるスクリーン映像と巨大ジオラマを通して水源地の森を体感できます。
- 龍泉寺(奈奈良県吉野郡川上村大滝346):土倉庄三郎の墓所がある寺です。
土倉庄三郎の遺産:現代社会へのメッセージ
土倉庄三郎の生涯は、私たちに「公益の追求と先見の明」の重要性を教えてくれます。彼は、私財を投じて道路や教育機関を整備し、その事業で得た利益を惜しみなく社会に還元しました。彼の「青山二十分の一」という哲学は、現代の企業経営における「社会貢献(CSR)」や「地域創生」といったテーマに、深く通じるものです。彼の林業技術は、一過性の流行ではなく、100年単位の長期的な視点に基づくものでした。吉野の山林が今もなお美しいのは、彼の先見の明と、未来の子孫への責任感があったからです。土倉庄三郎の物語は、一人の実業家が、その信念と情熱によって、地域の、そして国の未来を形作ることができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、事業を通じて社会に貢献することの真の豊かさを、力強く語りかけているのです。
(C)【歴史キング】
関連する書籍のご紹介