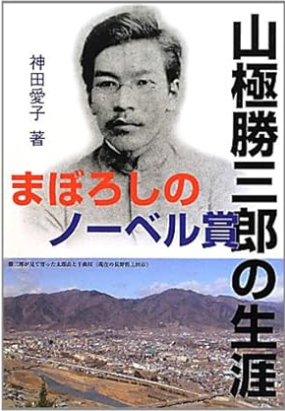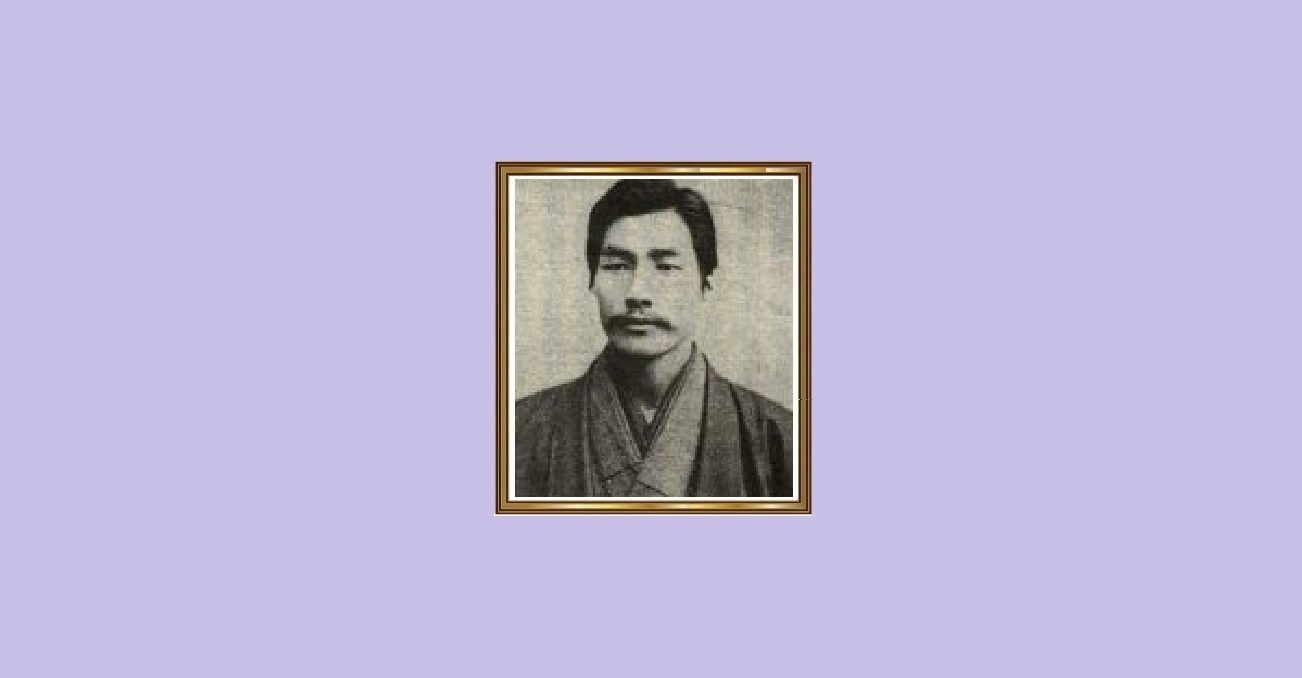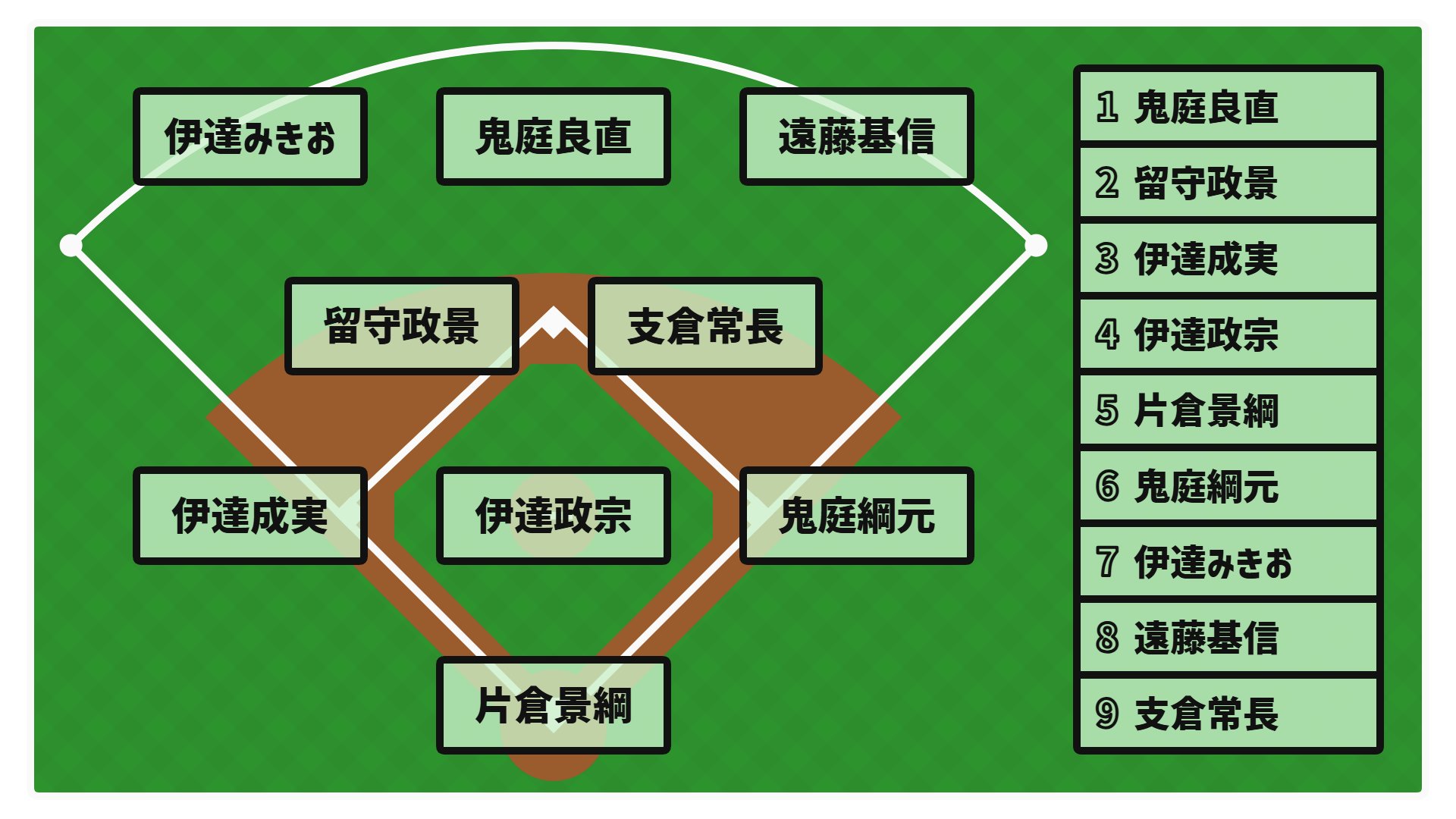過小評価されている『幻のノーベル賞受賞者』の日本人3名│北里柴三郎│秦佐八郎│山極勝三郎


こちらのコラムは、2号が担当しました🙇♂️
『幻のノーベル賞受賞』の日本人たち
今でこそ日本人のノーベル賞受賞者が数多く現れており、皆さん素晴らしいという一言では表せないような偉業を達成した方たちです。しかし、一昔前は、栄光の『ノーベル賞』選考にも人種差別の壁があった。それはもしかしたら、随分薄らいでいるだけで、今も存在しているかもしれない。なぜ、そうなったか。その大きな原因の1つに、先の大戦で日本が敗戦国となった事実を挙げたい。別に戦争を美化したいわけではない。ただ、自分の思う客観的事実を述べているのだ。
敗戦国となった日本や、戦争によって有利となった欧米諸国は、東南アジア系を下に見ていたというのは否めないだろう。これは被害妄想ではない。事実だ。
本当は日本人・初めてのノーベル賞受賞者となった湯川秀樹先生の前に、何人もの日本人たちが初受賞の偉業を人種差別によって阻まれてしまったのだと私は言いたい。このコラムや、当サイト【歴史キング】では、事実をありのままに伝えていくということ、正しい認識を広めてきたいということを目的としている。そんな私や私たちの想いが、少しでも伝われば、これ幸いだと思う・・・と実にジジ臭い結びにて、前置きを終わりにさせていただく。
🏅幻のノーベル賞受賞者
北里柴三郎さん、秦佐八郎さん、山極勝三郎さん

人はどのような時に天を仰ぐのだろうか。
ふと考えてみる。例えばサッカーの試合でエースストライカーが絶好のシュートチャンスを外してしまったら、頭を抱えたり、場合によっては天を仰ぐかもしれない。メジャーリーガーで日本が誇るスーパースター大谷翔平選手が絶好球を打ち損じてしまったとする。驚くかもしれないが彼はユニコーンではなく人間なのだから、天を仰ぐかもしれない。なるほど。人間は失敗したら空を見上げるかもしれないのだ。
私の場合はどうだろうか。公営ギャンブル・競馬に狂っていた頃、渾身の単複馬券をルメール騎手騎乗の競争馬に賭けまくった1日があった。合計200万円以上は注ぎ込んだだろう。ところがあの現役JRAナンバーワンジョッキー・ルメールをもってしても、その日は1度も馬券内にくることはなかった。私のお金はみるみるうちに溶けていった。最後の購入馬券も無惨なゴミ屑となったとき、私は天を見上げていただろうか。否。ルメールジョッキーは天を仰ぎ、画になっていたかもしれないが、私は、とある非常階段で見事に膝から崩れ落ち、地面のスチール素材をただひたすらに眺めていた。どうやら例外もあるようだ。
さて、夜、空を見上げたら何が見えるだろう。都会では見えにくいが、天気が良ければキレイな星空が見える。私には夜空を見上げる習慣はないが、今までの人生において星空を見て、キレイだと思ったことは何度もある。昼に空を見上げると青空がキレイだし、夜に空を見上げると星空がキレイなのである。
数え切れないほど多くという例えをするとき「星の数ほど」と表現する。実際、星の数というのは天文学的数字だ。天気の良い日に天文台で天体観測をしたとしよう。天体望遠鏡の使い方にも慣れてきて、やがてたくさんの星を捉えることができるようになる。
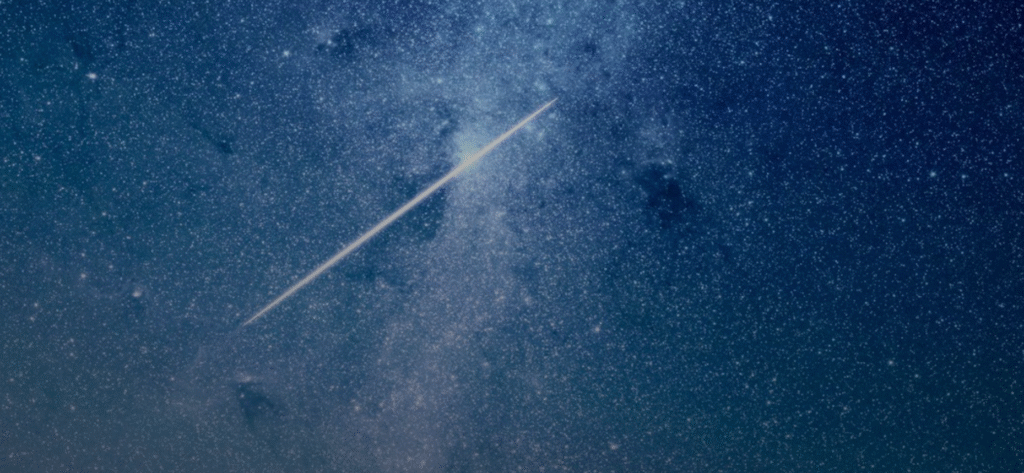
「あの星の名前はなんて言うんですか?」
「ああ、あれはアンパンマンだよ」
「あの星はなんて言うんですか?」
「あれは王貞治だよ」
そんな返答を受けたら、面白くない親父ギャグだと思うかもしれない。しかし本当にそういう名前の星が現実にある。夜空にきらめく星は、その第一発見者が命名したりするので、人の名前に由来する星はたくさんあるのだ。
世界で最も偉大な賞の1つがノーベル賞だ。
現在は『医学・生理学』『物理学』『化学』『文学』『平和』『経済学』と6つの賞があり、毎年3人までが受賞している。このノーベル賞の由来というのは、ご存知、「ノーベル」という人の名前である。「人類に最大の貢献をもたらした人々」に受賞資格があるのがこのノーベル賞なのだから、一体ノーベルはどのような偉大なことを成し遂げたのだろうか。
そのノーベルの過去に触れる前に、1つの映画を話に出したい。2023年にアメリカで製作された「オッペンハイマー」である。原爆の父と言われる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの物語であり、広島と長崎に堕とさなくても良かった核爆弾を作ったとされる人物である。世界で唯一の原爆被爆国である我々日本にとっては、なんともセンシティブな話だ。人類史上最恐の兵器とも考えられる核爆弾を生み出した彼は、科学者としてはとてつもないものを生み出したのかもしれない。しかし人間としてこのようなものを作って良かったのだろうかとずっと苦悩したという。実はノーベルも似たところがある。
ノーベルの本名はアルフレッド・ノーベルと言う。

スウェーデンの化学者であり、発明家でもある。350もの特許を取得しており、その中で最も有名な発明が「ダイナマイト」だ。ノーベルはダイマナイトの発明により巨万の富を得ることになるのだが、ご存知ダイナマイトはニトログリセリンを主剤とする爆薬だ。しかし決して兵器として作られたものではない。いや、正確に言うと兵器として使われる可能性も十分に考えていた。
彼のロジックはこうだった。
「一瞬で戦争を終わらせるものがあるのなら、それが抑止力となり結果的に平和な世の中を迎えることができるのだ」と。
そもそもはダイマナイトというのは、トンネル工事などで作業をスピーディーに円滑に行うことを目的に作られたものである。しかし結果的にはノーベルの想定していた悪い方の使われ方で、大量殺戮兵器として戦争を激化させてしまう発明となり、彼は死ぬまで思い悩んだという。そしてそのノーベルの遺言によって開設されたのがノーベル賞であるが、ダイナマイトの発明で得た財産の大半はそれに注ぎこんだ。
最高の栄誉と言われるノーベル賞も、そんなノーベルの葛藤から誕生したものである。
今まで日本人のノーベル賞・受賞者数は28人おり、国別のランキングで言えばスイスの30人に次いで7位となる。アジア国としては1位なのだから、素直に誇れる数字ではないか。偉大なる歴代受賞者たちには最大限の賛辞を送りたい。さて、日本で初めてノーベル賞を受賞したのは誰か。1949年に物理学の分野で受賞した湯川秀樹さんが初めてである。1901年の第1回から、実に40年以上の時を経て“ようやく”であった。しかし実は湯川さん以前に、惜しくも受賞を逃した日本人たちがいる。いつぞやのコラムでも名前を挙げ、またの機会に触れたかった人物たちだ。
北里柴三郎さん、秦佐八郎さん、山極勝三郎さん
らを紹介したい。


昨年2024年7月に、日本に新紙幣が登場した。ご存知のように千円札は野口英世さんから、北里柴三郎(きたざとしばさぶろう)さんにバトンタッチされた。
紙幣の肖像画という点では野口英世さんがパイセンで、後輩が北里柴三郎さんになるのだが、現実世界は違う。北里さんが所長を務めていた伝染病研究所(現・東京大学医科学研究所)に入職し、そこで学んだ1人が野口さんだった。
北里さんは細菌学の分野で多大な功績を挙げた。国内外の感染症の撲滅と医学の進歩に大きな影響を与えた。いの一番に浮かぶ功績は、やはり破傷風菌の純粋培養ではなかろうか。当時不可能と言われたことを世界で初めてやってのけ、不治の病であった破傷風の血清療法を生み出したのだ。これにより世界中の多くの命を救ったのだ。
ここでノーベル賞の受賞資格を振り返りたい。
それは物理学、化学、生理学・医学、文学、平和(後に経済学がプラス)の各分野で「人類に最大の貢献をもたらした人々」に授与される賞であるということだ。
北里さんの功績は申し分なしで、当然のように第1回ノーベル賞の候補にあがる。
ところがこの時、記念すべき第1回ノーベル生理学・医学賞を受賞したのはドイツのフォン・ベーリングであった。ベーリングは、近代細菌学の開祖(細菌学の父)と呼ばれるドイツのロベルト・コッホの元で北里さんと共に細菌学を学んだ。そして北里さんらとの共同で、血清療法の研究に心血を注いだ。ベーリングのノーベル賞受賞は、この血清療法が理由となった。しかし、確かに共同研究という事実はあるのだが、この療法は北里さんが発見した方法を応用したものであった。ではなぜ、北里さんではなくベーリングが受賞することになったのか。それは北里さんはベーリングをサポートしたのであって、最も称えられるべきはベーリングであるというのだ。いやいや、おかしい。ベーリングの研究は称賛されるべき、素晴らしいものだ。しかし北里さんの破傷風研究があってこその研究成果だったのだ。ちょっと厳しく言えばベーリングの研究成果は二番煎じなのだ。しかし結果は先にお伝えしたとおり、北里さんはサポート役であったのだと判断された。そのように無理やりこじつけられたと言えるかもしれない。ノーベル賞が功績で評価されるのはそのとおりだとは思うが、ベーリングには、ドイツからは国を挙げての応援があった。逆に日本では北里さんの足を引っ張るというマイナスの動きがあったらしい。しかしたとえそうであったとしても、霧の中に隠れている真実を捉えるかごとく、本当の成果を選考側には見抜いて欲しかったのであるが、そうはならなかった。
北里柴三郎さんに学んだ人物の1人、秦佐八郎(はた さはちろう)さんはどうだろうか。ドイツのパウル・エールリヒと共に、梅毒の特効薬であるサルバルサンを開発した細菌学者である。サルバルサンは人間をずっと苦しめてきた難病・梅毒に対する歴史的な治療薬であった。秦さんはエールリヒの研究所で梅毒治療剤サルバルサンを開発したのだから、見方によってはエールリヒが導いたとも言える。エールリヒの貢献度も大きい。しかしやはりサルバルサンを作ったのは誰かと聞かれたら、秦佐八郎さんの方である。ところがノーベル生理学・医学賞を受賞したのはエールリヒ1人だけであった。
人工癌研究のパイオニアとして知られる山極 勝三郎(やまぎわかつさぶろう)さんはどうだろうか。世界で初めて人工発癌に成功した人物だ。この功績は逆説的に考える必要がある。当時、癌の発生原因というのは不明であった。つまり人工的に癌が発生させられるのなら、治療も可能だと考えることができるわけだ。実際、山極さんの研究成果は後の研究者たちの土台となる。ところがこの人工癌研究において、ノーベル生理学・医学賞を手にしたのはデンマークのヨハネス・フィビゲルであった。なぜ私が驚いているかというと、フィビゲルが先に成功したといわれる人工癌は実は誤りであったからだ。更に驚くべきなのは、当時からそのような視点で語られる意見があったのにもかかわらずなのだ。北里さん然り、秦さん然り、山極さん然り、何かおかしいのではないだろうか。この頃の選考委員会で「東洋人にはノーベル賞は早すぎる」との発言があったともされる。人種差別・・・。考えたくはないが、ノーベル賞という最高の賞の選考においても、やはり疑ってしまう。

あくまで個人的な考えを述べさせてもらうコラムなのだから、私的な意見であると前置きさせてもらった上で、私が思う結論を語りたい。それは、湯川秀樹さんが初受賞されるまでの間、単純に日本人がノーベル賞を受賞するのは無理だったのだと考えている。もっと言えば日本人というくくりではなく、東洋人が難しかったのだ。私は第1回のノーベル生理学・医学賞は北里柴三郎さんが受賞すべきだったと思う。しかし悔しいが、当時は今よりも人種差別がひどい時代だった。ヨーロッパ中心で考えられる世界であり、アジアの国は二の次、三の次だ。そんな背景・バックボーンの中で、第1回のノーベル賞が東洋人(日本人)であろうはずがない。北里柴三郎さん然り、秦佐八郎さん然り、山極勝三郎さん然り、今の時代であれば全員ノーベル賞を受賞していたかもしれない。当時に国の援護や、アピールがあれば、結果が違っていた可能性はあるにはある。しかしそれでもやはり不利であったのだと私は見ている。数々の欧米人たちが受賞し、その輝かしい受賞歴を積み上げた後だから、ようやく東洋人(日本人)にも順番がまわってきたというのが私の思う考えだ。
人間や人間が作り上げた社会というのは権威に弱い。長いものにまかれる。おそらく生物学的に考えても、より強い遺伝子を残すためにDNAレベルでも語れるのではないだろうか。今の世の中でもそういうものだ。昔より見えにくくなっているだけで、時折ヒョコっと顔を出す。
良い物なのに選ばれない。
正しいものが正当に評価されない。
真実なのに真実と認められない。
なぜなら人間は権威に弱いからだ。そこにはしがらみや権力、驕り、見栄といった幼稚なものまで存在する。
過ちを繰り返すのが人間なのであるが、過ちを正すことができるのもまた人間なのである。私は後者に希望を見たい。そのはずなのだが・・・。
今、アルフレッド・ノーベルは空から私たちを見下ろし、何を思っているだろうか。
権力・権威によって、せきとめられている事柄があったり、本当に正しいものが世に広まらない弊害こそ、大発明・ダイマナイトで吹き飛ばしたいだろう。
(C)歴史キング 2025.04.23
関連する書籍のご紹介

北里柴三郎(上)-雷と呼ばれた男 新装版 / 山崎 光夫 (著)
(中公文庫 (や32-5)) 文庫 – 2019/6/20
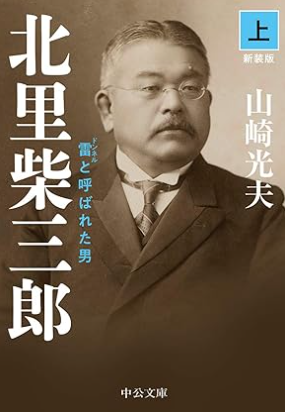
第一回ノーベル賞を受賞するはずだった男、北里柴三郎。その波瀾に満ちた生涯は、医道を志した時から始まった。「肥後もっこす」そのままに、医学に情熱を傾ける柴三郎は、渡独後、「細菌学の祖」コッホのもと、破傷風菌の純粋培養と血清療法の確立に成功する。日本が生んだ世界的医学者の生涯を活写した伝記小説。
北里柴三郎(下)-雷と呼ばれた男 新装版 / 山崎 光夫 (著)
(中公文庫 (や32-6)) 文庫 – 2019/6/20
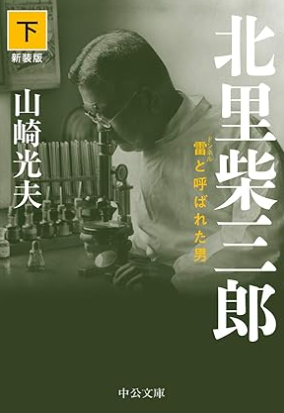
帰国した柴三郎は、福沢諭吉の支援を得て、伝染病研究所の設立を果たす。そこへ香港でペストが大流行との報が入り、現地へ。調査団からも感染者が出る過酷な状況下で、柴三郎はペスト菌を発見する。一方、東大閥との争いが激化。政治の思惑にも巻き込まれ、柴三郎は伝染病研究所を失うことになるが――。〈解説〉大村 智

サルバルサン戦記~秦佐八郎 世界初の抗生物質を作った男~ Kindle版 / 岩田 健太郎 (著)
形式: Kindle版
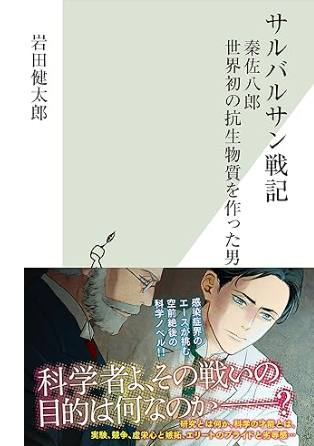
島根県出身の細菌学者・秦佐八郎(1873~1938)。難病だった梅毒の特効薬「サルバルサン」(世界初の抗生物質)を、ドイツのエールリッヒと共に開発し、多くの人命を救った男である。その佐八郎の人生を、現代の感染症界のエース・岩田健太郎がノンフィクション・ノベルとして描きだす。研究とは何か、科学の才能とは、実験、競争、虚栄心と嫉妬、エリートのプライドと劣等感、研究倫理……現代に通ずるテーマとして問いかける。