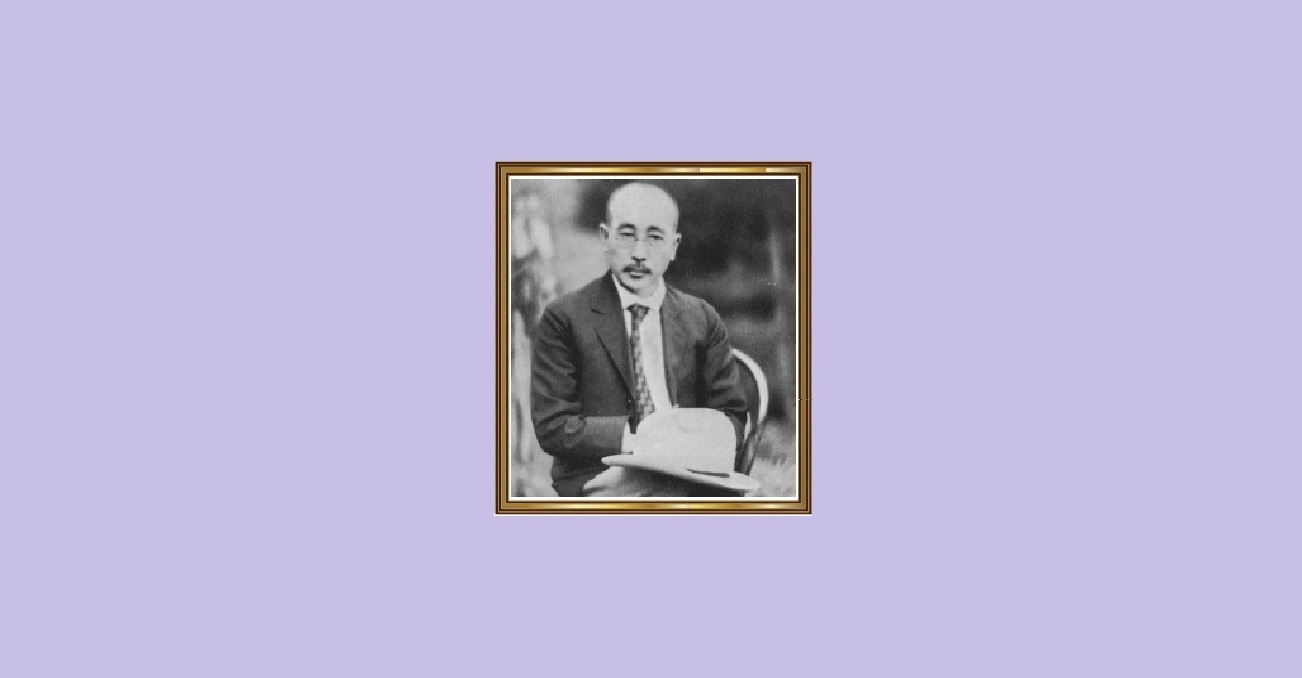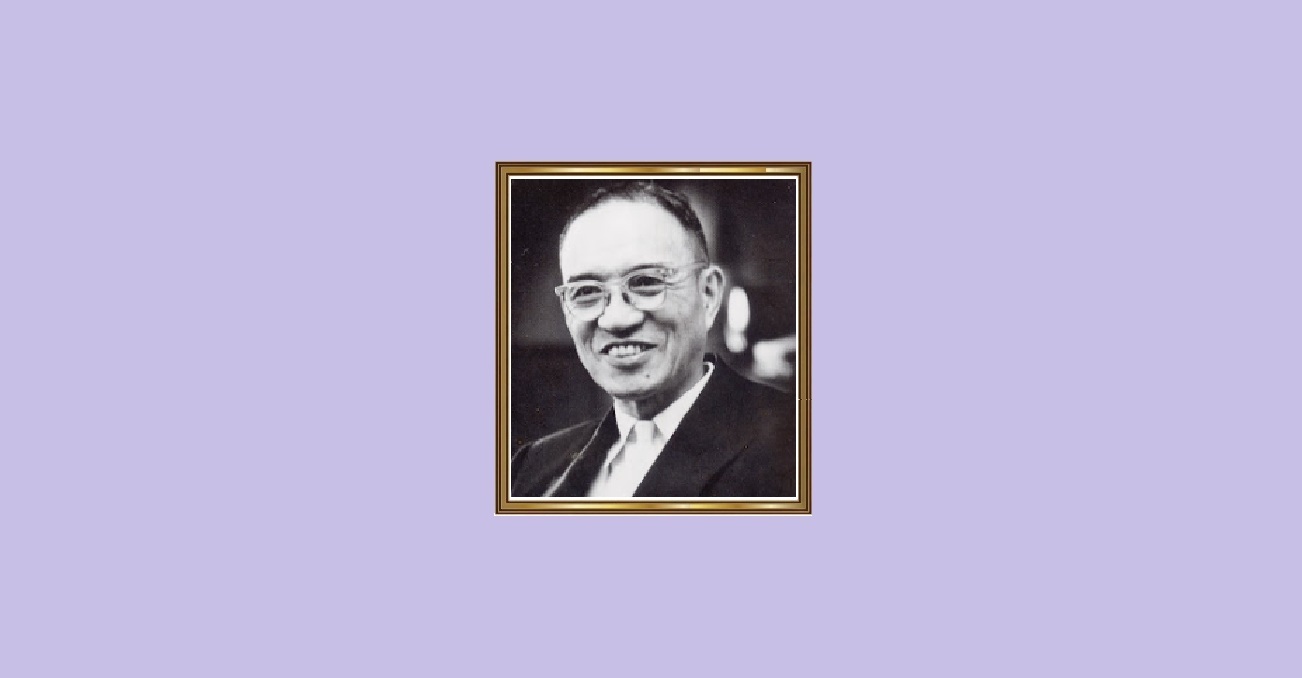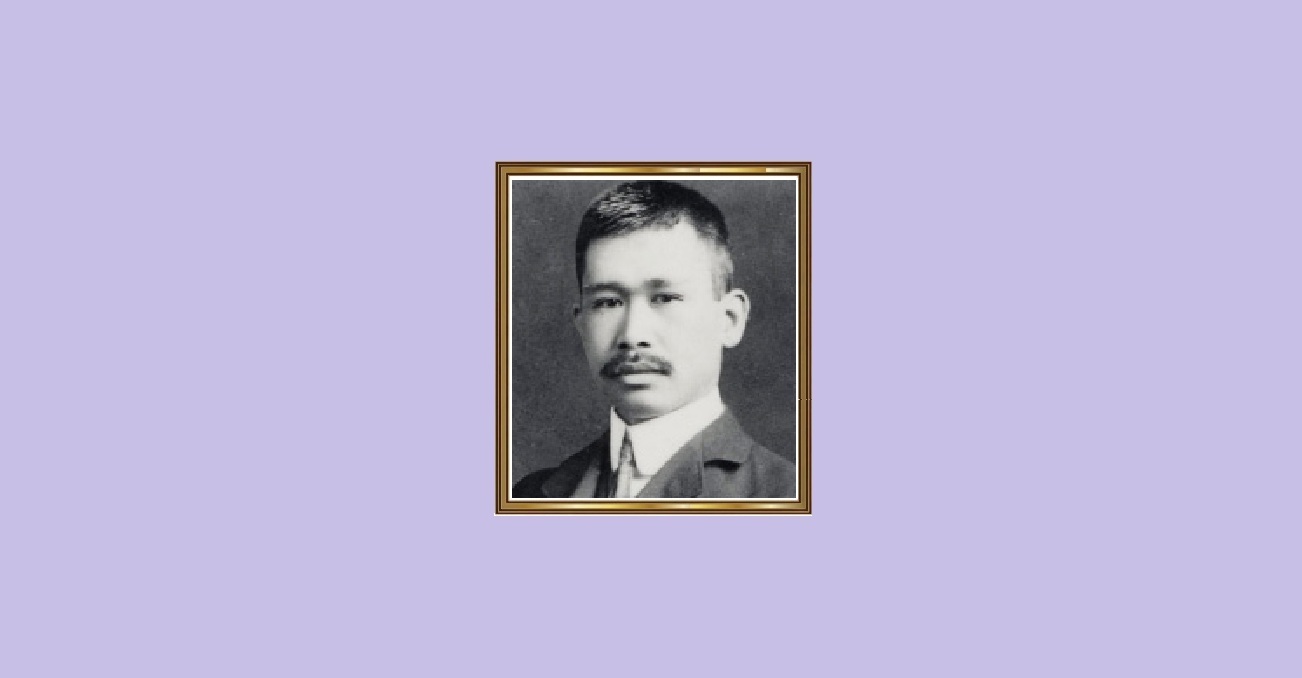栃木県の偉人:印南丈作 — 那須野が原を緑に変えた、不屈の開拓魂


栃木県
「那須野が原の開拓は、人々の生活を安定させ、国益を増進させる」
この言葉は、栃木県日光市に生まれ、生涯を那須野が原の開拓に捧げた印南丈作(いんなみ じょうさく)の強い信念を表しています。当時は水利に恵まれず、不毛の原野とされていた那須野が原に、那珂川から水を引く壮大な運河計画「那須疏水(なすそすい)」の実現に尽力しました。その不屈の精神と、同志・矢板武(やいた たけし)との固い絆が、わずか5ヶ月という驚異的な速さで那須疏水を開削させ、今日の豊かな那須野が原の礎を築いたのです。
幼少期の苦難から開拓への使命感へ
印南丈作、出生名・神山源太郎は、1831年(天保2年)、下野国都賀郡日光入町本町(現在の栃木県日光市)に生まれました。若くして那須郡大田原の印南家の養子となり、家業を継ぎました。彼は、戸長(町村の長)や県の勧業課附属(かんぎょうかふぞく)といった要職を歴任する中で、広大な原野「那須野が原(なすのがはら)」の存在を知ります。那須野が原は、那珂川と箒川に挟まれた複合扇状地で、地中に厚い砂礫層が堆積しているため、雨や川の水がすぐに地下に浸透してしまう、水利に恵まれない土地でした。江戸時代初期から一部の地域で用水路の開削は行われていましたが、大部分は草刈り場として放置されており、開拓が進んでいませんでした。丈作は、佐久山宿(現在の栃木県大田原市)の高台から那須野が原を一望するたびに、この広大な原野を開拓することこそが、人々の生活を安定させ、国益を増進させる道だと考えるようになりました。
盟友・矢板武との運命的な出会い
丈作が那須野が原の開拓への使命感を抱き始めた頃、同じく開拓の夢を抱いていた人物がいました。それは、那須郡矢板(現在の栃木県矢板市)の名主の家に生まれた矢板武(やいた たけし)です。矢板は、公用で那須野が原の南端を往復する中で、都からわずか40里(約160km)のこの広大な土地が、雑草の生い茂るままになっていることを憂い、水路を開削してこの地を美田へと変えることを決意していました。丈作より18歳年下の矢板でしたが、二人は公用で会う機会があり、那須野が原の開拓という共通の夢を語り合ううちに、意気投合。彼らは、那須疏水の開削という壮大な計画を実現するために、共に歩むことを誓い合いました。
那須疏水の開削:困難を乗り越えた不屈の精神
二人は、那須野が原開拓の第一歩として、那珂川の水を引く水路の開削を計画します。当時、その工事費用は16万5千円という莫大な額でした。しかし、二人の熱心な思いが国のお役所に届き、政府からの補助金を得られることになりました。しかし、工事は順風満帆ではありませんでした。水路の途中に砂礫層が厚く堆積しており、水が地下に浸透してしまい、末端まで届かないという問題に直面します。また、資金が不足し、工事が中断されるなど、数々の困難が彼らの前に立ちはだかりました。それでも、丈作と矢板は諦めませんでした。二人は、那須開墾社を組織し、社長に丈作が就任。開墾事業を推進する傍ら、飲料水確保のための小規模水路の開削を政府に請願し、1882年(明治15年)、那珂川の清流を那須野が原に呼び込むことに成功します。この成功を足がかりに、二人は、大水路開削を求める請願運動を強力に展開。私財を投じて、難工事とされていた隧道(ずいどう)の試掘を行うなど、政府に開削の必要性を訴え続けました。そして1885年(明治18年)、ついに那須疏水開削が政府に認められ、着工。南一郎平(みなみ いちろべえ)を総監督に迎え、那須疏水の開削が始まりました。そしてわずか5ヶ月という短い期間で、那珂川から那須野が原を横断する全長16.3キロメートルの水路が完成。疏水が完成した時、人々は涙を流して手を取り合い、喜びを分かち合いました。
晩年と後世への遺産
那須疏水の開削を成功させた丈作は、その後も疏水の維持管理団体「那須水組」の設立・運営に指導的役割を果たしました。しかし、長年の激務と心労がたたり、那須疏水完成からわずか3年後の1888年(明治21年)、55歳で死去しました。彼の死後も、那須疏水の開拓事業は受け継がれ、今日の那須野が原は、広大な水田地帯となり、日本を代表する農業地帯へと発展しました。那須野が原の一画には、彼の功績を称える顕彰碑が建立され、那須野が原の人々によって、その偉業は今も語り継がれています。
印南丈作ゆかりの地:那須開拓の足跡を辿る旅
印南丈作の足跡は、彼の故郷である日光市から、那須野が原の開拓に生涯を捧げた那須塩原市へと繋がっています。
- 烏ヶ森(からすがもり)神社(栃木県那須塩原市):那須野が原の開拓に尽力した印南丈作の頌徳碑が建立されています。
- 那須野が原博物館(栃木県那須塩原市):那須野が原の歴史や自然、開拓の様子を学ぶことができる博物館です。
- 印南丈作翁屋敷跡(栃木県那須塩原市三区町):丈作が晩年を過ごした屋敷跡で、市指定の史跡となっています。
- 常磐ヶ丘(栃木県那須塩原市二つ室):那須野が原を一望できる小高い丘で、丈作とその妻、開拓に尽力した仲間たちが眠っています。
- 那須疏水の取水口(栃木県那須塩原市):那須疏水の開削の起点となった場所です。
印南丈作の遺産:現代社会へのメッセージ
印南丈作の生涯は、私たちに「不屈の精神と挑戦」の重要性を教えてくれます。彼は、水利に恵まれない那須野が原という困難な土地を前に、決して諦めることなく、壮大な運河計画を実現させました。彼の偉業は、単なる土木事業ではありません。それは、人々の生活を安定させ、豊かな社会を築くという、明確なビジョンに基づいたものでした。彼の不屈の精神は、現代の私たちが直面する様々な課題を乗り越えるための勇気を与えてくれます。また、盟友・矢板武との強い絆は、大きな目標を達成するためには、個人の力だけでなく、志を同じくする仲間との協力がいかに大切かを物語っています。印南丈作の物語は、現代に生きる私たちに、困難な課題に立ち向かう勇気と、真のリーダーシップとは何かを問いかけ続けているのです。