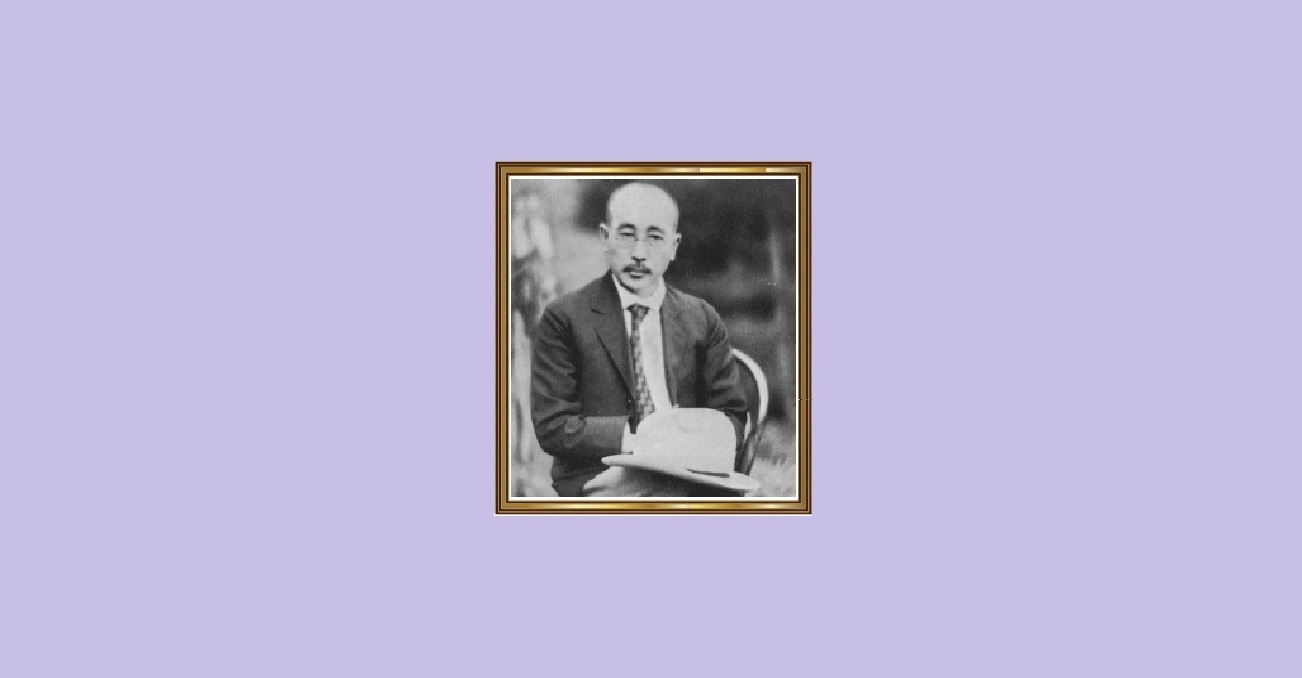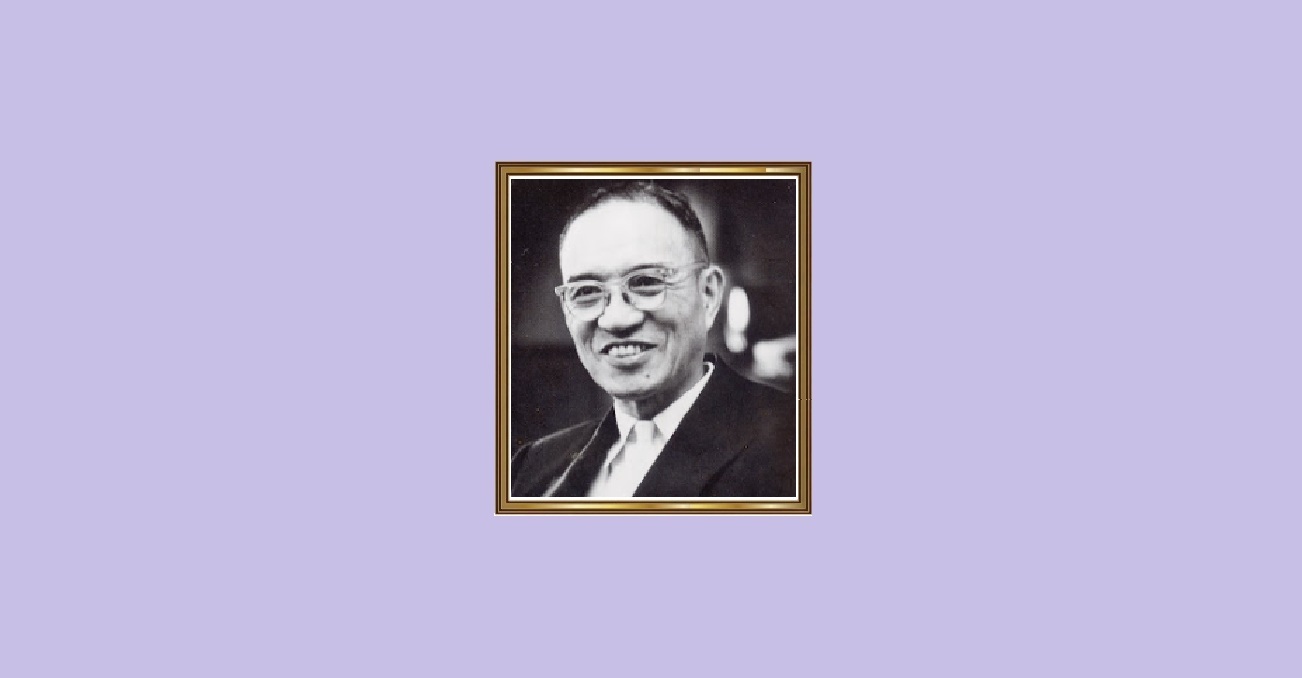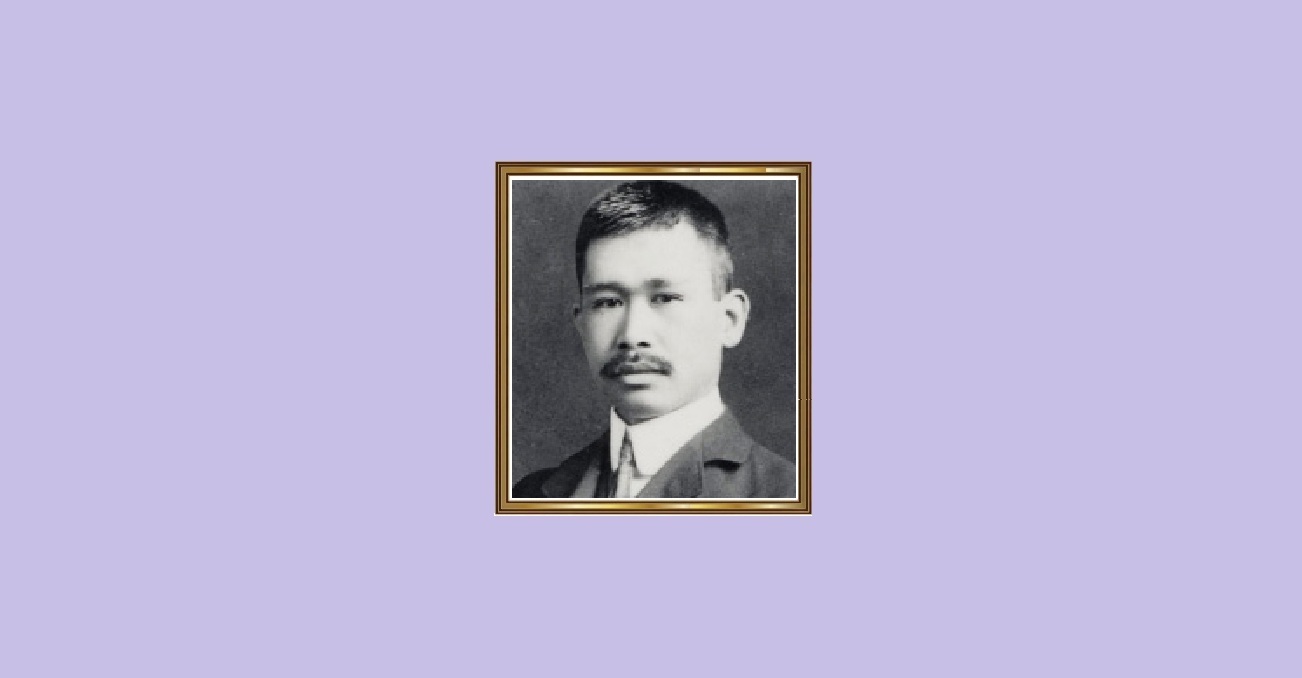宮崎県│岡山県の偉人:石井十次 — 「鍬鎌主義」を貫き、2千の命を救った「児童福祉の父」
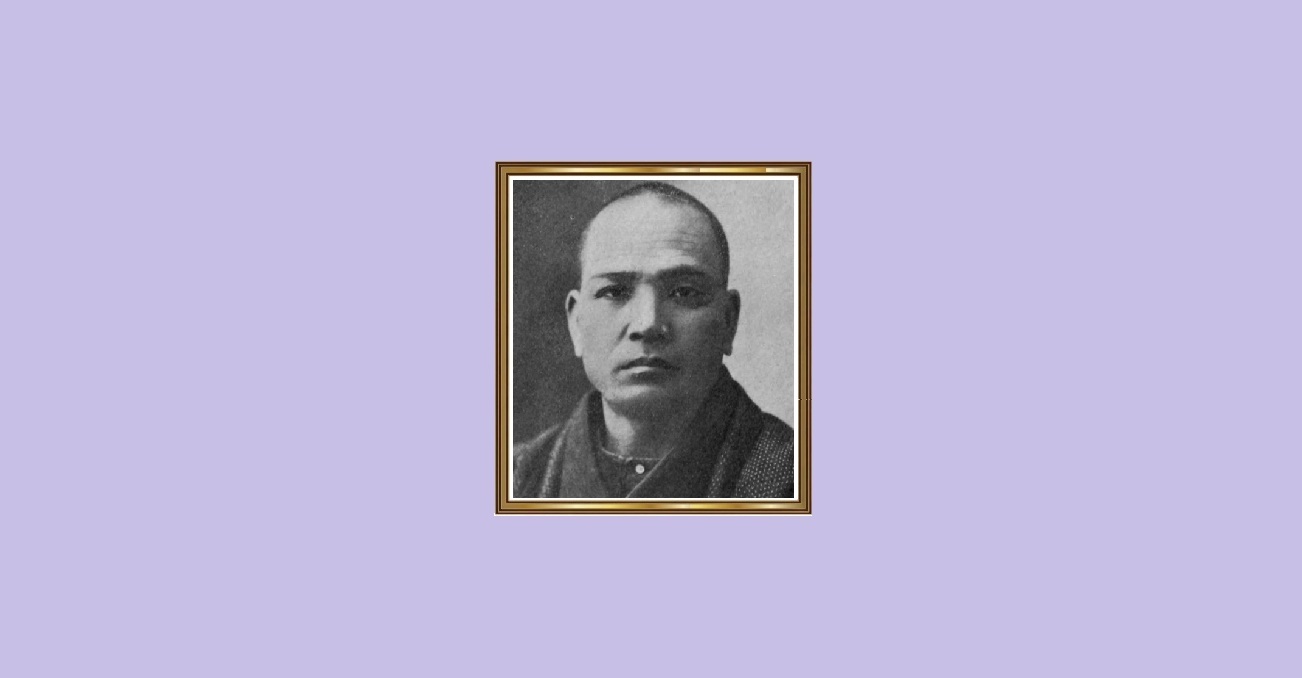

宮崎県│岡山県
「なんじ、自ら茶臼原にあり、鍬鎌主義を実行し理想の国を建設すべし」
この言葉は、日本の福祉事業の先駆者、石井十次(いしい じゅうじ)が、孤児救済事業の究極の理想として掲げたものです。日向国児湯郡上江村(現在の宮崎県高鍋町)に生まれた彼は、医者の道を捨て、生涯を孤児救済に捧げました。地震や飢饉で路頭に迷った2,000人を超える子どもたちを救い、宮崎県の茶臼原に「理想郷」を築こうと奮闘。その献身的な行動とキリスト教信仰に根ざした博愛精神から、「児童福祉の父」と呼ばれています。
幼少期の感化と、医学への道
石井十次は、1865年(慶応元年)、高鍋藩の下級武士の家に生まれました。幼い頃から母・乃婦子(のぶこ)が貧しい人々を助ける姿を見て育ち、十次自身も、友人がいじめられているのを見て、母に新調してもらったばかりの帯を友人に与えるなど、困った人を助けずにはいられない性格でした。彼の思想形成に大きな影響を与えたのが、高鍋藩の藩校「明倫堂(めいりんどう)」の教育です。明倫堂で学んだ十次は、年長者を敬い、困窮者を助け合うという儒教的で徳を重んじる気風の中で育まれました。17歳の時、宮崎病院長の荻原百々平(おぎはら どどへい)医師との出会いをきっかけに、医師を志し、岡山県甲種医学校(現・岡山大学医学部)へ入学。この頃、彼は岡山基督教会で金森通倫(かなもり みちとも)牧師から洗礼を受け、キリスト教の博愛精神に触れました。
医書を焼く決意と「孤児教育会」の設立
在学中の1887年(明治20年)、十次は、巡礼の旅の途中で困窮した女性から、一人の男児を預かったことをきっかけに、孤児救済を決意します。医学の道に進むか、孤児救済の道に進むかの二者択一を迫られた十次は、「二人の主に仕えることはできない」というキリスト教の聖句に従い、生涯を孤児救済に捧げる覚悟を固めます。彼は、6年間学んだ医学書をすべて焼き捨てて医学校を退学。そして、岡山市の三友寺に「孤児教育会」(後の岡山孤児院)の看板を掲げました。この時の十次、23歳。彼の決心は、当時の社会で最も安定した職業である医者の道を捨てるという、不退転の覚悟の現れでした。
苦難の経営と「時代教育法」の実践
岡山孤児院は、その後の日本の近代化が産んだひずみにより、収容児童が激増します。明治24年(1891年)の濃尾地震、明治25・26年の岡山大洪水、明治39年の東北大凶作など、天災や飢饉のたびに、孤児院は被災孤児を積極的に受け入れました。特に東北凶作では、825名もの孤児を受け入れ、院児数は一時1,200人を超えました。
独創的な養護方法と自立教育
十次は、単なる施しに終わらせず、孤児たちが社会に出て自立できるよう、独創的な養護と教育を実践しました。
- 鍬鎌(くわかま)主義教育: 「幼児は遊ばせ、子は学ばせ、青年は働かせる」という「時代教育法」を編み出し、労働を通じて自立心を育む教育を実践しました。
- 実業教育: 院内に「活版部」「理髪部」「機業部」などの事業部を設け、子どもたちに手に職をつけさせ、孤児院の収入源としました。
- 満腹主義・密室主義: おなかいっぱい食事を与える「満腹主義」と、子ども一人ひとりと向き合う「密室主義」を導入し、心と体の健康を重視しました。
- 家族制度と委託制度: 保育士を中心とした「家族制度」や、孤児を里親に預ける「委託制度」(後の里親制度)を日本で初めて導入しました。
音楽幻燈隊と「土倉詣で」
孤児院の経営は常に資金不足に悩まされましたが、十次は、子どもたちによる「音楽幻燈隊」を編成し、全国で公演を行いました。演奏会と活動写真で孤児院の実情を伝えるというこの活動は、日本国内だけでなく、ハワイ、台湾、中国まで及び、十次の名を世界に広めました。この活動を通じて、彼の最大の理解者となったのが、倉敷の実業家・大原孫三郎(おおはら まごさぶろう)でした。大原は、十次に共鳴し、その後も孤児院の最大の支援者となり、彼の死後もその事業を引き継ぎました。
理想郷「茶臼原」への挑戦と最期
フランスの思想家ルソーの『エミール』に感化された十次は、「自然の中で自由に遊び、学ぶ」理想郷の建設を目指し、1894年(明治27年)、故郷宮崎県の茶臼原(ちゃうすばる)への移住を始めます。
- 茶臼原への移住: 岡山から、宿舎や学校を解体して船に積み、馬車で10kmの山坂道を運ぶという大事業を敢行。18年かけて全面移住を完了させました。
- 茶臼原憲法: 大自然の中で、「私心私欲なき」「私有財産なき」「鍬鎌主義をもって労働する」「神様を中心とする」国を建設するという、「茶臼原憲法」を制定し、キリスト教精神に基づいた理想的な農村共同体を目指しました。
しかし、長年の無理がたたり、持病の腎臓病が悪化。1914年(大正3年)、長女友子の出産を電報で知った直後、永眠。享年48という若さでした。
石井十次の遺産:受け継がれる友愛の精神
十次の死後、岡山孤児院は一旦解散しましたが、その精神は弟子や支援者に受け継がれました。
- 石井記念友愛社: 十次の孫である児嶋虓一郎(こじま こういちろう)が、第二次世界大戦後の孤児救済のため、茶臼原の地に設立。現在も児童養護施設を運営しています。
- 石井記念愛染園: 大原孫三郎が設立。後の法政大学大原社会問題研究所の前身となる救済事業研究室が付設されました。
- 公益財団法人 石井十次顕彰会顕彰事業: 1992年に「石井十次賞」が創設され、児童福祉に尽力する団体に贈られています。
石井十次ゆかりの地:愛と献身の軌跡を辿る旅
石井十次の足跡は、彼の故郷である宮崎県高鍋町から、孤児院を設立した岡山、そして理想郷を築いた宮崎県木城町へと繋がっています。
- 石井十次生家(宮崎県児湯郡高鍋町大字上江2044):高鍋町馬場原に今も残されている石井十次生誕の家。現在親族の方々によって管理されており、外観のみ見学できます。
- 石井記念友愛社・石井十次記念館(宮崎県児湯郡木城町椎木644-1):彼が理想郷を築いた茶臼原にあり、資料館では彼の功績を伝えています。
- 石井十次像(高鍋町中央公園内・宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋):郷土の英雄として像が建てられています。
- 石井十字像(宮崎県総合文化公園内・宮崎県宮崎市船塚3-210):宮崎の偉人・小村寿太郎、川越進、石井十次、若山牧水、高木兼寛、安井息軒の銅像が設置されています。
- 新天地育児院(岡山県岡山市門田本町):岡山孤児院の家族舎(一棟)が移築・保存され「石井十次記念館」として保存されています。石井十次胸像も設けられている。
- 岡山孤児院発祥の地(岡山県岡山市東区上阿知):社会事業家石井十次が明治20年にこの地の辻堂で困窮者の子を引き取り、彼の岡山での孤児院救済教育の活動の緒になった。
- 三友寺跡(岡山県岡山市中区門田屋敷1-9-31):明治20年(1887年)に、石井十次が、寺内に孤児教育会を設立した。昭和20年(1945)岡山大空襲によって本堂など諸堂を焼失、山門のみは焼損したものの現存する。
- 石井十次墓所(宮崎県西都市穂北5248-19※茶臼原農村公園内):石井十次と子供達が開拓した茶臼原台地の中に茶臼原農村公園が整備され、石井十次の墓があり、胸像と茶臼原憲法の石碑も建てられています。
石井十次の遺産:現代社会へのメッセージ
石井十次の生涯は、私たちに「自己犠牲と利他主義」の重要性を教えてくれます。彼は、医学の知識や社会的地位といった自己の利益をすべて捨てて、社会の最弱者である孤児の救済に身を捧げました。彼の「鍬鎌主義」の精神は、現代社会における「自立支援」と「共生」の理念に深く通じています。単なる施しではなく、教育と労働を通じて子どもたちに生きる力を与えるという彼の方法は、現代の福祉制度にも大きな示唆を与えています。石井十次の物語は、一人の人間が、その強い信念と博愛精神によって、社会のひずみが生み出した悲劇に立ち向かい、多くの命を救うことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、理想を追求する勇気と、真の社会貢献とは何かを、力強く語りかけているのです。