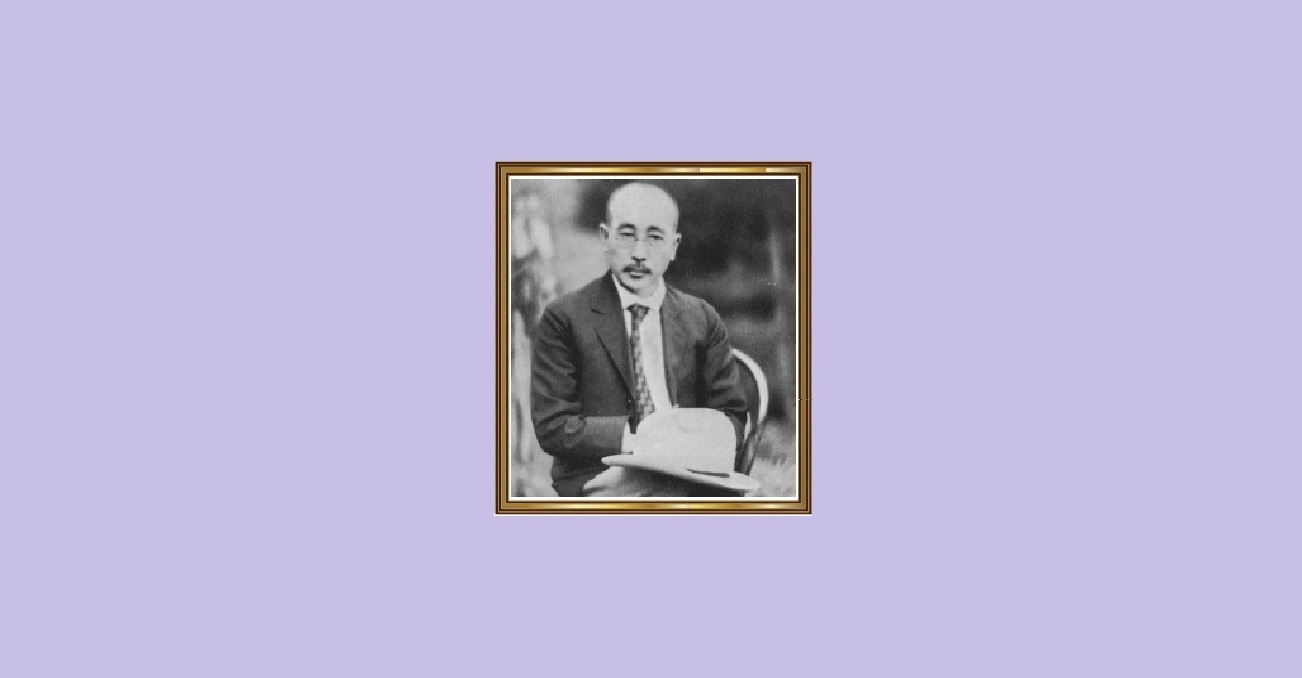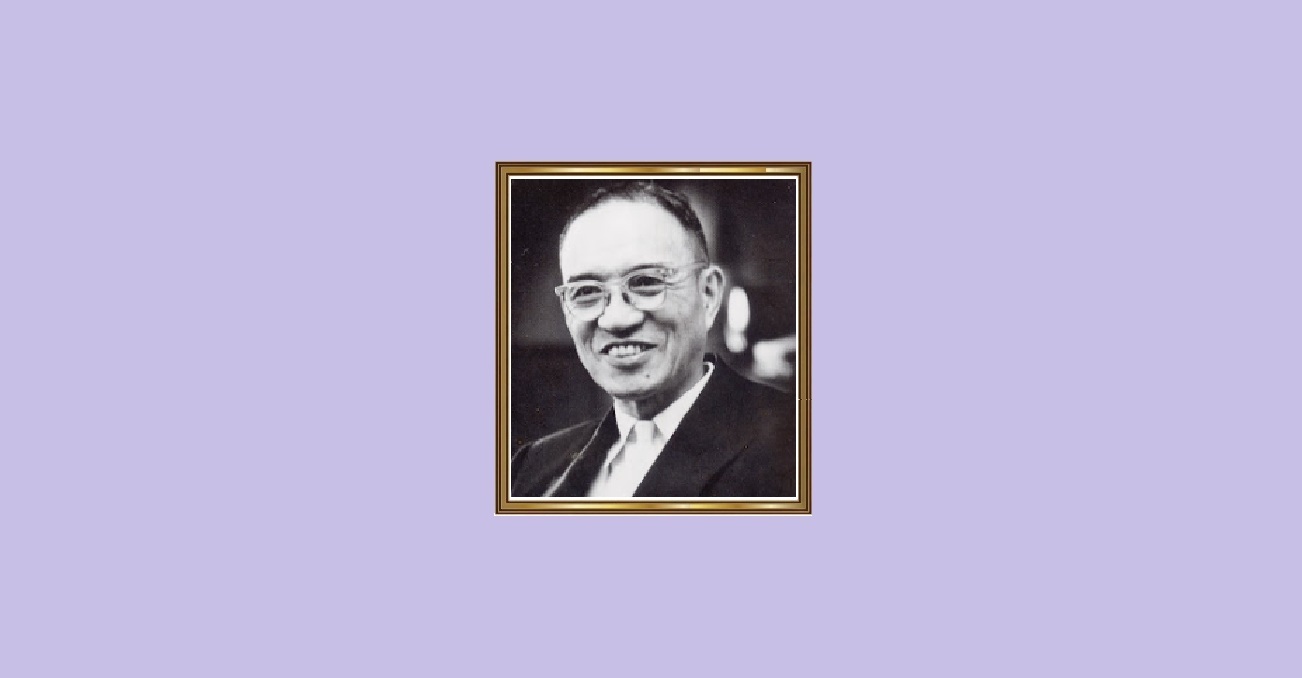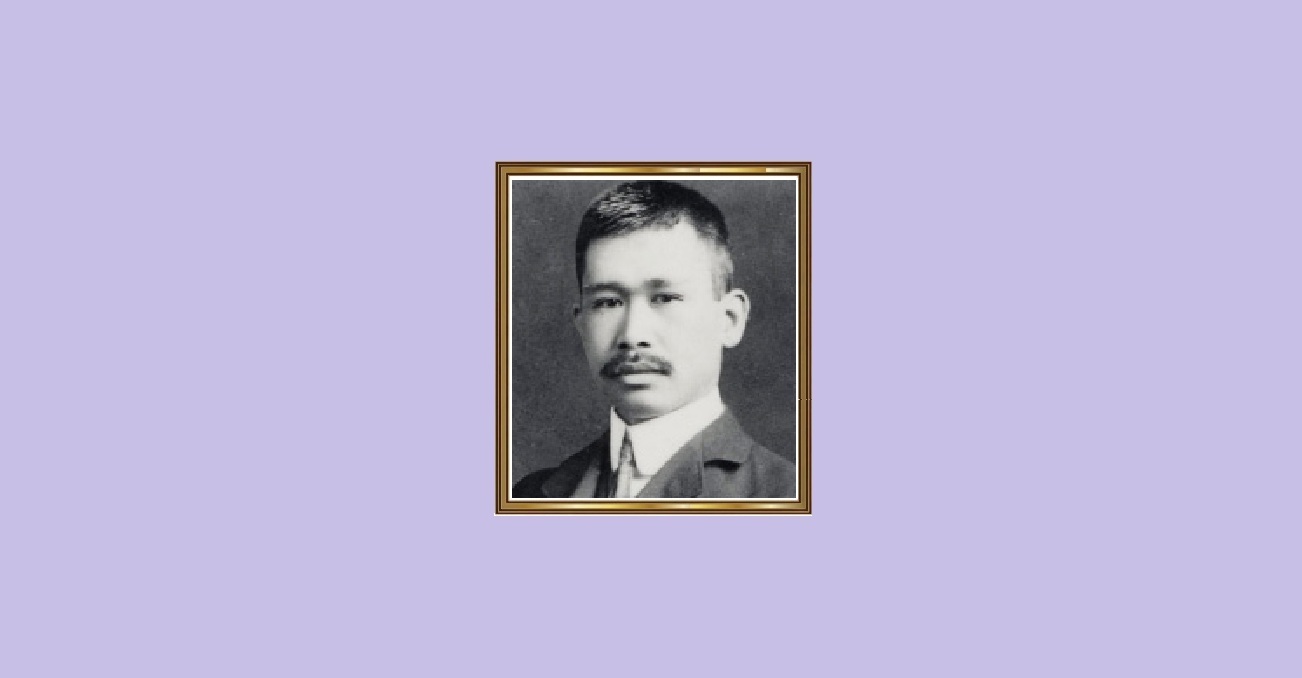東京都の偉人:勝海舟 — 江戸無血開城を実現し、100年先の中国を予見した「幕末の三舟」
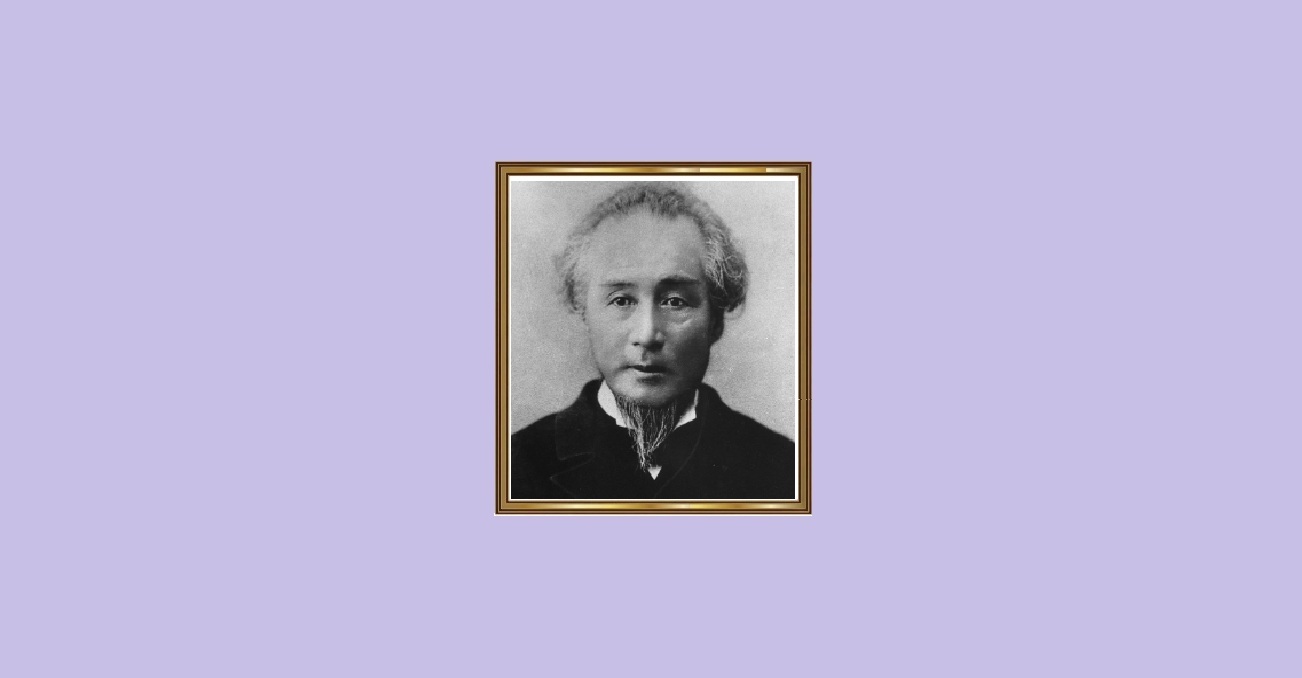
プロフィール
勝海舟(かつ かいしゅう)
1823(文政6)年3月12日生│1899(明治32)年1月19日没(75歳)
「幕末の三舟」「明治維新・幕末のキーマン」
「世間は生きている。理屈は死んでいる」
この言葉は、幕末という激動の時代に、常に現実を見据え、日本の海軍と外交の未来を切り拓いた勝海舟(かつ かいしゅう)が残したものです。江戸本所(現在の東京都墨田区)に生まれた彼は、幕臣でありながら身分や藩の枠を超えて坂本龍馬らを育成し、「幕末の三舟」の一人に数えられました。彼の最大の功績は、新政府軍の西郷隆盛を説得し、江戸の町を戦火から救った「江戸城無血開城」の実現です。その生涯を通じて、勝海舟が示し続けた驚異的な先見の明は、単なる国内政治にとどまらず、100年後の東アジアの国際情勢にまで及んでいました。
幼少期の苦難から海軍の道へ
勝海舟、幼名・麟太郎(りんたろう)は、文政6年(1823年)、江戸本所亀沢町で、御家人・男谷家から旗本・勝家に婿養子に入った父・勝小吉(かつ こきち)の子として生まれました。勝家は家禄41石という貧しい旗本でしたが、海舟の曽祖父は盲人ながら高利貸しで成功した「米山検校」であり、その才能と豪胆さは血筋として受け継がれていました。幼少期の海舟を語る上で欠かせないのが、9歳の時に野良犬に襲われ、瀕死の重傷を負った事件です。父・小吉は、この時、刀を枕元に突き立て「ここで死んだら犬死に」と海舟を励まし、自らも水垢離をして息子の回復を祈願しました。この生死を彷徨う経験が、海舟の胆力と不屈の精神を培い、後に彼が犬を苦手にする原因にもなりました。16歳で家督を継いだ海舟は、直心影流剣術の免許皆伝を得る一方、蘭学医・永井青崖(ながい せいがい)に弟子入りし、蘭学を学び始めます。蘭学修行中には、全58巻のオランダ語辞書『ドゥーフ・ハルマ』を1年かけて2部も筆写したという逸話が残されています。
蘭学塾「氷解塾」と「海軍伝習所」
海舟は赤坂田町に私塾「氷解塾」を開き、蘭学と兵法学を教えました。蘭学者・佐久間象山の知遇を得た彼は、象山の勧めもあり西洋兵学を修めます。嘉永6年(1853年)の黒船来航を受け、幕府が海防意見書を広く募集すると、海舟は西洋式兵学校の設立を提言し、老中阿部正弘の目に留まります。安政2年(1855年)、彼は異国応接掛附蘭書翻訳御用に任じられ、念願の役入りを果たし、長崎海軍伝習所に入門しました。長崎ではオランダ人教官に師事し、通訳も兼任する多忙な日々を送ります。船酔いに苦しむ体質ではありましたが、海軍に関する知識を貪欲に吸収し、その後の日本の海軍建設の基礎を築きました。
咸臨丸での渡米と「神戸海軍操練所」
万延元年(1860年)、幕府が日米修好通商条約の批准書交換のために遣米使節を派遣する際、海舟は護衛艦「咸臨丸(かんりんまる)」の軍艦操練所教授方頭取として渡米します。この航海には、福沢諭吉やジョン万次郎も乗り組んでいました。海舟は、帰国後に軍艦奉行並に昇進すると、文久3年(1863年)、神戸に海軍操練所を開設します。この操練所は、幕臣だけでなく、坂本龍馬らを育成し、後の明治維新を担う多くの人材を育成しました。海舟は、坂本龍馬に「日ノ本第一の人物」と評され、師弟関係を超えた強い絆を結びました。
戊辰戦争と「江戸無血開城」
元治元年(1864年)、軍艦奉行に就任した海舟は、公議政体論(諸侯と幕府が共同で政治を行う思想)を支持し、幕府の独断的な政治に反対する立場をとりました。しかし、第二次長州征討の停戦交渉に失敗するなど、政局は混乱を極め、海舟は一時蟄居を命じられます。慶応4年(明治元年、1868年)、戊辰戦争が勃発し、新政府軍が江戸に迫ると、海舟は江戸幕府最後の陸軍総裁に任命されます。幕府内部では徹底抗戦を主張する声も多かった中、海舟は江戸城での市街戦を回避し、江戸の住民150万人の生命と財産を戦火から守るため、和平交渉に踏み切ります。3月13日と14日、海舟は新政府軍の参謀西郷隆盛と会談し、江戸城の開城と徳川宗家の存続を条件に、江戸城の無血開城を成し遂げました。この歴史的な決断により、日本の近代化の礎となる江戸の町は守られ、海舟は「江戸の恩人」としてその名を不朽のものとしました。
中国観の予言と「不敗の外交」
明治維新後、海舟は参議兼海軍卿、枢密顧問官を歴任しましたが、政府の要職に固執することなく、辞退や短期間での辞職を繰り返しました。彼は、旧幕臣の代表として、徳川慶喜の赦免に尽力し、榎本武揚ら旧幕臣の就労斡旋や生活支援にも奔走しました。
100年後の中国を予見した洞察力
勝海舟の驚くべき先見性は、彼の中国(清国)観に最もよく現れています。彼は、日清戦争(1894-1895年)に大反対の立場をとり、戦勝に沸く当時の日本に対し、厳しい警鐘を鳴らしています。「支那は国家ではない。あれはただ人民の社会だ」と喝破した海舟は、清国の人々は帝室や政府の興廃には関心がなく、自分の利益を重んじる経済的な民族であると見抜いていました。「剣や鉄砲の戦争には勝つても、経済上の戦争に負けると、国は仕方がなくなるヨ。そして、この経済上の戦争にかけては、日本人はとても支那人には及ばないだらうと思ふと、俺は密かに心配するよ」海舟がこの予言を残した100年後、その言葉通り中国は経済大国として台頭し、世界経済に大きな影響を与える存在となりました。彼のこの洞察力は、当時の外交官や政治家の中でも群を抜いていました。
宿敵・福沢諭吉との確執
海舟は、終生の宿敵福沢諭吉との間にも、複雑な関係がありました。諭吉は、咸臨丸の航海中に海舟の指揮官としての態度に不満を抱き、後に『瘠我慢(やせがまん)の説』で、海舟の江戸城無血開城と新政府への仕官を厳しく批判しました。しかし、海舟は諭吉の批判に対し、「行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与らず我に関せずと存候」(世に出るも出ないも自分がすること、それを誉める貶すは他人がすること、自分はあずかり知らぬことと考えている)と泰然と構え、一切弁明も批判もしませんでした。

大河ドラマの勝海舟
🟣昭和42年(1967年)『三姉妹』
内藤武敏さん(当時40歳)
🟣昭和43年(1968年)『竜馬がゆく』
加東大介さん(当時56歳)
🟣昭和49年(1974年)『勝海舟』
松方弘樹さん(当時31歳)、渡哲也さん(当時32歳)
🟣平成2年(1990年)『翔ぶが如く』
林隆三さん(当時46歳)
🟣平成10年(1998年)『徳川慶喜』
坂東三津五郎さん(当時41歳)
🟣平成16年(2004年)『新選組!』
野田秀樹さん(当時48歳)
🟣平成20年(2008年)『篤姫』
北大路欣也さん(当時64歳)
🟣平成22年(2010年)『龍馬伝』
武田鉄矢さん(当時60歳)
🟣平成25年(2013年)『八重の桜』
生瀬勝久さん(当時52歳)
🟣平成30年(2018年)『西郷どん』
遠藤憲一さん(当時56歳)
📍勝海舟ゆかりの地:近代日本の胎動を辿る旅
勝海舟の足跡は、彼の生まれ故郷である江戸から、蘭学を学んだ長崎、そして最期の地である東京へと繋がっています。
- 勝海舟生誕の地(東京都墨田区両国4-25-3両国公園内):海舟が生まれた父の実家である男谷家の跡地に建つ碑です。
- 勝海舟銅像(東京都墨田区吾妻橋1-23・墨田区役所うるおい広場):彼の功績を称え、墨田区役所の広場に建てられた銅像です。
- 能勢妙見堂(東京都墨田区本所4-6-14):海舟が子供のころ犬に噛まれて重傷となった居りに、父小吉はこの妙見堂で水垢離をして息子のケガが平癒することや出世を祈った。勝海舟晩年の胸像があります。
- 勝海舟寓居の地(長崎市筑後町2-10・聖林山本蓮寺):長崎に滞在中、大乗院に宿泊し、長崎の女性、梶くまとの間に一男一女をもうけました。くま(法名は容誉智顔麗光大姉)の墓は、本蓮寺隣の聖無動寺の梶家墓地にあります。
- 勝海舟寓居(専稱寺)跡、大坂海軍塾跡(大阪府大阪市中央区淡路町3-2-13):海舟は、大坂の寓居先である専稱寺に海軍塾を開いた。この場所は、元治元年(1864)9月11日、勝海舟と西郷隆盛がはじめて会見した場所でもある。文久3年(1863)9月24日、勝海舟は神戸海軍操練所の開所準備のため神戸に移り、私塾も大坂から神戸の海舟邸に移された。
- 海軍操練所跡の碑(兵庫県神戸市中央区新港町17-1):この周辺にあったと言われており、京橋筋南詰に神戸海軍操練所跡碑が建てられている。重さ10トンにおよぶイカリをモチーフにした碑の下には本の形をした碑があり、海軍操練所跡の由来が書かれている。
- 勝海舟寓居地碑(和歌山県和歌山市舟大工町28):海舟は1863年に紀淡海峡に面する加太や友ヶ島に配備した台場(砲台)の確認に度々、訪れ「このうち、4月2日~13日、橋丁の商家、福島屋へ滞在したと、日記に残っています。
- 常林寺(京都市左京区田中下柳町33):海舟が京都で宿坊として利用していたと伝わる寺。
- 西郷南洲勝海舟会見之地碑(東京都港区芝5-33-1):江戸城総攻撃を目前にした慶應4年3月13日、14日の両日薩摩屋敷において勝海舟と西郷隆盛の会見が行われ、歴史的な無血開城がなされました。この重要な会見の地については諸説があるようですが、13日の予備的会談は高輪の薩摩屋敷、14日の最終会談はこの碑の建つ田町の蔵屋敷で行われたようです。
- 海舟が愛した和菓子屋・壺屋総本店(東京都文京区本郷3-42-8):明治維新の折、江戸の大店は「新政府の世になって商いを続けていては、長年に渡ってお世話になった徳川様に申し訳が立たない」と次々に暖簾を下ろしていった。壺屋もまた廃業を決意していたが、常連客であった勝海舟から「市民が壺屋の菓子を食べたいと言っているから、続けるように」と諭され、再開したのだという。今も店内にはこの時に贈られた「神逸気旺(しんいつきおう)」の書が大切に飾られている。神頼みをするのではなく、気力をもって事に当たる、という意味。
- 大田区立図書館・洗足池図書館勝海舟コーナー(東京都大田区南千束2-2-10):海舟の墓は洗足池図書館に隣接する洗足池公園北側にあり、大田区指定文化財となっています。この所縁にちなんで、平成8年(1996年)改築開館時より洗足池図書館に「勝海舟コーナー」を設置しました。勝海舟の著作・伝記・研究書、勝海舟をテーマにしたフィクションなどを収集しています
- 大田区立勝海舟記念館(東京都大田区南千束2-3-1):海舟の功績や大田区との縁を紹介するとともに、海舟の想いと地域の歴史を伝える記念館です。
- 勝海舟夫妻の墓(東京都大田区南千束2-14-5・洗足池公園内):海舟は、官軍のおかれた池上本門寺に赴く途中、洗足池畔に憩い、風景にうたれ、その縁でここに別荘を構えました。後に海舟の遺言で、屋敷裏の台地に葬られたと伝えられます。妻である民子の墓は、後に青山墓地から移設されました。区指定文化財。
💬勝海舟の遺産:現代社会へのメッセージ
勝海舟の生涯は、私たちに「現実主義と大局観」の重要性を教えてくれます。彼は、理想論や感情論に流されることなく、常に日本の国益と未来を見据え、最も合理的な道を選択しました。彼の「公議政体論」や「三国同盟構想」は、現代の国際政治にも通じる、多角的な視点とバランス感覚の重要性を示しています。勝海舟の物語は、一人のリーダーが、その卓越した洞察力と実行力によって、国の運命を変え、多くの人々の命を救うことができることを証明しています。彼の精神は、現代に生きる私たちに、理想と現実の狭間で、常に最善の選択をする勇気と、100年先を見据える大局観を持つことの大切さを、力強く語りかけているのです。
©【歴史キング】
関連する書籍のご紹介

海舟語録 (講談社学術文庫 1677) / 勝 海舟 (著), 江藤 淳 (編集), 松浦 玲 (編集)
文庫 – 2004/10/9
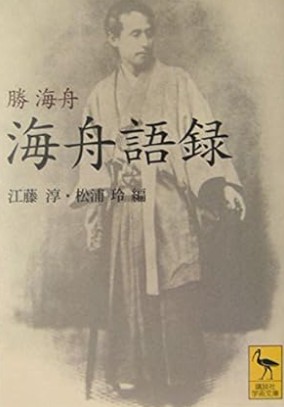
奔放自在、縦横無尽!幕末・維新を語り、明治の政局を評する海舟の炯眼と叡智
官を辞してなお、陰に陽に政治に関わった勝海舟。彼は晩年、ジャーナリスト巌本善治を相手に、幕末明治の政情や人物等について奔放に語った。本書では、『海舟餘波』『海舟座談』等として知られるそれらの談話を詳細に検討、日付順に再構成し、海舟の人柄や、その炯眼、叡智を偲ばせる肉声の復元を試みた。『氷川清話』の姉妹編をなす貴重な歴史的証言集。
これは、まったく新しい観点から編集した勝海舟の『語録』である。かつて巌本善治が編纂した『海舟餘波』、『海舟座談』に収められている談話を、あたう限り初出に遡って検討し、配列をあらため、かつ適切な注を点した。時代を超えて語りかけて来る海舟の叡智は、かくして歴史のなかにも正しく位置づけられるようになったのである。――<本書「まえがき」より>